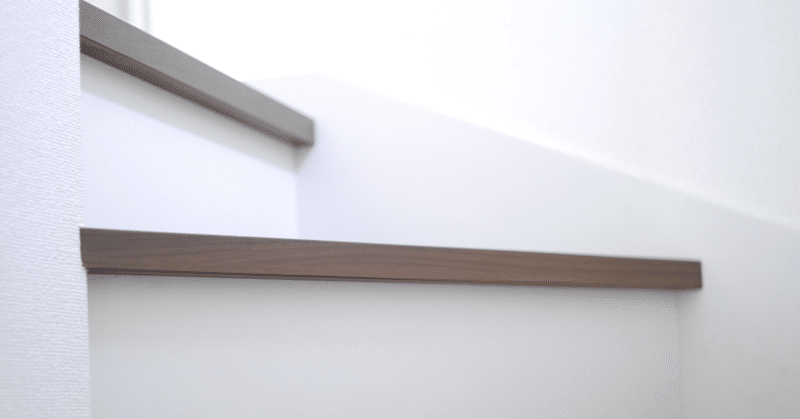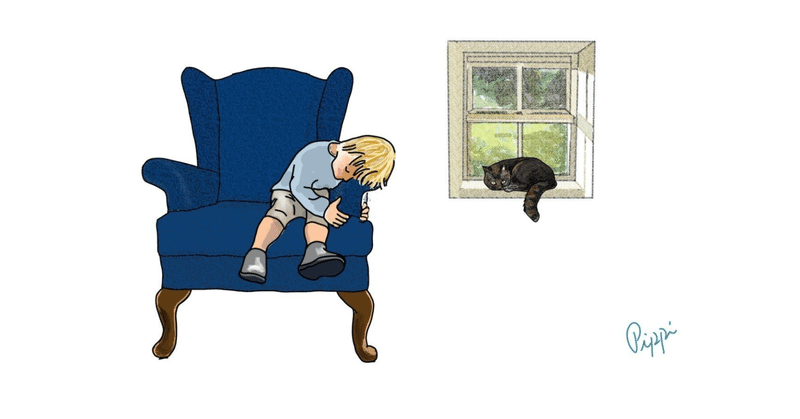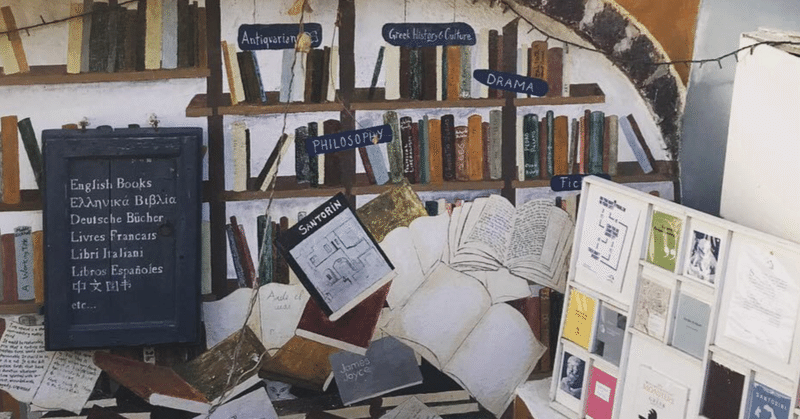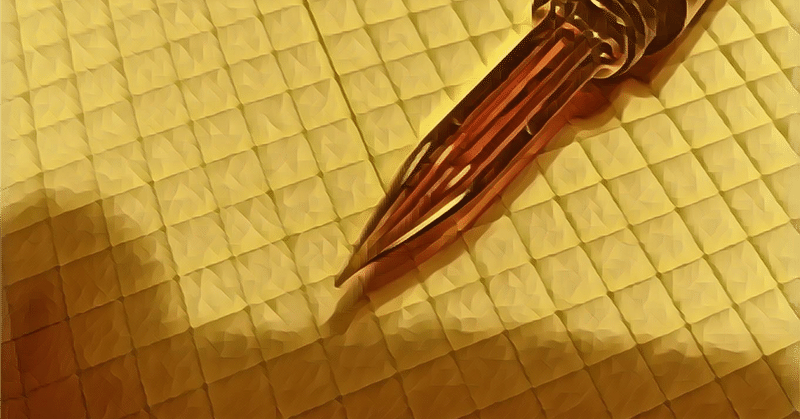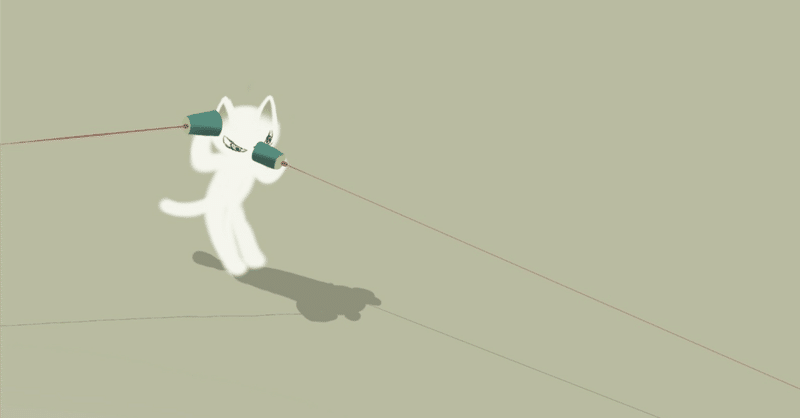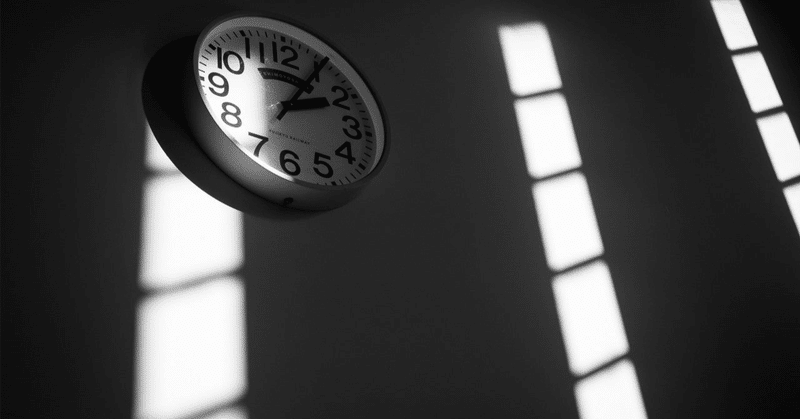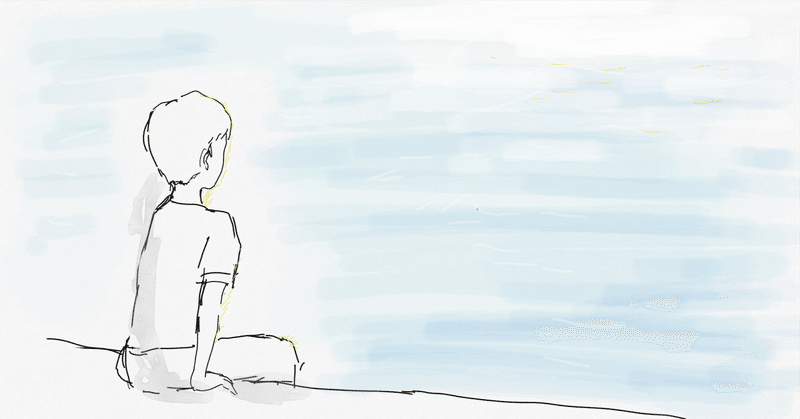#小説
「鏡」という「文字」、鏡という「もの」(「鏡」を読む・01)
「「鏡」を読む」という連載を始めます。江戸川乱歩の『鏡地獄』の読書感想文です。体調というか病状が思わしくないので、この連載は不定期に投稿していくつもりでいます。
◆「鏡」という「文字」、鏡という「もの」
江戸川乱歩の『鏡地獄』の最大の奇想は、鏡ではなく「鏡」という「文字」を真っ向からテーマにしたことだと私は思います。この短編のテーマは、鏡という「もの」ではなく、「鏡」という「文字」だと言いたい
人間椅子、「人間椅子」、『人間椅子』
今回は「立体人間と平面人間」の続きです。それぞれが別の方向をむいた言いたいこと(断片)がたくさんあり、まとまりのない文章になっています。申し訳ありません。
お急ぎの方は最後にある「まとめ」だけをお読みください。
人間椅子から「人間椅子」へ
江戸川乱歩の『人間椅子』の文章は朗読に適していると思います。音読してすらすらと頭に入ってくる文体で書かれているのです。特に難しい漢語が使われているわけ
タブロー、テーブル、タブラ(『檸檬』を読む・02)
引きつづき、梶井基次郎の作品を読んでいきます。今回も『檸檬』です。
・「共鳴、共振、呼応(薄っぺらいもの・06)」:対象作品『愛撫』
・「出す、出さない、ほのめかす(『檸檬』を読む・01)」:対象作品『檸檬』
引用にさいして使用するのは『梶井基次郎全集 全一巻』(ちくま文庫)ですが、青空文庫でも読めます。
◆表象に対する紡錘形の立体のささやかな抵抗*タブロー、テーブル、タブラ
丸善の
立体、平面、空白(薄っぺらいもの・05)
今回は、蓮實重彥著『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』のうち、「Ⅰ肖像画家の黒い欲望――ミシェル・フーコー『言葉と物』を読む」をめぐっての読書感想文です。
この「フーコー論」は、「薄っぺらいもの」というシリーズを始めるきっかけになった文章の一つでもあります。初めて読んだのはずいぶん前のことですが、以来私にとって気になる文章であり続けています。
引用文の余白に書く
*「顔と視線との離脱現象」
直線上で迷う(線状について・01)
直線上で迷うことがあります。嘘ではありません。誰もが経験していることです。私もしょっちゅう経験しています。
証拠があります。ハードエビデンス(hard evidence)、動かぬ証拠というやつです。
たとえば、こんなふうにです。動画をご覧ください。
ごめんなさい。
動かぬ証拠ではなく、動く証拠(soft evidence?)でした。
*
小説には始まりと終わりがあ