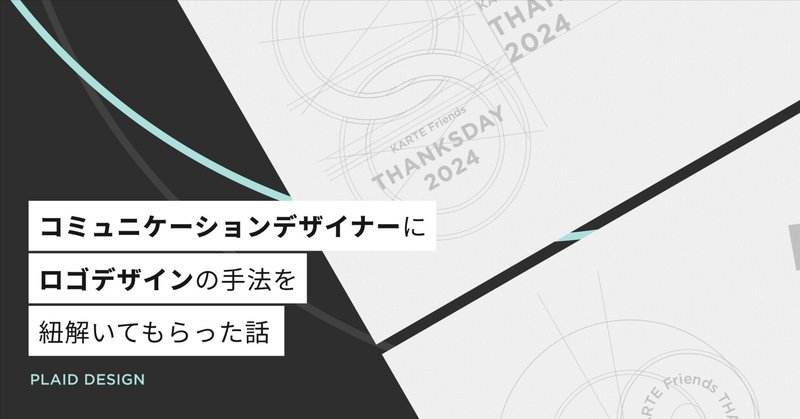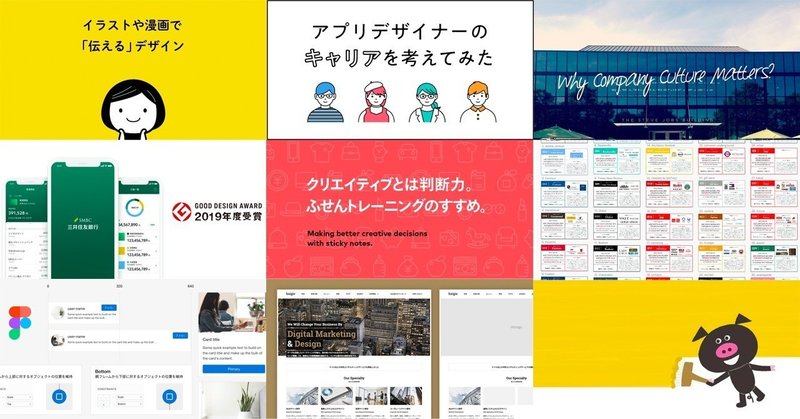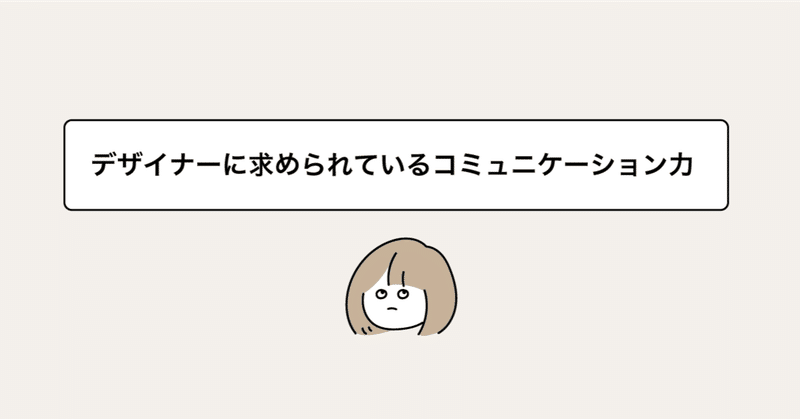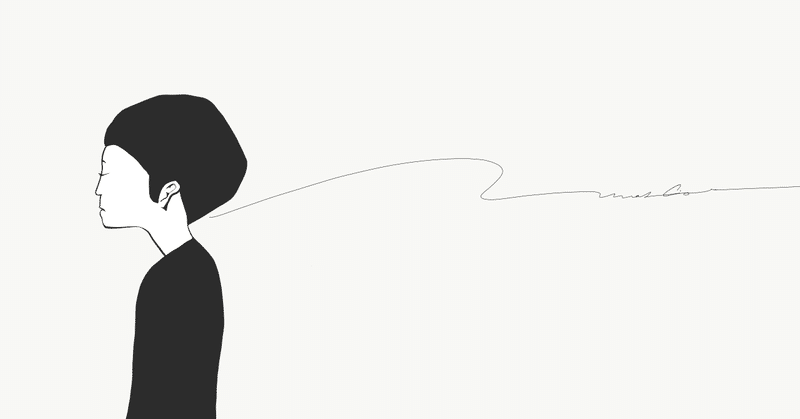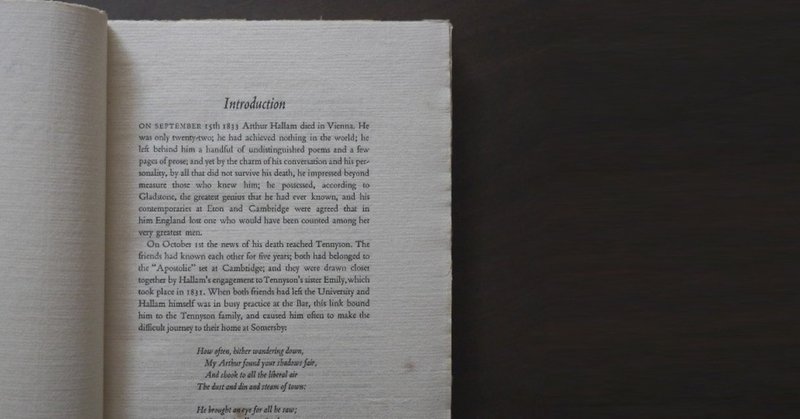#グラフィックデザイン
コミュニケーションデザイナーにロゴデザインの手法を紐解いてもらった話 【ゆるくないようでかなりゆるいデザイナー勉強会 Vol.2】
こんにちは!プレイドのデザインチームのなんでも屋さん ayacchi ( @222078 ) です 🙌🏻
ゆるくないようでかなりゆるい デザイナー勉強会 、久々の記事公開です。
ナレッジシェア自体はチーム内でかなりリズムづくりが進み、直近は週1ペースで会を開けていたりするので、アウトプット化についても力を入れ直して行きたい所存です 💪🏻
この勉強会について
今回は、コミュニケーション
DESIGN : parable ロゴ&ブランディングデザイン「気づきを仕掛ける」
医療系の転職サポート「転職ガーデン」を運営している会社、parable Inc.ロゴを中心としたブランディングデザインをOUWNが担当しました。
今回はアートディレクションをOUWN代表・石黒が、そしてデザインは昨年新卒で入社したfumiが担当。貴重な提案資料(!)と一緒に、思いの込もったインタビューをお届けします。
parableについて
ー お仕事はどうやって依頼を受けたんですか?
f
DODO DESIGNのアートディレクターの育て方
ビズリーチのコミュニケーションデザイン室では、「明日から活用できる引き出し」をテーマに、デザイン業界の第一線で活躍されているさまざまな方を講師にお招きし、業務やキャリア開発に生かす勉強会をはじめました。
今回の勉強会は、大胆なアイデアとユーモア溢れるクリエイティブで数々の広告を手掛けるDODO DESIGNの代表取締役/アートディレクターの堂々 穣さんと、入社2年目デザイナーの栗原 あずささんを
DESIGN : フォント座談会
いつもよりリラックスモードで、OUWNメンバーがフォント(書体)について話します。今回は事前に石黒が質問を用意し、それぞれが回答を持ち寄りました。
Q1. 自分がよく使う書体は?
石黒 :
色々ある中であげるとしたら、AG Old Face。
作ったのはドイツの人で、Gunter Gerhard Langeっていう方がデザインしたものです。Akzidenzっていう書体がデジタルになるときに今の
2019年が終わるまでにデザイナーが絶対に読むべきnote50選
こちらの記事を拝見させて頂き、これのデザイナー版を読みたいなと思ったので、自分でまとめました。
ただ調べていくうちに今まで読んだことのなかった神noteがどんどん出てきたので、結果的に2019年という枠を飛び越え、50選までいってしまいました。
偉大な先人たちの英知が全てのデザイナーに届くことで、世の中がデザインによってより良くなっていったらいいなと思います。
また最後の組織デザインについて
デザイナーに求められているコミュニケーション力
スマートキャンプデザインブログ、モリシゲです。
私は普段からさまざまなデザイナーのブログを読んでいますが、「デザインはコミュニケーションだ」「基礎能力の中でも最も大事なのはコミュニケーション能力だ」という内容がたびたびテーマとして取り上げられています。
今回はそれらのデザインブログで言及されている「コミュニケーションのあれこれ」をかいつまんで、私のデザイン経験としても共感できる部分を中心にまと
デザインで迷った時 「そもそも」を考えれば8割クリアできる説。
よく仕事でデザインをしてて
迷う事ってあるんじゃないでしょうか。
「レイアウトは1カラムで行くか、無難に2カラムにするか」
「コーラルピンクだとオシャレだけど弱い、ただ普通のピンクだと強い」
「この要素はどれだけ大きく配置すべきか」
僕はあります。80代のジジイの頻尿並みにあります。
そんな時、大概の場合は今から説明する
「そもそも論」に則って、考えれば8割は解決できるように思うので
ご紹介
超リアル!「デザイン費の算出方法」をお伝えします。恋のABC。工数、付加価値、経験値。
◎ なぜ、デザイン費を伝えるか?
私がnoteで文章を発信するのは、「デザイナーではない人に、デザインを伝える」ことが、第一の目的です。SNS上で、こんな光景を見たことはありませんか?
---
◎ 問題こそ、改善発見伝。
お客さんとのやり取りの中、何か問題が起こった場合、よほどのことがない限り、私は “120%デザイナーが悪い” というスタンスでいます。その方が、次につなげる改善点が見える
グラフィックデザインにおける「次元」への課題とその解決策
前回、受注脳に陥りがちなデザイナーが、自分発信で個展をする意味をどこに見出すのかという葛藤と、どのような思考でそれを打破したかの記録を書いた↓
グラフィックデザイナーが個展をする意味をずっと考えていた
簡潔にいえば、受注脳であるデザイナーの思考を逆説的に利用し、グラフィックデザインというジャンルそのものをクライアントに見立てることで、それを突破するという方法をとった。そして、『GRAPHIC