
ネタバレ〈エセ過保護〉社会の日本人
私の「note」記事を、何百人かの人が読んで(見て?)くれているはずだが、そうした中で、私が「ネタバレ」という言葉を避けていることに気づいた人は、たぶん一人もいないと思う。
いわゆる「ネタバレ」が問題になるような「作品評」的なものには、必要に応じて、
「以下、作品のネタをバラしている部分がありますので、未読の方はご注意ください。」
といった「注意書き」を付すこともあるが、何でもかんでも「無難に付けておく」というようなことはしないので、そうした記事の本数は、おのずと少ない。
したがって、よほど勘の鋭い「読める人」でないかぎり、私が「ネタバレ」という言葉を、意識的に避けていることには気づかないだろう、ということである。
そんな鋭い読み手というのは、数百人程度では1人もおらず、数千人か、1万人に1人程度だろうというのが、私の「一般的読者」認識なのである。

なぜこんなことを書くのかというと、文章を書く者は、プロであれアマチュアであれ、「言葉」に鈍感であってはならない、と考えるからだ。
ほかのところで「私は詩歌オンチであり、言葉に対する鋭い感性を欠いている」といったことを自ら書いているように、私自身、言葉というものについて、特別鋭い感性など持っていないことは自覚している。
しかし、そんな私でも「これは、嫌な言葉だな」とか「使いたくないな」というものが、ごく稀にある。
それが、私にとっては、例えば「自転車」を指す「チャリ(ンコ)」という言葉であり、あるいは、「ネタバレ」なのだ。
もちろん、私は、この2つの言葉が、客観的に「ゲスな言葉」だとか「頭の悪い言葉」だ、などと言うつもりはない。人それぞれに、育ってきた環境も違えば、その性格や感性も違うのだから、感じ方が違うのも当然なら「嫌な言葉」「使いたくない言葉」が、人によって違うというのは当然だと思うからである。
しかしながら、問題なのは、そもそも、そういう「自分なりの、言葉に対する感性」が無いに等しい人たちが多い、という事実なのだ。
「みんなが使っていれば、何も考えずに平気で使って、何の疑問も持たない」反面、それが社会的に「不適切な言葉=使うべきではない言葉」だとされ「それなりの説明」が加えられると、今度は「もっともだ」とばかりに、あっさりその言葉を捨てて、平気でいられるような、言葉についての「感性欠如」の人たちの存在が、私には我慢ならない。
○ ○ ○
私が「チャリ」という言葉が嫌いなのは、この言葉に「育ちの悪い軽薄さ」を感じるからだ。
「自転車」と言っても「チャリ」と言っても、ほとんど発声所要時間に違いはないから、この言葉は、口語経済的に発明されたものではなく、ありふれた「隠語」趣味から生まれたものであろうことは、容易に想像できる。
「自転車」と当たり前に言わず、「チャリ」という「隠語」を使うことで、自分が、何か特別な存在(あるいは、そのグループの仲間)になったような、一種の「エリート」気分を味わうのであろう(当初は、そうであった)。
これは、無闇矢鱈と「ジャーゴン(専門用語)」を使いたがる学者などにも見られることだから、「学力的な頭の良し悪し」の問題ではなく、その人間の「人品」的な部分での、頭の良し悪しの問題だと言えるだろう。つまり、「隠語」や「専門用語」を、さしたる必要もないのに、やたらに使いたがる人間というのは、薄っぺらな「カッコつけたがり屋」でしかなく、要は、本質的な部分で、バカだということである。
では「ネタバレ」の方はどうか?
私の若い頃には、まだこの言葉は無かったのだが、ここ20年ほどの間に徐々に広がってゆき、今では、適宜この言葉を使わない者は、「無作法」な人間だとさえ思われそうな勢いである。
しかし、この言葉が、どのような出自や必要性を有し、どのように使うのが適切なのかと、それを考えて使っている者は、たぶん100人に1人もいないだろう。1000人に1人くらいは、いてほしいものではあるが、それもかなり疑わしい。
○ ○ ○
この「ネタバレ」という言葉は、主として「ミステリー小説=推理小説」、特に「本格ミステリ」の世界から生まれてきた言葉と考えて良いだろう。

(※ 出演した人気女優が、インタビューに答えて「私、今度、犯人役をするのよ(したのよ)」と応えたという話がある。そういう、のどかな時代だったのだ)
周知のとおり、いわゆる「本格ミステリ」には、しばしば「トリック」というものが作中に仕掛けられている。そして、その「トリック」とは、作中の犯人が、作中世界の人々に仕掛ける「トリック」と、作者が読者に仕掛ける「トリック」の、主に2種類がある。
たとえば、前者であれば、ある人物が、外からは出入りのできない「密室」の中で、背中にナイフを突き立てられて死んでいた。彼は、どのようにして殺されたのだろうか、といったものが、いわゆる「密室トリック」である。
こうした作品の「紹介文」を書く場合、当然のことながら「この作品には、密室殺人が登場するが、じつは、これは殺人事件ではなく、単なる事故だったのだ。男が誤って転倒した際に、背中にナイフが突き刺さってしまっただけである」などと書いてはいけない。つまり「ネタを割ってはいけない」。そんなことを書いてしまえば、もう誰もこの作品を読まなくなってしまうからである。

しかし、昔は、こうした「不用意な紹介文」というのが、ときどき目につき、読者からの批判を浴びることがあった。その時に言われたのが「ネタをバラすな!」「ネタバラしをするな!」といった言葉であった。
つまり、「ネタ」は勝手にバレるものではなく、それをバラす人(書き手)がおり、その人(書き手)が気をつけなくてはならないことだと認識されていたから、これらは「ネタをバラすな!」「ネタバラしをするな!」という言葉となっていたのである。
ところが、昨今の「ネタバレ」という言葉は、「ネタがバラされている」という「状態」を指すもの、そうした「結果状態」の説明であって、「ネタをバラしてはいけない」という「主体性」が、そこからは消えているのだ。
無論、「バラす人」がいなければ「バレた状態」になることはないのだが、なぜ「すべきこと。すべきでないことをしないこと」という「当為=Sollen」の問題であったものが、いつの間にか「主体性」を欠いて、「状態」の問題にズレてしまったのだろうか?
たぶんそれは、インターネットが普及して、誰もが文章を公にできる環境が整ってくると、「書き手としての主体的責任」という、それまでは「当然」だったものを、引き受ける覚悟のない人、引き受けたくない人が増えてしまったので、「ネタをバラす、バラさない」という「主体性」の問題が、主語を欠いて「ネタがバレている、バレていない」という「状態」の問題へと、中性化されたのではないだろうか。
つまり、昔なら「誰の責任か」と鋭く問われたのが、今は「その状態になっていることがまずい」という「誰も責められない」方向へとズラされたのだ。
昔なら「バレてしまったことも問題だけれど、しかし、それはバラした者に問題があり、その無自覚を是正してもらわないことには、同じことが繰り返されてしまう」というような感覚だったものが、今では「誰がやったかが問題ではなく、ネタのバレた状態こそが問題なのだ。だから、その状態を、あらかじめ告知しておけば、被害は食い止められるはずだ」というスタンスに変わったのである。
さらに言い換えるなら、昔の考え方は「ラディカル(根源的)」な是正だったのに対し、今は「実利的」是正に変わったということになるだろう。一一こうすれば、「書き手」は「この文章では、ネタをバラすべきか、バラさない方がいいのか?」と、「いちいち頭を使わなくて済む」のである。
これは、たしかに「経済的」であり「実利的」ではあるのだけれど、しかし、それは「ラディカルさ(根源性)」を欠いた「結果オーライ」でしかないがために、書き手がこれに馴れてしまい「頭を使わなくなる」と、当然、おのずと徐々に、バカになる、ということである。
それにしても、なぜ、昔の書評家や評論家は、しばしば不用意に「ネタばらし」をしたのであろうか?
それは、自分たちの書いているものが、「作品紹介」を主たる目的とした「宣伝的紹介文」であるのか、その作品が、いかなるものを含意する作品なのかを論じた「批評・評論文」なのかの区別が、十分についていなかったからであろう。
「ミステリ=推理小説」というのは、昔も今も「通俗小説=エンタティンメント小説」だと認識されているために、ミステリを対象とした、本格的な「文芸評論」というものが発達せず、肩書きとして「ミステリ評論家」を名乗ってはいても、「評論家」の名に値しない「紹介文章屋=紹介ライター」でしかない人が、多かったからである。
つまり、作品の「宣伝的紹介文」なら、商品の肝の部分である「ネタ」をバラしてはいけないのだが、作品を分析検討して、その意味するところや価値を論ずる「批評・評論文」の場合は、作品の重要要素として、いやでも「トリック」や「犯人名」などにも触れなければならない。
したがって、本来なら、書き手は、自分の書くものが「宣伝的紹介文」なのか「批評・評論文」なのかの区別を、ハッキリとつけて、その形式的書き分けをしなければならないのだ。
ところが、実質的には「紹介文章屋=紹介ライター」の域を出ない者が、聞こえの良い「評論家」を名乗り、自分がいっぱしの「文芸評論家」だと勘違いして、「紹介文章」でしかないものを「批評・評論文」の類だと思って書いたがために、不用意にも、触れる必要のない「トリック」や「犯人名」をバラしてしまい、読者からの批判を浴びることになったのである。
だが、前述のとおり、書き手が「すべての人」に広がった現在、そうした人たちに「自分の書くものが、単なる感想付き紹介文なのか、批評・評論文なのか、の区別をつける」ことを求めるのは、無理であろう。

その昔「プロの書き手」として「ミステリー評論家」とか「推理小説評論家」と名乗っていた、それなりの「プロ」ですら、こうした「区別」が、ろくに出来ていなかったのだから、知識もなければ技量もなく、ましてや責任意識などない「アマチュアライター」にそれを求めるのは、(建前としては「プロアマ関係なく、文章を公にするからには、責任感を持たなければならない」とは言うものの)現実問題としては、どう考えても、無理な話である。
だから、そういう素人が、何も考えないで書いた文章において、読者に被害が広がらないようにするために、「ネタバレ」という「中性的」な言葉が生まれ、自然と普及したのであろう。
そしてそれは「本格ミステリ作品における、トリックや犯人名」あるいは「結末(落ち)」などに止まらず、あらゆるジャンルの作品の「ストーリー展開」を含む、あらゆる要素へと、「無難に」拡大利用されるようになっていったのである。
またその結果、「念のために」「無難に」といった具合にでも「ネタバレ注意」をつけておかないと、ちょっとしたことを「ネタバレ」呼ばわりされ、それを「義務不履行」や「不作為の罪」だと非難されるケースも出てきて、表現者は「ネタバレ注意」をつけることが、半ば「義務」として強いられることになり、今や、「あえて、言明しない」という「表現」への制限にさえなっているのである(例えば、観客を驚かせるために、ホラー作品であることを隠して、作品を公開するようなことは、事故防止の観点から禁じられ、できなくなってしまった。こうした表現の不自由は、どんどん拡大している)。

(※ この表紙画も、今なら「ネタバレ」だと言われる蓋然性が高い)
前述のとおり、この「ネタバレ」という言葉は、「書き手の主体性(責任の引き受け)」は問われずに、もっぱら「読者の被害の予防」を目的にしている。つまり、これさえ冒頭に掲げておけば、「何を書いても大丈夫(免責される)」というわけである。
だが、こんなものに頼って、文章を書いていたら、書き手の思考能力のレベルが落ちるのは、必然的だと言えるだろう。なにしろ、責任意識を持たず、好きに書けば良いだけなのだから、頭を使う必要などないからだ。
しかし、この問題は、書き手に止まるものではない。
「ネタバレ」という言葉が「実利的に便利なもの」「責任回避の道具」として普及してくると、今度は読者の方が、それだけを見て、この文章は「ネタを割っている」文章であるかないかを判断してしまうようになる。
一一つまり、その文章が、「宣伝的紹介文」なのか「批評・評論文」なのかの区別を、「ネタバレ注意」という看板の有無だけで判断するようになり、その文章の、タイトル、掲載形式、長さと行った複数要素から、読者個々が「自分で判断する」ということをしなくなってしまうのだ。
その結果、読者の多くは、その文章が「宣伝的紹介文」なのか「批評・評論文」なのかの区別をつけられない、その能力を持たない、頭の悪い読者になってしまうのである。
つまり、「ネタバレ注意」の看板は、端的に言って、書き手と読者の双方に対する「エセ過保護」なのだ。
そんな「経済性」だけの便利な道具に、何も考えずに頼っていると、書き手も読者も、気づかぬうちに徐々に、バカになるしかない。
これは、過剰な「リスクヘッジ」社会であり、そのための「エセ過保護」社会である日本にいたのでは、ピンと来ない話なのだろうが、諸外国において、日本以上の「エセ過保護社会」というのは、滅多にあるものではない。
それを典型的に示すものとしては、カント哲学者である中島義道の名を世に知らしめた、長編社会エッセイ『うるさい日本の私 「音漬け社会」との果てしなき戦い』(1996年)がある。(本書タイトルは、川端康成のノーベル文学賞授賞記念講演でのスピーチ「美しい日本の私」を皮肉ったもの)
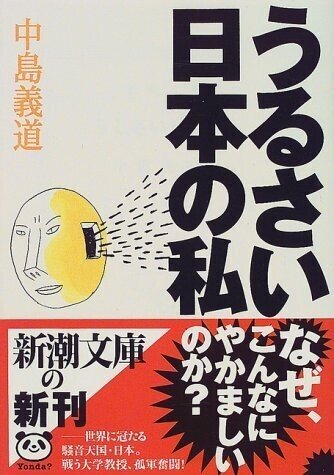
この本の内容を、記憶に基づいて簡単に紹介すると、こうなる。
海外での研究生活から帰国した中島は、日本の社会に蔓延している、過剰な音に驚き、その押しつけがましい過保護性に怒りを覚えた。駅に行けば「二列に並んで、お待ちください」「白線の内側でお待ちください」「まもなく電車がまいります」「高齢者や体の不自由な方を見かけたら、何かお手伝いしましょうか、と声をかけましょう」とか、そういう放送が流れてくる。無論、こうした「過剰放送」は、駅構内に限ったことではなく、電車内でも、街のあちこちでも、一方的に流れてくる。日本人にとっては、これはもはや「当たり前の環境音」でしかないのだが、海外生活の長かった中島の耳には、こうした音たちは、異状なものでしかなかった。海外の諸都市には、こうした過剰な音声の氾濫はなく、もっと自然で静かだったのである。そして中島は、そちらの方がまともであり、日本が異状なのだとしか思えなかった。なぜなら、こうした音声で促されている内容とは、まともな大人であれば、言われなくても承知していることでしかなく、言っても言わなくても、それをする人はするし、しない人は言われてもしないのだから、こうした放送は、うるさいだけで、無駄なのだ。
だが、日本では、こうした「無駄に過保護」な放送が、決して無くならない。
「ああしましょう、こうしましょう。ああしてください、こうしてください」

中島は、一人の「主体的に生きる大人」として、こうした「過干渉」が我慢がならなくて、30年以上にわたってこれに抵抗し、すっかり「変人」として知られるようになったが、日本社会の方は、少しも「まとも」にはならなかった。
話を戻せば、つまり「ネタバレ注意」という看板は、この種の「エセ過保護」であり「過干渉」の一種なのだと言えよう。日本人社会は、人が何歳になっても、「エセ過保護」「過干渉」であり、それを、日本人らしい「親切心」や「細やかな配慮」からなされるものだと、自画自賛的に自己肯定する。
しかし、すこし察しの良い人なら容易に気づくことだが、これらの「エセ過保護」や「過干渉」は、日本人らしい「親切心」や「細やかな配慮」からなされるものなどではなく、要は「責任逃れ」なのである。
例えば、駅において、前記のようなアナウンスが流れるのは、事故が起こった際に、電鉄会社の責任を、すこしでも軽くするための措置でしかない。「我々は日頃から、このように注意喚起をおこなっているのだが、その人は、それに従わなかったので、事故になってしまったのだ」とかいったことである。
要は、何かあった時の「予防線」として「あれにこ注意してください。これにも注意してください」と言っているのであり、決して、相手のことを思っての「親切心」から言っているのではない。その本音は「ここまで助言してあげているんだから、あとは自己責任ですよ」ということなのだ。
つまりこれらは、日本人が好きな「自己責任論」であり、特に「責任者」側が、なるべく責任逃れをするための「自己責任論」という、責任回避策なのである。

したがって、「ネタバレ」という言葉に、何の疑問も覚えないような人間とは、何も考えていない人間、責任者の側に飼いならされている人間、言葉に鈍感な人間、要は、頭の悪い人間だということになる。
一一「ネタバレ」という言葉を「主体的」に使っているのではなく、「ネタバレ」という言葉に、良いように使われているのが、こうした人たちなのだ。
だから、私は「ネタバレ」という「便利な言葉」を、なるべく使わないようにしている。そうした「便利な言葉」を何も考えないで使っていると、何も考えずに、与えられたパターンだけでものを書き、自分が書いているつもりになっている、中身のないバカになってしまうからだ。それを、恥ずかしいことだとも気づけない、バカになってしまうからなのだ。
「ネタバレ」という、当たり前に使われている言葉ひとつでも、ものを考えている人間と、考える習慣のない人間とでは、これだけの開きが生じてしまうのだが、私はこれが自慢になると思って書いているわけではない。
読んでもらえばわかるように、これは「当たり前」の話でしかない。ただ、その「当たり前」にも達しない、「過干渉」の「エセ過保護」に育てられた、頭の悪い「こども大人」が多すぎるに過ぎない。
だから、私は、中島義道同様に「変人」と思われるのを承知で、「バカばっかりだ!」と吹いて回らなければならないのである。
(2022年7月13日)
○ ○ ○
○ ○ ○

