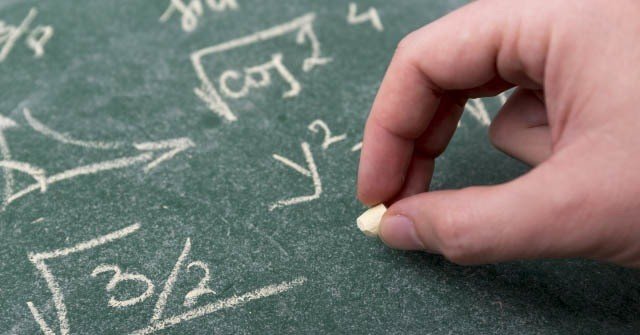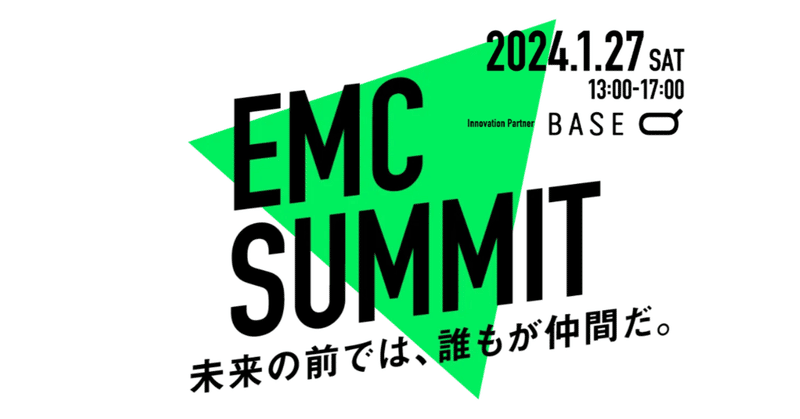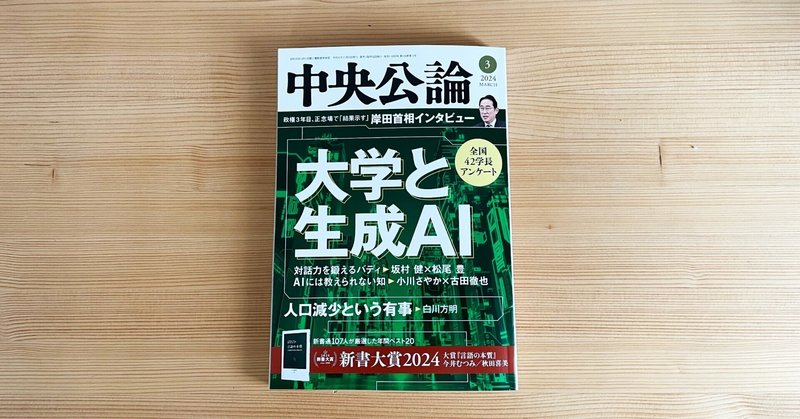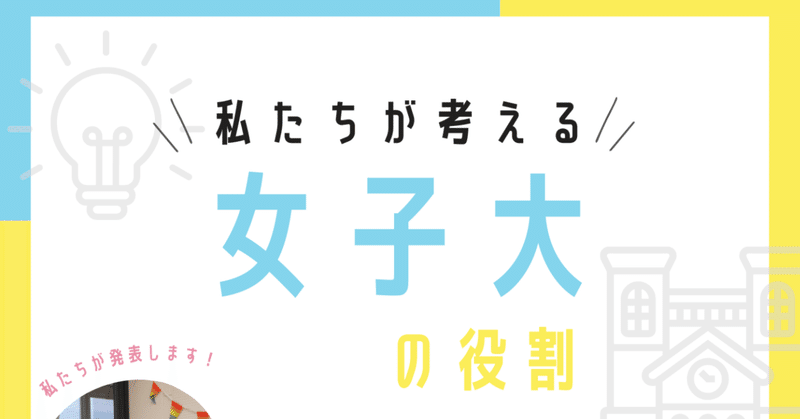#大学教育
独自のカルチャーに”浸れる”環境が人を育てる。武蔵野大学EMCのイベントから考える、大学で学ぶ意味とは何か
インターネット上に無料の学びがたくさんあるなか、大学で学ぶ意味とは何なのだろう?こういった問いは、メディアやネットの書き込みを見ていると定期的に目にします。私自身もたまに考える問いではあるのですが、今回、見つけた武蔵野大学のイベントはその答えの一つになるかもしれません。
スタートアップ界隈の”熱さ”を体現した大学イベント
では、どんなイベントなのかというと、「EMC SUMMIT −未来の前で
大学にしか成し得ない視点!? 西南学院大学のリリースから考える、よりよい教育を後押しするための広報活動
大学のプレスリリースには、イベント告知がテーマになっているものもよく目にします。今回、見つけた西南学院大学のリリースも、そんなイベント告知の一つなのですが、内容がなかなかユニークでした。こういう情報発信って大学だからこそだし、工夫次第で広報の可能性が広がるように感じます。
公開練習をプレスリリースすることの意味
ではどんなプレスリリースなのかというと、同大学の法学部公認学生団体「Seinan
影響するのは教育だけじゃない?近大の取り組みから考える。大学による生成AI活用のリスクと難しさ
第170回芥川賞の受賞者がChatGPTを一部使って小説を書き上げたことで話題になっていますが、生成AIの発展はほんと目覚ましいものがあります。今回、見つけたプレスリリースはそんな生成AIの大学での活用についてです。近畿大学の取り組みなのですが、今後、こういうのが増えていくのかもしれませんね。
生成AIを使って大学職員の業務効率を上げる
今回のリリースは、近畿大学でChatGPTに使われている
変化の過渡期だからこそ考えたい。フェリス女学院大が取り組む、学生の発表で問いかける”我々とは何か?”
歯止めのきかない少子化、コロナ禍を経ての学びや学生意識の変化、にわかに高まっている学び直しへのニーズなどなど。大学の置かれた状況が刻々と変わってきているのは、大学関係者でなくても、なんとなく感じている人は多いように思います。今回、見つけたフェリス女学院大学の取り組みは、こういった変化の過渡期だからこそ、より大事になる取り組みだと感じました。大学はどうあるべきかを考えるのは、大学のマネジメント層だけ
もっとみる育てると増やすは違う?異色の講演会から感じる、ベンチャー企業創出拠点づくりをめざす近畿大学の本気
つい先日、近畿大学のインキュベーションの話題を取り上げたところなのですが、今回も近大のインキュベーションネタです。見た瞬間は、これってどうなの!?と感じたのですが、あれこれ考えた結果、一周まわってこれはこれで有りなのかなぁと思うに至りました。何であれ、目的さえ明確なら、そこに至るアプローチは自由なのかもしれません。
近大「KINCUBA Basecamp」で開催する異色の講演会
今回、取り上げ
ヒントは成蹊大の特設サイトにあり!? “学び方のレシピ”の集積から考える「学修者本位の教育」への向き合い方。
「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」で示された「学修者本位の教育への転換」は、これからの教育の方向性を示す指針として、どの大学も大いに意識しているように思います。とはいえ、これをどのようにすれば教育に実装できるのでしょうか。多くの大学が模索段階だとは思うのですが、このたび成蹊大学が公開した特設サイトは、この難問を考えるうえで、いいヒントになりそうに感じました。
複雑に絡まり合いながら
ChatGPTは、大学の学びを加速させるのか壊すのか。いま大学が求められる生成系AIとの向き合い方を考える。
インターネットやスマートフォンの登場で、私たちの生活が大きく変化したように、いま話題になっているChatGPTも、私たちの生活を根っこのところから変えていくテクノロジーのように感じています。連日、ChatGPT関連のニュースが出ており、各大学もこのオーパーツの卵とどう向き合うか、いろんなスタンスを表明しています。進化のスピードが早すぎて、来月ぐらいにはまた状況が変わっているかもしれないのですが、と
もっとみる時代は超効率重視?近大の調査から見えてきた、新たな学生の学びスタイルをどう受け止めるかについて考える。
コロナ・パンデミックがはじまって2年半が過ぎました。アフターコロナの社会はどうなるのか?みたいなことが話題にはあがるものの、コロナがどこかのタイミングできれいに収束して、コロナのない世界がはじまる、というのは、おそらくないように感じます。
グラデーション的に変化しつつ、気がつけばコロナがあまり気にならない、コロナと共存した社会になっていた……、そういうのが現実的なのではないでしょうか。であれば、
”対面の価値“の最大化は、大学キャンパスだけではなし得ない。近大が取り組む、大学街活性化策の意義を考える。
新年度に入って、学生たちがキャンパスに戻ってきました。活気のある大学の風景やざわめきはやっぱりいいもので、構内を歩いているだけで元気をもらえます。その一方で過去2年間のキャンパスがとてもイレギュラーな状況だったのだと、あらためて感じさせてもくれます。
このイレギュラーの状況は大学だけでなく、その周辺、つまり大学街にも大きな影響を与えました。今回、見つけた近畿大学の取り組みは、活気がもどった大学が
そもそも別物!?大学のこれからを左右するかもしれない、これからのキャリア教育&支援について考える。
今回、取り上げるのは立教大学のオンラインイベントです。オンラインイベント自体もう今となればめずらしくないうえ、このイベントが取り上げているテーマもそこまで突飛なわけではありません。でもこれは……と思ったのは、このイベントがキャリアイベントと銘打っていたからです。大学のキャリア教育、キャリア支援というのは、これから先ものすごく変わっていくんだろうなと、このイベントを見つけてしみじみと思いました。
これから支持される学びは、いち大学では成立しない?学びのオンライン化がもたらす、新たな学びの評価軸を考える。
魅力的なオンラインの学びにある2つの共通点オンライン授業という学び方が大学教育に本格的に取り入れられるようになり、なんだかんだでもうすぐ1年が経とうとしています。当初は対面授業の代替として、対面でやってきたことを何とかしてオンラインに置き換えようとする取り組みだったように思います。でも、時間が経ち、学びのコツや特徴がわかるようになってきて、じわじわと内容が変化してきているようです。今回はそんな新し
もっとみる変わらなければ、変われない。近大と成蹊大が先陣を切る、オンライン教育を加速させる教育連携が熱い。
今なお続く新型コロナの一連の騒動のなかで私たちが手に入れたものに、思いのほかリモートでやれるという実感と、それを支援するサービスやテクノロジーというのがあるように思います。大学の遠隔授業は、まさにその成果を象徴するものでした。この成功体験を踏まえ、遠隔授業が発展すると、大学のあり方が大きく変わるだろうと考える大学関係者は少なからずいるし、ネット等の記事にもそういった論調のものを目にします。私も、そ
もっとみる