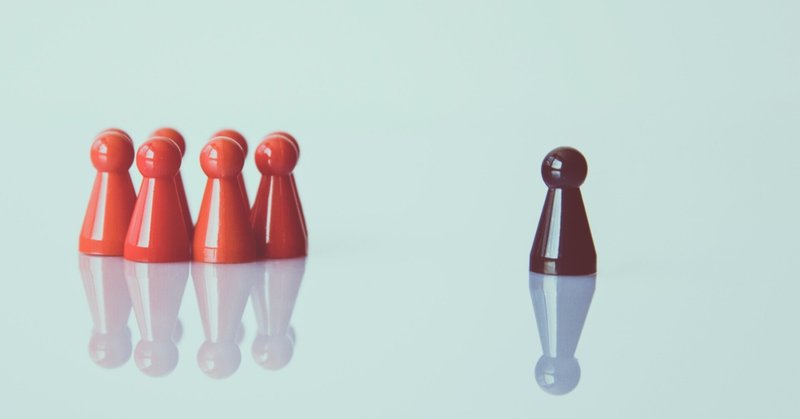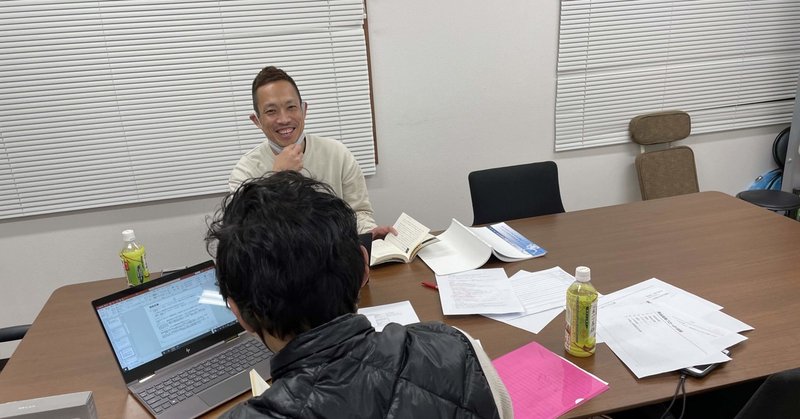- 運営しているクリエイター
2020年12月の記事一覧
一見「優秀そう」なリーダーが、メンバーをつぶす諸悪の根源になっていないか
リーダーだけはいつも元気なのに、メンバーには覇気がなく、チーム全体の雰囲気もどんよりしている。よく見られる光景だ。この場合、外部から一見しただけだと、「せっかく良いリーダーが率いているのに、やる気や能力の足りないメンバーが集まっているのか」というようにも見えてしまう。
しかし、実際はそうではないケースはとても多い。それがこの、一見すると「優秀そうで、いつも元気な」リーダーの行動こそが、諸悪の
大事にしたいプロセス志向
『神は細部に宿る』
という言葉は昔の建築家か大工かが言った言葉らしいですが、ヴァールブルク、フローベル、アインシュタイン、ル・コルビジェ、ニーチェ等、錚々たる偉人達も用いていることからもわかるように、売上さえ上がれば、利益さえ出ればいいってものではないものです。
目先だけ見ている人にとってはそれでもいいのかもしれませんが、目先だけを追えば追うほど「木を見て森を見ず」状態に陥り、中長期的な継続が
未契約のまま進めたプロジェクトが途中で頓挫。「お金は払いません」は通用するのか
システム開発のプロジェクト活動は、言ってみれば長い長い距離を走るマラソンのようなものです。
しかし本物のマラソンは選手が1人でゴールを目指し、ペースを上げるも落とすも、あるいは体調に異常を来して途中でレースをやめてしまうも、全て走っている本人が判断できます。
けれどもシステム開発においては、ユーザーとベンダーが協力してゴールを目指すため、マラソンと言うよりは
お客さまとの間では「二人三脚」
コモディティ化とは、価値をデザインすること
最近よくコモディティ化という言葉を耳にします。この言葉を聞くたびに脳裏をほんの一瞬ちらりとかすめる違和感があります。うまく言語化できるかわかりませんが、、、そんな想いをnoteにしてみたいと思います。
コモディティ化とは経済とかマーケティング用語らしいのだけども、斬新だった商品も時を経てやがて市場に多くの同類の商品が出回るようになりメーカーごとの個性がなくなり一般化していく状態のことです。
コ
プロジェクトマネジメントの資格を取ってみよう
やあどうも。
あおはるおじさんだ。
今週は勉強ウィークということで
PMOの資格勉強に挑戦していました。
↓
何事もプロジェクトであるプロジェクトとは何か?
ここでは「独自の目標を設定し、期限までに達成させる一連の活動」と定義されておりまして、前例のないことに挑戦することを指します。
甲子園を目指すのもプロジェクトだし、文化祭の出し物を作るのもプロジェクトだし、身近なところでは友達と旅行
『聴く』力が経営力を左右する②|聴き合う組織をつくる『YeLL』のnote
こんにちは。エールの篠田真貴子です。
前回は、「きくこと」が経営にとって大切とは、どういうことかをお話ししました。
経営においては、新しい価値を創造し(イノベーション)、 組織の人々の方向を揃えてこれを実現し(社内コミュニケーション)、その過程で様々なステークホルダーと理解をすり合わせていくこと(社外コミュニケーション)が必要です。
これらの活動全てにおいて対話、つまり背景や文脈が異なる相手や、
『聴く』力が経営力を左右する①|聴き合う組織をつくる『YeLL』のnote
こんにちは。エールの篠田真貴子です。
私は、様々なビジネスリーダーにお会いする機会があります。
「エールは、社外人材がオンラインで1on1を提供する会社です」と自己紹介をすると、「傾聴ですか。部下の話を遮らずに聞けってやつですよね」と反応いただくことが少なくありません。
「きく」ことを研修などで学んだことがある方がたくさんいるんだなぁ、と嬉しくなります。同時に、「きく」を狭く捉えてしまっても