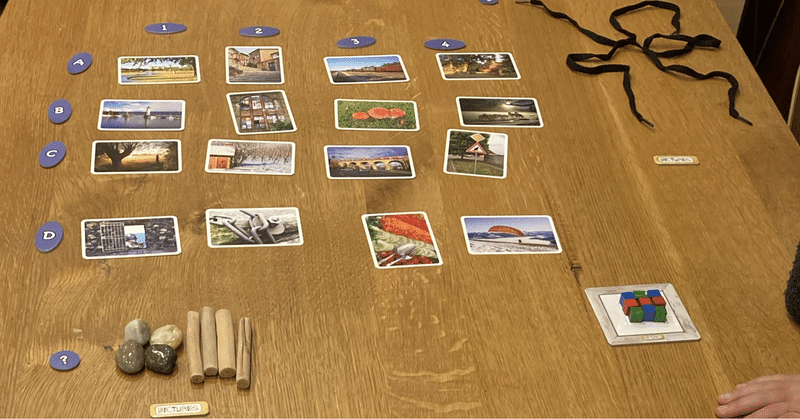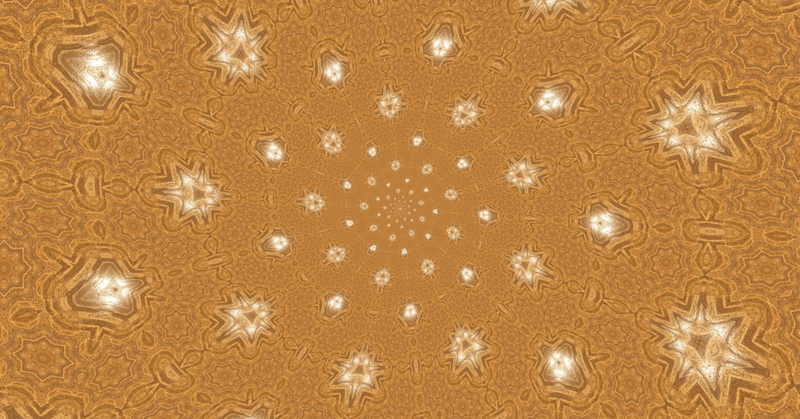#子育て
7月11日(お向かいさん)
長女の下校時間が早かったのをうっかり忘れ、一時間半遅れて帰宅。扉には張り紙。
「むかいの柴田です。長女ちゃんを預かっています。」
やってしまった。
すぐに向かいの家へ。
幸いなことに次女と歩いているといつも優しく声をかけてくれる柴田さんは、熱中症を心配して長女にアイスを食べさせ、涼しいクーラーの部屋で過ごさせてくれていた。すぐに家から出てきてくれた柴田さんは、
「ごめんねー!もっと早く気付
6月30日(子どものしたいこと)
ティッシュを出したがる子どもの話を聞く。うちの子も二人ともティッシュ期があり、一瞬の隙でも与えると部屋中ティッシュまみれになったものだ。
この時期は、わたしは自分の片づけたい欲求と子どもの散らかしたい欲求が闘っていた気がする(一歳半から二歳前くらい?)。
そんなときにちょっと癒されたのは『ちらかしぼうや』という絵本。
最後に、「いいさ、また片付けるさ」みたいなセリフがとても印象的で、なんだか微
329日目(ぐずる子どもを楽しい気持ちにさせて保育園まで行く方法)
「今日は保育園だよ」
「行かない!おうちにいる!」
こんなやりとりから始まった祝日明けの木曜日。さあ、どうしたものか
妻をあっさり見送るいつもなら、
「母ちゃん送りにいく」
と言いだすの次女だが、今日はあっさり
「バイバイ。」
母ちゃんになんともそっけない態度。昨日はずっと「母ちゃんがいい」と言い続けて、長女が一緒に遊ぼうとすると突っぱねる始末だったのに。
妻曰く、
「きょうは昨
察する(子どもの気持ちを)
気持ちを察して欲しいよく女の人が口にする言葉だ。私たち男はあまりそんなことを考えないばかりに、直接的にきいたり、聞かずに行動したり、何も言われないからやらなかったりすることで、投げかけられる。女性はなぜ、この言葉を口にするのだろう。
女の発達心理学小さい子どもを見ていると、言語能力が男と女で明らかに違う。理由はよく分からないが、これは子育てや教育の現場にいたことがある人はよく経験することだ。女の