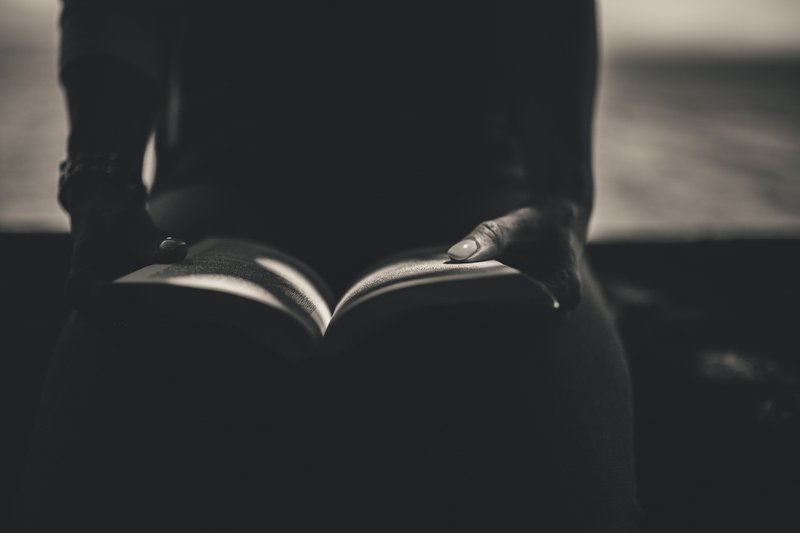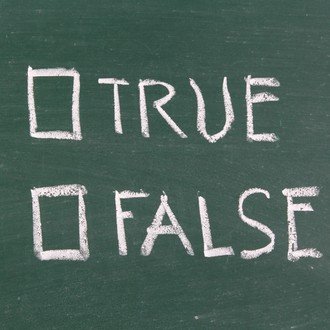#ネット
『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件
▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。
筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね
『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。
▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では
「偽情報経済」(216頁)
という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ
『「いいね!」戦争』を読む(17)SNSは「承認」が最大の目的の件
▼前号では、「フェイクニュース」という言葉が広まっただけでなく、「フェイクニュース」の「定義」そのものが変えられてしまったきっかけが、アメリカ大統領選挙であり、なかんずくトランプ氏の行動だったことに触れた。
「フェイクニュース」は、もともとの「真実でないことが検証可能なニュース」という意味から、「気に入らない情報を侮蔑(ぶべつ)する言葉」、つまり、「客観的」な言葉から、とても「主観的」な言葉に変
『「いいね!」戦争』を読む(16) 「フェイクニュース」誕生の論理
▼ここ数年、ネットの中で「嘘(うそ)」が蔓延(まんえん)するスピードが、やたら速くなった。
すでによく知られるようになったある常識について、『「いいね!」戦争』がわかりやすく説明していた。
ちなみに2019年7月10日の21時現在、まだカスタマーレビューは0件。
▼MIT(マサチューセッツ工科大学)のデータサイエンティストたちが、ツイッターの「噂の滝(ルーマー・カスケード)」(まだ真偽が検証
『「いいね!」戦争』を読む(15) 「アラブの春」が独裁に繋がった理由
▼「アラブの春」が、なぜ独裁主義に吸収されてしまったのか。『「いいね!」戦争』は、「確証バイアス」や「エコーチェンバー」現象などの知見を使って絵解きしている。
▼毎度おなじみ、カスタマーレビューはまだ0件だ。2019年7月10日10時現在。
▼以下の引用箇所を読めばわかるが、この経緯から引き出せる教訓は、「アラブの春」だけに限った話ではない。ジョージ・ワシントン大学公共外交・グローバルコミュニ
『「いいね!」戦争』を読む(14) 「確証バイアス」は脳の最悪の衝動の件
▼「インターネットと戦争と生活」について考えさせられる名著『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」は、人間の「脳」をめぐるネット戦略の中間報告になっている。
▼2019年7月8日現在で、まだカスタマーレビューは0件。0件のまま半月も経つと、なんだか面白くなってきた。
▼前回は、記事が真実であるかどうかは重要ではなく、「なじみがあるかどうか」で判断が分かれる、と
『「いいね!」戦争』を読む(13)記事は「真実」でなくても構わない件
▼今号で紹介するのは、「オンラインの生態学」とでもいうべきものだ。
『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」の続き。
▼前号は、最近よく目にする「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」の簡単な解説だった。
▼ところで、『「いいね!」戦争』には、まだアマゾンでカスタマーレビューが1件もつかない。2019年7月7日現在。
▼先に「オンラインの生態学」と書いた
『「いいね!」戦争』を読む(12) 「友だち」の数ですべてが決まる件
▼人間には、仲間を求める本能がそなわっている。それが「ホモフィリー」(同質性)だ。前号では、この「ホモフィリー」が、SNSとのつきあい方を考えるキーワードであることにちょっとだけ触れた。
▼『「いいね!」戦争』では、この「ホモフィリー」(同質性)のくわしい仕組みを説明しているが、その説明の中に、さらに2つのキーワードが入り込んでいるので、一つずつチェックしていきたい。
2つのキーワードというの
『「いいね!」戦争』を読む(11)「事実」とは「合意」の問題である件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」に入る前に、第4章のラストに紹介されている術語(ターム)に触れておこう。
「ガスライティング」
これは〈パートナーが真実を操作もしくは否定することによって相手を支配しようとする関係を指すようになった〉(188頁)ということで、不思議なネーミングの由来は、有名な映画(もとは舞台)の「ガス燈」だ。
悪い夫の策略によって、
『「いいね!」戦争』を読む(10)ロシアの「荒らし工場」体験記
▼ウェブ戦略ではロシアが一歩先を行っている現状が『「いいね!」戦争』に書かれていた。キーワードは「4つのD」。
▼相変わらず、アマゾンのカスタマーレビューは0件のまま。2019年7月4日現在。
▼具体的には「荒らし(トロール)工場」というものをたくさんつくる。
プーチンを絶賛する青年運動組織「ナーシ」や、政府が焚(た)きつけた企業十数社が母体になり、デタラメをネット世界に蔓延させる、圧倒的な
『「いいね!」戦争』を読む(9)ロシアが編み出した「4つのD」
▼正確には、ロシアの戦略に対して、アメリカのシンクタンク研究員が名づけたものだが、「4つのD」というキーワードがある。
これが、『「いいね!」戦争』の理論的な一つのクライマックスだ。
▼相変わらず、2019年7月3日現在でカスタマーレビューが1件もない。謎だ。
▼ロシアのネット戦略の前提は、ロシア連邦軍参謀総長だったヴァレリー・ゲラシモフ氏が唱えた、
「政治的・戦略的な目標を達成するための
『「いいね!」戦争』を読む(8) 国がネット対策に本気出した結果www
▼『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第4章は、「帝国の逆襲 検閲、偽情報、葬り去られる真実」というタイトル。
なんだか恒例になっちゃったが、本書について、2019年7月2日現在でもカスタマーレビューがない。不思議だ。
▼第4章では、まず政府がインターネットの接続速度を遅くする「スロットリング」について紹介されている。
〈必要不可欠なオンライン機能は継続しつつ、大規模なつなが
『「いいね!」戦争』を読む(7) 戦争犯罪を暴くアマチュアたち
▼『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第3章のラスト。3つのキーワード、「クラウドソーシング」「市民レポーター」「オシント革命」のうち、最後の「オシント革命」について。
本書について、2019年6月30日のお昼現在でもカスタマーレビューがない。不思議。
▼「オシント革命」は、一つめのキーワード「クラウドソーシング」によって生まれたものだ。
「オシント」は「OSINT」で、「オ
『「いいね!」戦争』を読む(6) 「市民レポーター」に敬意を表する件
▼前号では、『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第3章から、3つのキーワード、「クラウドソーシング」「市民レポーター」「オシント革命」を取り出した。
今号は「市民レポーター」について。適宜改行。しかし、2019年6月29日現在で、まだカスタマーレビューがついていない。不思議。
▼「市民レポーター」というのは、「命がけ」の場合がある。
〈ソーシャルメディアを使って、既成メディア