
石牟礼道子 『苦海浄土』 : イタコ作家の秘められた〈実像〉
書評:石牟礼道子『苦海浄土 わが水俣』(講談社文庫)
解説を読んで驚いた。
私は、講談社文庫の旧版(1972年刊)で読んだので、解説は、渡辺京二による「石牟礼道子の世界」である。
なお、講談社文庫の現在の新版の「解説」がどうなっているのかは知らない。
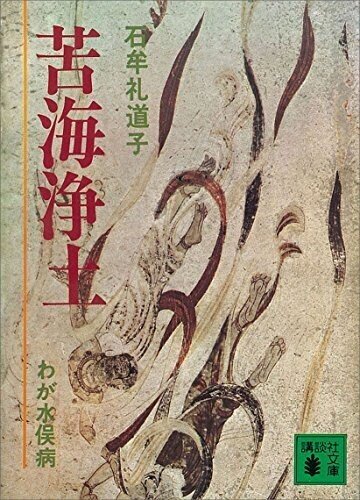
渡辺京二は『熊本市在住の日本の思想史家・歴史家・評論家。代表作に幕末・明治期の異邦人の訪日記を網羅した『逝きし世の面影』などがある。』(Wikipedia)人で、私もこの人の比較的新しい著作である『バテレンの世紀』(新潮社・2017年)を読んでいる。
渡辺と石牟礼道子との関係は、前記解説「石牟礼道子の世界」に、
『(※ 本書『苦海浄土』の)「あとがき」にもあるように、本書の原型をなす『海と空のあいだに』は、昭和四十年十二月から翌四十一年いっぱい、私が編集していた雑誌「熊本風土記」に連載された。』
とあるとおりで、言うなれば、渡辺は、作家・石牟礼道子と『苦海浄土』の誕生に立ち会った、「生みの親」の一人とも呼んで良い人物である。
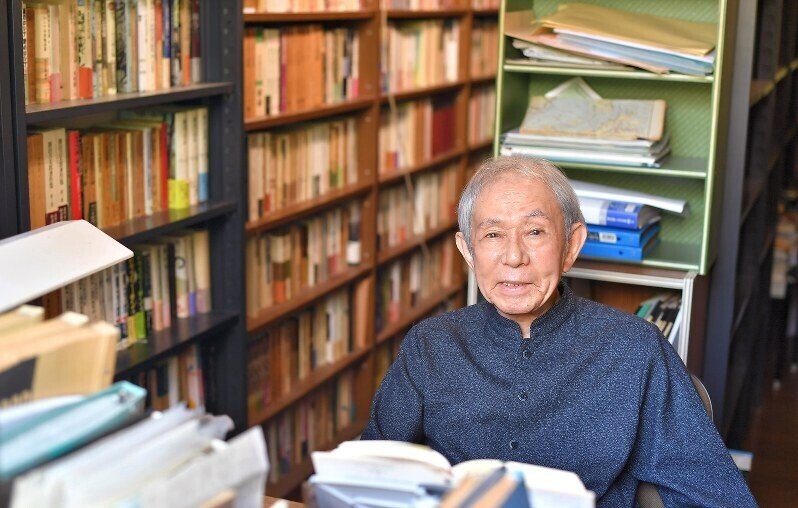
その渡辺が、この解説「石牟礼道子の世界」で何を書いているのかと言えば、石牟礼の『苦海浄土』は「世間でそう思われているようなノンフィクション(ルポルタージュ)ではなく、フィクションだ」と断じた上で、それを「正当化している」のである。
現実の事件である「水俣病」問題について書かれた『苦海浄土』は、多くの人にとっては「ノンフィクションとしての、ルポルタージュ」として読まれてきた。
「水俣病患者の痛み」を、この作品を通してこそ知った、という人は少なくないはずだ。
だが、解説者の渡辺に言わせれば、この作品が「ノンフィクションとしての、ルポルタージュ」だと思うような人は、「文学」というものが、まったくわかっていない、のだそうだ。
渡辺はまるで、「文学」の範囲を確定する権限を持った権威ででもあるかのように、そう厳しく断じた上で、どう読んだって、『苦海浄土』は、石牟礼の『私小説』であって、「現実」を「そのまま忠実に描いた作品」などではない、と明言し、保証する。
『私小説』とは、どういうことかというと、この作品は「水俣病」と「水俣患者」に取材し、それをもとに、「水俣患者に仮託して、石牟礼が、自分の水俣への思いとその内面世界を書いた小説」だ、ということだ。
一一だが、それは「ペテン」ではないのか?
○ ○ ○
石牟礼道子の『苦海浄土』が「水俣病」を扱い、世に「水俣病」の存在を知らしめた作品であることは、もちろん私もよく知っていたし、この作品を『世界文学』とまで絶賛する人のいることも知っていたから、「水俣病」の問題と合わせて、いずれは読まなければならない作品だと、長らくそう思ってきた。
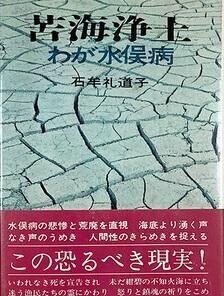

(1969年・昭和44年初版単行本の口絵)
実際、もう二十年以上も前に、私は『苦海浄土』『天の魚 続・苦海浄土』や『椿の海の記』を文庫本で買い揃えていたのだが、その折には、他の本を優先してしまい、その3冊を積読の山に埋もれさせてしまった。
しかし、昨年(2021年)、ジョニー・デップの主演で、水俣の惨状を世界に報じた写真家ユージン・スミスの活躍を描いた、アンドリュー・レヴィタス監督の映画『MINAMATA -ミナマタ-』が公開されたのでこれを観、続いて今年は、『ゆきゆきて、神軍』などで知られるドキュメンタリー映画の巨匠・原一男監督が20年をかけて制作した、6時間に及ぶドキュメンタリー映画『水俣曼荼羅』が公開されたので、これも観た。
つまり、いよいよ、本命たる『苦海浄土』を読む準備は整ったということで、今回、二度目か三度目かは失念したが、また『苦海浄土』を贖い、やっと読むことができたというわけである。
一一ところが、『苦海浄土』本編を読み終わって、どうにも「引っかかる」ところがある。
何かといえば、この作品は「ノンフィクション」なのか「小説(の一種)」なのかということだ。
少なくとも、この作品を「ドキュメンタリー」と呼ぶのは、どうにもしっくり来ない。
正確に言うならば、この『苦海浄土』は「ノンフィクションの中に、フィクションが、フィクションだという断りなしに、組み込まれている作品」なのである。
本作において、水俣病の「歴史的経緯」と「事実関係」を紹介した部分については、「ノンフィクション」と呼んで差し支えのないものになっており、その部分については、特別優れたものではない。ここに書かれている程度のことなら、もっと緻密で客観的で正確な本が数多く刊行されているであろうことは、容易に想像できる程度のものでしかなく、この「ノンフィクション」部分の価値は、その「先駆性」にあったと言えるだろう。だから、いま読めば、「水俣病」に「完全に無知な人」以外は、特段どうということのない内容なのである。
本書『苦海浄土』は、全7章からなっており、第一章と第二章は、こうした「ノンフィクション」部分だと言って良いだろう。私は、このあたりを読んでいるときは「それほどの作品でもないじゃないか」と思った。
ところが、第三章「ゆき女きき書」に入ると、その内容や文体が一変する。
この第三章は、実在の水俣病患者の女性・坂上ゆきについて書いた部分なのだが、「前書き」的紹介ののちに、坂上ゆきの「一人称」の語りが始まる。
第三章は「ゆき女きき書」であり、坂上ゆきが語ったことを、石牟礼道子が『きき書』するという体裁になっており、この坂上ゆきの「語り」が、きわめて「文学的」であり、それまで「ノンフィクション」として凡庸とも言えた『苦海浄土』が、ここからガラリとその相貌を変えて、輝きだすのだ。
私は、この『きき書』部分を読んで、「これか、これがあるから、『苦海浄土』は名作と評価されるようになったのだな」と、完全に腑に落ちたのである。
そして、こうした『きき書』は、取材対象を変えて、第四章、第五章と続き、第六章では石牟礼自身と水俣の関わりが紹介され、第七章では、全編のまとめ的に、再び「ノンフィクション」的な事実関係が語られて、本作『苦海浄土』は、いったん幕を降ろすのである。
つまり、端的にいえば、本作『苦海浄土』の魅力とは、「ノンフィクション」部分にはなく、それを「額縁」として語られる『きき書』部分にこそある。
そこが「文学的」であり、読む者をぐいぐいと惹きつけるのだ。
だが、この『きき書』は、坂上ゆきらの語ったことを「忠実に再現したもの」ではない。
彼女たち水俣病患者は、その病による言語障害を発症しており、きわめて聞き取りづらい発話しかできないからだ。
例えば、こんな具合である。
『う、うち、は、く、口が、良う、も、もとら、ん。案じ、加え、て聴いて、はいよ。う、海の上、は、ほ、ほんに、よかった。』(P127)
ところが、これを、石牟礼道子が「案じ、加えて(どういうことを言いたいのかを推察して読み取り、解釈を加えて)」書くと、次のようなものになるのだ。
『一一うちは、こげん体になってしもうてから、いっそうじいちゃん(夫のこと)がもぞか(いとしい)とばい。見舞にいただくもんなみんな、じいちゃんにやると。うちは口も震ゆるけん、こぼれて食べられんもん。そっでじいちゃんにあげると。じいちゃんに世話になるもね。うちゃ、今のじいちゃんの後入れに嫁に来たとばい、天草から。
嫁に来て三年もたたんうちに、こげん奇病になってしもた。残念か。うちはひとりじゃ前も合わせきらん。手も体も、いつもこげんふるいよるでっしょが。自分の頭がいいつけんとに、ひとりでふるうとじゃもん。それでじいちゃんが、仕様ンなかおなごになったわいちゅうて、着物の前をあわせてくれらす。ぬしゃモモ引き着とれちゅうてモモ引き着せて。そこでうちはいう。(ほ、ほん、に、じ、じぃ、ちゃん、しよの、な、か、お、おな、ご、に、なった、な、あ。)うちは、もういっぺん、元の体になろうごたるばい。親さまに、働いて食えといただいた体じゃもね。病むちゅうこたなかった。うちは、まえは手も足も、どこもかしこも、ぎんぎんしとったよ。
海の上はよかった。ほんに海の上はよかった。うちゃ、どうしてもこうしても、もういっぺん元の体にかえしてもろて、自分で舟漕いで働こうごたる。いまは、うちゃほんに情なか。月のもんも自分で始末しきれん女ごになったもね……。』(P127〜128)
こうした「語り」に、胸を打たれない人はいまい。
『苦海浄土』の第三章、第四章、第五章は、このような『きき書』であり、この部分こそが、多くの読者をとらえ、水俣の問題に目を向けさせたのは、間違いのないことであり、その点で石牟礼道子の功績の大きさは、誰人にも否定できないものだった。
だが、「引っかかり」を覚えたのは、こうした『きき書』部分での、水俣の素朴な人たちの「語り」が、その「文体」が石牟礼道子の手になるものだとしても、あまりに「文学的に美しい」という点である。
こう言ってはなんだが、発話に詰まりながらとはいえ、田舎の素朴な漁民たちに「このようなことが語り得るだろうか」という疑問を、私は持ったのである。

無論、先にも引用した部分に、水俣病患者である坂上ゆきの『案じ、加え、て聴いて、はいよ。』とあるとおり、実際には、ゆきは、このとおりの「内容」を語ってはおらず、石牟礼が「案じ、加え(想像で補い、書き加えた)」部分も少なからずあるのだろう。それをいちがいに非難するつもりはないが、『きき書』の部分が、あまりにも「文学的に過ぎる」ので、これは「ノンフィクション(きき書)としては、やりすぎているのではないか」と疑ったのである。
つまり、この文学的な『きき書』の部分は、いわゆる「事実を素材にして書かれた、フィクション(創作)」なのではないかと、そう疑われたのだ。
なぜ、こうした「ノンフィクション(きき書)としては、やりすぎているのではないか」と、問題にするかというと、それは「水俣病」は、「被害者」だけの問題ではなく、「加害者」も現に存在する問題だからである。
たしかに「うまく語れない被害者」の「思いを汲んで」、「被害者になり代わって、被害者の思いを代弁する」こと自体は、かまわないと思う。
しかし、それが行きすぎて、石牟礼が「勝手に想像を膨らませた、想像の産物」を「水俣病被害者の思い」だとするのは、やりすぎではないかと思うのだ。それは所詮「解釈」でしかなく、「事実」ではないだろう、ということだ。
たしかに、石牟礼は、水俣病患者に寄り添い、水俣病患者の利益にかなう仕事をし、「なり代わって語られた言葉」については、その患者自身も「納得」したり「よく書けている」あるいは「私とは思えんくらいに、よう書けとるばい」くらいの評価や承認や支持を与えたのかもしれない。
だが、そうした「半創作の証言(きき書)」を持って、非難される者、悪役を振られ、憎まれる者は、堪ったものではないし、そもそも、そういうやり方は「フェアではない」のではないだろうか。
水俣病を発生させた「チッソ株式会社」は、その「事実行為」によって断罪されるべき「加害者」だし、事実そうであるのに、その加害責任についての「情状証拠」に、この『きき書』もどきの「半フィクション」が混入するのは、被害者側にとっても、むしろマイナスなのではないか。
事実において断罪できる相手を断罪するのに、どうして「作り事」を混入させなければならないのか。

世間の目を惹き、世間の同情を惹いて、自分たちの味方につけられるなら、そんな「細かいこと」など、どうでもいいではないか、ということなのだろうか?
実際問題として、少々「うさん臭い手口」を使おうと、それで世間の同情を惹き、世間の目を惹きつければ、裁判闘争のおいても、政治的闘争においても、「有利になる」というのは事実だろう。
だが、だからと言って、こんなやり方を容認して良いのか? 「勝てば官軍」で良いというのだろうか?
一一実際、石牟礼道子の『苦海浄土』を読んで、このような疑問を持った人は少なくなかったのだろう。
「この作品は、ノンフィクションなのか、フィクション(小説)なのか、それとも、その両方の合わさった、ヌエ的な作品と呼ぶべきなのか?」
考えてみれば、『苦海浄土』という作品は、そのあたりが「曖昧にされてきた作品」だったのではないだろうか。
世間一般の印象は「水俣の現実を描いた作品」ということで「ノンフィクション」に近い印象でありながら、本の売り方としては「文学」という側面が強調され、要は「小説」であり「ノンフィクションではない」ということを、におわせている。
だから、実際に読んでみるまでは、この作品は、その位置付けが、いまいちハッキリしないのだ。
そして、そんな作品だからこそ、『世界文学』とまで高く評価する文学者もいる反面、一般的な「日本文学史」において、この作品が大きく扱われたり、大きく位置付けられるのを目にする機会がないように、私は思うのだ。
つまり、この作品の評価は、大きく「分かれている」のではないだろうか。
一方には、その「文学性」を高く評価すると同時に、この作品が「水俣病」問題で果たした社会的功績をも、抱き併せで高く評価する人たちがいる一方で、「ノンフィクションという枠組みの中に、しれっとフィクションを組み込む」というような「インチキ臭さ」を容認できないと評価する文学者も少なくないのではないか。
ただ、後者の人たちは、『苦海浄土』が「水俣病」問題で果たした、大きな「社会的役割」を考慮して、「あえて批判しないでいる」だけなのではないか。
文学の問題、あるいは、倫理的な問題としては、言いたいことがいろいろあるけれども、苦しんでいる水俣病患者の人たちのことを考慮して、患者たちの「守護神」になっている石牟礼道子への批判を、あえて控えてきたのではないだろうか。

だからこそ、石牟礼道子の旧友であり、恩人でもある、つまり、ひと一倍関係の深い渡辺京二は、『苦海浄土』は徹頭徹尾「文学」作品であり、石牟礼道子の言わば「私小説」であり、要は「フィクションであって、ノンフィクションなどではあり得ない」と言い切り、この作品が「ノンフィクション」だなどと思って読むのは、それは読む方の間違いであり、能力が無さすぎるのであって、そうした「誤読」の責任は「石牟礼道子にはない」と、この文庫解説で、石牟礼の「擁護・救助・免責」を為そうとしたのではないだろうか。
○ ○ ○
『 石牟礼氏はこのような事態(※ 水俣病問題)の展開に、つとめてよくつき合って来たといってよい。それは彼女の責任であったわけであるが、そういう経過の中で、彼女にある運動のイメージがまとわりつき、彼女の著作自体、公害告発とか被害者の怨念とかいう観念で色づけして受けとられるようになったのは、やむをえない結果であった。
しかし、それは著者にとってもこの本にとっても不幸なことであった。そういう社会的風潮や運動とたまたま時期的に合致したために、この優れた作品は、粗忽な人びとから公害の悲惨さを描破したルポルタージュであるとか、患者を代弁して企業を告発した怨念の書であるとか、見当ちがいな賞賛を受けるようになった。告発とか怨念とかいう言葉を多用できるのは、むろん文学的に粗雑きわまる感性である。それは文句なしにいやな言葉であり、そういう評語がこの作品について口にされるのを見るとき、その誕生に立ち合ったものとして、私はやりきれない思いにかられる。本書が文庫という形で新しい読者に接するこの機会に、私は、本書がまず何よりも作品として、粗雑な観念で要約されることを拒む自律的な文学作品として読まれるべきであることを強調しておきたい。』(P308〜309)
ここで、渡辺が何を言っているのかといえば、それは、
一一『苦海浄土』は、元来「文学作品」であるのだから、それが仮に、結果として「社会的な影響」を行使したとしても、その事実において、この作品や作者が「社会的な責任」を負わなければならない筋合いなどない。
この作品を「社会告発的なルポルタージュ」作品だと読んだのは、読者の「文学的無能力」による「誤読」に過ぎず、それは作者である石牟礼道子の責任ではない。
むろん、石牟礼は、個人として「水俣問題」に誠実に関わってきた。そのせいで、誤解を招く側面があったかもし得ないが、しかしそれは、作者個人と小説作品を区別できない、読者の無能力の責任でしかなく、石牟礼の責任とは言えない。
一一と、大筋こういうことだ。
『 実をいえば『苦海浄土』は聞き書きなぞではないし、ルポルタージュですらない。ジャンルのことをいっているのではない。作品成立の本質的な内因をいっているのであって、それでは何かといえば、石牟礼道子の私小説である。
(中略)
私のたしかめたところでは、石牟礼氏はこの作品を書くために、患者の家にしげしげとと通うことなどしていない。これが聞き書だと信じこんでいる人にはおどろくべきことかも知れないが、彼女は一度か二度しかそれぞれの家を訪ねなかったそうである。「そんなに行けるもんじゃありません」と彼女はいう。むろん、ノートとかテープレコーダーなぞは持って行くわけがない。彼女が患者たちにどのようにして接触して行ったかということは、江津野埜太郞家を訪なうくだりを読んでみるとわかる。彼女は「あねさん」として、彼らと接しているのである。これは何も取材のテクニックの話ではない。存在として彼女がそういうものであって、そういうふれあいの中で、書くべきものがおのずと彼女の中にふくらんで来たことをいうのである。
(中略)
といったふうに続けられる対話が、まさか現実の対話の記録であるとは誰も思うまい。これは明らかに、彼女が自分の見たわずかの事実から自由に幻想をふくらませたものである。しかし、それならば、坂上ユキ女の、そして江津野老人の独白は、それとはちがって聞きとりノートにもとづいて再構成されたものなのだろうか。つまり文飾は当然あるにせよ、この二人はいずれもこれに近いような独白を実際彼女に語り聞かせたのであろうか。
以前は私はそうだと考えていた。ところがあることから私はおそるべき事実に気づいた。仮にE家としておくが、その家のことを書いた彼女の短文について私はいくつか質問をした。事実を知りたかったからであるが、例によってあいまいきわまる彼女の答をつきつめて行くと、そのE家の老婆は彼女が書いているような言葉を語ってはいないということが明らかになった。瞬間的にひらめいた疑惑は私をほとんど驚愕させた。「じゃあ、あなたは『苦海浄土』でも……」。すると彼女はいたずらを見つけられた女の子みたいな顔になった。しかし、すぐにこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。
この言葉に『苦海浄土』の方法的秘密の全てが語られている。それにしても何という強烈な自信であろう。誤解のないように願いたいが、私は何も『苦海浄土』が事実にもとづかず、頭の中ででっちあげられた空想的な作品だなどといっているのではない。それがどのように膨大な事実のデテイルを踏まえて書かれた作品であるかは、一読してみれば明らかである。ただ私はそれが一般に考えられているように、患者たちが実際に語ったことをもとにして、そこに文飾なりアクセントなりをほどこして文章化するという、いわゆる聞き書の手法で書かれた作品ではないということを、はっきりさせておきたいのにすぎない。本書発刊の直後、彼女は「みんな私の本のことを聞き書だと思っているのね」と笑っていたが、その時私は彼女の言葉の意味がよくわかっていなかったわけである。
患者の言い表していない思いを言葉として書く資格を持っているというのは、実におそるべき自信である。石牟礼道子巫女説などはこういうところから出てくるのかも知れない。この自信というより彼らの沈黙へかぎりなく近づきたいという使命感なのかもしれないが、それはどこから生まれてくるのであろう。』
(P309〜312)
これである。
石牟礼道子は『きき書』と書いていたが、坂上ゆきらの「語り」は、じつは「聞き書き」ではなかった。
石牟礼が「多分、こんなことが言いたいのだろう」と勝手に想像して書いた、「モデル付きフィクション」であったのだ。
しかも、これは、石牟礼が『「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」』と言っているとおりで、「確信的になされた創作」であり、しかも渡辺が『文飾は当然あるにせよ、この二人(※ 水俣病患者)はいずれもこれに近いような独白を実際彼女(※ 石牟礼道子)に語り聞かせたのであろうか。/以前は私はそうだと考えていた。』と書いているとおりで、『苦海浄土』を自らの雑誌に掲載させていた渡辺でさえ、当初は同作を「ノンフィクションとしてのルポルタージュ」だと思っていたし、同作はそのような書物として公刊されたのである。
一一つまり、『苦海浄土』は、連載時においても、初刊時においても、当たり前に「水俣病のルポルタージュ作品」として公にされていたのであって、どこにも「小説・文学作品・フィクション」だと「断られてはいなかった」のだ。
ならば、人々が『苦海浄土』を「ルポルタージュ」として読むのは、当然ではないか。
なにしろ、雑誌掲載責任者であった渡辺京二自身にしてからが、当初は、この作品を「ルポルタージュ」だと思っていたのは、彼が『ところがあることから私はおそるべき事実に気づいた。』『私はいくつか質問をした。事実を知りたかったからである』と書いているとおりで、それまで彼は『事実』を知らなかったし、石牟礼から『事実』を知らされてもいなかったのである。
つまり、石牟礼は、『きき書』と称して「ノンフィクション」を装い、その「事実を、故意に隠していた」ことに、十分「自覚的」だったのだ。だからこそ、渡辺に追求されて『いたずらを見つけられた女の子みたいな顔にな』り、その上で、ヌケヌケと『すぐにこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」』という態度をとれたのである。
要は、石牟礼道子は、故意に、渡辺京二はもとより、世間を欺いていた「故意犯」だったということなのだ。
「なりゆきでそうなった」というようなことでない、というのは『本書(※ 『苦海浄土』)発刊の直後、彼女は「みんな私の本のことを聞き書だと思っているのね」と笑っていた』という証言にも、明らかなのである。
渡辺は、この「解説」において、『苦海浄土』という『この優れた作品は、粗忽な人びとから公害の悲惨さを描破したルポルタージュであるとか、患者を代弁して企業を告発した怨念の書であるとか、見当ちがいな賞賛を受けるようになった。』などと、多くの「善意の読者」を「粗忽」者呼ばわりしているが、石牟礼の身近にいながら、長らく騙されていたのは、他ならぬ渡辺京二その人だった。
なのに、なぜ渡辺は、自身と同レベルでしかない、世間の読者一般を「粗忽」呼ばわりしてまで、『苦海浄土』が「明らかな文学作品」だということに、しなければならなかったのか?
それは無論、「石牟礼道子の確信犯的ペテン」を知った後からは、彼自身もその「共犯者」であったからだろう。

『〈この日ことにわたくしは自分が人間であることの嫌悪感に、耐えがたかった。釜鶴松のかなしげな山羊のような、魚のような瞳と流木じみた姿態と、決して往生できない魂魄は、この日から全部わたくしの中に移り住んだ。〉
こういう(※ 石牟礼の)文章はふつうわが国の批評界では、ヒューマニズムの表明というふうに理解される。この世界に一人でも飢えている者がいるあいだは自分は幸福にはなれない、というリゴリズムである。この文をそういうふうに読むかぎり、つまり悲惨な患者の絶望を忘れ去ることはできないという良心の発動と読むかぎり、『苦海浄土』の世界を理解する途はひらけない。そうではなくて、彼女はこの時釜鶴松に文字どおり乗り移られたのである。彼女は釜鶴松になったのである。なぜそういうことが起こりうるのか。そこに彼女の属している世界と彼女自身の資質がある。』(P312)
『 こういう表現はおそらく日本の近代文学の上にはじめて現れた性質のものである。というのものは、海の中の景色を花にたとえるという単純な比喩をこれまでのわが国の詩人が思いつかなかったなどという意味ではもちろんなく、ここでとらえられているようなある存在感は、近代的な文学的感性では触知できないものであり、ひたすら近代への上昇をいめざして来た知識人の所産であるわが近代文学が、うち捨ててかえみなかったものだという意味である。この数行はもちろん石牟礼氏の個的な才能と感受性が産んだものにちがいないけれども、その彼女の個的な感性にはあるたしかな共同的な基礎があって、そのような共同的な基礎はこれまでわが国の文学の歴史ではほとんど詩的表現をあたえられることもなかったし、さらには、近代市民社会の諸個人、すなわちわれわれにはとっくに忘れ去られていた。
その世界は生きとし生けるものが照応し交感していた世界であって、そこで人間は他の生命といりまじったひとつの存在にすぎなかった。』(P314)
渡辺はここで、「何」をしようとしているのか。
それは、石牟礼道子の「ルポルタージュに見せかけた創作」という「ペテン」を、石牟礼本人に「故意は無かった」ということで、「免責」しようとしているのである。
そして、この手口とは、世間にもよくある「被疑者は犯行時、心神喪失状態であったので無罪」という弁護の「応用編」である。
近代的合理主義的なものの見方では、石牟礼道子を理解することはできない。石牟礼は、前近代的な能力、「巫女(イタコ)」的と言っても良い特殊能力(感性)の持ち主であり、いうなれば、釜鶴松の生き霊を「口寄せ」して、その時は『釜鶴松になったのである。』。
したがって、この時に語られたことに、石牟礼の「故意」は働いていないから、彼女の「犯意」を問うことはできない。
近代主義のとらわれた人々には理解できないだろうが、石牟礼道子という稀代の作家の真相(であり世界)とは、こういうことなのだ。一一という、これは「スピリチュアル詐欺」でしかない、と言っても良いだろう。
(著書『常世の花 石牟礼道子』を持つ若松英輔は、スピリチュアリスト)
渡辺のいう「石牟礼道子の世界」とは、このように「近代合理主義」では推し測れない世界だから、現代の合理主義からすれば、彼女のしたことが「詐欺やペテンの類い」に見えたとしても、「そうではないのだ」と、渡辺は主張する。
石牟礼はその時、本当に、その人(坂上ゆきや釜鶴松)になりきっているのだから、そのとき語られた言葉は「創作(作り事)」だとか「嘘」だということではないのだと、そう渡辺京二は、石牟礼道子を庇って強弁し、バカバカしい「スピリチュアルな独自解釈」を、私たちに強いるのである。
しかし、もしもこんな理屈が通るのなら、多くの「詐欺・ペテン」においても、「故意」の立証は不可能になるだろう。
詐欺師が法廷において「いや、騙すつもりはなかったんです。その時は、私も本気でそれを信じており、それを善意からみなさんに語っていただけであり、その壺を買うことで、みなさんが幸せになると確信して、オススメしていたんです。」と、言い訳するようなものなのだ。
ともあれ、この「容疑者」でさえも、きっと「イタコ」体質の人だったのだろうと、少なくとも渡辺京二なら信じてくれるはずだ。
だが、私は、こんな言い訳の「嘘」など、どんなに「偉い先生」が保証しても信じはしないし、そういう「近代的合理主義的懐疑」を持っている人間だから、これまで「霊感商法」の被害に遭うこともなかったのである。
『 彼女の表現に一種凄惨の色がただようのは当然である。使われるままに港で朽ちていく漁船の網とか、夜カリリ、カリリと釣糸や網を喰い切る鼠たちなどという、不気味な形象が、彼女の文章のあいまに現れる。手をこまねき息を詰めるほかない崩壊感である。この作品で描かれる崩壊以前の世界があまりにも美しくあまりにも牧歌的であるのは、これが崩壊するひとつの世界へのパセティックな挽歌だからである。
しかし、もともとそれは、有機水銀汚染が起こらなくても、遠からず崩壊するべき世界だったのではなかろうか。石牟礼氏は近代主義的な知性と近代産業文明を本能的に嫌悪をする。しかし、それはたんに嫌悪してもうどうにもならないものであり、それへの反措定として「自然に還れ」みたいな単純な反近代主義を開始してみでもしようのないことである。彼女はそういうふうにとれる不用意な言葉をエッセイなどに書きつけつけているけれども、世情流行のエコロジー的反文明論や感傷的な土着主義・辺境主義などが、そういう彼女の言葉にとびついて、「水俣よいとこ」みたいなことを言い出すと、彼女が描いている水俣の風土が美しいだけに、どうしようもなくなるわけである。』(P316)
上の引用文の前半部分は「文学者」である渡辺京二が、自身の「文学者」的な筆力を存分に振るった「華麗なレトリック」で、読者を「石牟礼道子の世界」に引き込もうとしている部分である。人を騙すには、才能はもちろん、もっともらしい演出(レトリック)こそ大切なのだ。
そして、後半部分で、石牟礼道子と「エコロジー運動」を切り離そうとしているのは、事実として石牟礼がそうした運動に関わって、そのような発言もし、そのような運動の「カリスマ」に祭り上げられているにも関わらず、そういうものは、結局のところ、いずれ「文学者」石牟礼道子の評価を揺るがす、マイナス要素にしかならないということを、渡辺は、賢く見抜いているからである。
どういうことかと言うと、石牟礼道子を「すごい作家」だと持ち上げている「一般読者」の大半は、ニューエイジ的な「エコロジー思想」にかぶれた、あまり「文学作品を読んでいない人たち」でしかないし、石牟礼をやたらと持ち上げる文学者というのも、同様に、石牟礼と「運動」とを一体的に捉えている者ばかりだからだ。
言い換えれば、エコロジー的な立場に立たないかぎり、石牟礼道子の小説というのは、それそのものとしては「雰囲気のある、主情的な美文」文学でしかない、ということである。
実際、石牟礼道子の小説は、『苦海浄土』以外、広く読まれている作品もなければ、知られている作品もない。
石牟礼ファンなら知っていても、文学一般のファンの多くにとっても、石牟礼道子は「『苦海浄土』の人」であって、他にどんな作品があるかまでは、ほとんど知らないはずで、石牟礼が1993年に紫式部文学賞を受賞した作品のタイトルを言える人など、ほとんどいないはずだ。
たしかに、石牟礼道子には、作家的な才能がある。それは、私だって認める。
だが、いくら才能のある人だからといって、「創作」でしかないのものを『きき書』だといって発表するのは、「ペテン」でしかない。
また、実際のところ『苦海浄土』は、「水俣病」という「現実」に関わるものだから、その「話題性」において世間の注目を集め、下世話に言えば、売れ続けているのである。『苦海浄土』三部作を除いても、石牟礼道子の小説が「売れている」などと思う人は、読書家ではない。
言い換えれば、石牟礼道子の「評価・評判」の半分以上は、「水俣病という厳しい現実」にかかわった「おかげ」であって、純粋に、石牟礼道子の「作家的力量」によるものではない、ということだ。
渡辺京二は、前記のとおり、
『そういう社会的風潮や運動とたまたま時期的に合致したために、この優れた作品は、粗忽な人びとから公害の悲惨さを描破したルポルタージュであるとか、患者を代弁して企業を告発した怨念の書であるとか、見当ちがいな賞賛を受けるようになった。』
と言っているが、これは「盗人猛猛しい」言い草でしかない。
というのも、「水俣病」の方から石牟礼道子に「作り事でもいいから、世間に広くアピールするものを書いてください」と頼んだのではなく、石牟礼の方が、自分から近づいていき、自分の「創作」を「現実の事件=水俣病」に絡め、そうと断らず、わざわざ「世間に誤解をさせるような形式」で書き、発表した。それが『苦海浄土』なのだ。

石牟礼が『「みんな私の本のことを聞き書だと思っているのね」と笑っていた』というのは、石牟礼が『苦海浄土』の「創作」(フィクション)部分が『聞き書』(ノンフィクション)だと、世間で「誤解」されるのを、むしろ喜んで受け入れていたということであり、これは彼女が「故意犯」である(意図して行ったことである)ことの、何よりの証拠だ。
それを「石牟礼道子は、巫女的作家だから、彼女に作り事をしたという故意はなく、したがって、それを反社会的な行為だとだ断罪することはできない」などと、無理な弁護をしている渡辺京二も、所詮は、自覚的な「事後従犯」でしかないのである。
ちなみに、このレビューを書くためにネット検索していたところ、石牟礼道子と渡辺京二の関係を描いた、米本浩二の『魂の邂逅』についての、ノンフィクション作家・梯久美子によるレビューを見つけたのだが、そこには、次のようなことが書かれていた。
『 米本さん、やっぱり書いたのですね。『評伝 石牟礼道子 渚に立つひと』から3年、この本が出るのをわたしは待っていました。かならず書いてくれるに違いないという確信をもって。
(中略)
ともに家庭を持つ身であった二人の、半世紀にわたる深いかかわり。編集者と作家でもなく、闘争の同志でもなく、夫婦でもない。けれどもたしかに女と男であり、あえて名付けるならば、愛としか呼べないものがそこにはあることが、3年前の評伝からは伝わってきました。でも、それだけではわたしは満足できなかった。もっと深く、この二人のことを知りたく思ったのです。
(中略)
これまでだれも踏み込まなかった二人の関係(石牟礼さんが晩年、まるで聖女のようにメディアで扱われていたこともあるのでしょう)。本書『魂の邂逅 石牟礼道子と渡辺京二』で、米本さんはそこに、覚悟をもって踏み込んでいます。それは、石牟礼さんのもとに繰り返し通い、彼女の療養を支えた人たちとともにその晩年を見届けることになった米本さんだからできることだったに違いありません。』
ハッキリ言って、私は、男女の仲になど興味はないし、有名人だからと言って、特別に大目に見る気もない。
いずれにしろ、渡辺京二が、石牟礼道子と深くつながった人間であったのであれば、上の文庫解説のような「世間を欺くペテン」によって、石牟礼道子を庇うべきではなかった。
「真の愛」があるのならば、是々非々で、事実は事実として認めるべきは認め、批判すべきことは批判すべきではなかったか。
しかし、渡辺が、その「疑惑」を追求した際の、石牟礼の態度を見れば、当時からすでに、渡辺は、石牟礼のコントロール下にあったと見て良いだろう。
この時、石牟礼は、渡辺が「真相に気づいた」としても、決して自分(石牟礼)を告発することなどできないと、そう見切っていたのである。だからこそ、余裕しゃくしゃくに「笑って見せた」のだ。
『瞬間的にひらめいた疑惑は私をほとんど驚愕させた。「じゃあ、あなたは『苦海浄土』でも……」。すると彼女はいたずらを見つけられた女の子みたいな顔になった。しかし、すぐにこう言った。「だって、あの人が心の中で言っていることを文字にすると、ああなるんだもの」。』
いまどきの言葉でいうなら、これは、若き石牟礼道子の「てへぺろ」だったのである。
(2022年9月27日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
