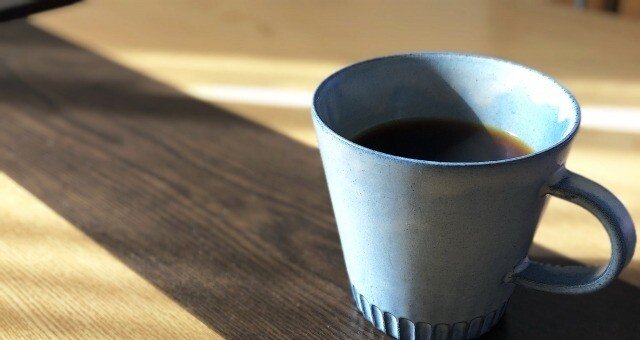
- 運営しているクリエイター
#キャリア資本
アスリートから学ぶ、セカンドキャリア
アスリートのキャリア形成支援を行う、スポーツキャリアサポートコンソーシアム。アスリートの方や専門家の方のお話をお聞きする機会がありました。アスリートではない誰にでも参考になるエッセンスをご紹介します。
失敗の数が多いことが強みになる
「挑戦の分、失敗も多く、そこから軌道修正してきたことが強み」
元アスリートのそのような言葉に、ハッとさせられました。
現役時代、アスリートは試合等で結果を出すこ
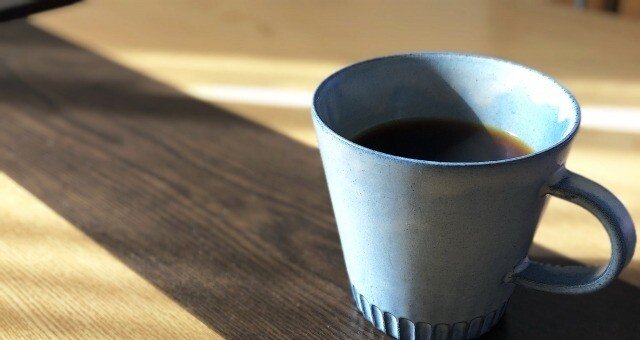
アスリートのキャリア形成支援を行う、スポーツキャリアサポートコンソーシアム。アスリートの方や専門家の方のお話をお聞きする機会がありました。アスリートではない誰にでも参考になるエッセンスをご紹介します。
失敗の数が多いことが強みになる
「挑戦の分、失敗も多く、そこから軌道修正してきたことが強み」
元アスリートのそのような言葉に、ハッとさせられました。
現役時代、アスリートは試合等で結果を出すこ