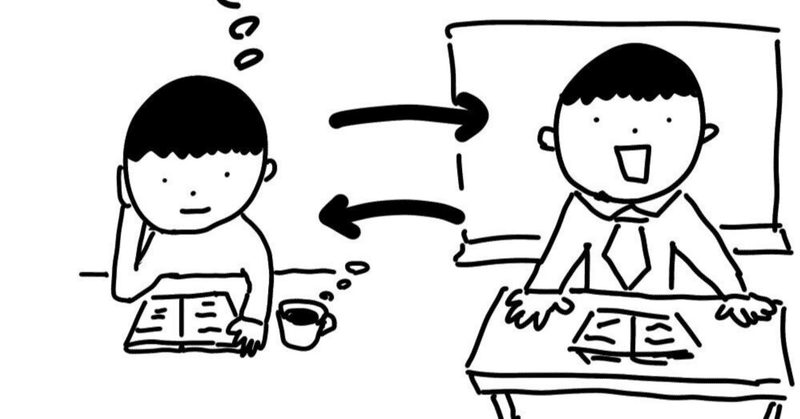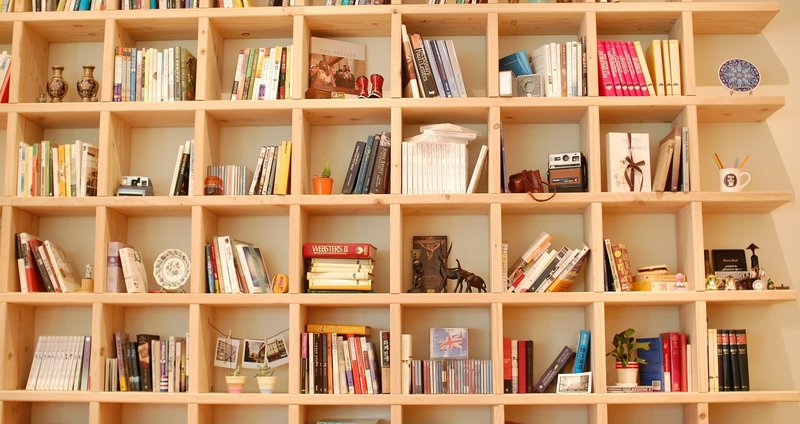
年間100冊を15年間続けてきました。でも、本当に知らないことばかり!というかアウトプットがまだ少ないなあと感じています。過去に読んだ本は「読書ログ」としてまとめてきたので、それ…
- 運営しているクリエイター
2022年6月の記事一覧
マックス・ヴェーバー「職業としての政治」岩波文庫
「君主論」にならぶ政治学のテキストである。俺が政治云々とかいうのも、ちゃんちゃら可笑しいが、参院選が近づく中、まったく無関心ではいられず、書棚にあった本著を取り出して再読してみた。
この本が出た1919年は第一次大戦に敗れた混迷を極めるドイツ。その時代に「天職としての政治家」を待望していたヴェーバーの切実さが生々しい。下記の言葉に彼の哲学は凝縮されているように感じる。
政治家の資質について考え
諏訪哲二「教育改革の9割が間違い」ベスト新書
表紙に書かれていたアクテイブラーニングが是か非か、ということより「プロ教師の会」名誉会長としての教育の見解が紹介されている本だった。でもそれがかえってよかったような印象もあった。教師という特殊な職業を持つものの性というか正体をよく見抜いているなと感じた。
教師が陥りやすいのが「私は生徒の立場に立って考えている、生徒のことを真剣に考えている」といった勝手な思い込みだ。そういう正義感でつっぱしる