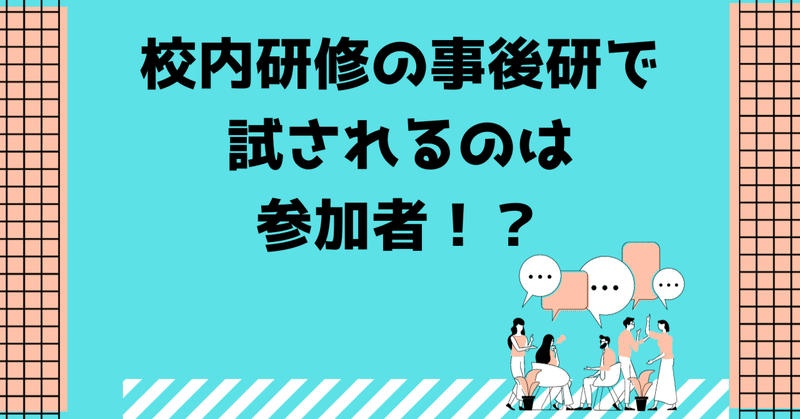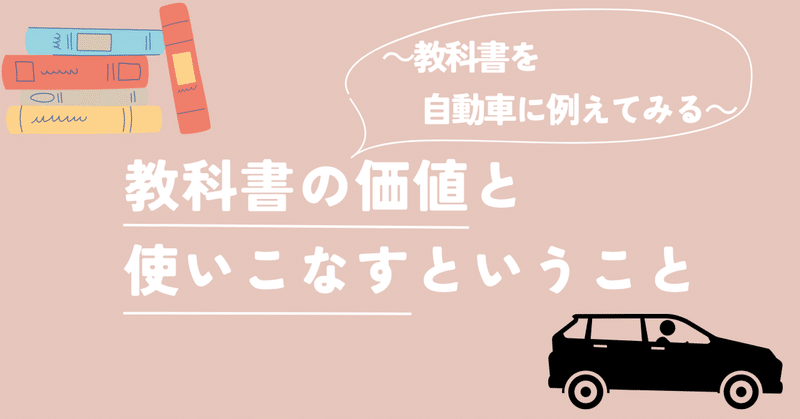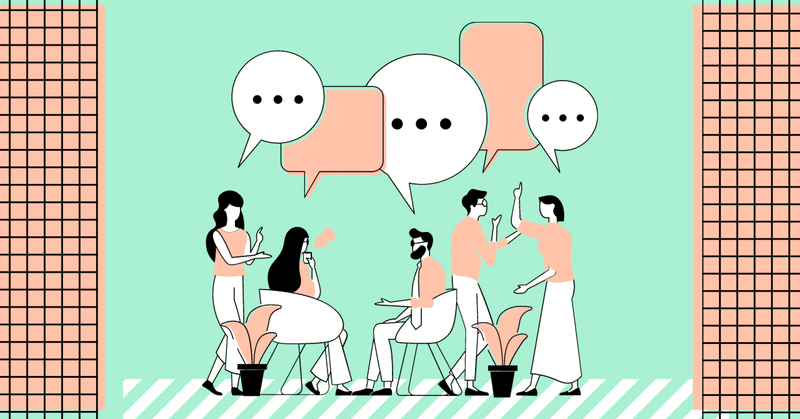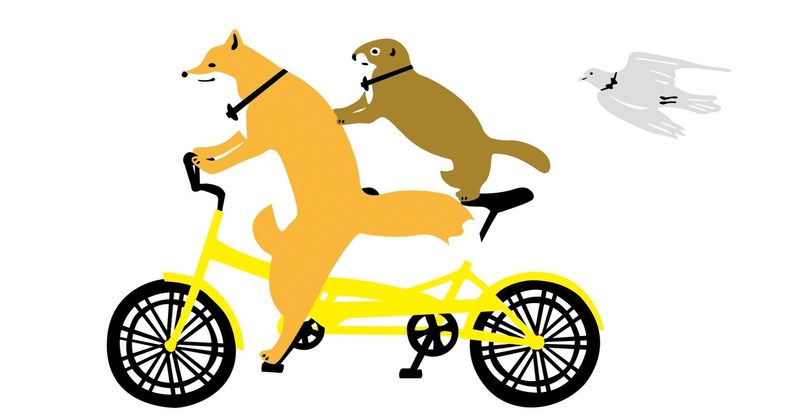#授業
試されるのは参加者!?校内研修の「優秀な」参加者3選~あなたは10個褒めることができますか?~
X(旧Twitter)で、このようなポスト(ツイート)をしたところ、自分のポストにしては珍しく?反響をいただきました。
https://x.com/tsukemen1313/status/1709893327305462229?s=20
自分は、立場や機会に恵まれ、おそらく一般の教員としては考えられないくらいの数の研究発表会や事後研修に参加させていただきました。(自治体もたくさん。開催者側
教科書の価値と、使いこなすということ~教科書を自動車に例えて考える~
「教科書めっちゃよくできている」
教材研究をしていて、ふと思ったわけです。
そんなことをきっかけに、教科書について考えたことを書き留めておきます。
1 教科書の価値に改めて気付く
例えば小学校3年生の社会科の教科書。
最初に学ぶ、子どもが自分が住んでいる地域や市区町村の様子を捉える単元を挙げてみます。
「教科書に載っているのは、子どもが住んでいるところ以外の地域なので、どう扱えば
校内研究の難しさと改善へのヒント ~演繹的な校内研究と帰納的な校内研究~
校内研究(校内研修)に難しさを感じる教員の方は少なくないと感じています。
今回は、時事通信社「内外教育(2022.9.27)」に掲載の、奈須正裕「学校における理論研究の進め方」から、校内研究の方向性について考えてみます。
※本来の意味は異なりますが、ここでは便宜上「校内研究」に表現を統一します
1 校内研究が背負うもの
前提の整理ですが、いわゆる校内研究は、主に3つの側面を背負って
子どもが「自分の世界に引きつける」授業とは?~「フォーマルな知識」と「インフォーマルな知識」から~
1.子どもの考えを大事にしたいのだけど…
「子どもなりの発想を大事にしたい」「その子その子の考え方を尊重したい」と考える教員は少なからずいらっしゃるかと思います。特に、幼さ十分に残る小学校段階であればなおさらではないでしょうか。
しかしながら、学習指導要領で示された学習内容を十分理解するには、なかなかそうも言ってられない…「計画していた範囲が終わらない!」と思わず愚痴をこぼしてしまう教員の
「対話」と「思考」の関連性 ~活発な「話し合い」授業から考える~
「対話」することは良いこと、という流れが世の中にあるかと思います。
確かに「対話」することで誰かと関わったり、悩みが解決したりします。
「対話」がないと、分かり合っていない、分かってくれない、無視している…という状態になってしまうこともあります。
では、そもそも「対話」とはいったいどのようなものを指すのでしょうか。
今回は、学校現場における「対話」から、「思考」との関連性に
席を立ってうろうろしてしまう子どもへの考え方&支援@小学校
※いわゆるADHD傾向の子ども向けの支援です。
※忙しくて本を読んだり、研修会に出たりする時間がない、もしくは、いろいろな本を読んだり聞いたりしたけど、具体的にどうしていいか分からない…という方に、是非読んでいただければと思います。
0.はじめに発達障害の可能性があるとされる児童生徒の割合は6.5%といわれています(2012年文部科学省公表)。30人学級ならば1~2人といったところですが、約10