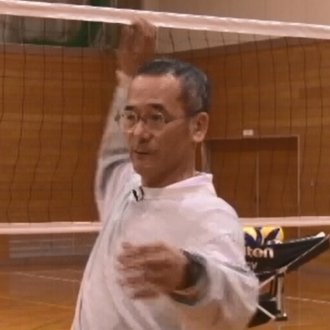#驚く
「教える」の多くは幼児的欲求?
面白い体験を伺った。とある女性が初めてテレビゲームをやってみたら、普段からやってる息子が「そこはこうしたほうがいい」「次はこうなるから気をつけて」と教えてくれて、かなりうっとうしかった、と。他方、やったことのない夫は一緒にドキドキしながらうまくいくと驚いてくれて、嬉しかったという。
その経験から、人間には教えたがる本能があるのではないか、という指摘がなされていた。これは大変面白い話だと思う。教え
結果をほめるとつけあがることが、プロセスをほめると「頑張り無罪」になることが。ではどうすれば?
子育てでも部下育成でも、「ほめて育てる」本がかなり出ている。しかしほめると「つけあがる」という現象がしばしば起き、まるで勉強しなくなったり働かなくなったりする。ほめる言葉は子どもや部下のやる気を高めるどころかますます動かなくなる原因になったりする。これはなぜなのだろうか?
「100点ばっかりなんてすごいね」と、結果ばかりほめたり、「営業成績トップなんてすごいね」と成績はかりほめたりすると、逆にや