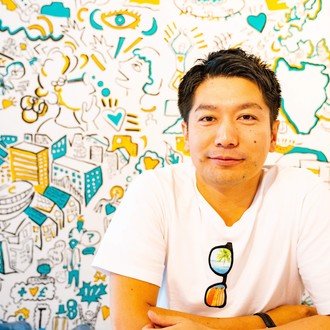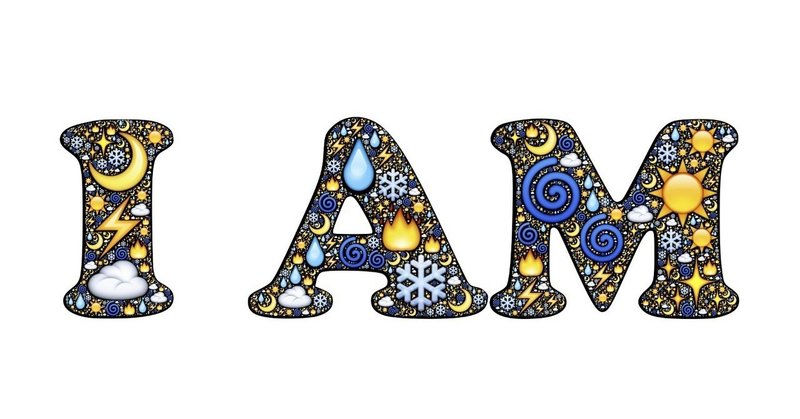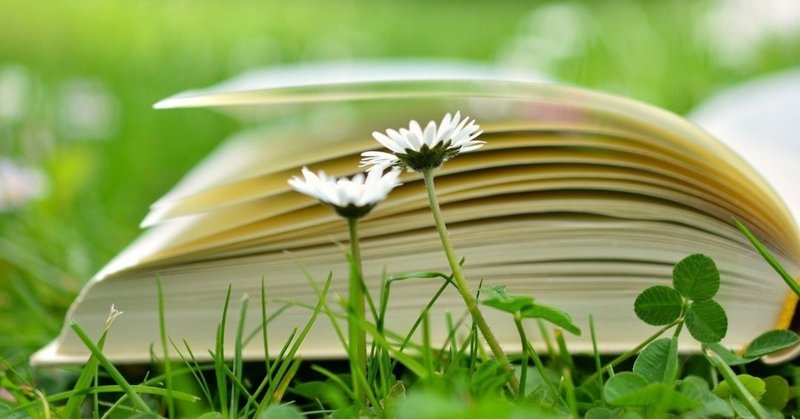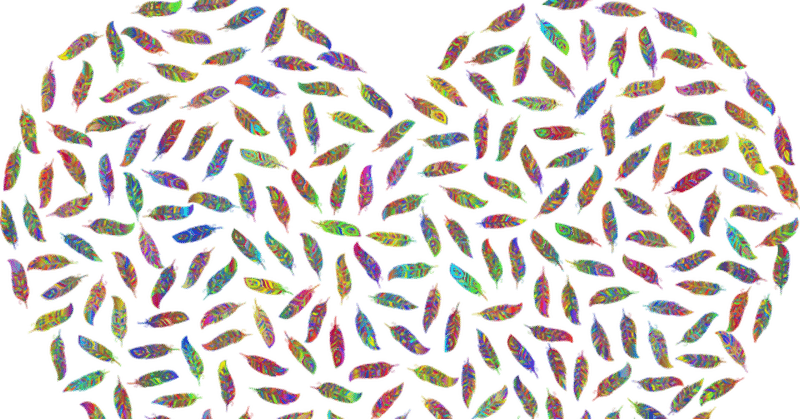- 運営しているクリエイター
#ウェルビーイング
暮らしと仕事のウェルビーイングというのにやっと腹オチしたという話。
今頃かよ!!という突っ込みを社内外から受けてしまいそうですが、タイトル通りの話を書いてみたいと思います。
2019年に「何気ない日常をより豊かに Augmentation for Well-being」ということを目標にAug Labというバーチャル組織を立ち上げました。
コンセプト段階のプロトタイプから積極的に発信してきたので、結果的に社内外の多くの方から意見を頂きました。特に、発信してきた
ウェルビーイングは北極星みたいに目指すけど辿り着けない存在
『ウェルビーイングをどのようにKGIとかKPIとして設定するべきか?』
この半年くらい良く聞かれる質問の1つです。質問する気持ちは、めちゃくちゃよくわかります。
テクノロジーでWell-beingに貢献する!!という目標を掲げて以来、私もよく悩みます。
技術者として考えると、どれくらい貢献したかを定量化したくなりますし、その数値をどうやったら上げられるのか?どれくらいまで上げられるのか?とい
ユーザが消費者から生産者になるとき持続的なWell-beingが生まれる
今月のDIGITAL Xでのコラムは、『偏愛』が感性価値の高いプロダクト/サービスを生むということで、書かせて頂きました。
今週のNoteはこのコラムの補足的な記事を書いてみたいと思います。コラムの中では、偏愛からプロダクト/サービスの開発のプロセスとして、
(1)偏愛マップの作成
(2)偏愛マップの共有・対話
(3)偏愛情報の拡張
というのを紹介しました。この中で、一番難しいのは、(3)の
「ロバストなウェルビーイング」というキーワードが巡り巡って。
おおよそ1年前に「2030年 テクノロジーと生きるわたしたちのWell-being」というテーマのパネルディスカッションを企画しました。
『WIRED』日本版編集長の松島 倫明さんのモデレートのもとで、Enhance代表の水口 哲也さん、大阪大学 社会技術共創研究センター 赤坂 亮太さんとのトークという貴重なお時間を頂くことができました。
トークの内容自体の詳細は是非↑のyoutubeを見て頂
Well-beingは金持ちの道楽という指摘を考えたら、最後はNew Luxuryに行き着いた
「Augmentation for Well-being:何気ない日常をより豊かに」の実現を目指す「Aug Lab」というものを作ったのが2019年4月。メーカでモノづくりをしながら、Well-beingということに考え始めたのが珍しかったのか、多くの方々とディスカッションさせて頂くことができました。その中で、定期的に質問・指摘を受けてきたのが、今回のタイトルにさせて貰った
「Well-bein
慶應大学・コネル社のBTC人材と連携してWell-beingのための技術と社会実装に挑む
11月18日にパナソニックの"Aug Lab"において、「Augmentation for well-being~何気ない日常をより豊かに~」というコンセプトを一緒に目指して頂ける共同研究パートナーの公募結果発表させて頂きました。
まず、短い公募期間にも関わらず、多くの研究者、クリエータの方々から応募を頂きましたこと、感謝申し上げます。公募に応募するということは何度もありましたが、公募する側にな
WIREDと徒然草と。
今週は国際ロボット展もあり、プレス発信もし、ということで色々と書きたいことがありますが、そちらはまた今度ということで。
今月のWIRED様で、現在進めている「身体や感性の拡張技術によりWell-beingを目指す『Aug Lab』活動」について書いて頂きました。テクノロジーに関連する仕事をしている身としては、大変嬉しい想いです。様々な場所で丁寧に取材頂きましたWIRED関係者の方々へ感謝申し上げ
太田直樹さんに教えて頂いたFairであることと主観的であることの大切さ
ワクワクや楽しさなどの感性の拡張によるWell-beingの実現を目指した「Aug Lab」の活動の一環で、ICTやデジタルの専門家であり、挑戦する地方都市とともに未来づくりをされている太田直樹さんにインタビューをさせて頂きました。
インタビューは前編・後編に分かれていますが、前編では「テクノロジーがどのようにすればWell-beingに貢献できるのか?」ということを、特にデータという観点などか
偏愛と結び付いた圧倒的当事者意識でWell-beingに向けた研究テーマを探す
テクノロジーを使ってヒトのスキルや感性を引き出し、拡張することでWell-beingに貢献することを目指している「Aug Lab」では、アイデア創出を目的としたワークショップを定期的に行っています。
アイデア出しの段階で特に意識しているのは、以下のWIRED記事でもタイトルとして付けて頂いているように、アイデアでトライしたいことに主体があるのか?、言い換えると、引き出し・拡張することで解きたい問