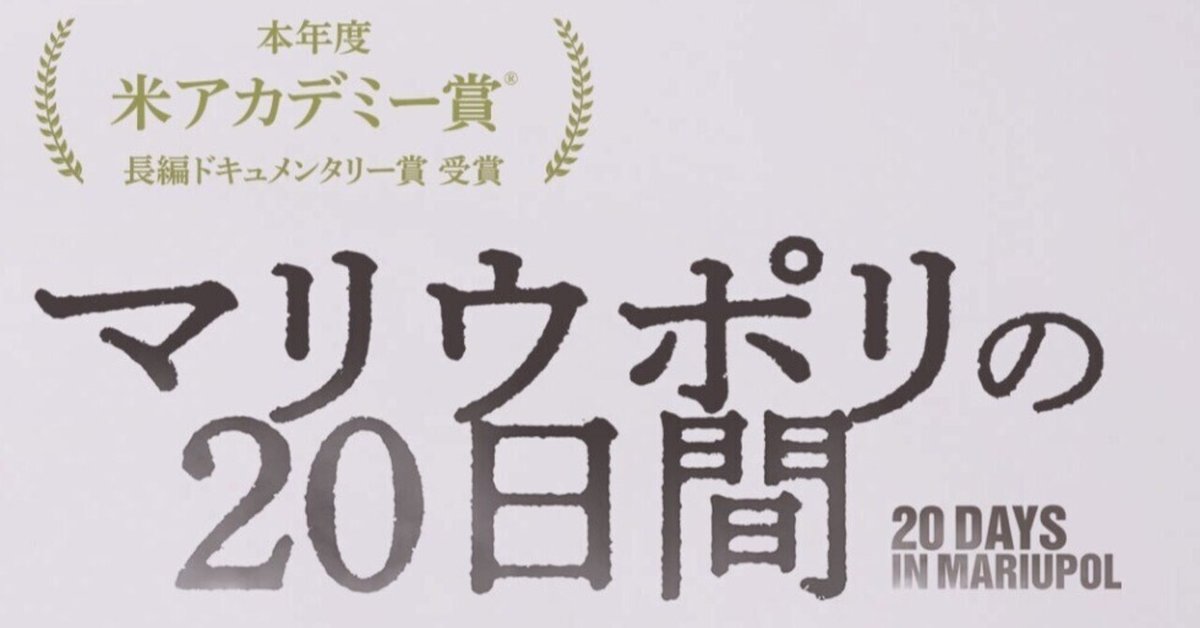
映画 『マリウポリの20日間』 : 事実をして語らしめる、 結果としてのプロパガンダ映画
映画評:ミスティスラフ・チェルノフ監督『マリウポリの20日間』 (2023年・ウクライナ映画)
「第96回 アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞受賞作」である。
だからこそ、終わりの見えない「ウクライナ戦争」に、いささか倦み疲れてきた私たちの間でさえ、話題にもなり得た作品だ。

だが、「アカデミー賞」が、アメリカ映画界の賞だということを意識した人が、いったいどれだけいただろうか?
例えば、カンヌ映画祭が、フランス映画を世界に売り込むために設立されたのと同じように、アカデミー賞もアメリカ映画の世界覇権のために作られた賞であり、カンヌ映画祭などの各種映画祭とそれに伴う映画賞というのも、結局のところ、自分たちの作品を売り込むことを目的として、アカデミー賞を真似たものなのだが、そのことを理解した上で、「有名な」映画賞をありがたがっている人が、いったいどれだけいるだろう?
こう書くと「本作のように、優れた外国作品だって、ちゃんと顕彰しているじゃないか」と言う人がいるだろうが、その程度の発想しか無いから、戦争も無くならないのである。
例えば仮に、ウクライナ軍側の非難されて然るべき残虐行為を撮ったドキュメンタリー映画があったら、アカデミー賞はそれも顕彰するだろうか?
言うまでもないことだが、わざわざライバルである外国作品を顕彰するのは、ハリウッドがお人好しだからではなく、「公正中立」をアピールすることで「賞の権威」を保つためである。「身内贔屓ばかりしている」と言われないようにするためであって、全世界の作品を「公平に顕彰する」ためなどではない。
アメリカの映画界関係者が、もっぱら外国の優れた映画のために、善意から金を出すことなど、あるわけがない。
一一もっとも、アメリカ(ハリウッド)の場合は、外国作品に賞を与えておいて、その優れた映画作家をヘッドハンティングしてきて「ハリウッド映画を撮らせる」という、いつもの奥の手もあるから、外国映画を顕彰するというのは、単なる「アリバイ作り」だけではなく、実益にもつながっている。
また、それでなくても映画作りというのは「金がかかる」のだから、偉大なる「アカデミー賞」を与えてもらい、世界の有名監督の仲間入りをさせてもらって、金集めも楽になるというのなら、どこの国の映画監督だって、ありがたくアカデミー賞を頂戴するだろうし、ハリウッドに招かれれば、喜んで馳せ参じもするだろう。

ことほど左様で、アカデミー賞に限った話ではなく、「映画賞」というのも、そもそも「政治的」なものなのであり、当然「現実政治」ともつながっている。
第二次世界大戦時のナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺である「ホロコースト」を扱った映画なら、アカデミー賞は喜んで賛辞を送るだろう。だが、ユダヤ資本が入っているハリウッドにとって、ユダヤ人(イスラエル民族)によるパレスチナ人虐殺を扱った映画が、アカデミー賞を取ることは、金輪際ないだろう。もちろん、そうした作品が、本作に劣っているからではない。単に「政治的に不都合」な内容だからだ。
本作は、たしかに、命がけの取材によって「戦争のリアルな悲惨さ」を伝えた貴重な映像記録だし、これを撮った監督以下のスタッフのジャーナリスト魂に、賛辞を惜しむつもりはない。
しかし、本作が「アカデミー賞」を受賞したのは、この作品だけが、他に抜きん出て優れていたからではない。
このような「戦場の悲惨さ」を伝えるドキュメンタリー映画なら、他にいくらでもあるのだが、なのにどうして本作が(このタイミングで)アカデミー賞を受賞することになったのかといえば、もちろんそれは、本作が、戦争当事国であるウクライナだけではなく、それを支持し支援するアメリカにとっても、「政治利用」できる「道具」だからに他ならない。
この映画を見て「戦争の悲惨さ恐ろしさを感じる」などと言っている人は、これまで「戦場ドキュメンタリー映画」を見たことがないほど、現実の「他国の戦争」になど興味がなかったか、見ていても、ただ「消費」しているだけだったから、今更のように「戦争の悲惨さや恐ろしさを感じる」などと平気で宣えもすれば、日々新鮮な気持ちで「新たな悲惨さ」を消費できるのではないのか。

「この現実を直視しなければならない」とか「戦争は恐ろしい」とか「勇気を持って戦争を止めなければならない」とか「ロシアの暴挙を許してはいけない」とか「ウクライナと連帯しなければならない」とか、そんなことは、馬鹿でも商業コメンテーターでも言える「放言」なのだが、そういう言葉を聞かされ続けた人たちは、そういうコメントが「適切なのだ」と学習して、何も考えずにその口真似、私の言葉で言えば「くちコピペ」をしているだけ。
そんな中身のない型通りのコメントを口にし、それでなにやら一丁前の評論家にでもなったつもりで「私って、いま良いこと言った?」などと、内心満足しているだけなのだ。
だが、そんな自分の軽薄無情な内心にも気づけないほど、彼らは鈍感な人間であるからこそ、そんな「紋切り型」を平気で口にできるのである。
実際、「この現実を直視しなければならない」と言う人は「直視するだけで良い」と言いたいのだろうか?
そうではないと言うのなら「何をしろ」と言うのだろう? 「ウクライナの人々と連帯しろ」と言いたいのか? 結構なご意見だ。では、ウクライナの人たちを連帯するとは、具体的には何をすることなのか? 「後方の市民たちのための支援をしろ」ということなのか、それとも、それだけでは済まないから「ウクライナの戦争を支援しろ。ロシア軍を叩き潰して、ウクライナの東部4州を取り戻さなければならない」と言うのか? それは「この戦争に勝たなければならない。そうでないと、正義は実現されない」と、そういう意味なのか? ならばそれは「正義の戦争には加担しなければならない」ということであり、要は「戦争は、必ずしも悪じゃない」と認める、ということなのか? だとすれば「戦争に犠牲はつきものだ。敵国人は無論、自国民の犠牲も、ある程度はやむを得ない」ということなのか?
一一ということは、結局のところ「この現実を直視しなければならない」というのは、「戦争になったら、勝たねばならない」と、そういうことなのだろうか?

「戦争は恐ろしい」という人は、では、どうしろと言うのだろうか? 戦争が恐ろしいことなど、戦場の映像を見れば、子供でもわかることだが、大人は怖がっているだけで済まされる立場にはないのだ。
つまり、その怖い戦争に直面している今「何をしなければならない」と言うのだろうか? それとも「怖い、怖い」と言っていれば、それだけで良いということなのだろうか?
「勇気を持って戦争を止めなければならない」とは、占領された「東部4州」をロシアに割譲してでも、という意味なのだろうか? ならば、そうハッキリと言うべきだ。
それとも「それは許されない。それでは、やった者勝ちになるからだ」と、そういう話なのであれば、要は、「東部4州」を取り戻すまでは「戦争をやって、必ず勝て」ということなのだろうか?
しかしそれは、いま現在やっていることそのものであり、そういうことなら、「勇気を持って戦争を止めなければならない」という言葉も、結局は「戦争には勝たなければ意味がない。ただ止めるだけでは、本質的には負けである」と、そういうことなのだろうか?
しかしまたそれでは「戦争に反対している」とは言えないのだが、そういう理解でかまわないのだろうか?
「ロシアの暴挙を許してはいけない」というのは、これも要は「戦争に勝て」ということであり、「そのための犠牲は、やむを得ないから、そこは目を瞑れ」ということなのだろうか?

「ウクライナと連帯しなければならない」一一これはすでに書いたとおりなのだが、いったい「具体的に、どこまで」ウクライナを支援することを意味しているのか?
いま現在がそうであるように、西側陣営として、武器供与や部隊派遣までする覚悟があって言っているのか、それとも「直接的には戦闘には関与しないかたちで、後方支援に徹する」とでも言うのだろうか?
しかし、それはかつての「湾岸戦争」において、「平和憲法堅持」の建前を貫いて「財政支援」だけに止めた結果、世界から「日本は、金は出しても血は流さない」と笑われた、といって恥じ入り、その結果、自衛隊の海外派遣に道を開くことになった、その同じ道筋をたどり直し、さらにその先へと進むことになるのも認めようと、そう覚悟しているということなのか?
戦争当事国のウクライナと連帯するとは、結局のところ、そちら側について「一緒に戦争をする」ということではないのか?
要は、あなたが、「ただの一市民」や「ただのコメンテーター」として、その場かぎりのコメントをしていれば良いという、お気楽かつ無責任な立場に満足するのではなく、一人の責任ある大人として、ウクライナ戦争に対して、日本は「具体的に、どうするべきなのか?」くらいのことは、考えるべきではないのか?
あなたは、またまた自分がその立場にはないから、現実的な核心部分には、自覚的かつ無難に踏み込まずにおいて、その手前で「無責任な綺麗事」を並べ、それで悦に入っているだけではないのか?
もしもあなたが、アメリカ大統領だったら、日本の首相だったら、今の彼らと、少しでも違うことができたと、本気でそう思えるのだろうか?
それなら、あなたなら、具体的に何をすると言うのだろうのか? 「ロシアを追い返すまでは、いくらでも戦争協力をする」のか、それとも「残念だが、東部4州は諦めてでも、戦争を止めるべきだ」と、そう言うのか? 言えるのか?
予想される非難の声を一人で受け止める覚悟、汚れ役を引き受ける覚悟のある、そんな人が、上のような、綺麗事だけのコメントをしたりするだろうか?
するわけがなかろう。結局のところ、こうした「もっともらしいコメントや感想」というのは、「傍観者でいること」に(こっそりと)あぐらをかいているからこそ、言えることなのだ。
本来なら私たちは、「戦争をしてはいけない。だが、戦争には勝たなければならない」という、このダブルバインド状況に絶句するか、立場に関係なく、その矛盾を指摘してあれもこれも批判することで、「何様だ」と言われるほかないのだ。
「こんな立派な(世間ウケする)コメントをしている私って、かっこいい?」「なら、誉めて誉めて!」などと思っているからこそ、呑気に「その場かぎりの綺麗事」を、ご都合主義的に語ることができるのだ。

○ ○ ○
本作『マリウポリの20日間』の内容は、次のようなものである。
『ロシアによるウクライナ侵攻開始からマリウポリ壊滅までの20日間を記録したドキュメンタリー。
2022年2月、ロシアがウクライナ東部ドネツク州の都市マリウポリへの侵攻を開始した。AP通信のウクライナ人記者ミスティスラフ・チェルノフは、取材のため仲間と共に現地へと向かう。ロシア軍の容赦ない攻撃により水や食糧の供給は途絶え、通信も遮断され、またたく間にマリウポリは孤立していく。海外メディアのほとんどが現地から撤退するなか、チェルノフたちはロシア軍に包囲された市内に留まり続け、戦火にさらされた人々の惨状を命がけで記録していく。やがて彼らは、滅びゆくマリウポリの姿と凄惨な現実を世界に伝えるため、つらい気持ちを抱きながらも市民たちを後に残し、ウクライナ軍の援護によって市内から決死の脱出を図る。
チェルノフが現地から配信したニュースや、彼の取材チームが撮影した戦時下のマリウポリ市内の映像をもとに映画として完成させた。2024年・第96回アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞を受賞し、ウクライナ映画史上初のアカデミー賞受賞作となった。また、取材を敢行したAP通信にはピュリッツァー賞が授与されている。日本では2023年にNHK BSの「BS世界のドキュメンタリー」で「実録 マリウポリの20日間」のタイトルで放映された。2024年4月に劇場公開。』
(「映画.com」・『マリウポリの20日間』解説より)
ちなみに、本作を見た人の中で、ほとんど同じ邦題である、マンタス・クヴェダラヴィチウス監督の『マリウポリ 7日間の記録』(2022年)を見た人は、どれだけいるだろうか?
この『7日間の記録』の方は、ロシアによる占領後のマリウポリに潜入して、占領下に生きるマリウポリの人々の生活を取材したものである。
監督のマンタス・クヴェダラヴィチウスは「戦争を撮りたいのではなく、人々の営みを撮りたいのだ」として、あえた死骸さえ撮らなかったのだが、それでも、いまだ戦闘の続く占領下にある人々の「悲惨な生活」を、しっかりと映し出すことになったし、監督自身も、生きては帰れなかったのである。

だから、戦闘の真っ最中の『20日間』を撮り、その映像を持ち帰って世界に知らしめた、アカデミー賞受賞作『マリウポリの20日間』も、それはもちろん偉大な仕事であるけれど、あえて占領下のマリウポリに入り、あえて「戦争」を撮らずに、人々の営みを撮り、その結果、生きては帰れなかったマンタス・クヴェダラヴィチウス監督の残した仕事である『マリウポリ 7日間の記録』は、その内容や質において、本作『マリウポリの20日間』に決して劣るものではない。
ただ、ひとつだけ確実に言えることは、本作『マリウポリの20日間』には、戦闘シーンや残酷シーンが豊富で、「Z」の文字が書かれてロシアの戦車が、病院の7階から撮影しているカメラの方に向かって砲塔を旋回させるという、怖気立つようなシーンなどもあるから、その意味では、間違いなく「ハリウッド」向きの作品だった、ということである。
(2024年6月17日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
