
不安の波を越えて - パニック障害とともに歩む道
こんばんは。
寒さが厳しくなり冬本番になってきましたね。
タイヤ交換をそろそろしなければと思っている今日この頃です。
自分が小さいときに起こった出来事でトラウマになっていることはありますか?
トラウマになっていることが再び起こるとパニックになってしまうことは少なくありません。
そこで今回はパニック障害に焦点を当てて解説していきます。

1.パニック障害とは?
パニック障害は、突然かつ予期せずに起こる重度の不安発作、ちなみにパニック発作を繰り返す経験する精神疾患です。
世界保健機関(WHO)によると、パニック障害の生涯有病率は全人口の約1〜3%程度と推定されています。
男女差を見ると、女性は男性に比べて、パニック障害を発症する可能性が高いとされています。
パニック障害の診断は、通常、精神科医や心理療法士によって行われます。
治療には、認知行動療法や薬物療法が含まれることが多く、これらは発作の頻度や強度を減らし、全体的なものですパニック障害は適切な治療によって管理することが可能です。

2.パニック障害の特徴
主な特徴には以下のようなものがあります。
①パニック発作:
突然かつ予期せずに起こる極度の恐怖や不安のエピソード。
発作は通常数分間続き、しばしば身体的な症状を伴います。
②身体的症状:
心拍数の増加、胸の痛み、呼吸困難、めまい、発汗、震え、熱感や冷感、しびれ感など。
これらの症状はしばしば「心臓発作」と誤認されることがあります。
③予期不安と回避行動:
新たな発作への恐怖(予期不安)により、特定の場所や状況を避けるようになることがあります。
これにより日常生活に制限がかかり、社会的、職業的な活動に支障を来たすことがあります。
④不規則な発作:
パニック発作は、特定の状況や活動とは関連せず、予測不可能な状況で発生することが一般的です。
発作がいつ起こるか予測できないため、常に不安を感じることがあります。
⑤感情的影響:
発作とその恐怖は、うつ病や他の不安障害、自己評価の低下など、広範な感情的問題を引き起こす可能性があります。

3.パニック障害の原因
パニック障害の原因は完全には理解されていませんが、一般には複数の要因が複合的に作用していると考えられています。主な原因や影響要因は以下の通りです。
①遺伝的要因:
家族内でパニック障害や他の不安障害がある場合、それを発症するリスクが高まる可能性があります。
②脳化学と神経生理学的要因:
脳内の神経伝達物質のバランスの変化、特にセロトニンやノルエピネフリンなどが関与している可能性があります。
③ストレスと環境的要因:
重大な生活変化、ストレスが多い環境、身体的または感情的なトラウマ(例えば、重大な事故や身体的虐待)など、ストレスを引き起こす出来事がパニック障害の発症に影響を及ぼすことがあります。
④個人の気質:
自然に不安を感じやすい、またはネガティブな出来事に対して過敏に反応するような気質を持つ人は、パニック障害を発症するリスクが高いかもしれません。
⑤物理的健康状態:
特定の医学的状態や薬物の使用がパニック発作を引き起こすことがあります。例えば、心臓病、甲状腺機能亢進症、喘息、薬物の乱用やカフェインの過剰摂取などが関連している場合があります。
⑥発達的要因:
幼少期の経験、特に親や保護者との関係や家庭環境がパニック障害の発症に影響を与える可能性があります。

4.パニック障害の日常生活への影響
①社会的な避け行動:
パニック発作への恐怖から、発作を経験した場所や状況を避けるようになることがあります。これにより、公共の場所への外出、旅行、大きな集まりなどが困難になる場合があります。
②職業上の制約:
発作の予測不可能性や職場でのストレスにより、職務を継続することが難しくなることがあります。発作の恐怖や回避行動によって、キャリアの選択や職場でのパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。
③日常活動への影響:
日常生活において、常に次の発作がいつ起きるかという不安を抱えることがあります。これにより、買い物、運転、家事などの一般的な活動が困難になることがあります。
④人間関係への影響:
パニック発作やそれに伴う不安が人間関係に影響を与えることがあります。家族や友人との関係に緊張をもたらしたり、新しい人間関係を築くことが難しくなることがあります。
⑤感情的な影響:
恐怖、不安、孤立感、無力感などの感情的な問題を引き起こすことがあります。これらの感情は、うつ病や他の不安障害へとつながることがあります。
⑥身体的健康への影響:
頻繁なストレスや不安が身体的健康に悪影響を及ぼすことがあります。これには、頭痛、消化不良、疲労などが含まれます。
⑦自己イメージと自己効力感:
パニック障害は自己イメージや自己効力感に影響を与えることがあり、自分自身を助ける能力に疑問を持つようになることがあります。
パニック障害を持つ人々は、これらの日常生活への影響に対処するために適切な治療やサポートを求めることが重要です。認知行動療法、薬物療法、リラクゼーション技術などが役立ち、発作の管理と日常生活の質の向上に寄与します。

4.パニック障害とともに歩む道
パニック障害と診断された方が豊かな人生を送るためには、症状の管理と日常生活の質の向上に焦点を当てたアプローチが有効です。以下に、パニック障害との付き合い方や人生を豊かにするためのいくつかの方法を紹介します。
①専門家のサポートを受ける:
認知行動療法や他の心理療法を通じて、パニック発作のトリガーや対処法を学びます。
必要に応じて、医師の指導の下で薬物療法を受けることも検討してください。
②発作への対処法を学ぶ:
深呼吸、リラクゼーション技術、マインドフルネスなど、発作時に役立つ技術を習得します。
③ストレス管理:
ストレスを軽減するための方法を見つけ、定期的に実践します。瞑想、ヨガ、ウォーキングなどが有効です。
④健康的な生活習慣を維持する:
良質の睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動を心がけます。
カフェインやアルコールの摂取を控えることも、発作の軽減に役立ちます。
⑤情報を共有する
家族や友人に自分の状態を説明し、理解とサポートを求めます。
必要に応じて、職場での適応措置について話し合います。
⑥ポジティブな活動に参加する:
趣味や興味のある活動に参加し、ポジティブな経験を積み重ねます。
⑦自己受容:
パニック障害はあくまで一部であり、自分自身を丸ごと受け入れることが大切です。
自分自身との優しい対話を持ち、自己批判を避けます。
⑧日記をつける:
発作のトリガーや感じる不安、日々の感情を記録することで、自分自身をより深く理解します。

5.終わりに
いかがでしたか?
このコラムを読んでパニック障害への理解を深めて前向きな気持ちで向き合うことができたら幸いです。
もし、悩んでいる人がいたら話を聞いたり相談に乗ってあげてくださいね。
【BRAINTRAIN-オンライン&LINE/X(Twitter)無料相談 実施中-】
ぜひ少しでもお悩みがある方やひとりで抱えれない方はご相談ください😌
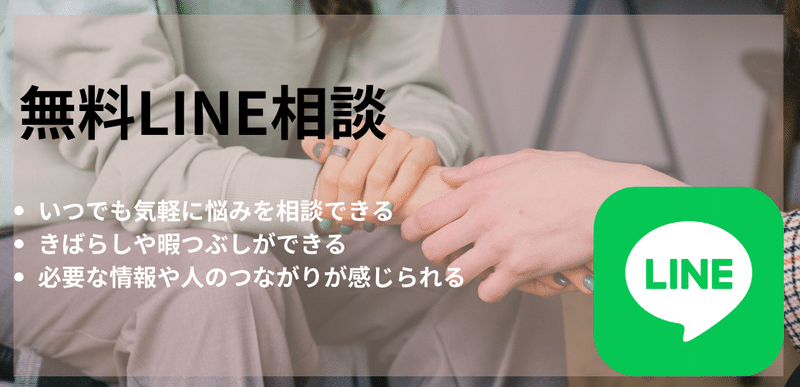
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
