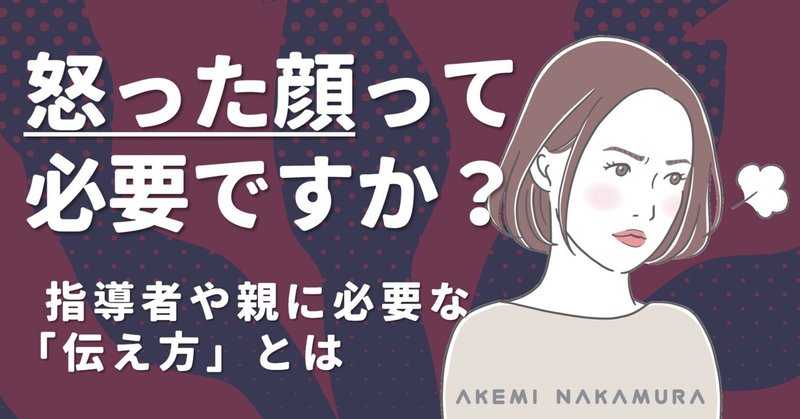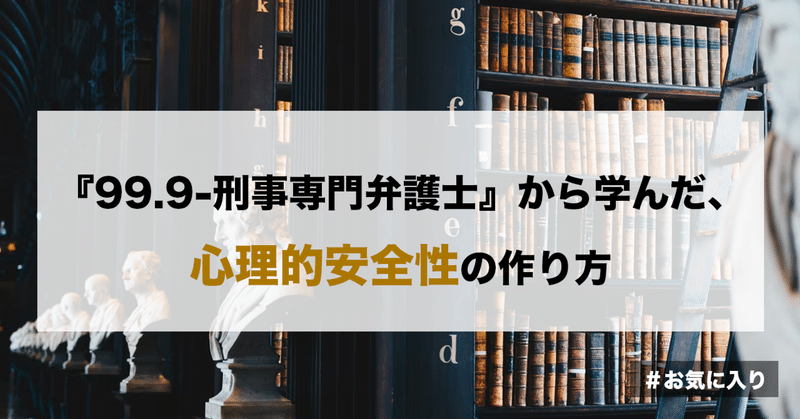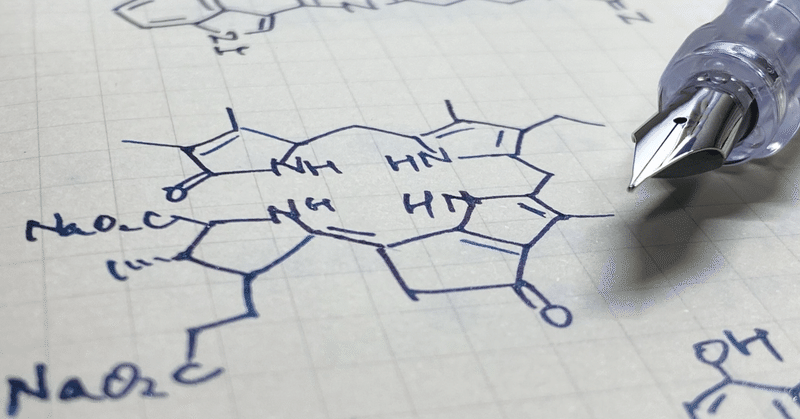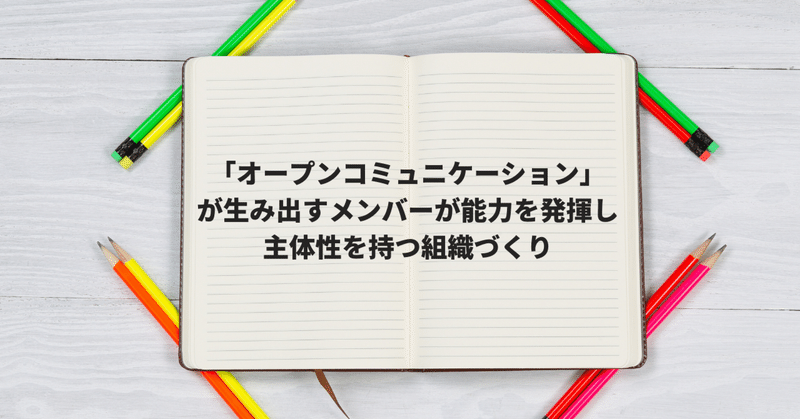- 運営しているクリエイター
#日経COMEMO
「手応え」を与えるサンドイッチ・フィードバックとは
良いフィードバックをもらえるととても嬉しい気持ちになり、やる気が湧いてきますが、一方で、フィードバックをもらってなんだか悲しい気持ちになったり、凹んだりすることもあります。
そのような経験があるからこそ、他の人のアイデアにフィードバックするときは「良いフィードバック」になるよう気をつけています。そのなかで「良いフィードバック」に気をつけているなかで、「サンドイッチフィードバック」を自分なりに解釈
ボクが「言葉の力」について思うこと。
みなさんこんにちは、澤です。
前回の記事も、とてもたくさんの方に読んでいただいてうれしいです!
※「スキ」してる人はボクも好きです!へんてこなアイコン写真がランダムに出ますので、ぜひポチってみてくださいね!
さて、今回のテーマは「言葉の力」です。
まずはこの記事。
さすがはマーケティングのプロ、言葉の力を知っておられる!!と感動した記事でした。
ほんのちょっとの言い回しで、伝わり方が全
褒めないでください!
こんにちは、ナラティブベースのハルです。突然ですが、わたし、褒められるのがとても苦手なんです!よく人の育成や子育てについて「褒められて伸びるタイプ」とか「褒めて伸ばす」とかいう言葉を聞いてきました。その度に「褒めること」を意識的にチャレンジしてみたのですが、なんともわざとらしーい感じになってしまいます。そもそも自分が「褒められて伸びるタイプ」つまり「褒められてモチベーションがあがるタイプ」ではない
もっとみる興味ない人を引き込むための、「主語を小さくする」話し方
会議やプレゼンテーションで一番大切なのは、相手を引き込むこと。
でも、相手が聞きたがっている場合は良いのですが、興味が無かったり、面倒だな…と思われている場合、相手を自分の話に引き込むのは難しいですよね。
私が一番難しいなと感じているのは、非常勤講師として教壇に立っている大学の授業です。大学生は、興味があって授業を取る人もいますが、単位のためにしかたなく取っているような人もいます。
そして、
ドラマ『99.9-刑事専門弁護士』から学んだ、心理的安全性の作り方
先月、部のメンバーとの1on1についての記事を書いたところ、過去一番の反響でした。ありがとうございます。
今日は、前回の記事で書ききれなかった、私なりの信頼関係の作り方について書きたいと思います。
前回の記事では、1on1の最後に本人に自分の発言を振り返ってもらって、気づきを言語化してもらうことが大事だと書きました。
しかし、もしも目の前にいる私が信頼できる人間でないと、気付いたことを素直に
サイエンスにも「コミュニケーション力」が必要
桝太一さんの退職で有名になった「サイエンス・コミュニケーション」 皆さんは、「サイエンス・コミュニケーション」という言葉をご存知でしょうか?文字通り、「科学」を「伝え・対話」する仕事です。
最近、日本テレビのアナウンサーだった、桝太一さんの退社の記事で、「サイエンス・コミュニケーション」という言葉が登場し、そこで初めて触れた方も多いのではないでしょうか?
この様に、既知のように説明している私
私たちは、なんのためにお酒を飲むのか〜「目の前の人の話を聴く」ことのススメ
Photo by Markus Spiske on Unsplash
ビール市場はどこへ向かうのか1987年に発売されたアサヒスーパードライは、バブル時代に大学生だった私にとって、まさにお酒の象徴であった。そのスーパードライが、発売以来のフルリニューアルという。2000年ごろをピークに右肩下がりでスーパードライの販売量が減り続けていること、コロナ禍で店舗売上が下がり、ビール売上首位から転落したこ
「オープンコミュニケーション」が生み出すメンバーが能力を発揮し主体性を持つ組織づくり
リモートワークが中心の状況が2年以上続いている中、企業におけるチームのコミュニケーションも大きく変化しました。コミュニケーションの変化に伴い、チームビルディングの方法も変化が見られているのではないでしょうか。
今回は「テレワーク環境下でのチームビルディング」をテーマに書きたいと思います。
チームビルディングとは「チームビルディング」という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。基本的には組織
モノ言う社員の声がより良い組織を創る
こんにちは。Funleash志水です。前回の記事もスキとコメントをいただきありがとうございました!私自分も少し時間を見つけて1年の振り返りを行い、来年やりたいことに考えを巡らせることができました。
知らない方もいらっしゃると思うので少しだけ触れると、私はキャリア人生のほとんどを外資系企業で過ごしました。3年前に仲間とともにファンリーシュという会社を立ち上げて現在はさまざまな業種&形態の日本の組織
「ギブファースト」の罠 〜ギブギブモンスターに気をつけろ!
お疲れさまです。uni'que若宮です。
コロナ禍が長期化の様相を呈し、経済的に個人にも企業にも大きな打撃となっています。その不安からちょっと世の中がピリピリしてきて、ストレス値が高まっています。そんな時だからこそ助け合いの気持ちが重要です。
「ギブファースト」という言葉をご存知でしょうか?
「ギブ&テイク」のうち「テイク」を考えずに、まず「ギブ」しようよ、ということなのですが、実はギブには
「先スプレイニング」に気をつけろ! 〜「良かれ」と「先回り」が潰す3つの機会
お疲れさまです。uni'que若宮です。
今日はちょっと子育てや教育から考えたことを書こうと思います。
街にはびこる「○○スプレイニング」「マンスプレイニング」や「ホワイトスプレイニング」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
「マンスプレイニング」や「ホワイトスプレイニング」は「女性に対する男性(マン)」と「人種的少数派に対する白人(ホワイト)」と「explaining(説明する)」が組