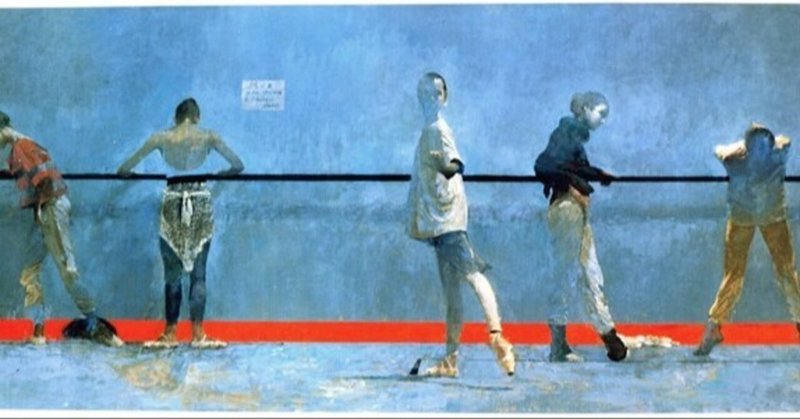みんなの文化 第3号目です。
大体、250~300ページで、次号へ向かいます。
こちらでは、わたしの代弁をしてくれる、あるいは、わたしを新しい世界へと導いてくれた大切な記事を、…
- 運営しているクリエイター
#小説
つまらない私について 2
一見すると、ふつうにしっかりして見えるそうだが、ちがう。
しっかり、障がい者です。と、いうのも変な言い方だが、しっかり、障がい者です。
では、どんな困難を抱えながら…、間違えた。
どんな特性とつきあいながら、生活しているのか。
今回は、未だにビビりなつまらない私が、少しずつ自身の障がいと向きあいはじめ、生活している様を、写真を交えてお話します。
連載数は、未定。
計画立てられないんだから、あたり