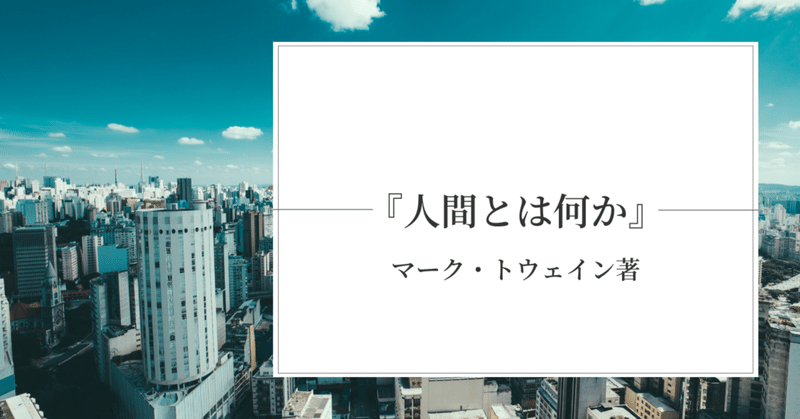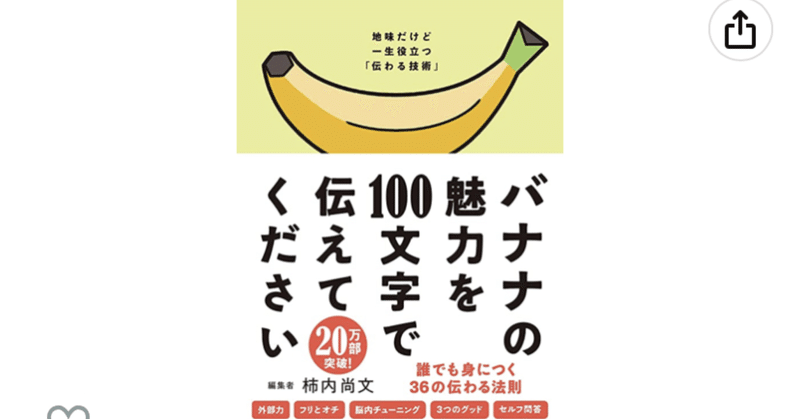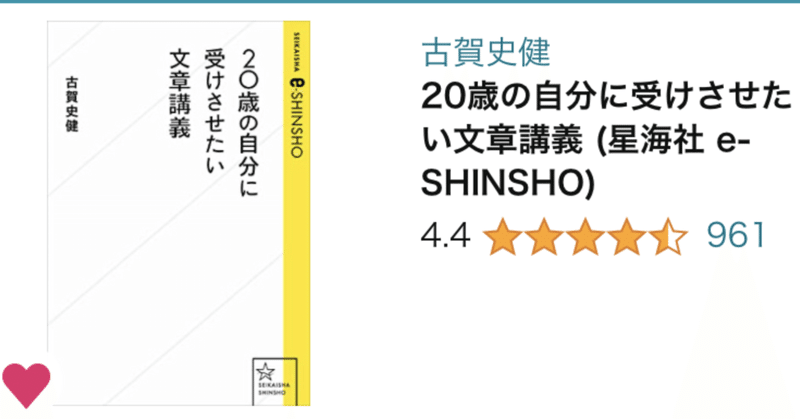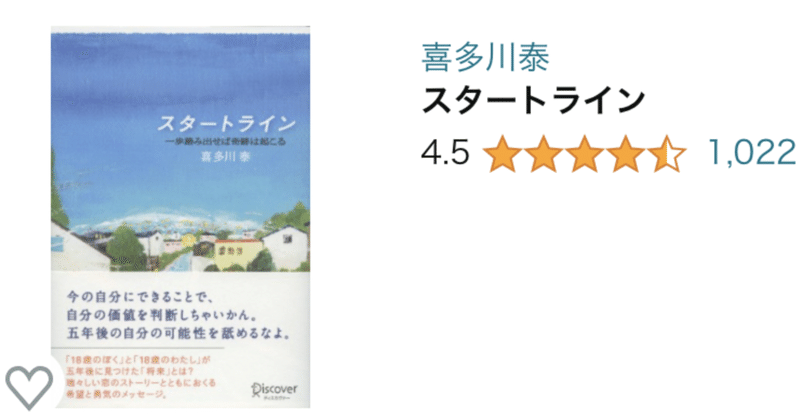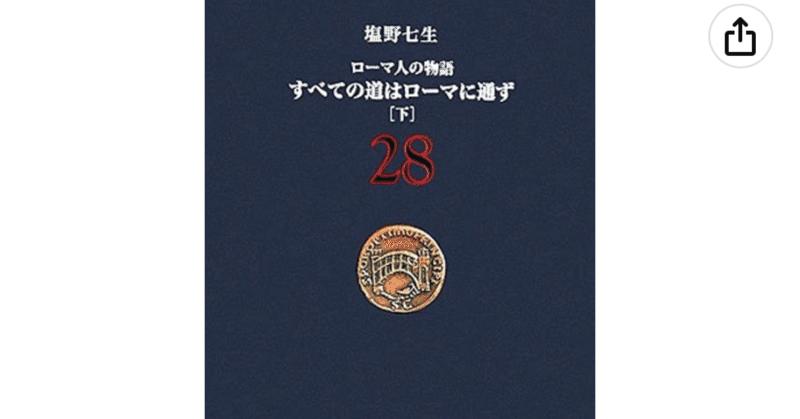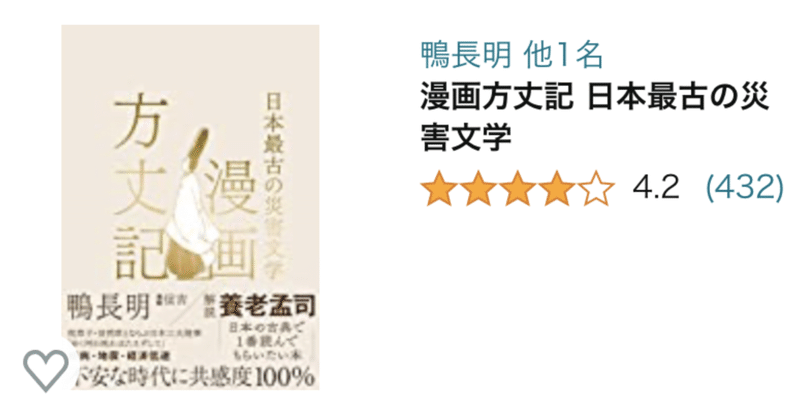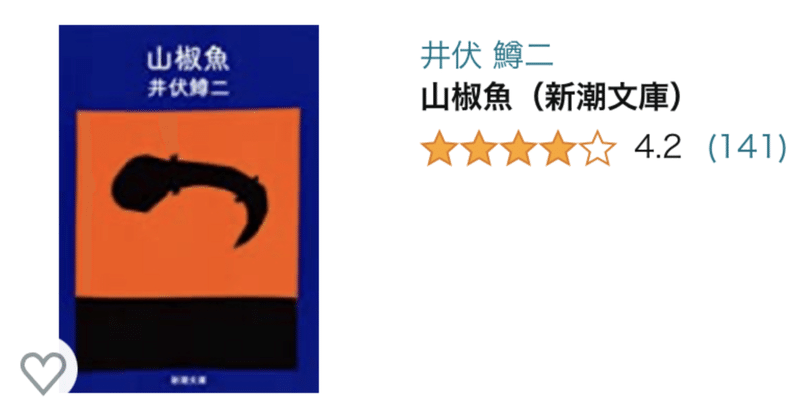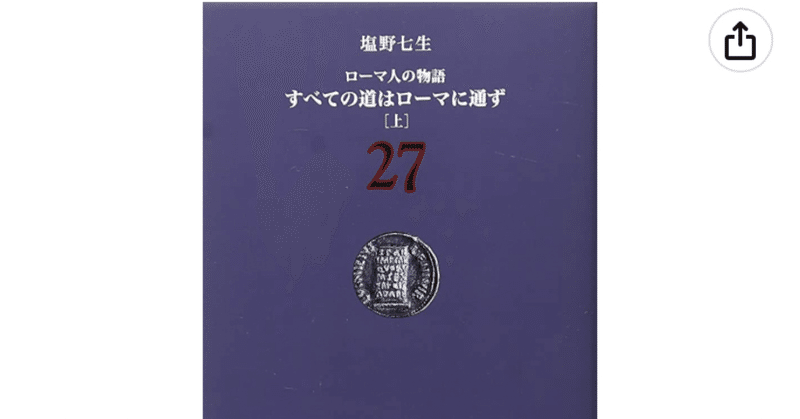#読書感想文
『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』
『20歳の自分に受けさせたい文章講義 (星海社 e-SHINSHO)』原稿
古賀史健著
著者はフリーランスライター
1973年福岡県生まれ。かねて映画監督を夢見るも、大学の卒業制作(自主映画)で集団作業におけるキャプテンシーの致命的欠如を痛感し、挫折。ひとりで創作可能な文章の道を選ぶ。出版社勤務を経て24歳でフリーに。30歳からは書籍のライティングを専門とする。
「話すこと」と「書くこと」は
『ローマ人の物語 28』
「ローマ人の物語 28」
塩野七生著
「ローマによる平和」を人々が享受できた背景には、社会基盤の充実があった。本書では、インフラのなかでも、水道、医療、教育が取り上げられている。
印象に残ったこと
①水道、浴場
ローマの水道は、流し放しだった。そのため、塩素などの消毒をしなくても、水質は良好だったらしい。
公衆浴場は、男女混浴だった。(ハドリアヌス帝が、男女別浴に変えてしまったが。)