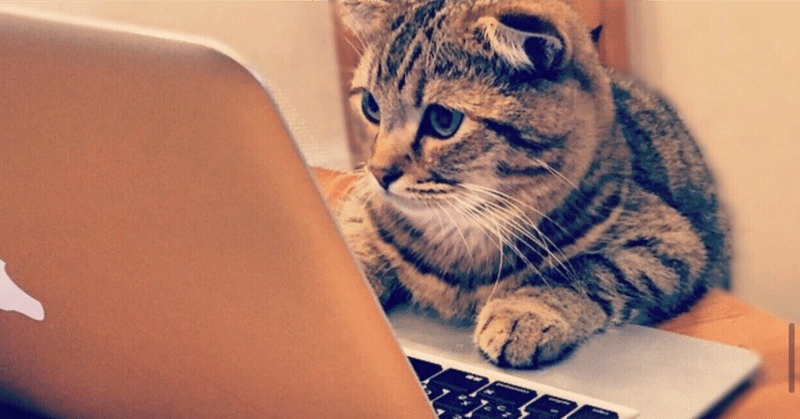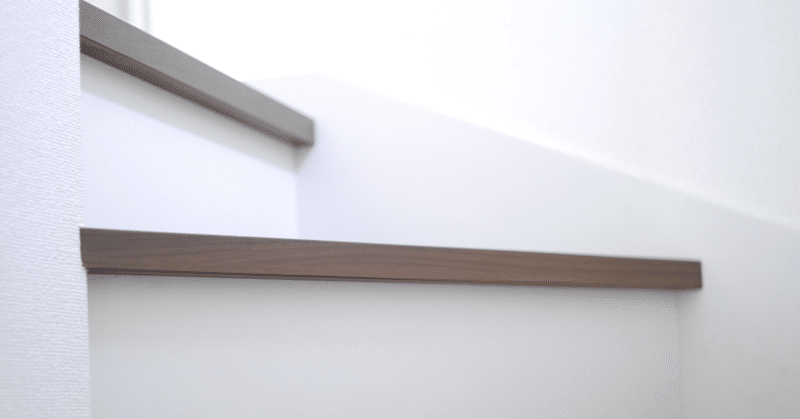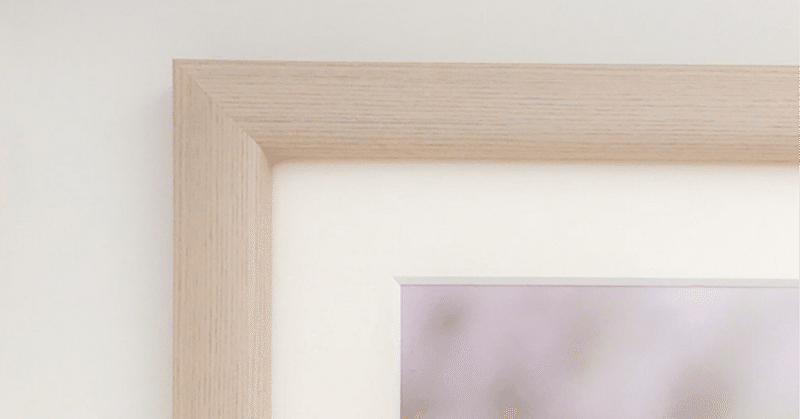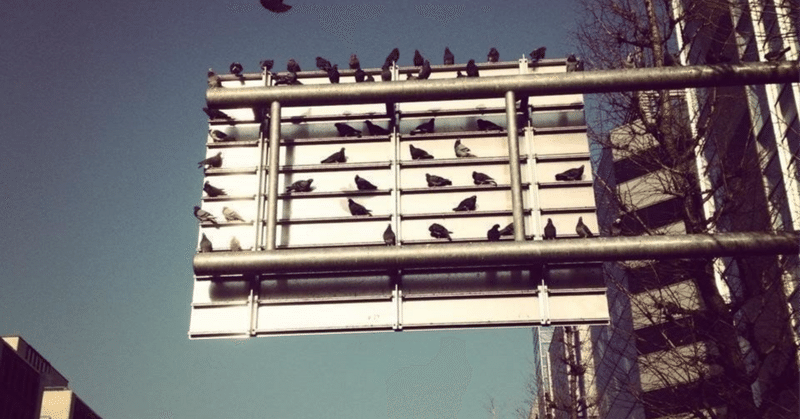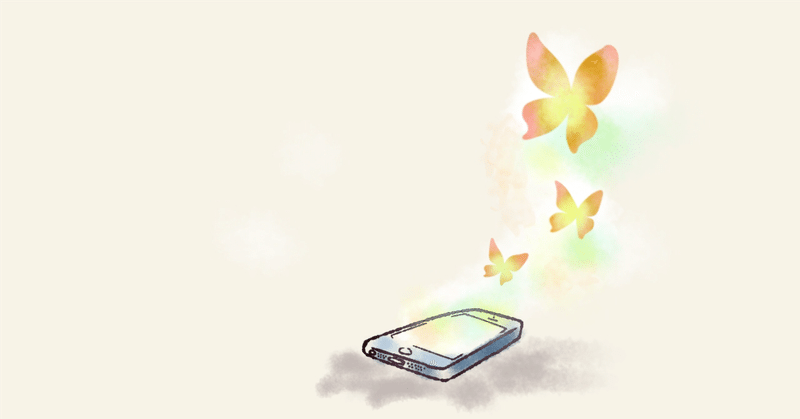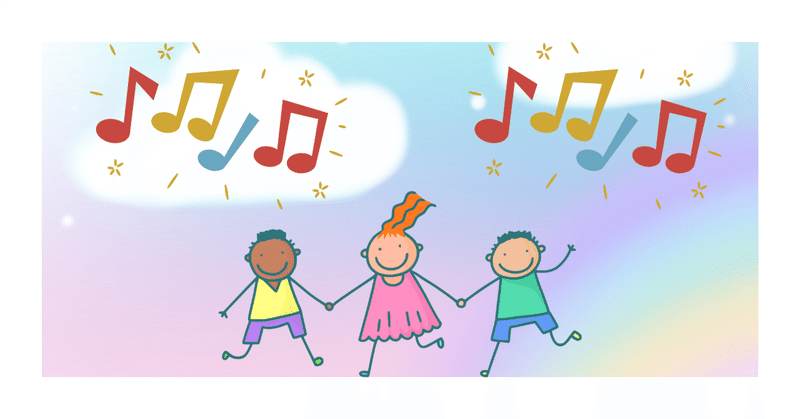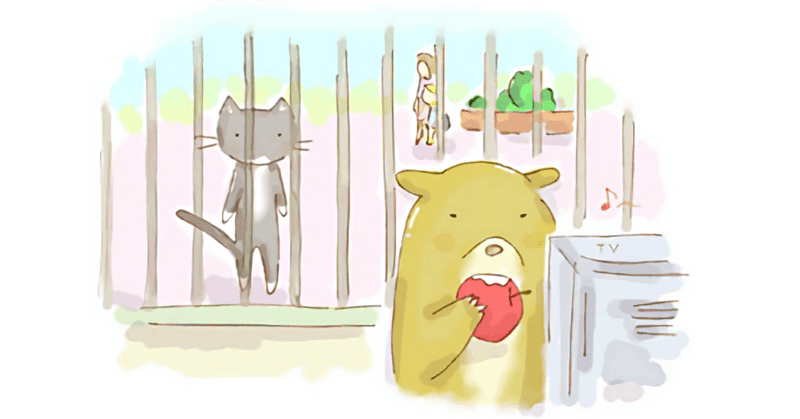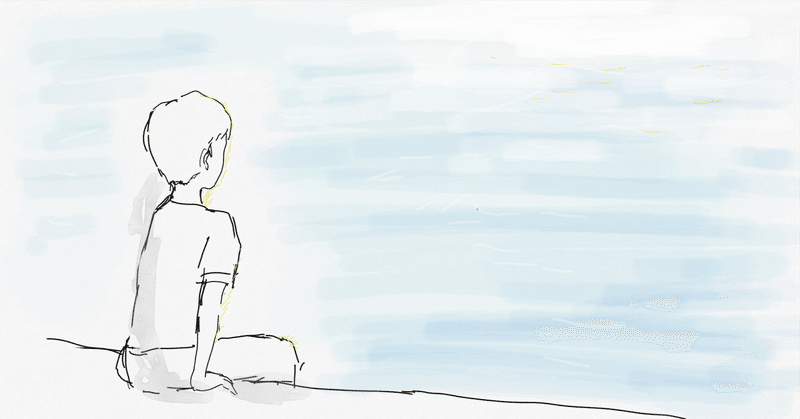#日本語
「ここには何もない」という「しるし」
space・空間・空白、sense・方向・意味、order・順序・序列
*「空白・区切り・余白」の捏造
蓮實重彥『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』所収の「Ⅰ肖像画家の黒い欲望――ミシェル・フーコー『言葉と物』を読む」を読んでいて頭に浮ぶのは、英語の「space」と、その語義である「空間」と「空白」です。
簡単に言うと、
・「空間」とは現実の立体に「ある」もの、または「感じられる」もの
で、
とりあえず仮面を裏返してみる(断片集)
今回も断片集です。見出しのある各文章は連想でつないであります。緩やかなつながりはありますが、断章としてお読みください。今後の記事のメモとして書きました。
看板、サイン、しるし
街を歩くと看板がやたら目に付きます。目に付くと言うよりも、こちらが無意識に探しているのかもしれません。無意識に物色しているとも言えそうです。
たぶん、そのようにできているのでしょう。看板は人の目を惹いてなんぼだと
蝶のように鳥のように(断片集)
今回の記事では、アスタリスク(*)ではじまる各文章を連想だけでつないでありますので――言葉やイメージを「掛ける」ことでつないでいくという意味です――、テーマに統一感がなく結びつきが緩く感じられると思います。
それぞれを独立した断片としてお読みください。
*
ない。ないから、そのないところに何かを掛ける――。
何かに、それとは別の何かを見る――。これが「何か」との出会い。遭
見えない反復、見える反復(反復とずれ・02)
人において、反復と「ずれ」(差違)は別個に起こるものではないし、対立するものでもないのではないか。そんな話をします。ややこしそうに聞こえるかもしれませんが、歌や詩を例にして具体的に話すつもりです。
見えない反復、見える反復
唱歌「故郷(ふるさと)」(作詞:高野辰之、作曲:岡野貞)です。
この歌では、ある反復が起こっているのですが、それは聞き取れるでしょうか? つまり、反復をずれとして聞き