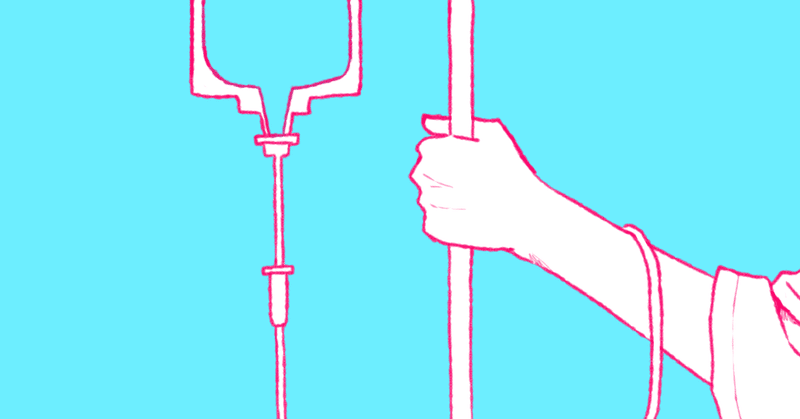
『人間終曲』
『人間終曲』
人間は忘れっぽい生き物であるらしい。
はじめて会ったときはこんなに可愛い人は他にいないと思っていて、あんなに好きだった彼女のこともやがておざなりになり、最近では会うのも些か面倒になってきた。そして、そんな自分をフンコロガシ以下のクソな人間だと思うと自己嫌悪に襲われ、生きていることがだんだんと嫌になってくる。圧死なんかで悶えて死んで、彼女に詫びを入れたい。
看護師の阿久津さんと付き合ったのは一年半以上前のことだった。私は病院の手術室で五年くらい働いていて、そこで阿久津さんと知り合ったのだ。
無論、私は看護師や医師や医療技師や薬剤師などではなく、ただの医療物品管理者である。手術室で使用する様々な物品を管理するだけの仕事だ。
阿久津さんは私の四つ下であり、まだ新人の看護師だった。小柄で、痩せており、丸顔で色白のあどけない顔をしている。そして、目がきれいだった。透明に澄んでいる。その目で私を見ながら、反抗期の小生意気な少女のような懐かしい声を出した。
私は阿久津さんの声が好きである。いつまでも聞いていたいと思わせるその声で突然、「死ね!」とか言われて面罵されても絶対に怒らないであろう。
出会った時分、私は阿久津さんを見るだけで、心が千々に乱れて、呼吸が苦しくなり、赤面した。
手術室の廊下ですれ違うとき、阿久津さんは私にさわやかな笑顔で、「おつかれさまです!」と律儀に挨拶していく。私は嬉しかった。それだけで元気になった。この仕事をしていてよかったと心の底から思った。そのうち、阿久津さんが私の視界に入ってくるだけで、妙にそわそわするようになった。
はじめて阿久津さんとまともに会話をしたときのことを今でもはっきりと覚えている。
ある日の夕方、私は複数の手術室があるフロアから少し離れた小部屋で物品の在庫を数えていた。
すると、ゴム手袋をした阿久津さんが入ってきて、
「お疲れさまです!成田さん」
と言った。私は阿久津さんが私の名前を知っていたという想定外の出来事に喫驚し、どぎまぎした。
そして、頭のなかが真っ白になり、喉元から言葉が何も出てこなかった。挨拶もまともに返せない。
しかし、阿久津さんはえくぼを見せて笑って、
「成田さんはいつもひとりで夜遅くまで残っていますよね。わたしのなかではそんなイメージです。日勤のわたしたちは夕方の定時になると、すぐに帰るので。あまり無理なさらずに、体には気をつけてくださいね。でも、もし、ここで具合が悪くなったりして、倒れたりなんかしても、助けてくれる人は周りにいっぱいいますから。もちろん、わたしも!」
と言うと、顔を真っ赤にさせた。
私は烈しい動悸がした。間を取って、「ありがとうございます」と笑いながら返したが、その声は無様なほどふるえていた。そして、毎日、朝から晩まで働き、残業し、心身ともに疲弊していた私は、阿久津さんのその言葉に心が救われたような気がした。
ニヶ月後、私は例の小部屋で物品の補充をしていると、阿久津が入ってきた。阿久津さんはムーミンのメモ帳とボールペンを持ち、棚に整然と収納してある物品を見ながら、真剣にメモを取っていた。私は何となくすぐに阿久津さんに声をかけなかった。
その後、阿久津さんは物品のことで私にあれこれ質問してきた。似たような形の物品でもパッケージやラベルの微妙な差異などで用途の異なる商品も案外多いので、私はそれらを阿久津さんに縷縷と説明した。阿久津さんの手のなかにあるメモ帳にはびっしりと文字が書き込まれている。私はそういった阿久津さんの仕事に対する熱心な姿勢に感心して、
「ずいぶんと勉強熱心ですね」
「ええ。わたし、ぺえぺえですから」
と言って、はにかんだ。そして唐突に、
「成田さんは神ですね」
「どういうことですか?」
「だって、わたしが困っているときはいつでもやさしく、何でも丁寧に教えてくれるから…」
と生真面目な顔でそう言うと、前髪を触った。
私は胸がどきどきし、耳が赤くなった。
小部屋の真っ白な壁が天井の蛍光灯の電気でまぶしく感じていたが、それ以上に阿久津さんの存在が私にとって何よりもまぶしく感じられた。
その後、私はその小部屋で何度も阿久津さんと遭遇した。そして、互いの連絡先を交換して、ご飯を食べに行き、しばらくして付き合うことになった。
私は阿久津さんと出会うまで、六年くらい彼女がいなかった。だから、阿久津さんと付き合ったとき、私はナースステーションの前でよさこいを踊りながら哄笑したいほど、気持ちが舞い上がっていた。
しかし、その気持ちはいつの間にか薄れていた。常に心が弾むような何とも言えないあの淡い感情は一体どこに行ってしまったのだろう。私は阿久津さんのことよりも自分の趣味や友達と遊ぶことを優先するようになった。挙句、ひとりでいたいという私の悪癖が露呈してきて、休みの日も阿久津さんに嘘をついてまで、ひとりで過ごすことも少なくなかった。私は自分のことを嫌なヤツだと思った。また、私は恋愛不適合者なのかもしれないと感じた。
やがて、阿久津さんが手術室の看護師を辞めるとき、「毎日、ここで働いていると、全身麻酔で手術台に眠らされている裸の患者さんたちのことが、『人』ではなくて『物』に見えてくる恐ろしさを感じるようになってきた。そこにいるのが一人の生身の人間ではなく、一体の人形が置いてあるような感じ」と言って、頬骨のあたりからこめかみにぬけるように色をのせたチークをゆがめて苦笑した。
それは直接的に患者と接する看護師ではない私でも理解できる感覚だった。日々、手術室で働いているとその環境が当たり前になり、はじめは抵抗を感じていた物事でも、すぐに何も感じなくなってくる。
たとえば、はじめの頃は、私が何かの用事で手術室に入ると、皮膚の焦げるような独特の刺激臭がするので嘔吐を催した。のみならず、開腹した患者のむきだしの臓器や床に飛び散った血液などを見たときはぎょっとし、その後の昼ご飯が喉を通らないことさえあったが、そういったことが、いつのまにか平気になるのだ。感覚が麻痺してくるのである。
無論、手術室の環境と自分の恋愛を一緒くたにして考えるのは愚昧なのかもしれないが、阿久津さんが私の隣にいることが当たり前になると、出会った時分の純真無垢な気持ちを失ってしまい、阿久津さんに対して無関心になっていた。そして、私は阿久津さんの温かな心を平然と踏みにじっていたのだ。
ある日、手術室の廊下を歩いていたら、あの時分の阿久津さんの残像が見えた。顔を赤らめて、手術室のフロアを走り回っている阿久津さんの姿である。途端に胸が締めつけられて、呼吸が苦しくなった。
すると、手術中の患者の急変を知らせるエマージェンシーコールが鳴った。複数の手術室があるフロアじゅうにけたたましいブザー音が鳴り響く。
「エマージェンシーコール、エマージェンシーコール。医師は、至急、F室にお集まりください」
という冷静なアナウンスが流れると、フロアの空気が忽ち張りつめた。そして、各手術室に入っている看護師や医療技師たちが器械台などを押しながら、F室へ一目散に走っていった。医師たちも走る。
私はその騒々しい足音を耳に入れながら、「あの患者さん、命が助かるといいな」と思った。
手術室の廊下のそこここでは、手術中の赤いランプがものものしく光っている。心臓が疼いていた。
〜了〜
愚かな駄文を最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
大変感謝申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

