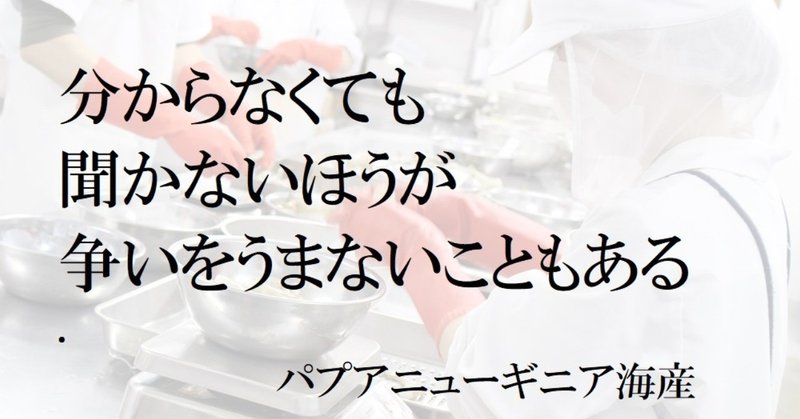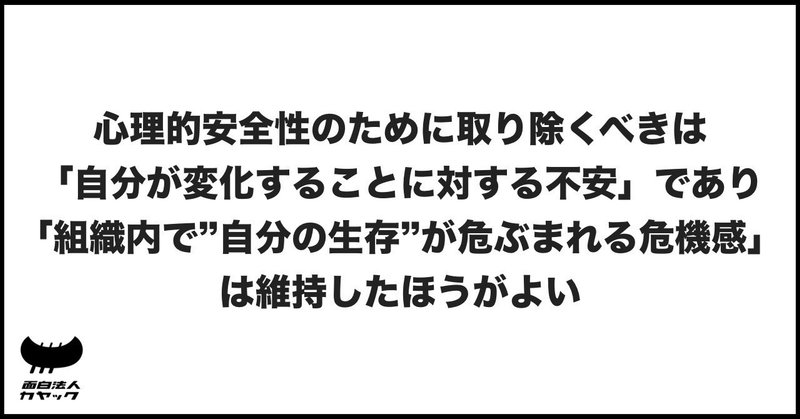- 運営しているクリエイター
2019年12月の記事一覧
見た目は大人、中身は子供
アニメの世界では逆を謳い文句にしているものもあるようですが、現実世界では見た目に反して精神年齢の低い大人が徐々に増えていると言われています。
私の身の回りにも多くて日々困っています。
「いつまでも少年のような心を持った男性」
というと聞こえがいいですが、節度や常識をわきまえなければそれはただのクソガキでしかなく、「精神年齢が低く、手のかかる幼稚な男性」というとマイナスなイメージしかありませ
067. 分からなくても、聞いてはいけないこと
同じことを聞かれても、Aさんにはイライラするけど、Bさんにはイライラしない。そんなことありませんか?
それを意識しながら作業する中で、ちょっと分かってきました。あの人はきっとイライラされるけど、この人はされないなと。
デザインマネジメント論が洗練されないわけ
八重樫文さん+安藤拓生さんの『デザインマネジメント論』を巡るポドキャストの4回目をリリースしました。
今回は4章から「デザイン推論」「創造性」「メタファー」「プロトタイピング」をとりあげました。いずれもイノベーションにデザインは有効だ!と強調されるときに使われる言葉です。これらがデザインマネジメントのなかでどう定義されているか?というわけです。
推論として「ディダクション(演繹推論)」「インダ
「デザインマネジメント」自体の意味のイノベーションが必要かも?
上の写真、ちょっとずれている変な景色だけど、こんな感じのバールで(あ、そういえば、カウンターのライトの電球が一つ切れてますね!)今日、『デザインマネジメント論』の6回目の対談を八重樫さんと行いました。画像から想像できると思うけど、やや低めの椅子に座って、我々の席のちょうど上にスピーカーがあり、そこでクリスマスソングがずっと流れている、という状況です。
およそ150ページの本について毎回1時間近く
人を動かす三原則とは?
デール・カーネギー著の「人を動かす」の中で、「人を動かす三原則」というものが出てきます。
これについて、自分ごととして考えてみました。
1)相手を批判しない。
仕事について他人と議論を交わすとき、往々にして主張が異なります。ある人は「それはAだ!」と言い、ある人は「それはBだ!」と言います。
自分と異なる意見をぶつけられたとき、「それは違う!」と思ってしまうのが普通だと思います。
ここで問題は、
システムで結果が出る人、出ない人
FROM ボブ・バーグ
私はよく、システムというものをビジネスで活用するメリットについて言及することがある。まず私が言うところのシステムの定義は、以下の通りだ。
私が唱えるシステムの定義
「システムとは、論理的なルールやノウハウに基づいたルールにしたがうことで、予測可能な結果を実現するためのプロセスである」。
そう、この定義づけで重要なのは、「予測可能な結果を実現する」という部分だ。分かりや
まるでコミュニティのマネジメントのような一貫性のある組織とは?
こんにちは、ミラティブという会社ををやっている、赤川と申します。
2019年は、ミラティブ社の経営を、七転八倒しながらやっていましたが、その中で、サービスとしてのコミュニティと、会社の組織との共通点を発見することができました。
サービスと会社組織、それぞれ異なるissueだったとしても、それらに一本の芯を通して、「面」として捉えれば、共通の解決策と、一貫性のある文化が浮かび上がってきて、そこか
あなたの影響力で「組織を動かす」ためには
“この記事は事業会社で働くデザイナーを中心としたコミュニティInHouseDesignersのアドベントカレンダーの記事です。”
プロダクトづくりにはデザイン思考や、リーンスタートアップなど、世の中には既存の優れたモノづくりのための思考法やフレームワークがすでに多く存在しています、
それらの方法論を利用することで顧客やチームの課題を解決することができると多くの書籍では語られていますが、そ
「海賊王に、おれはなるっ!」主人公には自信を、ライバルにはプライドを与えよ。
物語の主人公には、目先の勝利にとらわれずに遠くをめざす美学を持たせる。ただその美学をもつまえに、自信をもたせないといけない。なんとかなるって自信を持ってはじめて目先にこだわらないでいられる。
自信とは、途方もない目標に対して、なんとかなると思うことだ。孫さんが創業時にミカン箱の上に乗って、「自分はこの会社を豆腐屋みたいに1兆、2兆と数えられるくらいにもうかる会社にする」と言ったことと、ワンピース
カナダのスタートアップ企業で得た働きやすさに関する知見10選
バンクーバーにある某ウェアラブルデバイス制作のスタートアップ企業を退社して早数ヶ月たちました。
2年間のカナダ企業勤務で得た働きやすさに関する知見を独り占めするのももったいないので、記憶がまだ鮮明なうちにまとめておこうと思います。
いちエンジニア目線の雑感ですが、関係のない職種の方にも通じるところはたくさんあると思うので、ぜひ参考にしてください。
前情報としては、私は日本でweb/UIデザイナ
ミッション・ビジョン・バリューは誰のもの?
採用を運用含めまるっと担当する CASTER BIZ recruitingで責任者をしている@MihoMorikazuです。
先日、事業部の有志メンバーで集まって、事業部のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を再定義しました。
今日は、なぜ再定義したのか、どんな風にMVVを再定義したのか、どんなMVVができたのか、その後…について書きます。
こんな人が読むといいかも- 組織のミッション・