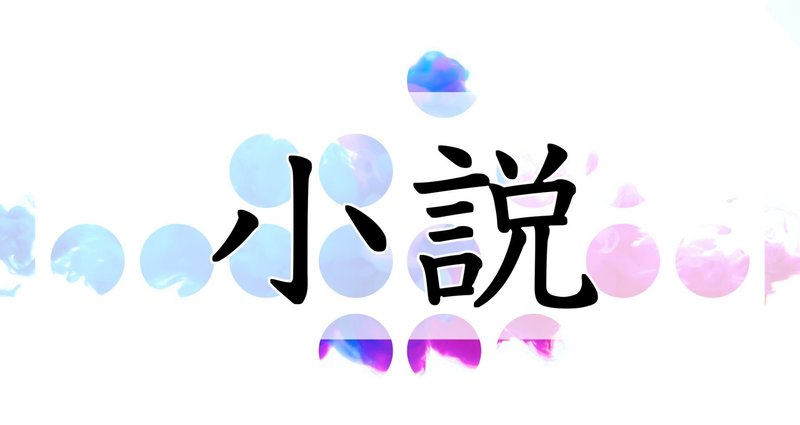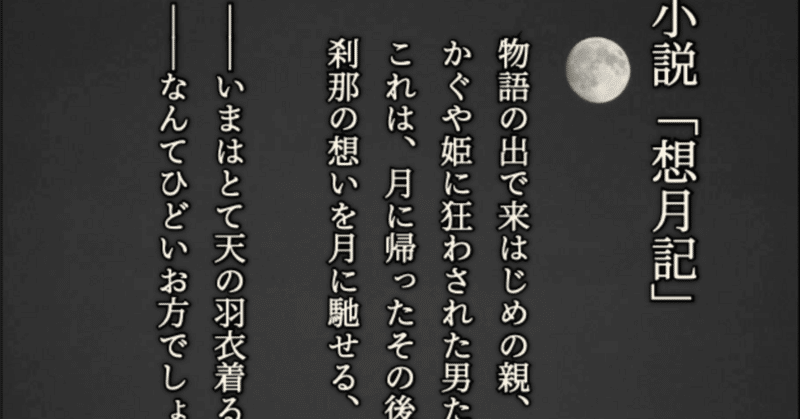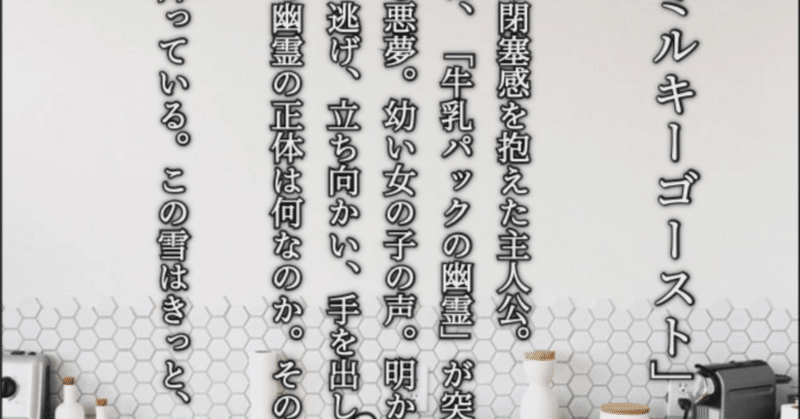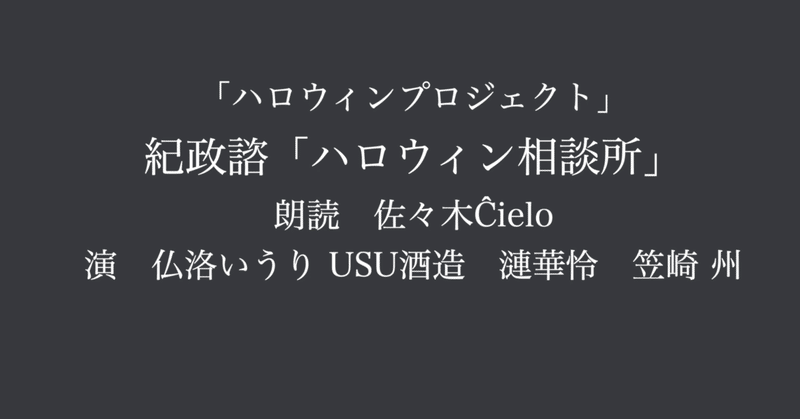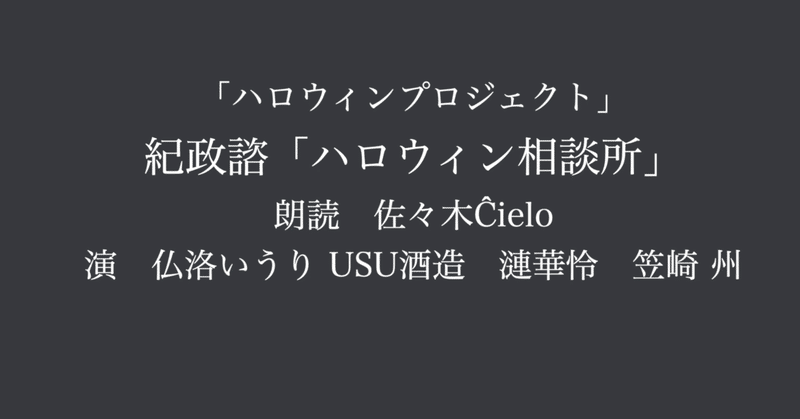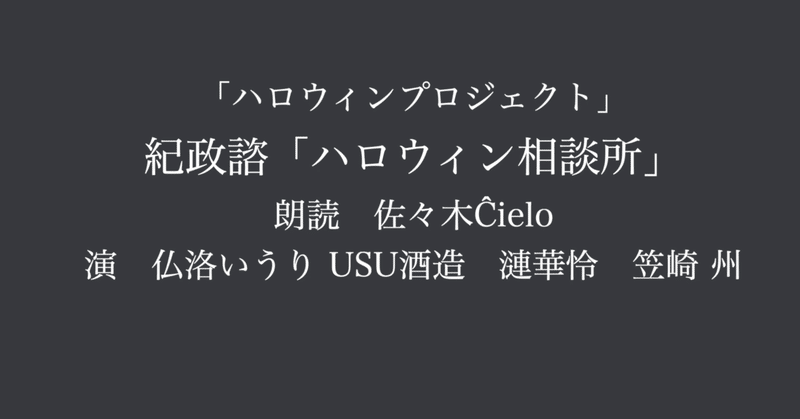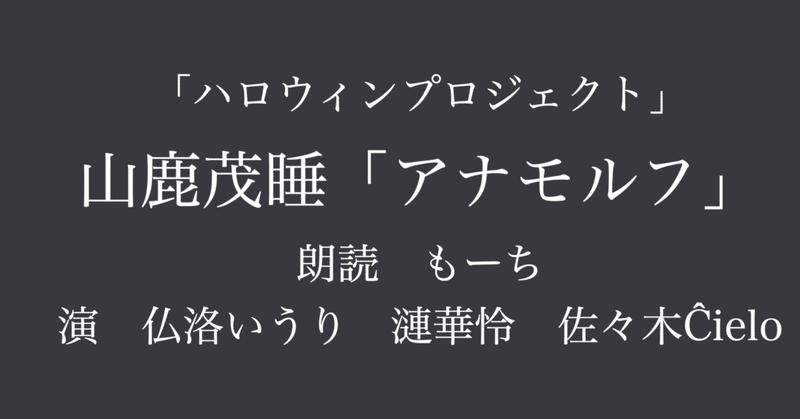#サークル
紀政諮「ハロウィン相談所」後編
狼男の少年の歌に、王女は聞き覚えがありました。
「レ・ミゼラブル」
「この街に来て、初めて仕事をくれたのは、どこの娘ともしれない女の人でした。『家出をしてきたの。けど怖いから護衛をしてくれない?』と僕を雇った彼女は、いろんなところへ連れて行ってくれた。そうして一緒に入った劇場で、そのミュージカルを見たんです。たからかに歌って、バリケードにこもって、王国軍に一矢報いながら死んでいく彼らに魅了された
紀政諮「ハロウィン相談所」中編
狼男の少年は、ポットを持って立ったままです。
「王女さま……いや、魔女さん、警官隊は明日にでも攻めてくる。そうですよね?」
魔女がびくりと驚きます。
「他の相談者さんからいろんな話を聞いていて、だいたいわかるんですよ。……ミイラ男さん、もう遅いんです。だから、僕らは成長をやめることにしました」
そういうと、狼男の少年はポットを窓の外へ放り投げました。陶器とガラスの割れる音がうるさく響きます。
紀政諮「ハロウィン相談所」前編
山のように積まれたお菓子。それに埋もれて幸せそうな息子。その笑顔を前にして、
「このお話を、ずっと読んでた」
そう語りだした。
昔々、貧民あふれる王都でのお話でございます。「トリックオアトリート!」と、ハロウィンでもないのに一年中お菓子をせがみ、代わりにちょっとした仕事を受け持つという商売が、貧しい子供たちの間で流行したんだそうです。使い勝手がよろしく、また、金でもないもののためにせっせこ
山鹿茂睡「アナモルフ」後編
「ほら、ゾンビさん行くよ?」
日没を感じさせない渋谷駅の光は、この世のものではない住人が支配していた。三笠はメイドゾンビと流行に乗ったコスプレをしてきた。特に調べるでもなく、周りを見ればそれが流行りなのかどうかイイジマにも理解ができた。視界に収まりきらない無数の人々は混ざることなく渋谷の光を反射させていた。
「メイドゾンビ、チャイナドレスの男、黄色いネズミに、青い猫? あれは総書記とSP!? バ
長谷川不可視「トリップ・オア・トリート」後編
「ダン!」
そのまま扉はバタン、と閉まってしまった。劣化の具合を差し引いても不自然に重厚な音だった。それっきり何の物音も聞こえてこない。
数分後、ドナベールは勇気を振り絞ってドアの前に立つ。長身のドナベールよりも更に細長いドア。ドアに触れるだけで生気を吸い取られるようだ。
「……はぁー」
開けたくは無い。だが超常的な何かを信じているわけでも無い。この恐怖から察するに中にいるのはひどくても多分
ささど「花火とその余熱」前編
「今年もたのしかったね、塔也くん」
関野遥が僕に笑みを向けながらそう言った。余裕を湛えた、世界の全てにーー彼女の認識する世界そのものに――慈愛を注ぐような、そのような笑顔だった。慎ましい美しさが遥を包み込んでいる。しかし、その姿は僕を幸せにはしてくれない。
大晦日の午後一一時三〇分、僕と遥は山奥の国道上にいる。道路自体は綺麗に舗装されているが、ガードレールを境界として、その先には暗い山肌が広が