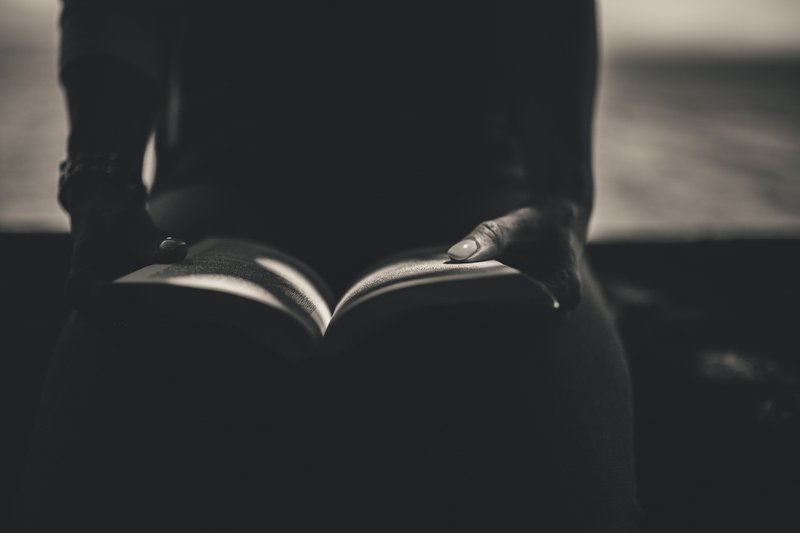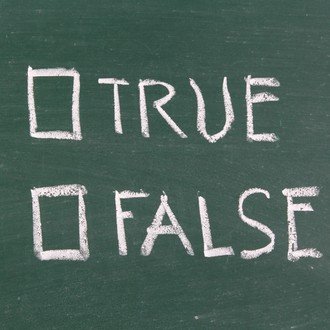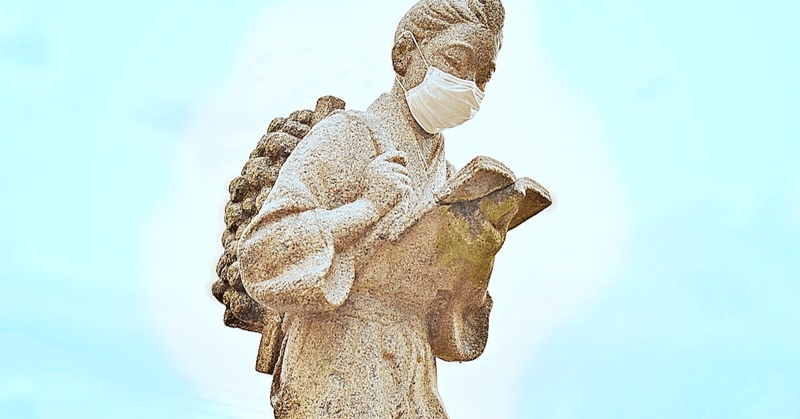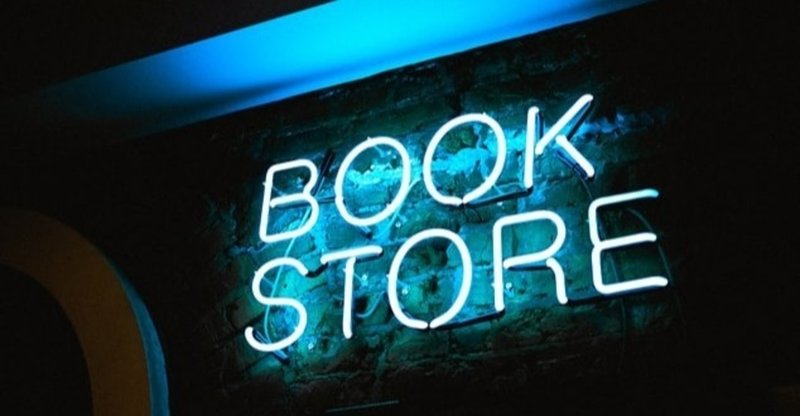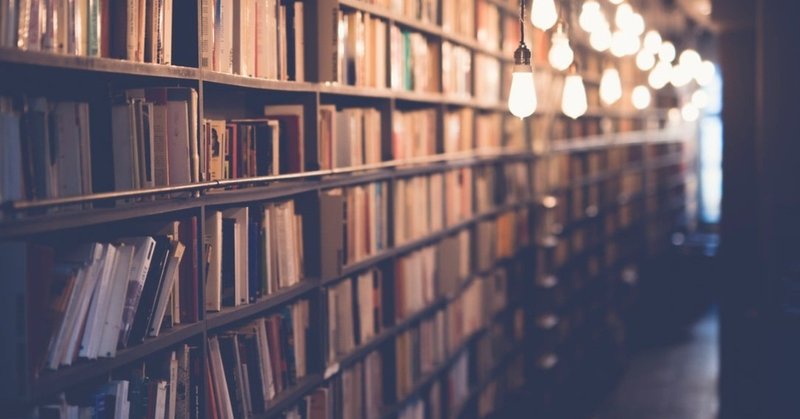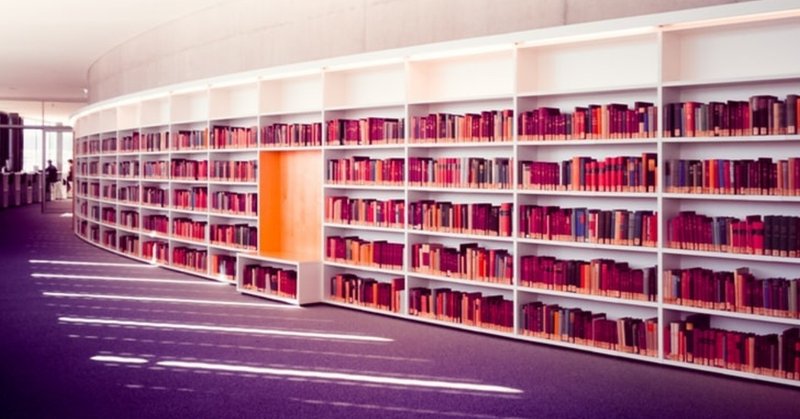#本
「アマゾン」の「あとで買う」機能がとても便利な話
▼新刊本を買う時、アマゾンの「あとで買う」機能はとても便利だ。「あとで買う」の一覧が、たとえ100冊を超えても、筆者のデスクトップで閲覧すると、1列に8冊の表紙が並び、次々と眺めることができて、とても一覧性が高い。
▼アマゾンの「この商品を見た後に買っているのは?」機能なども、思いもよらない本が出てきて、面白い。それらのなかで、気になったものを「カート」に入れて、「あとで買う」ボタンを押せば、あ
終戦記念日の新聞を読む2019(7)~産経新聞『経済学者たちの日米開戦』評
▼1冊の本をどう評するかで、評した人の考えがわかる。2019年8月15日付の産経新聞に、牧野邦昭氏の名作『経済学者たちの日米開戦』の著者インタビューが載っていた。(磨井慎吾記者)
▼この本の核心である、〈なぜ非合理的な開戦の決断に至ったのか〉の理由について。適宜改行。
〈牧野准教授は2つの要因を挙げる。1つは、人間はどちらを選んでも損失が予想される場合、失敗すればより巨大な損失を出す恐れがある
終戦記念日の新聞を読む2019(2)愛媛新聞「地軸」~言葉の底を読み解く
▼読み解く、という言葉の意味を考えさせてくれるコラム。2019年8月15日付の愛媛新聞「地軸」から。
▼冒頭は〈わが子を胸の下にかばい守ろうとした母親の姿は、皆の脳裏に焼き付いていた。広島市の原爆資料館には黒く焦げた親子の遺体の絵が何枚もある。〉
このコラムでは、広島市立大広島平和研究所教授の直野章子氏の知見が紹介されている。直野氏は「『原爆の絵』と出会う」(岩波ブックレット)の著者。
〈被
『「いいね!」戦争』を読む(19)人間が「フェイク」化しつつある件
▼ロシアが、たとえば「トランプを熱烈に擁護するアメリカ人」のアカウントを捏造してきたことは、国際的な大問題になったから、すでによく知られるようになった。
筆者は『「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」を読んで、2017年にツイッターに登場した「アンジー・ディクソン」という有名な女性女性が、〈ツイッターを侵食し、アメリカの政治対話をね
『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。
▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では
「偽情報経済」(216頁)
という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ
『「いいね!」戦争』を読む(17)SNSは「承認」が最大の目的の件
▼前号では、「フェイクニュース」という言葉が広まっただけでなく、「フェイクニュース」の「定義」そのものが変えられてしまったきっかけが、アメリカ大統領選挙であり、なかんずくトランプ氏の行動だったことに触れた。
「フェイクニュース」は、もともとの「真実でないことが検証可能なニュース」という意味から、「気に入らない情報を侮蔑(ぶべつ)する言葉」、つまり、「客観的」な言葉から、とても「主観的」な言葉に変
『「いいね!」戦争』を読む(16) 「フェイクニュース」誕生の論理
▼ここ数年、ネットの中で「嘘(うそ)」が蔓延(まんえん)するスピードが、やたら速くなった。
すでによく知られるようになったある常識について、『「いいね!」戦争』がわかりやすく説明していた。
ちなみに2019年7月10日の21時現在、まだカスタマーレビューは0件。
▼MIT(マサチューセッツ工科大学)のデータサイエンティストたちが、ツイッターの「噂の滝(ルーマー・カスケード)」(まだ真偽が検証
『「いいね!」戦争』を読む(15) 「アラブの春」が独裁に繋がった理由
▼「アラブの春」が、なぜ独裁主義に吸収されてしまったのか。『「いいね!」戦争』は、「確証バイアス」や「エコーチェンバー」現象などの知見を使って絵解きしている。
▼毎度おなじみ、カスタマーレビューはまだ0件だ。2019年7月10日10時現在。
▼以下の引用箇所を読めばわかるが、この経緯から引き出せる教訓は、「アラブの春」だけに限った話ではない。ジョージ・ワシントン大学公共外交・グローバルコミュニ
『「いいね!」戦争』を読む(14) 「確証バイアス」は脳の最悪の衝動の件
▼「インターネットと戦争と生活」について考えさせられる名著『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」は、人間の「脳」をめぐるネット戦略の中間報告になっている。
▼2019年7月8日現在で、まだカスタマーレビューは0件。0件のまま半月も経つと、なんだか面白くなってきた。
▼前回は、記事が真実であるかどうかは重要ではなく、「なじみがあるかどうか」で判断が分かれる、と
『「いいね!」戦争』を読む(13)記事は「真実」でなくても構わない件
▼今号で紹介するのは、「オンラインの生態学」とでもいうべきものだ。
『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」の続き。
▼前号は、最近よく目にする「フィルターバブル」と「エコーチェンバー」の簡単な解説だった。
▼ところで、『「いいね!」戦争』には、まだアマゾンでカスタマーレビューが1件もつかない。2019年7月7日現在。
▼先に「オンラインの生態学」と書いた
『「いいね!」戦争』を読む(12) 「友だち」の数ですべてが決まる件
▼人間には、仲間を求める本能がそなわっている。それが「ホモフィリー」(同質性)だ。前号では、この「ホモフィリー」が、SNSとのつきあい方を考えるキーワードであることにちょっとだけ触れた。
▼『「いいね!」戦争』では、この「ホモフィリー」(同質性)のくわしい仕組みを説明しているが、その説明の中に、さらに2つのキーワードが入り込んでいるので、一つずつチェックしていきたい。
2つのキーワードというの
『「いいね!」戦争』を読む(11)「事実」とは「合意」の問題である件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」に入る前に、第4章のラストに紹介されている術語(ターム)に触れておこう。
「ガスライティング」
これは〈パートナーが真実を操作もしくは否定することによって相手を支配しようとする関係を指すようになった〉(188頁)ということで、不思議なネーミングの由来は、有名な映画(もとは舞台)の「ガス燈」だ。
悪い夫の策略によって、