
映画 『オーソン・ウェルズのフォルスタッフ』 : 陽気なホラ吹き男の「孤影」
映画評:オーソン・ウェルズ監督『オーソン・ウェルズのフォルスタッフ』(1965年、スペイン・スイス合作映画)
オーソン・ウェルズによる「フォルスタッフ」である。
なんで邦題が『オーソン・ウェルズのフォルスタッフ』なのかと言えば、西欧では「フォルスタッフ」はあまりにも有名なキャラクターなので、タイトルだけでは、誰のどの作品を指しているのかわからにくいからであろう。同様の事例としては『ゴダールのリア王』もある。「リア王」が、あまりにも有名であるために、かえって日本では「ゴダールの」と付けているのだ。
もちろん、『リア王』は、ウィリアム・シェイクスピアの作品(戯曲)であり、「フォルスタッフ」も「リア王」と同様、シャイクスピアの創造したキャラクターなのだが、「リア王」の方は主人公であり、その名がタイトルになっているので、舞台を観たり、本で読んだりしたことがなくても、そのタイトルくらいなら聞いたことのある人も多いだろう。
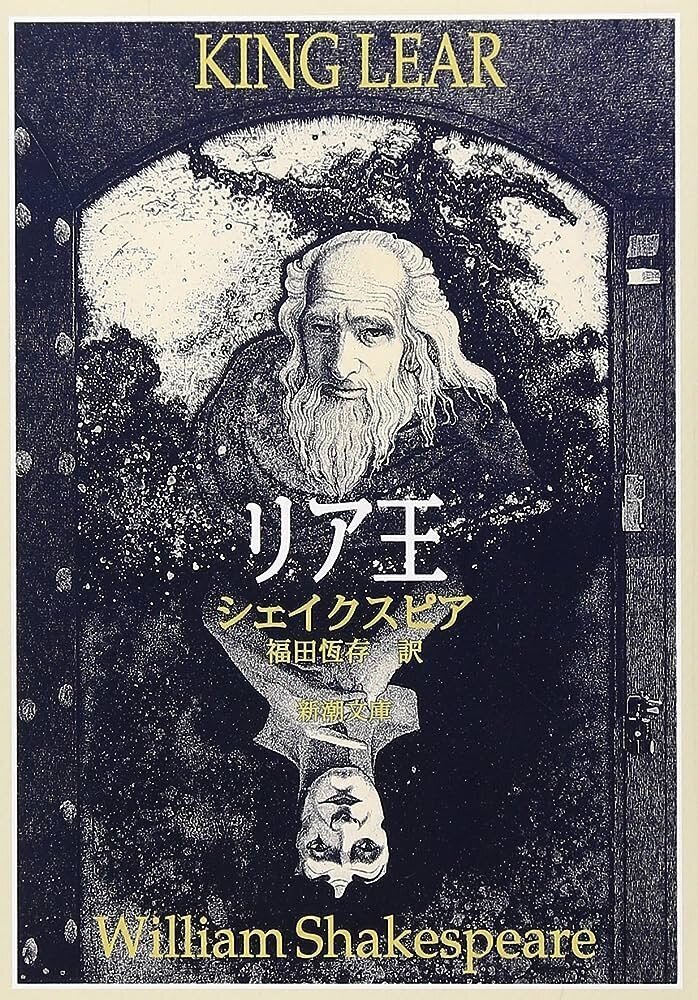
だが、シェイクスピアに「フォルスタッフ」というタイトルの作品はない。彼、フォルスタッフはあくまでも「脇役」だからだ。
フォルスタッフは、シェイクスピアの戯曲『ヘンリー四世』で初登場する脇役キャラなのだが、そのあまりにも魅力的な人物造形に人気が高まり、のちには、シェイクスピア自身が、フォルスタッフを主人公とした『ウィンザーの陽気な女房たち』を書くことにもなる。

このあたりの事情については、「Wikipedia」の次の説明が簡明なものであろう。
『サー・ジョン・フォルスタッフ(Sir John Falstaff)は、ウィリアム・シェイクスピアの作品(ヘンリアド)に登場する架空の人物。言語によっては「ファルスタッフ」とも。
大兵肥満の老騎士。臆病者で「戦場にはビリっかす」、大酒飲みで強欲、狡猾で好色だが、限りないウィット(機知)に恵まれ、時として深遠な警句を吐く憎めない人物として描かれ、上演当時から現代に至るまでファンが多い。
フォルスタッフ「名誉だと? そんなもので腹がふくれるか?」
シェイクスピアの生み出した数多くの劇中人物の中でも、「劇を飛び出して生きた」息子は二人だけだと言われている(フォルスタッフとシャイロック)。
『ヘンリー四世』(2部作)ではハル王子(後のヘンリー5世)の放蕩仲間として登場するが、第2部の最後に即位してヘンリー5世となった王子に追放されてしまう。続編の『ヘンリー五世』では、追放後まもなく失意の中で、(フランスで汗かき病のため)死んだことが仲間(ピストール、バードルフ)の口から語られるという形で紹介される。
ピストール「地獄ででもいいから、ヤツと一緒にいたいよ…」
もっとも、このようなフォルスタッフの「殺害」については、当時から人気の高かったフォルスタッフを勝手に登場させた戯曲などがまかり通っており、シェイクスピアはそのような事態を防ぐために、自らの「息子」を死んだことにして守らなければならなかったといわれている。
イングランド女王エリザベス1世がフォルスタッフをたいそう気に入り「彼の恋物語が見たい」と所望したため、シェイクスピアはフォルスタッフを主人公とした『ウィンザーの陽気な女房たち』を書いたと言う説もある。同作では勝手な思い込みから2人の夫人に恋を仕掛ける愉快な好色漢として描かれている。』
このように、フォルスタッフは、いわゆる「ヒーロー(英雄)」ではないし、かといって「ヒール(悪役)」でもない。
いわゆる悪漢ではあるのだけれども、単純な悪党ではなく、人間的な魅力と愛嬌を兼ね備えた、その肥え太った巨体に相応しい「幅のある」キャラクターであり、そこが多くの人から愛されることにもなったのである。

さて、私がなぜこの映画を観たのかというと、それはもちろん、敬愛するオーソン・ウェルズの作品だということと、昔からフォルスタッフというキャラクターには惹かれるものがあったからだ。したがって、この両者が交差するところに、興味を持たないわけにはいかなかったのである。
私が観たDVDには、小型パンフレットが付属していて、そこには映画評論家・吉田広明の「作品解説」と、英文学者・高山宏の寄稿文「フォルスタッフみたいなオーソン・ウェルズ」が収録されている。この高山文の中には、次のような部分がある。
『 神や名誉をキーワードにいわばどんどん精神化し始めていく時代(「近代」)に、これは未来永劫まったく変わることない人間の自然である「肉体」をまともにぶつけるとそれがそのまま、近代批判になるのだと言いだしたのも一九六〇年代の有力批評だった。ヤン・コットもその一人だったが、なにしろロシア人批評家ミハイル・バフチンによるラブレー研究や『ドストエフスキーの詩学』だった。バフチンが英訳されたのは『オーソン・ウェルズのフォルスタッフ』完成の後にはなるが、ヤン・コットやバフチンによる、近代文明が人間の肉体的部分をいかに「追放」してきたか論じる仕事は時代全体の大きな潮流となっていた。肉体を通じての近代批判を実行したとされた道化たちへの研究が一九六〇年代に爆発的に流行した事情は、今なお世界に誇ってよい人類学者、山口昌男の道化研究がまさしく一九六〇年代に突発したこと一点を思いだせば明らかだろう。ヤン・コットの盟友であり、バフチンの最強力推せん者だった故・山口氏にこそ見せたかった今回のリマスター版である。一九六五年完成版の方について氏がきっと何か面白いことを書いているはずだ。著作量が多すぎて、今は確認できていないが、多分。』
私に「フォルスタッフ」の存在とその魅力を教えてくれたのが、ここで紹介されている文化人類学者・山口昌男である。私は若い頃に山口の著作を読んでおり、多大な影響を受けた。
今、昔つけていた読書ノートを確認してみると、山口の著作を7冊ほど読んでいるのだが、それらの目次の中には「フォルスタッフ」の名は見当たらない。だが、これは「フォルスタッフ」の名を冠したエッセイが無いというだけで、山口は何度も「フォルスタッフ」に言及していたはずで、私はその影響を受けて、「フォルスタッフ○○の研究」といったタイトルの、無名の友人を扱った人物論を書いたこともある(○○の部分に、友人の苗字が入る)。
山口昌男の主著は、やはり『道化の民俗学』ということになるだろうが、山口がこの「道化(道化師、ピエロ、アルレッキーノ)」といったものをどのように捉えていたのかというと、別のエッセイ集のタイトル『笑いと逸脱』という表現が、一番わかりやすいのではないかと思う。
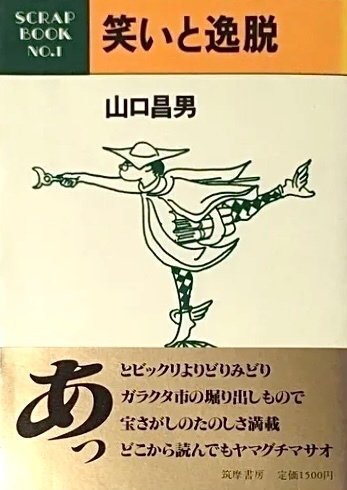
つまり、道化は「笑っている」「ふざけている」存在であり、その意味で「真面目」の対極にある。また、「ふざけている」というのは、「王道」「正統」といったものから「逸脱」した存在であることを意味する。
つまり、道化というのは「正統派」でも「正義の味方」でもなければ、バットマンのような「ダークヒーロー」でもなく、むしろ「ジョーカー」的な存在であり、その意味で「悪漢」であり「悪魔」なのだが、しかし「暗く」はないのだ。いつも「ふざけている」し「笑っている」悪漢であり、その意味で、アメコミヒーローの一人、バットマンの宿敵であるジョーカーこそが、「道化」のイメージに近いし、事実、『バットマン』に登場するジョーカーは、「道化師=ピエロ」と「悪魔」の合成されたイメージなのだと言えるだろう。

しかし、それに比べれば、フェルスタッフは、そこまでの「悪魔性」は持っていないし、もっと「庶民的」であり「人間的」で、そんな「愛嬌のある」キャラクターだからこそ、多くの人に愛されたのだと言えるだろう。
言い換えれば、フォルスタッフの「道化性」とは、ジョーカーのような「(神性に対する)悪魔性」ではなく、「(神性に対する)人間性」なのだ。
例えば、アカデミー賞をとった、トッド・フィリップス監督の映画『ジョーカー』のジョーカーが、世間の「きれいごと」に対する怒りと絶望から「闇堕ち」して「悪魔」になったのは、言うなれば「きれいごと」という「神性」を信じる「真面目さ」があったれればこそである。真面目に「きれいごと」を信じていたからこそ、その信頼を無惨に裏切られた「反動」から「笑うしかない」という「悲しい悪魔」としてのジューカーになったのだと言えるだろう。
だが、フォルスタッフの場合には、もとからそうした「真面目さ」などを信じてはいない。つまり「神」などという「絵空事」を笑い飛ばしてしまう、そんな良い意味での「不真面目さ」であり「庶民性」を持った存在なのだ。
彼は決して「頭が悪い」のではなく、「真面目一辺倒」の人間こそが「頭が悪い」と考えており、だからこそ彼は『時として深遠な警句を吐く』こともできるのである。
また、そんな彼だからこそ、ジョーカーのように「頭の悪い」闇堕ちなどしないのだ。単細胞にも「きれいごと」を真に受けているからこそ、それが裏切られたといって傷つき、その結果、真逆の「悪魔」に堕ちてしまうのであり、言い換えれば「人間、そんな単純なものではない。人間とは、神と悪魔の〝あいの子〟なんだよ」という「リアルな人間認識」さえ持っていれば、悪魔にまで堕ちることもなく、人間に止まっていることもできたはずなのだ。
つまり、フォルスタッフは、決して「真面目な知識人」でも「正義の人」でもないけれども、きわめて「人間的な賢い人」なのである。
そして、その賢さを、ことさらに見せつけるようなタイプの人ではなく、「悪徳もまた人間ゆえのものである」と考える、庶民的に「人間的な存在」だと言えるのだ。
○ ○ ○
さて、ここでやっと、『オーソン・ウェルズのフォルスタッフ』に移ろう。
本作の「あらすじ」は、次のようなものである。
『ボリングブルック公(ジョン・ギールグッド)がヘンリー四世として即位した1400年はじめの冬。皇太子ハル(キース・バクスター)は、下町のいかがわしい居酒屋“猪首亭”で、悪名高いフォルスタッフ(オーソン・ウェルズ)と放蕩無頼の生活を送っていた。その頃、ヴォークワスの居城では、先王の世継ぎの婚姻であるパーシー一族の勇敢な若武者ホットスパー(ノーマン・ロッドウェイ)が、妻のケイト(マリナ・ヴラディ)に送られて出陣していた。ホットスパーに比べて無茶苦茶な生活を送るハルに頭を悩ませるヘンリー四世。従臣ポインズ(トニー・ベックリー)が仕組んだギャズヒルの森での追いはぎ事件の首尾を豪語するフォルスタッフ。彼の武勇談は猪首亭の名物だ。娼婦ドル(ジャンヌ・モロー)をまじえて、夜は果てることなく、騒ぎは続く。名誉と大義をかけたシュルーズベリーの合戦でハルは、見事にホットスパーを討ち倒した。やがてヘンリー四世が、たび重なる叛乱鎮圧に疲れ果て病床についた。ついにハルは王宮に戻ることになった。固い絆で結ばれていたハルとフォルスタッフは、お互いに別れを告げた。真夜中の鐘をなつかしむシャロー(アラン・ウェッブ)の城に、王の死の知らせが伝わる。わが子のことのように勇んでハルの戴冠式に馳せ参じたフォルスタッフに、しかし、国王ヘンリー五世となったハルの言葉は冷酷だった。フォルスタッフに対する追放、投獄の命だった。彼は心に深い傷を受けてやがて死んでゆくのだった。』
(「映画.com」の「ストーリー」より)
若い読者のために書いておくと、舞台は、今のイギリスである「イングランド」だ。今のフランスと、ヨーロッパの覇権を賭けての長年の戦争を繰り広げていた、戦乱の時代の話である。
つまり、イングランド王リチャード二世の下の「諸侯」の一人であったボリングブルック公が、先王のリチャード二世を倒して廃位させ、ヘンリー四世となってわけで、言うなればヘンリー四世は「先王を裏切った」人物である。
戦乱の世だから仕方がないとはいえ、そのためにヘンリー四世に対して敵意を持つ諸侯も多かった。当然、『先王の世継ぎの婚姻であるパーシー一族の勇敢な若武者ホットスパー』もヘンリー四世を敵視しており、ヘンリー四世の嫡男であるハルのことも認めていない。
ところが、その皇太子ハルは、父親のヘンリー四世が、相次ぐ反乱に苦慮している最中に、巷の悪漢どもと遊び呆けていたのであり、その親友がフォルスタッフであったということになる。



やがて、ヘンリー四世が病いの床に伏すと、息子のハルは王城に呼び戻されることになり、フォルスタッフも自分の遊び仲間であったハルが王位に就けば、これで自分の身分も保証されて安泰だと喜び、喜んでハルを王城へと送り返す。だが、ハルは、イングランドの安寧を求める父王の苦悩を目の当たりにして心を入れ替え、父王の死に伴ってヘンリー五世となる。

その戴冠式に喜んで馳せ参じたフォルスタッフは、立場も弁えずに、大勢の臣下たちの前で、親友の王位継承に賛嘆の言葉を投げるのだが、その時のハルの表情は、まさに「一国の王」に相応しく「威厳に満ちて」いっそ冷たくさえあり、フォルスタッフを見下すようにして、その行いを難じ、追放を言い渡す。そして、それに従わなければ投獄するとまで言うのである。

この時の、フォルスタッフの表情が実に素晴らしい。もちろん、名優オーソン・ウェルズの演技が素晴らしいのだ。
あっけに取られつつも、決してそこには「裏切られた怒りや悲しみ」ではなく、むしろ「そうか。お前は本物の王になっちまったんだな」という、まるで「かわいい息子が、偉くなって、父の元を巣立ちする姿を見るような」、そんな寂しさと嬉しさが同居したような、なんともやるせない表情を見せるのである。

だが、そのあと、王城を去っていくフォルスタッフは「あんなことを言ったけれど、あれはみんなの前だったから、体裁を取り繕っただけのことさ。そのうち、お召しがあるに違いない」と独りごちる。
そして、実際、ヘンリー五世となったハルは、フォルスタッフを罰する必要はないと臣下に指示し、臣下から「それでは示しがつきません」と反対されるのだが、彼は「人間、厳しいばかりではいけない。大目に見ることも必要なのだ」と、年長の臣下を諭すのであった。
だが、そんなヘンリー五世のもとに「フォルスタッフの訃報」が届けられる。フォルスタッフは、口では「新王は俺を召し抱えてくれるに違いない」などと、自分に言い聞かせるように言っていたけれど、しかし彼は、心の底では「自分は、役目を終えた存在なのだ」という自覚を持っていたということなのだろう。だからこそ、気落ちして死んでしまったのである。
この映画を見ていて、感心させられるシーンの一つに、ハルの父親ヘンリー四世を演じた、シェイクスピア劇の名優として知られるジョン・ギールグッドの、王としての苦悩を語る独白シーンでの演技の素晴らしさだ。
そのシーンは、いわゆる映画的なリアリズムではなく、舞台演劇的な独白を、ギールグッドが滔々と語るのだが、その迫力が素晴らしく、映画であることを忘れさせて、違和感などまったく与えない、見事なものなのである。また、ギールグッドのこうした名演があってこそのヘンリー四世であったから、皇太子ハルの改心も説得力を持ったのだ。

だが、しかし、ここでひとつ言えるのは、DVD付属のミニパンフで、映画評論家の吉田広明も指摘していたとおり、ハルの実父であるヘンリー四世の「重厚さ」とか「王たる者の責任感」とかいった「真面目さ」とは、フォルスタッフの「軽さ」「無責任さ」の対極にあるものだ、という点である。
たしかにヘンリー四世は、「真面目な権力者」ではあっただろうが、そのために多くの者に血を流させることにもなった。その点、不真面目な悪漢であるフォルスタッフの犯罪とは、せいぜい追い剥ぎ程度であり、彼の語る「何人を殺した」とかいった自慢話は、所詮はホラでしかない。
つまり、ヘンリー四世とフォルスタッフは、「両極的」な存在であり、双方には「一長一短」があって、どちらか一方が正しいとは言えない、言うなれば「相補的」な存在なのである。
そして、皇太子ハルは、言うなれば、そんな二人を「父」として成長し、やがて「王」になったのである。
この物語の最後は、「ヘンリー五世」が、勇敢かつ情理を弁えた名君となったと語られて幕が閉じられるのだが、つまりヘンリー五世が、父王を超えた名君になれたのは、フォルスタッフという存在がいたからに他ならない。
無論、フォルスタッフの「子」のままでは、彼は堕落したチンピラのままで終わったけれども、フォルスタッフから学ぶべきことを学んだ後、フォルスタッフ的な限界を切って捨てたからこそ、彼は「名君」になれたのである。
だが、言い換えれば、フィルスタッフは、「名君を生むための捨て石」だったとも言え、その意味で、フォルスタッフには、その「陽気さ」にもかかわらず、「哀切感」がつきまとう。
だが、だからこそ、彼は多くの人に愛されたのであろう。単に陽気なだけではなく、この世を照らしたあと、やがてその役目を終えて沈んでいく夕日のような存在である彼に、人々は「人生」というものを見たのではないだろうか。
山口昌男の、あまりにも有名な「中心と周縁」理論も、言うなれば「王と道化」の、こうした弁証法的な関係を語ったものである。
どちらか一方だけが大切なのではなく、周縁は、中心を刺激し挑発することで「生気返し」をする必要不可欠な存在なのだ。決して、「神に対する悪魔」のような、単純に「中心に敵対する存在」などではない。そもそも周縁なくして、中心など存在し得ないのだ。
だが、それでも、そうした「周縁」の役目は、やはり「脇役」的であり、世間的には「不遇」なものとなりがちで、どこか「物悲しい陰」を帯ざるを得ない。
私がオーソン・ウェルズに惹かれるのも、彼にはそうした「陰」があるからだ。
「天才」だと謳われなからも、絶大な権力を揶揄ったために、今では「オールタイムベストワン映画」とも呼ばれる『市民ケーン』は、アカデミー賞を受賞することができなかったし、結果として、彼はハリウッドを追われることにもなる。
彼が作りたい映画は、ハリウッドが求めるような「明るく能天気」なものではなく、いつも独特の陰が差していた。
「破れ去るもの」「悪漢」「ペテン師」など、彼は、決して、人々が単純に憧れるような人物像のドラマを撮ることはせす、むしろ、そうしたものを「疑問に付す」ようなものばかりを撮りたがったがために、生涯、映画を撮るための予算を求めて、国々を渡り歩かなければならなかったのだ。
そして本作が、シェイクスピアの祖国「イギリス」の映画ではなく、「スペイン・スイス合作映画」の合作映画だというのも、そういう事情からなのだ。
スペインは、愚かにして聖なる騎士「ドン・キホーテ」を生んだ国であり、スイスは「どちらでもない国(中立国)」だというのは、いかにも象徴的なことではないだろうか。
したがって、オーソン・ウェルズが「フォルスタッフ」を演じたというのは、いかにも「そのまま」なのだ。
彼は「正統派の王」にはなれない「陰の王」なのであろう。私は、そんな彼の「孤影」に、どうしようもなく惹かれてしまうのである。

(2024年3月6日)
○ ○ ○
● ● ●
・
