
アンドレ・バザン 『映画とは何か』 : 「映画のリアル」とは何か。
アンドレ・バザンは、フランスの映画批評誌『カイエ・デュ・シネマ』誌の創刊メンバーにして、同誌の創刊から40歳の若さで亡くなるまで編集長を務めた人である。
また、同誌には若い映画マニア(シネフィル)が集って映画批評に健筆をふるい、そこからジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォー、ジャック・リベット、エリック・ロメールといった人たちが次々と映画作家(映画監督)デビューしていき、それまでのフランス映画とは一線を画した清新な映画を撮って、「ヌーヴェル・ヴァーグ」と呼ばれることになる流れを形成した一一というのは、映画の世界では、つとに知られるところである。
言い換えれば、かの「ヌーヴェル・ヴァーグ」は、『カイエ・デュ・シネマ』誌から始まったと言ってもよく、その指導的立場にあったのが、批評家アンドレ・バザンであったと、そうまとめても良い。
事実、バザンはしばしば「ヌーヴェル・ヴァーグの精神的支柱」だったと評されるし、ゴダールもバザンを『唯一にして真の批評家』と評しているほどなのだ。
そして、そんなわけでゴダールがきっかけで映画に興味を持った、映画の新参者としての私は、現在、ゴダールを中心に「ヌーヴェル・ヴァーグ」関連作家の作品を見たり、「ヌーヴェル・ヴァーグ」が乗り越えようとした、それ以前の作品を見たりしており、当然のごとくアンドレ・バザンの著作もまた必読書ということで、今回ようやく読むことになった。
で、実施に読んでみると、事前にイメージしていたのとは少々、いや、かなりイメージの違う批評を書く人であり、批評家であった。
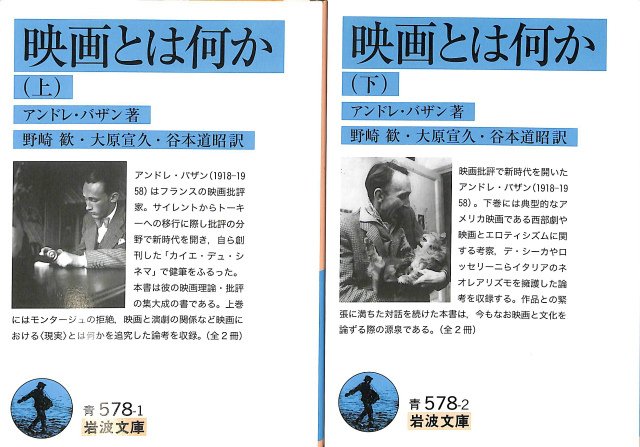
どうイメージと違っていたのかというと、「古いフランス映画」を攻撃した「ヌーヴェル・ヴァーグ」の頭領的な人なのであれば、当然「尖った」人なのかと思っていたのだが、そうではなかったのだ。
自身は新しぶるところなどなく、むしろ、オーソドックスに映画を論じ、映画を擁護する人だったのだ。
「古い映画を攻撃する」というのではなく、「新しい映画を擁護する」というタイプであり、言うなれば、「映画愛」だけではなく、そもそも「愛に溢れた人」という感じで、なるほどこの人なら『両親の離婚から孤独な少年時代を過ごし、幾度も親によって感化院に放り込まれるなど、親との関係で問題の多い少年』(Wiki)、要は「不良少年」だった若きトリュフォーを引き取って育てた、奇特な人だというのも、素直に納得することができた。
その人柄が、文章にハッキリと表れており、「未熟なものの成長を信じて、それを守り育てていく」という姿勢の明白な人であり、そんな批評家だったのである。
ちなみに、「訳者解説」の次の部分は、バザンのそんな人柄を、よく表しているので、最初に紹介しておこう。
『 ところで、バザンがその創刊にかかわり、死の直前まで編集長を務めた「カイエ・デュ・シネマ」といえば、「作家主義」によって知られる。伝統的フランス映画の「凡庸さ」を徹底的にこきおろす一方、ウェルズやヒッチコック、ジャン・ルノワールといった監督たちを無条件で賛美し、たとえ彼らが失敗作を撮ってもそこに「作家」の個性を見て取れるかぎり、凡庸な優良作よりはるかに刺激的だと考える。その先駆けとなったのは一九四六年十一月、バザンがウェルズの第二作『偉大なるアンバーソン家の人々』について「レクラン・フランセ」に寄稿した記事である。バザンは「オーソン・ウェルズは、間違いなく、作家の名に値する世界の映画作家の一人だ」と書いて、不評の作品を弁護した(※ 出典註記省略)。しかし同時に、バザンはトリュフォーら「カイエ」誌の若い友人たちが「作家」擁護を過熱させ、作家の「不謬説」つまり絶対視にまで進もうとする傾向にはくみしなかった。本書所収の「模範的な西部劇、『七人の無頼漢』」冒頭に記されているのは、中庸を忘れない批評家としての彼の心がまえである。』(P277)
○ ○ ○
本書『映画とは何か』は、著者バザン自身が断っているとおり、「映画とは、こういうものだ」という回答を示したような長編論考ではなく、バザンがその時々、求めと必要に応じて書いてきた、比較的短めの論考の、おおよそ編年体と言ってよい、アンソロジーである。
したがって、バザンの「映画観」がどのように発展変化していくのかもよくわかって、とても興味深い。
本書上巻では、まだまだ「第七芸術」としての立場を確立していなかった「映画」という表現を、既存の芸術である「文学」「演劇」「美術」等といったものとの関係において論じ、「映画」の画期的な「新しさ」を語ると同時に、そうした伝統的な芸術との避け得ない関係をどう考えるべきなのか、といったことを論じている。
つまり、「映画」が新しい芸術だからといって、言うなれば「純粋映画」を目指して、他の芸術との関わりを顧みないで進むというのではなく、「映画」というものが、他の芸術からどのようなものを汲んでいるのかを見定め、他の芸術との関わりから、何をどのような姿勢で摂取していけば良いのかというような、現実的なあり方を示しているのだ。
具体的にいうなら、「小説」や「演劇」の「映画化」といったことを、どう考えれば良いのか、といったこと具体的なことも語っており、この点などは、「アニメ」ファンである私の場合、「漫画作品のアニメ化」といった「今ここの問題」と通ずるものがあって、非常に興味深く参考になった。
一一この点については、ここで論ずることではないので、後日の論考に回すが、簡単に言うと、バザンの考えは「原作は尊重されなければならないが、表現形式が違う以上は、そのまま右から左へ機械的に写すというようなことは、原作を尊重することでも生かすことでもない」という、しごく真っ当なものであった。

さて、前記のとおり、本書上巻が、上に紹介したとおり「映画とは何か=他の芸術とは、どう違うのか」といった、言うなれば「原理論的な話」だったのに対して、下巻の方では、「映画」内ジャンルとしての、ハリウッド発の「西部劇」と、イタリア初の「ネオリアリズモ」の作品が具体的に論じられ、それを通して、バザンの基本的な構えである、「リアリズム」重視の考え方が示されている。

なお、ここでバザンの言う「リアリズム」とは、一般にイメージされるような「リアルな描写を重視した作品」とか「自然主義作品」といったことではない。
事実、本書でも、「リアリズム」と「自然主義」とは、まったく別の概念として使い分けられている。
では、どう違うのかと言えば、「自然主義」とは、一般に私たちのイメージする「自然主義文学」的な「自然主義」と思えばいい。要は、「人間や社会の、ありのままを写す」ことで、「ありのまま」を捉えて、それを表現しようという態度である。
一方、「リアリズム」というのは、「目見えるものそのまま」ではなく、目にみえる「未分化な情報の総体という現実」の中から、作家がそれぞれの感性や手法において、「リアル(なもの)」を取り出そうとする態度だとでも考えればいい。つまり「目見えるものそのまま」が「リアル」なのではなく、「リアル」とは、人間の目による「抽象化」を通して、初めて把握しうるもののことなのである。
で、こうした「リアル」理解を「面白い」と思うのは、これも私の場合だと「アニメーション」との絡みにおいて、ということになる。
アニメファン向けにわかりやすく言えば、「劇画調の絵柄のキャラクターであれば、それはリアルなのか?」「日常的な生活世界を描いた物語であれば、それはリアルなのか?」といった問題である。
もちろん、バザンの回答は「そうではない」ということになるのだが、しかし、私たちはいまだに、「劇画調のリアル」だとか「生活リアリズム」という「常識的理解」に捉われがちなのだ。
バザンの映画論における「リアル」とは、そうした世間並みのレベルに止まるものではない。
「映画」の、直近の祖先である「写真」は、「現実」を模倣する「絵画」「小説」「演劇」といったものとは決定的に違った、現実の「写像」である、とされる。
これは、今となっては、当たり前の話だと思われるかも知れないが、この違いの理解は、決定的に重要だ。なぜなら、「絵画」「小説」「演劇」に可能なのは、どんなに頑張っても「現実の模倣」でしかない(からこそ、芸術だと威張っていた)のだが、「写真」そしてその発展系である「映画」の場合は、「現実(の一部)」を直接フィルムに焼き付けるのだから、その点では、他の表現芸術には無い、特殊な優位性をハッキリと持っている(しかしまたその反面、そうした「優位性としての特質」に否応なく縛られてしまうという弱点もある)。
私は先日、蓮實重彦の著書『ショットとは何か』のレビューで、「実写映画」と「アニメ」の違いということを論じて、次のような趣旨のことを書いた。
「実写映画は、カメラで写せば、現実の一部を切り取ることができるけれども、その反面、ノイズとしての意図しない現実・情報も入ってくる。だから、映画は、そうした、過剰な現実の断片を、必要に応じて切り貼りし、情報を取捨選択することで作品が作られるのだが、アニメの場合は、もともと何もないところから作り上げられるもので、人間が意図的に作る(描き加える)ことをしないものは、何も画面には存在し得ないという特性があり、その意味では、実写映画とは真逆と言っていい(作り方の)方向性を持つものである。だから両者を、同じ「動画」として考えると、間違う部分があるだろう」
で、ここで私が気づいたのは、上の話は、結局のところ、バザンが本書で、「映画」と、「絵画」「小説」「演劇」などを区別して、「映画の特性」を語ったのと同じことだということなのた。
「実写映画」にあまり興味のなかった私は、「(二次元)アニメ」を、漠然と「映画の一種」だと考えていたのだが、バザンの線で考えるなら、「(二次元)アニメ」(※ 以下、単に「アニメ」と記す)の方が、良くも悪くも「絵画」「小説」「演劇」の延長線上にある存在(足し算の芸術)だというのが、よくわかったのである(※ なお、ここでは、人形などの実体物を齣撮りする三次元アニメは、別物と考えなければならない。この区別は重要である)。

そして、「実写映画」と「アニメ」が、その本質を異にするものなのであれば、「実写映画」というものが、単なる「実写映像」(つまり「動く写真」)に止まるものではなく、その手法において世界の「リアル」を描くためには、単に「実写」であれば良いということではなく、「実写映像」の中から、「現実の本質」を取り出してこそ、そこで初めて「リアル=現実」を表現し得たということになる。一一これが、バザンの目指す「リアリズム」なのだ。
つまり、私の言葉で言うなら、「アニメ」は「足し算の芸術」、「実写映画」は「引き算の芸術」とでも呼べよう。
だから、バザンの理論として有名な「反モンタージュ」というのも、単純に「モンタージュ」がいけないということではなく、「現実の断片の切り貼りによって、ひとつの世界としてのフィクションをでっち上げる」というようなやり方では、「映画」が本来持っていた「写像」の力を活かすことにならない、ということなのだ。
「実写映像」を切り貼りするのではなく、まずは「リアルを撮る。そして、それを生かす」ということを基本とし、その上でモンタージュということも、映画を作る上での避け得ないものとして考えるべきだ、というのがバザンの「リアリズム」なのだ。
「モンタージュありき」では、「世界の写像」性という特質を生かしきれないと、「ネオリアリズモ作品の持つ力」を検討する中で、バザンはそのように考えたのである。

だが、バザンは、だからと言って、「ネオリアリズモ」的な作品だけが「映画」だと主張しているのではない。
その証拠が「神話としての西部劇」というものの価値を積極的に認めて、さらにその一方で、そうしたものを頭から否定する「芸術至上主義というものは、映画では邪道である」とさえ言っているのだ。
その「意外」とも思える点に、バザンの基本的なスタンスがあると見て良いのである。
要は、バザンは、あらゆる可能性を否定せず、しかし、「映画」というものが持っている「世界の写像」という「特質」を生かすためには、「リアリズム」ということが重要となると、そう言っているのだ。
映画における「リアル」は、他の人間的な創作では生み出し得ないものを生み出し得るからこそ、そこを生かさなければ、「映画」のためにもならないと、一一私の理解したところでは、おおよそ、そのようなことを語っているのである。
で、以上のような説明では、なかなか理解しづらいとも思うので、最後に、私の完全オリジナルな具体的説明を付け加えておこう。
SF映画では「特撮(SFX)」という技法が、長らく用いられてきた。
例えばそれは、「現実には存在しないものを、存在するかのように見せる映像技術」であり、その典型的なものとしては「異形のモンスター」の描写などである、
昔は、こうしたものを描くのに、アナログの技術としての「SFX」が用いられ、そうしたものの代表的な作品として私が真っ先に思い浮かべるのが、ジョン・カーペンター監督の『遊星から物体X』(1982年)であり、そこに登場する「スパイダーヘッド」の描写である。あれを見た時には、本当に驚いたし、感動もした。
しかしながら、今ではこうしたものを描くのに、多くの場合「3DCG(三次元コンピュータグラフィック)」が用いられるというのは、周知のとおりで、いまや「CG」は、現実と見分けのつかないほどに「リアル」なものになっている。「SFX」が、どこまで行っても「手作り」感を脱し得ないのに対し、「CG」は「リアル」と見分けがつかない境域にまで達したのだ。

だが、すでに多くの人が気づいているとおりで、「CG」の「リアルさ」というものは、もはや退屈なものになっていると、そう言っても過言ではない。
「よくできている」とは思っても、そこに、ワクワクするようなものを感じることが、なぜかできない。
もちろん「見せ方の工夫」により、面白くすることは可能なのだが、ただ「リアルなだけ=現実そっくりに見えるだけ」では、もはや退屈なのだ。
しかし、その一方で、『遊星から物体X』における「SFX」の「スパイダーヘッド」や、「ウルトラマン」シリーズの「(優れた)ミニチュアワーク」などは、いま見ても感動的なのだが、この違いは、いったい何なのだろうか?
私が思うに、「3DCG」というのは、どんなにリアルになっても、所詮は「絵画」の延長であり、その意味で、バザンの言う意味での「リアル」ではあり得ない、ということなのではないだろうか。
つまり、「3DCG」とは、多くの場合に「実写映画」の中で使われてはいても、「実写映像の進化系」ではなく、あくまでも「二次元アニメの進化系」でしかない(それは、空間的な実体を持たない)から、バザンのいう意味での「リアル」、「世界の写像」としての「映画が持ちうるリアル」が、持ち得ないのではないか、ということである。
つまり、少なくとも、バザンの言う「リアル」とは、「現実に似ている、似せた作り物もの(非実在)」のことではなく、「(仮に)作り物ではあっても、現にそこに存在しているもの」のことであり、それを「映像化」するためには「実写」しかない、ということなのではないだろうか。
言い換えれば、「実写映画の目指すべき(優位性のある)リアル」と、「(二次元)アニメ」を含むその他の表現芸術の描き出す「リアル」とは、似て非なるものなのではないか。少なくとも、違った経路を辿って目指されるべきものなのではないか、ということである。
そうした意味でバザンは、「実写映像」を切り刻んで編集し、それで意味を持たせるという手法としての「モンタージュ」の偏重には反対なのだ。
そうではなく、「実写映像」がそもそも否応なく持っている「リアル」を生かすやり方こそが、「映画」を、最も映画たらしめるのだと、そう主張していると、私は斯様に理解したのである。
そして、そうであるならば、「アニメ」もまた「リアルであること(現実の模倣)」ではない「リアル」を目指すべきなのではないだろうか。
「現実模倣の力(説得力)」も否定しはしないが、「非存在」であることを前提とした「アニメ」には、「実写映画」には無い特性があるということを考え、その特性を生かす道を考えなければならない、ということである。
そして、こうしたことを学び得た事実からしても、バザンは今も決して古びてはいないと、そう言えるのである。
(2024年7月10日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
