
セルゲイ・エイゼンシュテイン監督 『戦艦ポチョムキン』 : イデオロギーとは、自覚困難な「色メガネ」の一種
映画評:セルゲイ・エイゼンシュテイン監督『戦艦ポチョムキン』(1925年・ソ連映画)
「モンタージュ」理論で知られる、セルゲイ・M・エイゼンシュテイン監督の第2長編にして、映画史を語る上で外せない、古典的な名作である。
ただし、内容的には、「万国の労働者よ、立ち上がれ!」という共産主義イデオロギーを宣伝鼓舞するための映画であり、今の日本で言えば「原子力発電は、日本の未来を支えるクリーンエネルギーです」とか言っている、東京電力や関西電力などの「テレビコマーシャル」の、偉大な先祖であり、その映画版だと考えれば良い。
完全な嘘をついているわけではないが、党派的な「正義」を語った作品であり、事の一面しか語っていないということくらいは、ぜひとも押さえておくべきものなのだ。
一一つまり、私がここで言いたいのは、本作『戦艦ポチョムキン』が「プロパガンダ映画だ」ということではなく、世の多くの映像作品は、今も昔も、多かれ少なかれ「プロパガンダ作品だ」ということである。

多くの人は、たいがいの映像作品を「プロパガンダ」作品だとは思わない。
だが、例えば「最後に愛は勝つ」的な「愛」だの「恋愛」の価値を絶対的なもののごとく語るような能天気な作品もまた、現実には即さない、ある種の宗教的な「党派イデオロギー」を語るものとして、一種の「プロパガンダ作品」なのだし、おのずと「宗教映画」というものは、すべて「プロパガンダ映画」である。
歴史上の人物を一面的に「偉大に」描いてみせるような伝記映画も、「日本は桜の国」的な手前みそにも一面的な描き方をするもの、あるいは「良き未来に向かって頑張ろう」的なものですら、その自覚の有無に関わりなく、すべて「プロパガンダ映画」の一種なのだ。
したがって、冷徹な批評眼を持ってすれば、「プロパガンダ(政治的宣伝)」を含まない映画などというものは、ほぼ存在しないわけなのだが、「プロパガンダ」というと、「共産主義プロパガンダ」とか「ナチスドイツのプロパガンダ」とかいったことしか思い浮かばない(推論力と想像力に欠けた)人というのは、その人自身が、ある種の「プロパガンダ」に、すっかり洗脳されきっている、ということであり、当然「理性的自己懐疑」を持つことなどできない。これが、私たちの現実だ。
その点、そんな人たちにでもわかるくらい、今や「わかりやすいプロパガンダ映画」と呼び得るものとなってしまった本作『戦艦ポチョムキン』そのものは、もはやそのイデオロギーを云々するにも値しないものだとも言えるだろう。

かつて本作を、「共産主義プロパガンダ映画」だという一面的な捉え方で全否定しようとする人たちに対抗して、日本における映画批評の草分け的な存在として尊敬される故淀川長治をはじめとした昔の映画マニアは、本作の「映画芸術」としての側面の重要さを強調することで、本作を救済したとも言えるだろう。
要は、ソ連共産主義の作品だろうと、ドイツナチズムの作品だろうと、イデオロギーだけでできているわけではなく、芸術作品としての「固有の美質」や「技術的功績」の問題は、また別の話として検討しなければならない、ということである。
無論、今でも本作を「共産主義プロパガンダ映画」だと指摘すれば、それだけで何かを言ったことになると思っているような、半世紀以上も知能の遅れた人は大勢いる。
だが、では、本作を映画芸術の「古典的名作」として言挙げする、映画マニアたちのような評価の仕方には、何の問題もないのであろうか?
「語られたイデオロギーだけで、その作品を評価してはいけない」などと、わかったようなことを言い、もっぱら「古典映画」としての本作の「技法面」だけを、知ったかぶりで論じたりすることが、はたして適切な評価だと言えるのか?
そうではあるまい。そもそも映画マニアが、そんなご高説を垂れ得るほど、イデオロギーというものの問題を、真剣に考えてきたと言えるのか。その問題の重さをわかっていると言えるのだろうか?
ろくに本も読まないで、映画ばかり見ていて、それでも「イデオロギーの問題くらいわかります」とでも言うつもりなのか?
そもそも「映画さえ見ていれば、何でもわかる」みたいなこと考えている、お気楽な人たちは、自分たちが、どれほどプチブル的な「映画芸術至上主義というイデオロギー」に染まっているか、その自覚など、カケラもあるまい。
例えば、淀川長治の「映画解説」というものもまた、「映画芸術至上主義」という党派イデオロギーに立脚した「プロパガンダ」なのだということすら、まるでわかっておらず、もちろんその自覚もなく「教祖様のおっしゃることは正しい」と、彼ら多くは、ただ右に倣っているだけなのである。

一一以上、簡単に「デプログラム(洗脳はずし)」をかましたところで、本作『戦艦ポチョムキン』について語ることにしよう。
前述のとおり、本作はわかりやすい「共産主義プロパガンダ映画」であるから、「今となっては」内容的にどうこういうほどのものではない。
簡単に言えば、歴史上の事件である「戦艦ポチョムキンの反乱」を描いた作品であり、反乱したのは水兵たちである。軍隊組織における下っ端を人間扱いぜず、ウジの湧いた肉を平気で食わせ、それで彼らをこき使っていた艦長以下の上級将官たちに対し、ひら水平たちが反旗を翻し、上級将官たちを海に放り出して艦を自主管理するとともに、ロシアで進行しつつあった労働者革命に呼応した、とまあ、大筋そんな話だと思っておけば十分である。


そんなわけで、今では本作の評価は、もっぱら「映像的映画技法」の問題として論じられる。そして、その中心となるのが、エイゼンシュテインの「モンタージュ理論」だ。
「モンタージュ」というのは、簡単に言えば、本来は無関係な2つの映像を「繋ぐ」と、そこに独自の意味が生じる、というものだ。
例えば、以前に論じた、ヒッチコックの名作『裏窓』だと、片脚を骨折したため、自宅アパートで安静にしていることを命じられた主人公が、ヒマに任せてアパートの裏窓から、裏のアパートの部屋べやの様子を覗き見して観察していると、そこで殺人事件らしきものが起こり、主人公は動けない体で真相を探ろうとする、と大筋そんなお話なのだが、問題は、連続させられた、次のような2つのカットである、
(1)ジェームズ・スチュワート演ずるところの主人公ジェフが、裏のマンションを見ている様子を写した「バストアップ」のカット
(2)ジェフの目に映っているものとしての「裏のアパートの様子」のカット


当然のことながら、この2つのカットは、別々に撮影されたものである。
(2)は、(1)のジェームズ・スチュワートの目に映っていたものではないのだ。
(1)でアップになったジェームズ・スチュワートの視線の先にあるのは「裏のアパートのセット」などではなく、監督やカメラマンなどがいる撮影所内の風景であろう。
また、(2)の「裏のアパートの様子」というのは、ジェームズ・スチュワートの「視野に入ったもの」ではなく、「カメラのフレームに入ったもの」に他ならない。
つまり現実には、(1)と(2)は、時間的空間的には、ほとんど無関係に「撮影された映像」なのだが、この二つを繋いで連続させ、それを観客に見せると、そこに「ジェフが裏のアパートの様子を覗き見している」という、現実には存在しなかった、架空の「意味(物語)」が(見る者の中に)生じるのだ。
だから、「凝視するジェフのアップ」の後に「ドラキュラ」を繋げば、「ドラキュラの登場に凍りつくジェフ」になるし、「凝視するジェフのアップ」の後に「幼女ヌード」を繋ぐと「ロリコンのジェフ」という物語が生まれてくるのである。一一「モンタージュ」とは、こういう「虚構を生むための技術」なのだ。
まあ、専門的な話は、まずWikipedia「モンタージュ」を読んできただき、その上で、専門書などを読んでいただけばいい。
そんなことを、素人の私が、知ったかぶりで「コピペ」しても、そんな「ありふれたモンタージュ」に、価値があるとは思えない。
そもそも、「不連続なイメージを連続させることで、そこに一連の物語を発生させる技術」ということであれば、ご大層な映画理論を学ばなくても、私たちはすでに絵本や漫画で、その原理を理解している。
つまり、あるページと次のページ、あるコマと次のコマは、現実には連続していない(不連続だ)が、形式的の接続させられることで、そこに「物語としての一連の時間」が流れているかのように錯覚させられているのであり、これもまた立派な「モンタージュ(編集)」なのである。
そもそも、編集のない作品は、作品ではあり得ない。人が恣意的に編集してこそ、それは「自然」ではなくなり、「作品」となるのである。
一一というわけで、「モンタージュ」の(一般的な)説明はこれくらいにしておこう。
本作『戦艦ポチョムキン』を見ていて、特徴的だと思うのは、(サイレント映画だということもあるのだろうが)とにかく、ひとつひとつのカットが短く、おのずとカット数が多くて、まさに「切り貼りモンタージュ」という印象が、きわめて強い作品だという点であろう。
そのぶんテンポは良くてダレることはないのだが、「役者の芝居をじっくりと見せる」とか「空気を描く」といったような、今の映画では当たり前にやっていることをやってはいない点にこそ、この作品の特殊性が感じられた。
本作における役者の演技は、あくまでもストーリーを進めるための「説明的」なものでしかなく、そのシークエンスの「雰囲気」を伝える「音楽」に乗るかのように、どんどんとカットが重ねられていって、あれよあれよという間に物語は進行するのである。
もちろん、現実には「音楽に乗る」のではなく、編集された映像に、後から「音楽がつけられる」のだが、私たちは、その映像と音楽を一体のものと誤認するから、「音楽に乗って」物語が進むかのように感じてしまうのだ。そこでは「映像と音楽のモンタージュ」によって「作中の空気」が虚構されていると、そう言っても良いだろう。
ともあれ、エイゼンシュテインの他の作品はまだ見ていないので、本作に見られる「過剰なまでのテンポの良さ」というのが、エイゼンシュテインの特徴なのか、本作固有のものかのかはよくわからない。
だが、ひとまず言えるのは、古くても「退屈させない映画だ」ということである。本作を、そう呼ぶ人は滅多にいないだろうが、本作は基本的に「アクション映画」だと、そう評して良いような作品なのである。


あと、特徴的なのは「印象的な俯瞰アングル」と「モブシーンの迫力」だろうか。
「印象的な俯瞰アングル」は、「こんな大昔に、どうやって撮ったんだろう」と感心させたれるし、「モブシーンの迫力」は「さすがはソ連映画。動員力が半端ではない」と感心させられる。
で、この二つのことから言えるのは、エイゼンシュテインというのは「スペクタクルの映像作家」であり「見て楽しい、驚きのある映像」を提供してくれる映像作家だということである。
もちろん、ソ連は「唯物論」の国であったから、「ブルジョア観念論」的に「内面の葛藤を描く」みたいな映画は求められなかったのだろうというのは容易に推察し得るところなのだが、しかし、『戦艦ポチョムキン』と言えば「赤ちゃんが乗った乳母車が、階段を落ちていくシーン」というくらい有名なシーンの「サスペンス」性も、あるいは、エイゼンシュテインが「歌舞伎」に興味を持っていて、そうした歌舞伎趣味(ド派手好み)が、後の作品『イワン雷帝』の「派手な衣装や様式美」に反映されていたという指摘も、そうした指摘自体は、もはや陳腐な「コピペ」に過ぎないのだが、だた、ここでひとつ言えることは、エイゼンシュテインは「思考の人」ではなく「目の人」だったという事実である。


だから、そんな彼が「ロシア革命の大義」をわりあい素直に受け入れていたのではないかと、そう推察することは可能だし、「抽象思考癖」が無いからこそ、意味に縛られることなく、表象である映像表現において、「新しい」ものを生み出すこともできたのではないか、とも指摘し得よう。
実際、1898年生まれの彼が『戦艦ポチョムキン』を撮ったのは「27歳」の時だし、その彼は「50歳」の若さで亡くなっているのだから、彼がどれほどの思索者であったかは、一度は疑ってみる必要があるだろう。
私たちは、エイゼンシュテインという、いかにも豪華な名前を持つ、今はなき「ソ連」という国の「古典映画の巨匠」を、そうした言葉のイメージから無意識的に「神格化」しがちだけれども、彼は、哲学者でもなければ思想家でもないし、文章を書く小説家ですらなかったのだから、もっぱら映像人間としての生涯を送った彼を「偉大な思想家」ででもあるかのごとくイメージしたり、またそのイメージから「共産主義イデオロギーの犠牲者」的な「紋切り型のイメージ」を持ってしまうというのも間違いだろう。

つまり、本作『戦艦ポチョムキン』を撮った当時、彼が本気で「共産主義イデオロギー」を信じていたとしても、何の不思議もないし、そのことをして彼を、私たちよりも「愚か」だと考えるのは、間違いだ。
実際、共産主義イデオロギーは、実現できるものだったのであれば、それはキリスト教における「神の国」の到来と同じくらい、素晴らしいものなのだから、それに多くの人が「期待」を寄せたのは、むしろ当然なことだったのだ。
だから私に言わせれば、現在「大谷翔平フィーバー」に酔っているような人の方が、「現実逃避」的という意味においては、よほど「愚か」であると思う。大谷翔平の活躍は、別にファン個々の活躍でも名誉でもないからだ。
それに、所詮彼自身は、「親友に銀行口座の管理を任せて(悪の道に転落させて)しまうような、社会人としては未熟な野球選手」にすぎない。しかし、それさえも「大谷翔平の純粋さ」という、信仰者ならではの「合理化」によって、まるで「美談」ででもあるかのように、イメージの改竄を行なってしまうのが、多くの大谷翔平ファンなのである。
まあ、詐欺被害に遭う人というのは、よく言えば、「他人」を疑うことを知らないという意味においては「純粋」なのである。「純粋に賢い」とは言えないところが、きわめて残念ではあるとしてもだ。
閑話休題。ともあれ、本作『戦艦ポチョムキン』の意義とは、少なくとも今となっては「映画史」的なものでしかない。言い換えれば、もはや本作は「映画オタクの必須アイテム」みたいなもので、それ以外の者には、あまり意味を持たない作品だと断じても、決して間違いではなかろう。
エイゼンシュテインよりも梶原一騎の方が偉大だという人がいても、それは間違いではないし、どっちもどっちで、どうでもいい「オタクアイテム」だと評価する人がいても、それはそれで否定できない、ひとつの立場であり見識なのである。
「ソ連の映画監督」ということで、アメリカの属国たる日本では、エイゼンシュテインは長らく「色眼鏡」で見られ、「映像作家」としての適切な評価を受け得なかった。だから、淀川長治などは、彼の「名誉回復」のために、彼の「映像作家」としての側面を強調したのだけれど、しかし、少なくともそれは、こと「映画マニア」の世界では、いささか解毒剤が効き過ぎて、おかしな毒として作用したといううらみがないでもない。つまり、エイゼンシュテインを、一人のソ連人芸術家として見る視点まで失って、ただ、普遍的なものとしての映画芸術史に位置づければ、それだけで事足りた気になるという、党派的に歪められた視野狭窄である。
たしかに、『戦艦ポチョムキン』は、「古典作品」としてみれば「それなりに面白い」し、「映画史」を考える上では、見ておいた方が良い、つまり「勉強しておいた方が」良い作品だとは言えるだろう。
だが、映画に、娯楽を求めているだけの、一般の映画ファンにとっては、本作はすでに、その「歴史的使命を終えた作品」でもあるのだ。つまり、この作品を見なくても、「人生における損失」になどはならないという意味であり、それは私がここで保証しておこう。
この映画を見るくらいなら、他に、見たほうがよい映画などいくらでもあるだろうし、何より「読むべき本」が、もっともっとある。
映画マニアの淀川長治が、いったいどのくらい本を読んでいたのか、いないかったのかは知らないが、いずれにしろ、たいていの映画より価値のある「本」というのは、それこそ読みきれないほど存在するのだという事実を、ここで強調しておくのは、「村の思想」から脱却(デプログラム)のためには、意味のあることであろう。
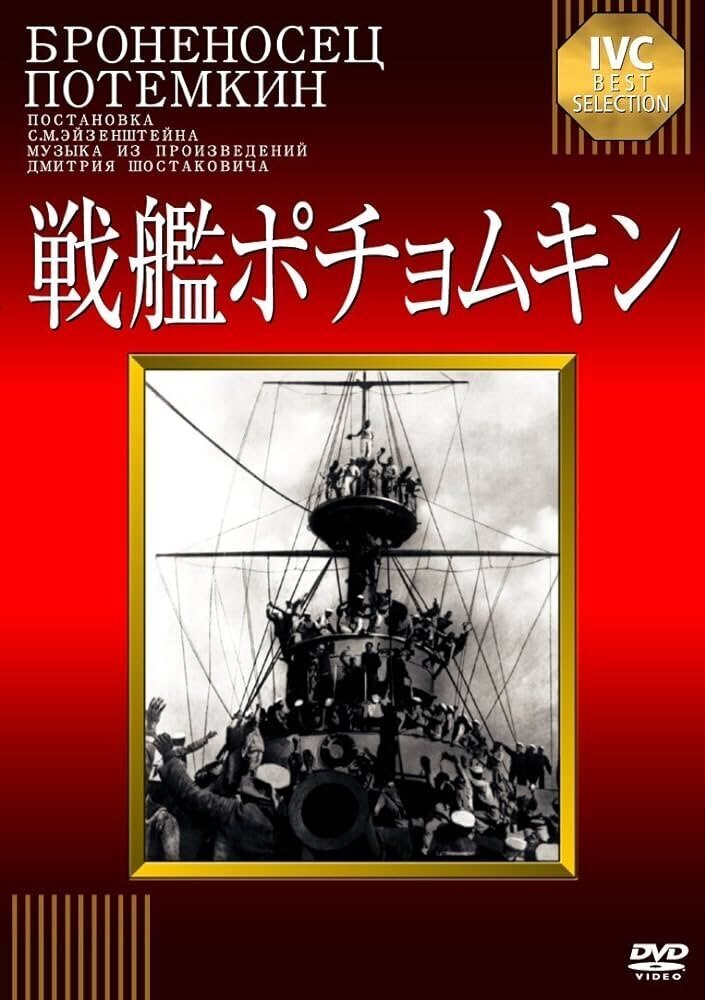
つまり、何も世の中、映画だけがすべてではないし、であるにもかかわらず、さも「映画は素晴らしい」というのを無条件な前提として書かれているかのような「映画論」というのは、そもそものところで「映画イデオロギー」に染まった「プロパガンダ」の一種でしかないのである。
繰り返すが、本作が「プロパガンダ映画」だと指摘する者も、「そんなことは自明の前提」だといった顔をしている映画マニアも、実際には、それぞれに、党派的なプロパガンダに踊らされていることに、まったく自覚的ではない。
「プロパガンダ」の問題とは、簡単に指摘できるものではないし、当然、その事実を自明視することの容易ではない、「難問」なのである。
「技法論」ばかりではなく、私たちは、「彼ら」と比べても、少しも賢くはない、ということくらいは、本作を見て学ぶべきなのである。
(2024年4月28日)
○ ○ ○
● ● ●
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
