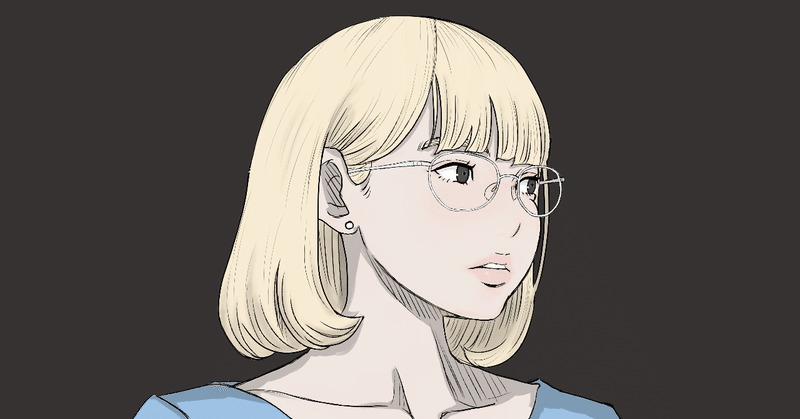- 運営しているクリエイター
#小説
『嘘の絵画』(超短編小説)
「なんだ、この奇妙な絵は」
「見ていると頭がおかしくなりそうだ」
街の美術館には、評判の悪い一枚の絵があった。数百年前に描かれたとされるその絵は「嘘の絵」と罵られ、街の誰からも忌み嫌われていた。というのも、その絵には存在しないはずのものが描かれていたのだ。
それは、夜空に浮かぶ無数の光だった。大陸の最果てにあるこの街の空は一年を通して万年雲に覆われている。空に光が浮いているはずがな
死と教育(666字)
13歳にして僕は小学校の担任を全員亡くしている。
6人の先生のうち、老人だった3人は病死。1人は焼死。1人は台風の日に屋根を修理しようとして転落死した。
最後の1人が山岸先生だ。4年生のときの担任だったが、昨日遠い街で殺されて、
山岸沙織(26)
という文字列に変化してしまった。
「真野くん」
山岸先生がこの上なくクリアな発音で僕を呼び止める。
あれは6年生の夏。
「受験することにしたって?」
なぜ物語は、スタートに戻るのか -『ついやってしまう体験のつくりかた』より
たとえば私が東京で暮らしていたとして、多くの人と同じように、コンクリートで固められた道を踏み、日々同じ場所へ通い、箱の中で「仕事」と呼ばれ、与えられた作業をこなしていたとして。
「そうではない場所」に憧れを抱いたとき、「どうしてこんなところに、居るのだろう」と、遠い「何処か」へ想いを馳せたくなる。
そして私は、旅に出る。長く、ながく、数年は帰ってこない世界の旅に。「今まではとは違う場所」を求め
短編小説「ゆなさん」
「ゆなさんって、呼んでよ」
はじめて参加となった、職場での忘年会。くじ引きでたまたま隣席になった彼女に、苗字をさんづけで呼びつつビールを注いだら、そんなふうに即答された。
ぼくは瓶ビールをかたむけながら首をかしげた。ゆな。その名は彼女の本名とまったく異なっていた。苗字、名前となんのつながりも感じられない。ひと文字すら重なっていないのだ。
「ゆなさん、ですか」
「そう。みんなからもそう呼んでもら