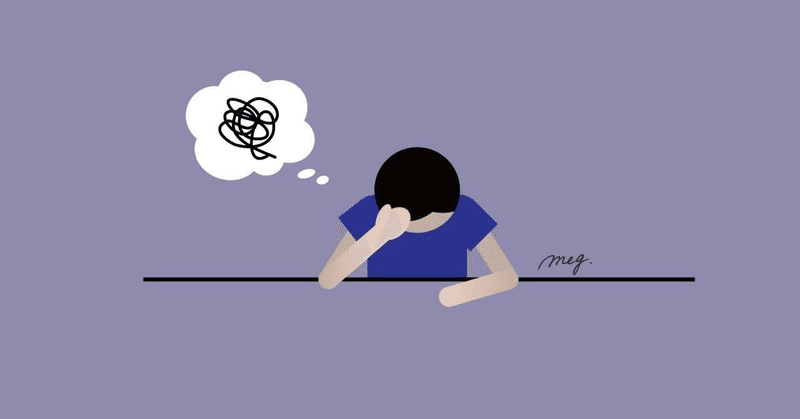
指導に行き詰まったときは
こんにちは。ぐうぽんです。
1年を通して学習指導をしていると、どうしても子どもたちが言うことを聞かない、騒ぐなど授業に集中できない時期があります。
私の場合は大体慣れてきた6月ごろと2学期後半の11月以降でしょうか。
本当にその頃は自分自身の指導の甘さを責めては体に不調をきたすことが多いです。
今回は自分が毎年のように苦しむ「指導の行き詰まり」について、備忘録程度にまとめようと思います。
見た目はベテラン。でもたった数年程度の教員人生
私は社会人20数年なので、そこそこなベテランになっていると思います。
しかし教員歴は数年程度。担任もしたことはありません。
でも周りから見られると見た目から「それなりに」やってきた実績があると思われているようで、いつも指導で行き詰まるたび「なんだよこの人、この程度しかできないの?」と言われていそうで怖いのです。
すいません、私、教員としては素人に毛が生えたくらいで、全然ダメなんです。
そう言えるのも最初のうちですから、見た目と中身のギャップの激しさに一人苦しむ毎日です。
(私みたいに社会人経験から先生になる人もいるんだよーーーー!!!)
教えてもらった「ノウハウ」
前々から指導に行き詰まったとき読んでいた本があります。
そこで色々ノウハウを知ったつもりでした。
しかし今回は休むことなくやってくる授業に対処できる心の余裕すらもなくなり、反抗的な子どもも増えてきて授業に向かうことに恐怖心さえ抱くようになりました。
食欲もなくなり、結構苦しい毎日でした。
そんなとき、私の甥っ子の担任の先生が職員室に戻られ、子どもの指導について雑談をされていました。
いつも気さくで明るくて、話しかけやすい先生だったので
「先生、相談があるのですが」
そう持ちかけました。
自分が抱えている悩み、うまくいかない授業、相談するにもどうしたら良いか分からず辛い・・
そんな胸の内を伝えつつ、2つの疑問を伺いました。
1つは叱れない自分の弱さと、言うことを聞かない子どもたちにどうすればいいのか。
2つ目はなにかあると立ち歩いてくる子が多い。どうすればいいのか。
先生から1つ目について
私なら叱らなくてもいい環境を作っちゃう。
それはとにかく褒める。
できたことを褒めてあげる。どんなことでも。
できない子を叱るより、できている子を褒めてあげて。
そうすると、できていない子が「褒めてもらいたい」気持ちに動く。
褒めてもらいたいから頑張る。
そうすればその子も褒められる。
褒められれば言うことも聞くし、やる気も出る。
そして課題取り組みについてもこんなアドバイスを。
できている子にはたくさんのやることを用意しておく。
できる子達はやることがあれば率先してやろうとする気持ちがあるから。
そして先生はできていない子に付きっきりで指導する。そうすることでできない子もできることが増えて、自信を持てるようになる。
低い子ができるようになると、それまでできていた子たちが「えっ、あの子ができるようになっている」と焦る。だから俄然頑張る。そして頑張りを褒めてもらえる。
一種の良いサイクルが生まれるのよ。
2つ目の疑問には
先生なりのルールを出しましょう。
私の授業ではこういうふうにしますよ、と。
例えば基本授業中は立ち歩かない。何かあれば手を挙げる。
必ず回るから心配しなくていいと言えば、子どもは安心します。
安心すれば勉強に取り組めます。
明確なルールを示すことで、もし子どもがルールを破ったら
「あれ?先生はそんなことしていいって言った?」と言えばいいし、そうすれば周りの子が「しちゃいけないって言ってたよ」とフォローしてくれるから「あ、やっちゃいけないんだ」と気づける。
先生自身を守る意味でも、ルールは大切よ。
・・・
聞いていて呆然としていました。
あまりの的確さ、確かに上手な担任の先生はまさにこのサイクルを実践できていましたし、先日支援で入ったクラスもできない子に担任の先生がマンツーマンで指導していました。
なるほど、そういうふうに持っていければいいのか。
それに自分ルールはパソコンの指導でやっていたことじゃないか。
なんで忘れていたんだ・・
一人苦しんでいた自分が情けなくなりました。
叱れない自分が取り組むべき指導方法とは
強い口調で指導すれば、子どもたちは言うことを聞きます。
ただしそれは一時的であり、内心では「なんだよ全然自分たちのことわかってないじゃないか」と反感を持っていることもあります。
私はそんな勇気も気概もありませんし、そもそも叱ること自体が体力のほとんどを奪われるくらい辛いものなのでできる限りしたくない。
むしろ「最後の手段」と考えています。
(叱り方を知らないと言ったほうがいいでしょう)
「ここの子どもたちはいい子達ですよ。素直で真っ直ぐで。ただ共働きの家庭が多いから愛情に飢えているところはあります。だからたくさんの愛情を与えてあげるのが一番だと思いますよ。」
そんな先生の言葉から、ようやく褒め言葉を取り戻しつつあります。
「すごいねー!」「いい姿勢だね」
「○○さんの目線、しっかり先生を見ていていいね」
「ここまでできたんだ!」「よくがんばったね!」
ポジティブな言葉で良さを認めて褒めることで、子どもは「自分はできる」と感じ、次のステップも頑張ろうと思える。
まさに相乗効果なんだとわかりました。
まとめると
・叱らなくてもいい環境づくり
・課題をたくさん用意して、暇を作らせない
・自分ルールの徹底(ここが弱いな自分)
しっかり実践できるようにしようと思いました。
そしてなにより「授業を最後まで受けてくれた子どもたちへの感謝」でしょうね。
受けることが当たり前じゃない。
拙い授業を理解しようと頑張ってくれていることへの感謝を忘れちゃいけないと思いました。
自分へのご褒美も
これは余談です。
私だけかもしれませんが褒めて褒めて与え続けると、逆に自分を褒めることを忘れてしまい、いつしか「自分はこんなに頑張ったのに誰も褒めてくれない」とエネルギーを枯渇してしまいます。
そうなると危険です。
必ず寝る前に「よう頑張ったわ私」と褒めたり、美味しいものをご用意することをお忘れなく。
#note #ICT #教育のICT活用 #ICT活用 #学校教育 #国語 #小学校 #毎日投稿 #気づき #考え方 #学び #勉強 #Chromebook #GIGAスクール構想 #クラスルーム #Classroom #情報教育 #情報活用能力 #教師 #教員 #時間講師 #教員初心者 #ICT支援員 #ICTを使う #授業改善 #授業改革 #教育の情報化 #教職課程 #学校現場 #教科でICT #エッセイ #随筆 #日記 #IT #情報 #日常 #普段使い #一人一台 #タブレット #GoogleEdu #教員養成 #情報通信技術 #独り言 #学習 #心理学 #つぶやき #プログラミング #パソコン #コンピュータ #学校 #教育
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
