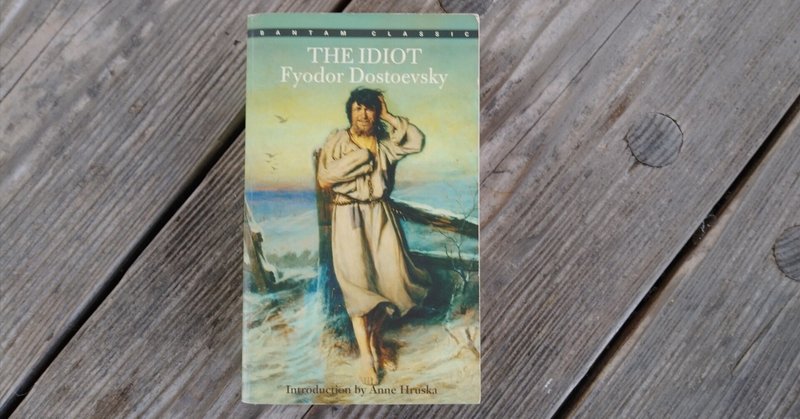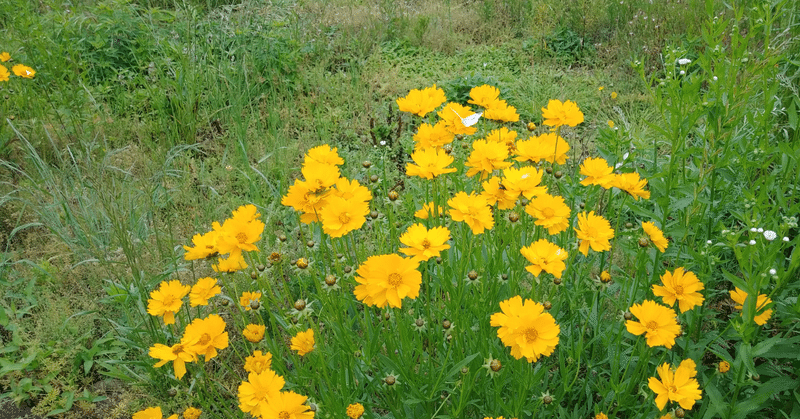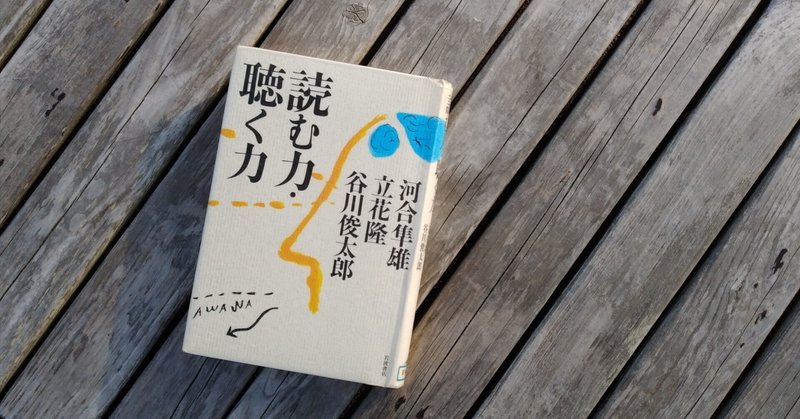#読書感想文
一語の宇宙 | くまのプーさん🐻と目的論 | teleology
teleology は「目的論」という意味。
目的論に基づくと、ある事象を説明するときに「~するために、こういうふうになっている」という言い方になります。
たとえば、雑草の生えている道を歩くと、ズボンに雑草の種子がくっつくことがありますね。
「ズボンに種子がくっつくのはなぜか?」という質問に「ズボンにくっつくのは、種子をなるべく遠くに運ぶためです」と説明されることがあります。これは目的論
英語 | 気になった比較級・最上級の使い方
最近しばらくの間、David Hume, "Selected Essays," Oxford World's Classics を読んでいる。
この中に、'Of the rise and progress of the arts and sciences' というエッセイが収録されているが、文法的にちょっと面白い表現があった。
比較級と最上級の使い方だが、2箇所を引用してみます。
Bu
英語原文を堪能しよう|文章のうまい哲学者|私の英語愛読書ベスト10
(1) 哲学書が読みにくい理由
哲学書は一般的に読みにくいものです。
その原因は「本当に難しいから」という場合もありますが、
①精緻に書こうとすると難解になりやすいこと
②著者が何を念頭においているのか、その前提がわからないこと
③独特な専門用語がわかりにくいこと
…などに起因することが多いです。
入門書のように、噛み砕いたものはさておき、哲学書の原書は難しいです。しかしながら、一般的
次の問いに答えなさい | 英語入試問題速報
この記事では、本日行われた妄想哲学大学の英語入試問題を取り上げます。まだ、正式な模範解答は示されていませんが問題は以下の通りです。
妄想哲学大学入試問題
(制限時間 10分)
妄想哲学大学英語入試より。
(出典)
www.illusional-philosophy-university-since-yesterday
問題
以下の英文は、H.G.Wells, "The Island
読書 | わたしの日本語修行
The other day, I read a book written by Donald Keene, the title of which is "My Japanese Training"( わたしの日本語修行) published from Hakusaisha(白水社).
According to this book, he studied French, German, and
読書感想文 | 和英標準問題精講
最近暑い。あまり頭を使いたくはない。けれども英語学習はつづけたい。
毎日、英語の学習というか、趣味で英語を学んでいる。別に普段英語を使わなければならない状況にあるわけではないから、英語に触れる必然性はまったくない。
けれども、中学生の頃からの習慣だから、まったく英語に触れない日があると気分が悪くなる。普段はどんなに忙しくても、1ページだけでも、読みかけのペーパーバックの英文を音読している
Over the Rainbow🏳️🌈
写真は先日わたし自身が撮ったもの。
きれいでしょ😊。
わたしの住む街は、最近、夕方まで雨で、夜になる頃にやむことが多かった。
だから、私はここ一週間で、数回大きな虹を見ることが出来た。
虹を見てるとき、
🎵「Over the Rainbow」🎵を
思い出していた。
https://youtu.be/HwkYgUZuAG0?si=XHGlKhBewdIuTHP1
https://yout
書評 | 英作文ナビ
大学受験はもう関係ないし、英検1級にも合格してから時間が経つから、英語の問題集や参考書に目を通すことがほとんどなくなった。グダグダと洋書を読んだり、TEDを聞いたり、『地球ドラマチック』を副音声で聞いたりしている。だから、英語を勉強しているという意識はあまりない。
#TED
#地球ドラマチック
ただ、そのような「読む」「聞く」だけだと「受け身」というか、情報を受信するというインプットばか