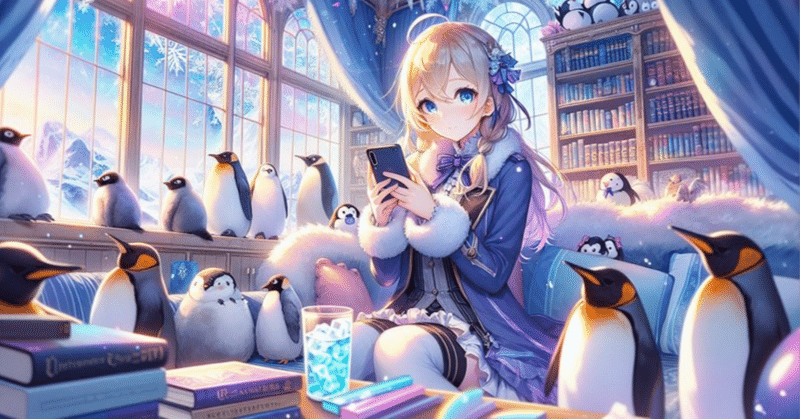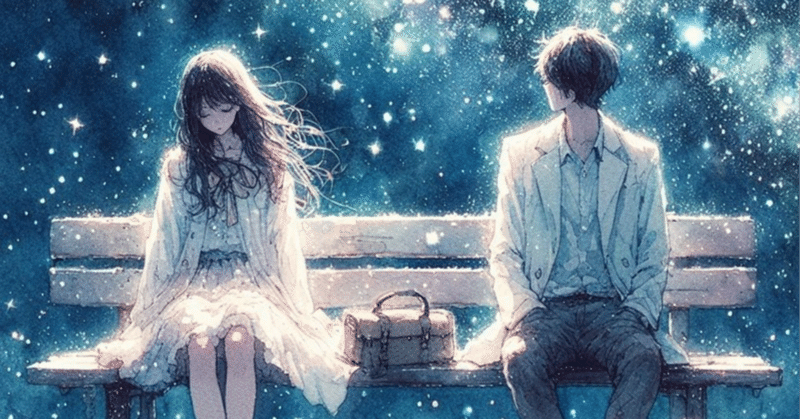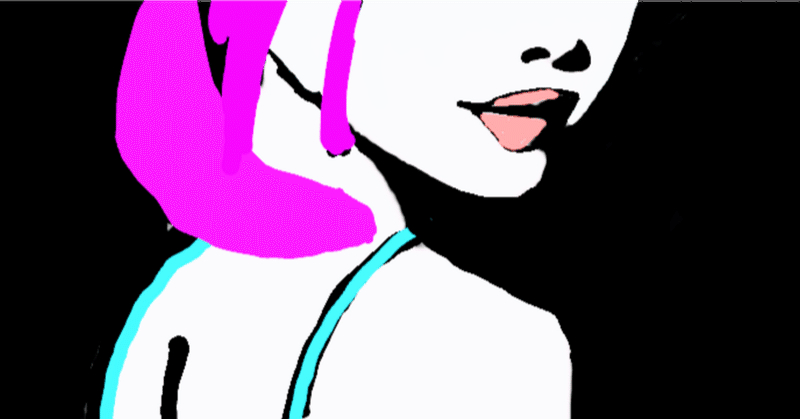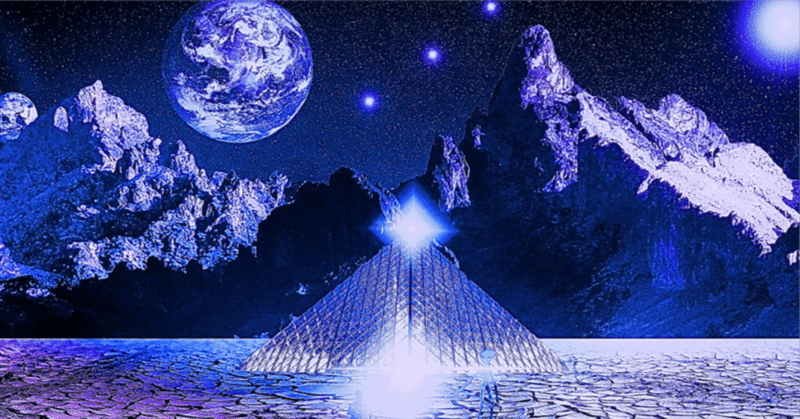- 運営しているクリエイター
#英語がすき
語学エッセイ | 冠詞について
英語の冠詞 | 日本語の助詞
英語を学習し始めてすぐに学ぶのが「冠詞」である。
「This is a pen.」 や「This is an apple.」のような文。初学者でさえ、「a」「an」という不定冠詞を知っている。しかし、1つのものと2つ以上のものとを文法的には区別しない日本語話者にとっては、「a, an」のような冠詞なんて必要ないのではないか?、という疑問を持つ。
たしかに
語学エッセイ | フランス語も多少知らないとなぁと思いつつ
英語
私が英語を本格的に学び始めたのは、中学1年生のときでした。小学6年生ときから塾で多少英語は学びましたが、アルファベットの大文字・小文字を覚えただけで、ローマ字すらきちんと覚えないまま中学生になりました。
中学生になってから現在に至るまで、短い時間とはいえ、ほぼ毎日英語に触れています。ペーパーバックの英語で書かれた小説や古典的名著を数ページ分音読するだけですが。
それでも一応は、
#おすすめ英語学習法 | TED | AIについて
「#おすすめ英語学習法」というタグを見つけたので、また記事を書いてみる。
語学学習には「絶対にこれが正しい!」という方法はないと思う。英語学習の話になると、甲論乙駁があるから「どれが正しい方法なのだろう?」と迷ったこともあった。しかし、語学をする上で何より大切なのは「つづけること」だろう。どんな優れた方法でも、一朝一夕には何も身につかない。
私は基本的には、辞書を手元に置きながら、単語を調
創作のための翻訳 | カズオ・イシグロ | 忘れられた巨人 / The Buried Giant
はじめに
なにか小説を書いてみたいのに、書き始められないということがある。
職業小説家ならば、締切や連載があるだろうから、書かざるを得ない状況にある。
趣味であったり、誰からも依頼を受けているわけでもない小説家を志す人は、アイデアがなければ無理して書かなくてはならないという義務はない。
しかし、趣味小説家といえども、淡い期待であったとしても、少なからず向上心はあるだろう。
私は
うまく聞こえて理解されやすい英語の読み方
英語の勉強の意味も込めて、ときどき英文学を朗読した記事をアップしている。
「自分のために」という意識が強いのでお聞き苦しいと思う。
この前はHenry James (作) The Portrait of a Lady の冒頭を朗読した。
お世辞にもうまい朗読とは言えない。
自分がどのくらいきちんと読めているのか、録音して自分の読み方を聞くと、問題点があらわになる。
朗読するとき
「動名詞and動名詞」が主語の場合、次に続くbe動詞は?
不定詞の場合たまに気になって調べて、結局忘れてしまうことは多々ある。
今回は忘れないように、いつもよりちゃんと調べてみた。
以前英文法の本で、不定詞(to+動詞の原形)の箇所を読んでいて、次のような文に出くわしたことがある。
To love and to be loved is the greatest happiness in life.
なにげない文なのだが、私が気になったのは、「