
中村哲 『ペシャワールにて 癩そしてアフガン難民』 : 「保守」 とは何か?
書評:中村哲『ペシャワールにて 癩そしてアフガン難民』(石風社)
「中村哲」という人の存在を、私は、昨年(2022年)公開された、谷津賢二監督・撮影による記録映画『荒野に希望の灯をともす 医師・中村哲 現地活動35年の軌跡』で知った。
もちろん、パキスタンだかアフガニスタンだかの、医療の行きとどいていない地域で、医療活動を行ってる奇特な日本人医師がいる、という程度のことなら何度か聞き及んでいたはずだが、それだけでは「国境なき医師団」などと同じような印象だから、「奇特な人がいるなあ」と感心はするものの、特に印象には残らず、そのまま忘れ去っていた。
そもそも、パキスタンやアフガニスタンが、どのあたりにある国なのかもはっきりとは知らず、「たぶん、中央アジアあたりかな?」くらいの認識しかなかった私では、中村哲医師の名前を記憶するほどの興味など、おのずと持ちようもなかったのである。
だが、大阪・十三のミニシアター「第七藝術劇場」へ、なにか別の映画を観に行った際に、この映画の予告編を観て、興味を持った。
なぜ興味を持ったのかと、思い返してみると、そこで描かれているのが、「僻地医療」の話ではなく「旱魃対策のための用水路工事」の話だったからであろう。しかも、この映画のポスターでもわかるとおり、その作業の少なからぬ部分が人力でなされ、中村医師はこの途方もない用水路計画を指導しつつ、自らも現場に立って作業したというのだがら、「僻地医療」の持つイメージとはずいぶんかけ離れて、「壮大かつ壮絶」な印象を受けたからではないかと思う。

この映画に感銘を受けたので、私は、中村哲という人をもっと知りたいと思った。
この映画でも、中村が「用水路敷設計画」にいたるまでの経緯がひととおり説明されてはいたものの、それだけでは、それまで中村についてまったく無知だった私には、用水路計画の壮大さとその人道的な偉業性は理解できても、中村哲という人がどういう人なのかが、いまひとつハッキリしなかったからだ。
それで、まず読みやすいところからと、ノンフィクション作家・澤地久枝との対談本(あるいは、澤地による、中村への聞き書き本)『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る アフガンとの約束』を読んで、なんと中村が、高倉健などの主演で何度も映画化された、火野葦平の小説『花と龍』の主人公で、北九州の沖仲仕の親方・玉井金五郎の孫にあたる人だと知らされた。言うなれば、「弱きを助け、強きを挫く」、任侠の人の孫だったと知って、深く納得させられたのである。
とは言え、この段階での私は、『花と龍』の内容や、玉井金五郎という人については、「Wikipedia」で調べた範囲の知識しかなく、あまり実感がなかったので、これまで興味のなかった小説『花と龍』を読むか、同じくあまり興味のなかった「任侠映画」を観るかしようと考え、手っ取り早く映画を観ることにした。
ただ、映画と言っても、たくさん作られているので、いちばんオーソドックスな内容になっていそうという理由で、山下耕作監督・中村錦之助主演版の『花と龍』を鑑賞した。
こうして、中村哲の祖父である玉井金五郎という人が、日本の近代史の中で生々しい存在として立ち上がってきた。
火野葦平は、玉井の長男だから、もちろんフィクションとして美化している部分はあるにしろ、任侠映画を観ていた昭和の大衆にとって、「任侠の人」とはどういうものとしてイメージされていたのかが、実感として感じられるようになり、中村哲という人が、単なる「奇特な医師」ではなく、日本の近代史につながる存在で、決して突然あらわれた「偉人」なのではない、ということがわかったのである。
その後、私はもう一度、中村哲その人にたち返って、彼の著書である『アフガニスタンの診療所から』を読んだ。
タイトルからも分かるとおり、同書で描かれているのは、中村が、大旱魃のアフガンで、医療の限界を感じ、井戸掘り事業を始めるに至る、「用水路計画」以前の時期であり、言うなれば、前記の映画で描かれた時期の「前の時期」を描くものであった。
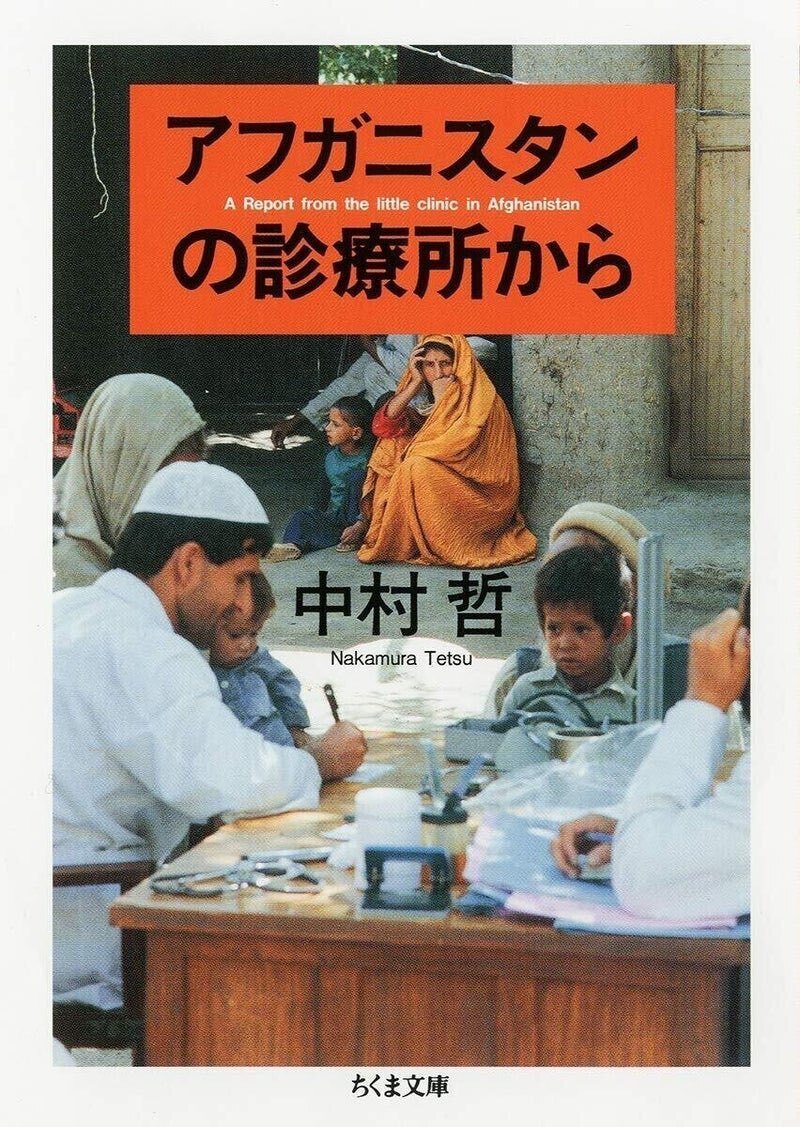
そしてそこには、中村の「アフガン戦争終結に伴う、国際支援によるアフガンの近代化」に対する見解が述べられていた。
それは、ひとことで言えば「性急な近代化の押しつけには、断固反対だ」というものであった。
○ ○ ○
本書『ペシャワールにて 癩そしてアフガン難民』で、主に描かれるのは、前記『アフガニスタンの診療所から』で描かれた時期の、さらに前の時期。
中村が、アフガン入りする以前の、パキスタンで活動した時期の話であり、パキスタンでの僻地医療を開始した時期のことである。
現在の「増補版」では、その後のエッセイも収録されており、私が読んだのはこの「増補版」だが、増補されたエッセイの内容は、おおむね『アフガニスタンの診療所から』の内容と重なっている。
私が、中村の個人史を遡るかたちで、その著書を読むことになってしまったので、結果的にそうなってしまったのだ。

さて、そんな中村を「弱者の側に立つ人」だと当たり前に理解するならば、多くの日本人の感覚からすれば、彼は「リベラル(自由主義者)」だと思えるし、「リベラル」が嫌いな「ネット右翼」などからすれば、中村は「パヨク(左翼)」だと理解されるだろう。
ところが、中村医師自身は、その著作の中で、何度となく自身を「保守」だと書いている。
彼が「保守」だというのは、彼の祖父が、有名な「侠客」であることを思えば、ある意味では当然のことなのだが、現在の日本人の場合「弱きを助け、強きを挫く」のは、「左翼」の専売特許であって、「保守」だの「右翼」だのというのは、「国家権力(権力者)」の「飼い犬」であり「番犬」だという印象があるから、中村のような人が「保守」だと名乗ると、少々「奇異な感じ」がするはずだ。
しかしながら、中村の行動に感心し支持する人であっても、えてして中村個人をカリスマ的に崇拝しがちでしかないだろうから、彼の「思想」がどういうものかということまで考えようとする人は、あまり多くないのではないだろうか。
つまり、「中村ファン」である人、多くの場合「左翼リベラル」の人たちは、中村が「私は保守だ」と言っても、「そうなんですか? でも、保守であっても、中村さん個人は立派な人ですよね。保守にも立派な人はいる」と、そんなふうに考えがちなのではないだろうか?
一一しかし、こうした中村哲理解は、贔屓の引き倒しに類するものでしかなく、中村当人にとっては、決して満足できる理解ではなかったと、私は思う。
だから、私は、本稿で、そのあたりについての「常識的な説明」をしておかなければならないと考えた。
ただ、中村を「偉人」として賛嘆しているだけでは、中村が何度も訴えたことの正反対に、無自覚に加担することにもなりかねない、とそう危惧したのである。
○ ○ ○
中村が「私は保守だ」と言った場合の「保守」とは、無論、今の日本で当たり前に流通している意味での「保守」ではなく、本来の意味での「保守」だ。
では、『今の日本で当たり前に流通している意味での「保守」』と『本来の意味での「保守」』とは、どう違うのか?
簡単に言えば、前者は『「国家権力(権力者)」の「飼い犬」であり「番犬」』、後者は「性急な改革への掣肘勢力」である。
前者は、今の日本人の理解そのままだから説明の必要はないだろうが、後者は、今や一般的な理解ではないので、ここでは、後者について説明しよう。
「保守」とは、本来『「国家権力(権力者)」の「飼い犬」であり「番犬」』を意味するものではなく、単に「反革命」を意味する。
では、「反革命」とは何かと言えば、それは「性急な近代化への反対」であり、要は「近代化は、伝統や慣習に配慮しつつ、緩やかになされなければならない」と考える立場である。
つまり、本来の「保守」とは、「伝統や慣習の絶対的維持(護持)や、それへの回帰(反動)」を求める人たちのことではない。
あくまでも、「近代化を唯一無二の理想として、しばしば、庶民の現実としての伝統や慣習を一顧だにしない、性急な近代化主義としての革命思想」に「反対する」、という「立場」なのだ。
「革命勢力=左翼」というのは、言うなれば「極端な理想主義」者である。
「人間は、古い慣習や迷信などにとらわれず、合理的な理性に基づく生活へと進歩していかなければならない。そうすることで、みんなが平等に幸せになれる、理想世界が実現できるのだ」というのが「左翼的な近代主義」。
そして、この「理想主義」が極端なかたちを採ったのが、「革命思想」だ。
無理なく徐々に変えていくというのではなく、「一気に変えてしまう。それまでの形式を、一気に転覆して、まったく新しいものを立てる」というのが「革命思想」なのだが、当然のことながら、この「乱暴」な思想には、現実には、少なからぬ「弊害」が伴なわれてしまう。つまり「革命のためには、多少の犠牲は致し方ない」として、暴力的な「切り捨て」が容認されがちなのだ。
だから、本来の意味での「保守」とは、こうした「革命思想の暴力性」や「独りよがり」に対し、「ちょっと待った!」と注文をつける立場なのだと言えるだろう。

「弱者のために、今の社会構造を改めなければならない部分があるという意見には、賛成だ。また、それをやろうとすると、既成の権力が、それを暴力的に妨害するというのも事実だろう。しかし、だからと言って、暴力には暴力で対抗すればいい、権力を叩き潰し、血祭りにあげなければ、理想の社会を実現することはできない、というような革命思想の乱暴さは、いかがなものか。それでは、理想を目指しながら、また違った過ちを犯すことにになるのではないか? 改善が必要だとしても、もっと穏健なやり方をすべきではないのか。その意味で、それまでの伝統や慣習を全否定して、自分たちの理想を押しつけるというのではなく、人々の思いに寄り添うかたちで、少しずつ改良していくべきなのではないだろうか」というのが、「保守」思想なのである。
したがって、本来の「保守」というのは、決して『「国家権力」の「飼い犬」であり「番犬」』などではない。
そこに問題があれば、それを「改善していくこと」については、何の異論もないという立場だからである。
「ただし、改善するにしても、性急なやり方ではダメだ」というのが、「保守」と「左翼」の違いなのだ。
「左翼」に「知識人」が多いというのは、裏を返せば、「左翼」は「観念的な理想主義者」が多い、ということだ。
なるほど、彼らの「(虐げられた人々などへの)善意」は疑い得ないとしても、彼はいささか「観念的な理想主義者」であって、悪く言えば「人生経験に乏しく、現実が見えていない。理想に目が眩んでいる、と言っても良い人々」だということになる。
だからこそ「左翼」は、しばしば「良かれと思って、やり過ぎてしまう」傾向がある。
だから、その「行き過ぎ」に対する「ブレーキ役」が、「保守」だということになるのだ。

例えば、かつて公明党は「自公連立政権」を組むにあたって、「なぜ、これまで敵対してきた自民党なんかと組むのか? それほど、権力が欲しいのか? 進んで権力に取り込まれるつもりなのか?」という、当然の疑問を持つ「創価学会員」たちに対し、次のように説明した。
「野党として、与党自民党にいくら反対しても、自民党が無視すれば、自民党の政策を変えることはできない。しかし、自民党が単独では政権を維持できない今なら、自民党と組むことで、自民党を掣肘できる立場に立てる。無視することのできない立場に立てるということです。だから、自民党が暴走しかければ、私たち公明党が、それに内部からブレーキをかける。つまり、私たちは、本当の意味での、権力のブレーキ役を担うために、政権に入るのです。」
一一要は、「公明党は、反動に突っ走りかねない自民党のブレーキ役になるのだ」というわけであり、言い換えれば「革命的な反動勢力である自民党に対して、それを掣肘する、権力内保守としての任務を担うのだ」ということである。
もちろん、これは「例示」であって、私個人は、公明党のこの「自己正当化論」を信じているわけではないのだが、私がこのたとえ話で言いたいのは、「保守」とは、「反革命」ではあっても、「反左翼」だとは限らず、「反右翼」でもあり得る、ということなのだ。
言い換えれば、「保守」とは、「反極端」であり「穏健改革主義(漸進主義)」なのである。
だから、「極端」なものに対しては、「右であろうと左であろうと、反対だ」ということになる。
そして、こう考えてくれば、中村哲の「保守」という自認も、理解できるはずなのだ。
○ ○ ○
そんなわけだから、中村哲は、「アフガニスタンを武力制圧して、共産主義国家に作り変えようとしたソ連(ロシア)」に反対しただけではなく、ソ連がアフガンから撤退した後に、アフガンに入ってきて、「アフガンの自由主義国家化を進めようとした、西側諸国」にも反対なのだ。
なぜなら、長所と欠点の両方があるにせよ、アフガンにはアフガンの「長い伝統と慣習」があって、それを無視して、「共産化」しようとしたり「自由化」しようしたりするのは、どっちも「乱暴」なことであり、当事者であるアフガンの人々の意志をないがしろにするものという点では、まったく「同じ蛮行」だ、ということになるからである。
ここまで説明すれば、日本人の多くも、中村の自己規定である「保守」の意味が理解できて、「それなら、賛成だ」と言うかもしれない。
けれども、問題が「具体的な話」になってくると、そう簡単に「中村さんに賛成」とは言えなくなるはずだ。
例えば「アフガンにおける、女性の高等教育」の問題である。

私が読んだ、中村の著書3冊では、この問題は触れられていない。
この問題が、日本をはじめ、自由主義諸国の間で大きく取り沙汰される前に中村が殺されたということなのかもしれないが、中村が、こうした難しい問題には、あえて触れなかったという蓋然性も十分にあろう。
なにしろ、中村は「現場」の人であり「目の前で苦しんでいる人たち」を助けなければならない立場の人であったから、「難しい問題ですから、じっくり議論をしてから、どうするかを決めましょう」などという「のんき」なことは言っておられず、機微に関わる難しい問題については、ひとまず「後回し」にしたというのは、十分にありえることだからである。
私たち日本人の多くは、アフガンの女性たちが、その「イスラム的慣習」のゆえに「高等教育から、再び遠ざけられている」という話を聞いて、「許しがたい」と考えるだろう。それで、現在の「タリバン政権」を批判することもしているはずだ。
しかし、実際のところ中村は、そんな「タリバン政府」を擁護しているのである。
「たしかに、男女は平等であるべきなのだから、アフガンの女性も高等教育を受ける権利が保証されなければならない。
けれども、アフガンの女性が多少とも高等教育を受けられるようになったのは、アメリカとソ連のアフガンへの政治的(軍事的)干渉の結果であり、言うなれば、外的圧力によって、止むを得ずに進められた近代化の結果だった。だから、ソ連がアフガンから撤退したあとに入ってきた、アメリカや国連をはじめとした自由主義勢力も、近代化路線を維持強化しようとした。
しかし、アフガンの少なからぬ人たちからすれば、アメリカや国連のやっていることは、ソ連のやったことと大差はない、ということにしかならない。つまり、アフガン人の意志を無視し、伝統や慣習を否定して、自分たちの思想を力づくで押しつけている、と考えたのである。
だから、彼らが、権力を取り戻した際に、反動化が起こるのも、いわば当然のことであり、彼らには、そうした選択肢も認められてしかるべきなのだ。
無論、最終的には、男女平等や、女性の高等教育は認められるべきだろう。だが、それは外圧によって、強制的に押しつけられるものであってはならないし、それをすれば、結局のところ失敗するか、大きな禍根を残すことになる。つまり、アフガンの近代化は、アフガン人自身が、自分たちの力で、納得しながら、少しずつ実現していくものでなければならない。
例えば、日本人の常識から、女性への高等教育を妨げるなんて、なんて前近代的で非人道的なんだ、なんて批判するのは間違いであり、傲慢なことなんだ」
と、大筋でこんな意見を、中村哲は持っていたのだ。

そして、こう説明すれば「なるほど、それもそうだな」と納得する日本人も多いだろう。
しかし、ことは、そんなに簡単な話ではない。
と言うのも、中村哲が「目の前で苦しんでいる人」を救うために、しばしば言いたいことを呑み込まざるを得なかったのと同様に、ある「ひとつの問題」の解決するためには、「別のひとつの問題」については、ひとまず「後回し(二の次)」にしなければならないという「難問」が、「保守」思考にはついてまわるからである。
「あれもこれも、いっぺんに解決だ!」というのが「革命」思想の理想なら、「それは無理だから、ひとつずつ進めるべき」だというのが「保守」思想である以上、「保守」は必ず、まず誰を助けるかの「優先順位」をつけなければならず、言うなれば、ひとまず「見殺しにする人々」の存在を容認しなければならない、ということである。
そして、中村哲にとって「やむなく見殺しにするしかない存在」とは、この場合「高等教育を妨げられた、アフガンの女性たち」なのである。
繰り返すが、中村とて、彼女たちが高等教育を受けられるようになれば良いとは思っているだろう。しかし、目の前の生き死に関わっている中村としては、ひとまず「高等教育を受けられないからといって、死ぬわけではない」という「優先順位」があるというのは、否定できない事実なのである。
一一そして、ここに「中村哲自身のジレンマ」もあるのだ。
『 ペシャワールにおいても、病気との戦いはしばしば予算との戦いである。殊に長期の投薬を要するらいのような慢性疾患は、他の急性で致命的なものと比べるとぜいたくとさえ思われる。対策が後手にまわるのはやむを得ないのである。僅か数百円程度の薬が買えないために死んでゆく者は数知れない。死の直前に数百万円を惜しみなく投ずる日本の医療は、遥か彼方の夢のまた夢である。
このため、少ない予算で多くの者を助けるとなれば、どうしても犠牲者の多い他の急性疾患に重点が置かれざるを得ない。同時に慢性疾患に対しては、治療期間の短縮が試みられる。予防から手をまわす保健衛生対策が最も重要なことも論を待たない。
このような絶望的な状況の中にあって、われわれ医療人は奇妙な矛盾に直面する。一方では一人の患者にいちいち構っておれぬコントロール計画全体の推進を図り、他方ではらいを病む人間の心深く触れながら濃密な診療をせざるを得ない宿命である。前者はWHOのようなマスとしての患者群のコントロールが重要なのであり、その極限はナチズムに通じる全体主義志向である(※ 全体のために、一部の犠牲には目を瞑る)。後者は、病気そのものの根絶を無視して自己満足的なチャリティ・ショーに通ずる極端な個人中心思考である(※ 目の前の事象にこだわって、全体状況には目を瞑る自己満足)。前者に立てば角がたち、後者に傾けば情に流される。ペシャワールにおいて、私は常にこの両者の間の緊張の中にあった。時には全体のコントロール計画のために鬼にならなければならず、時には(※ 他所での悲劇を含めて)すべてを受け入れる聖人のようにならねばならなかった。
個人的に言えば、私は人間に興味があった。らいの仕事に携わる者は、その愛憎、醜悪さと気高さ、怯懦と勇気、深さと軽薄、怒り、悲しみ、喜び、およそあらゆる人間事象に、極端な形で直面させられるからである。治療する者もされる者も、そこには濃密な人間関係が影を落としている。
全体の厳しい医療事業からすれば、WHOの言うように結核コントロールと(※ らいコントロールを)併合をするのが効率的であるという考えがある。コントロールの方法が似ているからという合併意見が結核の側からは強いが、今のところ良い協力が(※ らい治療者の側からは)得られていないという。(※ 結核治療者側からの)らい関係者の頑迷さに対するつぶやきと嘲笑も一度ならず耳にした。しかし私に言わせれば、この「頑迷さ」こそが、長年の忍耐を要するらいとの格闘を支えてきたものである。人間を数字やプランだけでは扱えぬ何者か、経済効率の優先で置き去りにされてはならぬ何者かが、らい治療に携わってきた人々の心の奥に漠然と根を下ろしているからである。医療が人間を対象とするものである限り、私自身は彼らの頑迷さと偏屈に親近感を覚える。』
(P41〜42・「※」印は引用者補足)
中村哲は、ここで「効率性と目の前の現実」の双方の重要性を認めながら、しかし、個人的には「目の前の患者の苦しみ」のこだわる医療者たちの「頑迷さと偏屈」に『親近感を覚える』と、ほとんど、そちらへの「支持」表明をしているように見えるし、読者の多くは、そんな中村の「選択」に共感するはずだ。

しかし、中村自身は、大旱魃によって、もはやアフガンの人たちの命を救うには、個々の「医療」では対処不能であり、それに固執することは『自己満足的なチャリティ・ショーに通ずる極端な個人中心思考』でしかないと判断して、清潔な水を得るための「井戸掘り」事業を始め、それでも不十分だとわかると、ついには「用水路計画」へと突き進んでいく。
当然、その結果として、彼は「医療の現場」からは遠ざからざるを得なかった、ということであり、これは、やむなく『経済効率の優先』を選んだ、ということである。
ところが、「高等教育を受けられないアフガンの女性」たちの苦しみを看過できず、性急な改革を望む人たちの「感情」というのも、実のところ、「数字やプラン優先ではなく、目の前で苦しんでいる患者の優先を」という『らい治療に携わってきた人々の心の奥に漠然と根を下ろしている(中略)頑迷さと偏屈』と、ある意味では、同質の「こだわり」だと言えるだろう。
またその一方、「全体を無理なく変えていくためには、申し訳ないけど、君たちのは高等教育を諦めてもらわないといけない」と言っているに等しい、中村哲の「保守」としての立場と、「医療の現場」から離れてでも「数字とプラン」としての「用水路計画」を優先せざるを得なかった中村の「非保守的な抜本的解決」の立場は、明らかに自己矛盾をきたしているのである。
だが、私はここで、中村を責めたいのではない。
私が言いたいのは、「保守」であれ「リベラル」であれ「左翼」であれ、何かを「良かれ」として判断するときには、必ずこの「矛盾」がつきまとうものなのだ、ということくらいは考えて、決断してほしいし、その責任の重さを感じてほしいということなのだ。
「アフガンの女性の高等教育」を早期に実現しようとすれば、「アフガンの人々の伝統や慣習」を踏みにじることになるし、「多くの人を救うために、医療の現場を離れて、用水路計画に専念する」ならば「医療の現場で救えたはずの人を、何人か死なせる」ことになるというのを自覚して、その上で、どちらかを選ぶしかない、という「決断」を、引き受けてほしいということだ。
いちばん見苦しく卑怯なのは、その時々、無自覚にもコロコロと立場を変えて「聞こえの良い方(立場)」を選んでしまうような人の、「軽薄さ」である。
そして、そうした「軽薄さ」とは、生涯「矛盾」の中で葛藤し続けた中村哲の苦しみを、ないがしろにするものに他ならないのである。
(2023年4月17日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
・
・
