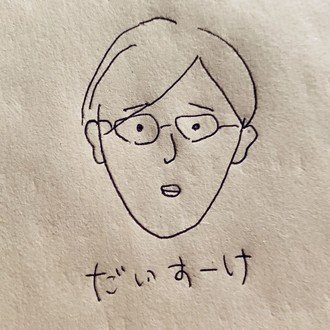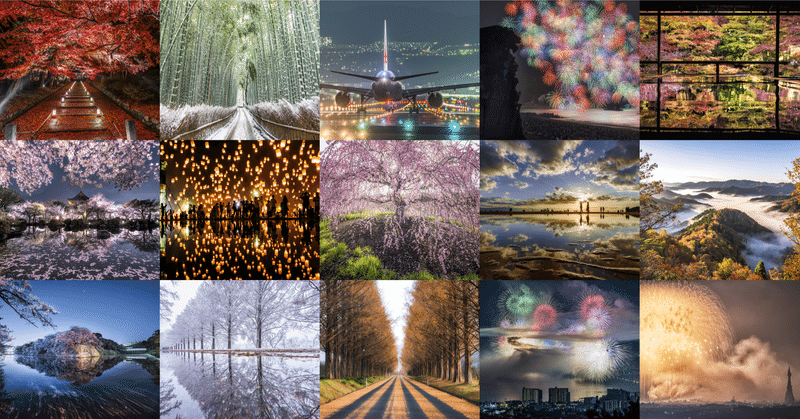#写真
世界を見つけるということ
「木洩れ陽」が好きでよく撮ります。美しいですよね。木々の隙間から光が射して映し出されたそれ。風に揺れるとまるで小さな子供たちがダンスしているようにも見えます。この言葉を生み出した豊かな感性に憧れます。ところで英語では「木洩れ陽」を一言で表せられないそうです。
英語では ”sunlight filters through the trees” のようなセンテンスで表現されるそうです。同じように日本
コロナ時代のリモートフォトグラフィー、始めます!
コロナ時代のカメラのあり方の一つとして、「リモートフォトグラフィー」が話題にあがりつつあります。最初にまず伝えておかなくてはいけないのは、これは既存の写真や撮影方法を否定するものでも置換するものでもありません。そこはまずご了解ください。
一方、これは「仕方なくやっていること」でもありません。制限された状況の中でできることを考えるのは、すべてのクリエイティブの原初的なエネルギー源だと思うのですが、
写真が好きではなかった。けれどわたしが女の子に映る、唯一の方法にも見えた。
向けてほしくなかった。
その視線をへし折ってしまおうかと思った。透明人間にはなれないから、誰の視界にも入らずに生きてしまおうかと思った。それがわたしを守る唯一の方法な気がして、だからこそわたしは顔出しもせずにこうして言葉だけを書き続けている。
全てを言葉で解決させたかった。
自分という鏡を誰にも見せることはない。
写真。それにわたしを映すことが怖かったのだ。
" わたしは一生、写真に勝てな
17の夏、君の背中に恋をした
「手作りのものを持ちよって、パーティーしようよ」
「いいな、それ!」
そう言いだしたのは綾で、その提案に真っ先に賛同したのは、綾が片想い中の貴史だった。
それに同意するように、私と奏太が顔を見合わせると、綾と貴史も嬉しそうに顔を見合わせた。
私たちは、来月高校を卒業する。
バスケ部だった奏太と貴史。
私と綾は、マネージャーだった。
部員みんな仲がよかったけれど、特に私たち4人はいつも一緒だった
「ボケる写真を撮る人は、ボケた人です」耳の痛いフレーズの裏側に
タイトルは、note主催のスマホ写真ワークショップにて、講師の鈴木心さんが繰り出した言葉だった。
なにを隠そう、私はボケが大好きだ。
開放万歳、F値1.4ラブ。背景なんてみんな溶けてしまえばどこだって美しい写真が撮れるし、玉ボケはキラキラしててかわいくて正義。そう信じて疑わずに生きてきた。今日のボケボケなアイキャッチ画像も、私が撮った写真だ。
Twitter上で「開放でしか撮れないやつはクズ