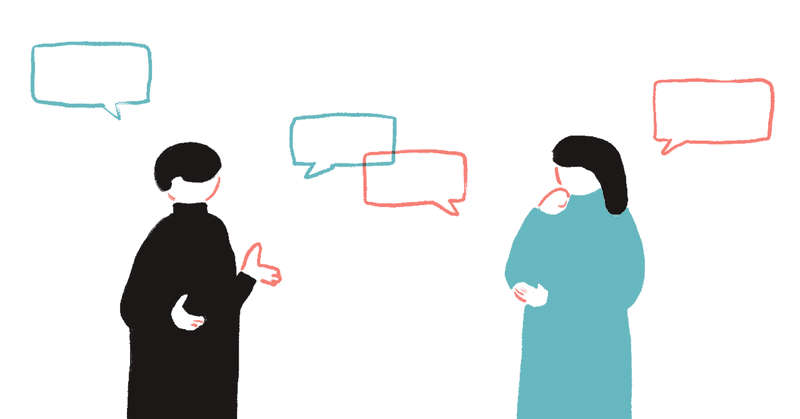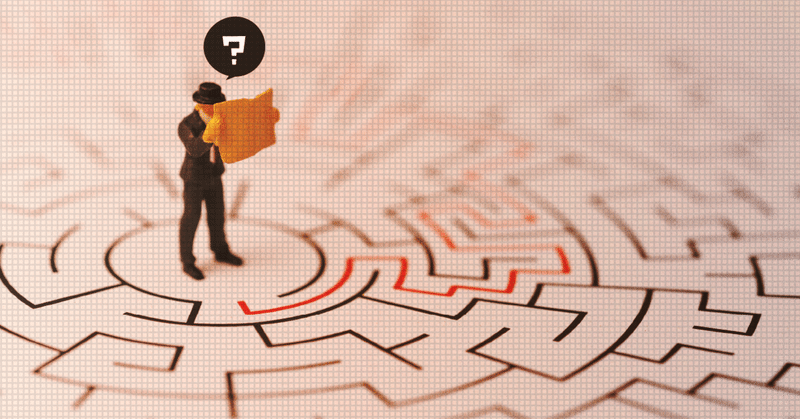#エッセイ
What型とWho型:都市型人材と地方社会がコミュニケーションで気を付けること
前回、こちらの記事でWhat型とWho型について書きました。
今回は、より細かく、それぞれが留意したいコミュニケーションについて書いていきます。
(※この記事は早い人で10分、平均15分、読了にかかります。)
What型はIメッセージを心掛けるI(アイ)メッセージとはなんでしょうか。それは、主語が「私」という形で発せられるメッセージです。「私は楽しい」「私は怒っている」「私は悲しい」「私はや
Whatに熱くなる都市、Whoに熱くなる地方
都市と地方のコミュニケーション作法の差ということを、何度も取り上げています。先日、愛知県三河地方出身で東京で修行をし、また三河に帰ってきた料理人の方と話す機会がありました。
そこで、仰っられていたのが
ということです。
『美味しい店』か『友達の店』か具体的には、
と。この『美味しい店』と『友達の店』は分りやすい選択肢だと思います。
休日の夜に時間がある時、『人間関係は特にないけど美味しい
若いとき腰の低かったあの人が、なぜ、年をとると尊大になるのか
そのこと自体の是非はさておいて、日本は年功序列が根強く残り、年上を敬う文化、習慣を持っています。語弊を恐れずに言えば、年をとるほど相応に態度を大きくして良いということ。
もちろん、『実るほど頭を垂れる稲穂かな』という言葉もありますが、一方で、地位のある人、立場のある人には、そこは役割として、どこか、それなりの偉そうな態度をとってもらった方が、組織や社会自体が安定するということもあるのではないでし
なんでも「ナントカ道」にせず、人生も企業も多角化しませんか
日本人は、なんでも「ナントカ道」にしてしまいがち
日本人は、なんでも「ナントカ道」にしてしまいがちなところがあると思っています。「柔道」「剣道」「合気道」「茶道」など、単語になっているものから、「野球道」「ラーメン道」などですね。「経営者道」などというのも気合い系のコンサルティングでは見かける表現です。
思い返せば、私がこどもの頃、30年前のラーメンのパブリックイメージは「ニーハオ!***アルよ
部活の大会が無くなった最終学年の人へ
様々な中高生の大会が無くなっている。
そんな中高生、特に最終学年の人は、今は予定していたことが無くなったショックと混乱があるかもしれない。
でも、この機会に、自分は「**部」をやりたかったのか、「**」をやりたかったのか。
例えば、野球部をやりたかったのか、野球をやりたかったのか。吹奏楽部をやりたかったのか、吹奏楽をやりたかったのか。そこをしっかり自覚的に捉える切っ掛けにして欲しいと思う。
「やりたいこと」と「出来ること」のアンバランスが攻撃性を生む
昨今、社会全体にストレスがかかる中、世の中に色んな言説が出てきています。
それぞれの立場で、見えている範囲が違っていたり、受ける影響の大小があったり、それまでの社会に対する関わり方やスタンスがあったりで、正義と寄って立つものが違っている。
私は、人ってそこまで悪人に出来てなくて、責任感とか優しさってのがあって、みんな『世の中に何かしたい』という気持ちがあると信じています。
これまでの世の中は
『実際に会わなくても友達になれる力』を-ノンバーバルと空気の力に頼らない
テレワークやWeb飲み会など、『実際に会わないコミュニケーション』がにわかに浸透してきました。実際に直接会うコミュニケーションとの違和感も感じながら、世の中が試行錯誤しているように思います。
ただ、私が元々出不精というのもあるのですが、自分を振り返ると、SNSの繋がりなどで、もう10年以上会っていない友人もざらです。留学時代の友人は世界に散っているので、直接会うことはなかなか難しい。正直なところ
冷静とポジティブとネガティブと
日本のコロナ対策をどう評価するか。多分に政治スタンスをはらむ問題でもあり、非常に炎上しやすいテーマでもあります。
では、なぜ炎上するのか。それは、これを、プロジェクトと置き換えたとき、3つの心理的態度が混在してしまっているからだと思います。
プロジェクトの評価は、『今起きていることの分析』を『冷静』に評価し、『これから起きる未来の予測』はネガティブに考え、『実際に行動に移したら』ポジティブとい