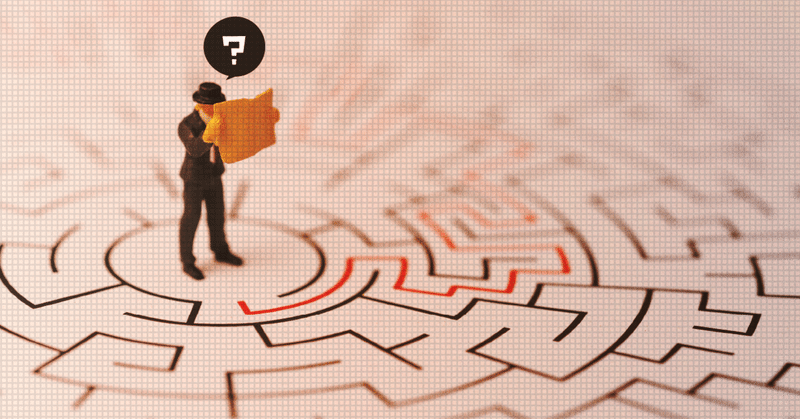
「やりたいこと」と「出来ること」のアンバランスが攻撃性を生む
昨今、社会全体にストレスがかかる中、世の中に色んな言説が出てきています。
それぞれの立場で、見えている範囲が違っていたり、受ける影響の大小があったり、それまでの社会に対する関わり方やスタンスがあったりで、正義と寄って立つものが違っている。
私は、人ってそこまで悪人に出来てなくて、責任感とか優しさってのがあって、みんな『世の中に何かしたい』という気持ちがあると信じています。
これまでの世の中は、『行動して結果を出すこと』が様々なことにおいて、価値のある行為とされてきました。そして、これまでの多くの危機に対しては、『何かをしよう』というアプローチでした。
2011年、東日本大震災の時も、『何かしたい』と思えば、現地にボランティアに行ったり、行けなくても物資を送ったり、募金に協力したり、『何かしたい』という気持ちを普通の人でも『行動』で表現することが可能でした。
社会問題、ソーシャルプロブレムのアプローチもそうで、『ボランティアをする』とか『NPOを立ち上げる』とか、『行動』『アクション』をもって解決をする方法は、平時なら、その選択肢がたくさん用意されています。
でも、今回は、『出歩かない/自宅待機』という、『何もしないこと』を求められています。いわば、行動に対し気持ち過剰になってる。社会のために何かしたい気持ちを表現する行動が用意されていない状態。
自宅で、何も行動しない中、普通の人が、社会のために出来そうな行動と言えば『社会的に有益な情報をシェアすること』これなら、机から動かず、いや、歩きながらでもスマホ1つあれば、出来ます。
でも、『社会的に有益』というのが、明らかに100人が100人見て有益なこともあれば、立場によって有益さに違いがあったりする。ましてや、『情報』に対して、評価や価値観が加わったり、『何を言ったか』ではなく『誰が言ったか』と言うことまで含めて、評価されるようになっています。
そうなると、『社会的に有益な情報をシェアすること』が『社会的に有益じゃないと思った情報のシェアを阻止すること』や『間違った情報を訂正すること』、『間違った情報を流す人を批判すること』に代わってき、やがて、強い攻撃性を持った言葉に変わってしまうのではないでしょうか。
タイトルに書いたとおり、『やりたいこと』と『出来ること』のアンバランス感が、焦りになり、やがて、攻撃性に変わってしまっているような気がします。
今、必要なのは、『何かしたい』という人々が自然に持つ社会への責任感を、無理のない形で発揮することが出来る、そんな仕組みが必要なのかもしれません。
最後までご覧いただきありがとうございました。 私のプロフィールについては、詳しくはこちらをご覧ください。 https://note.com/ymurai_koji/n/nc5a926632683
