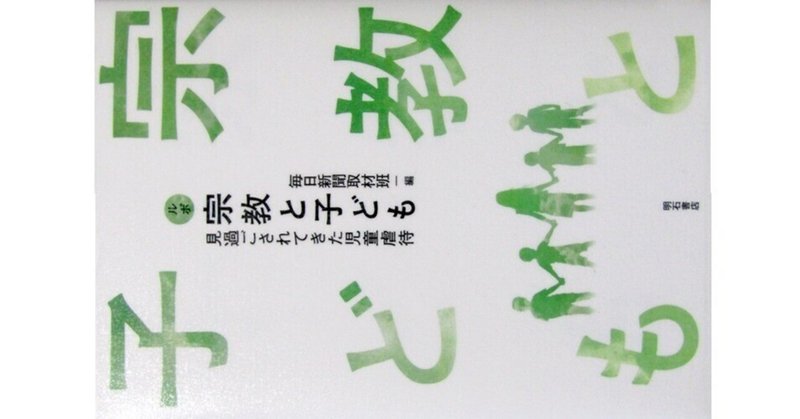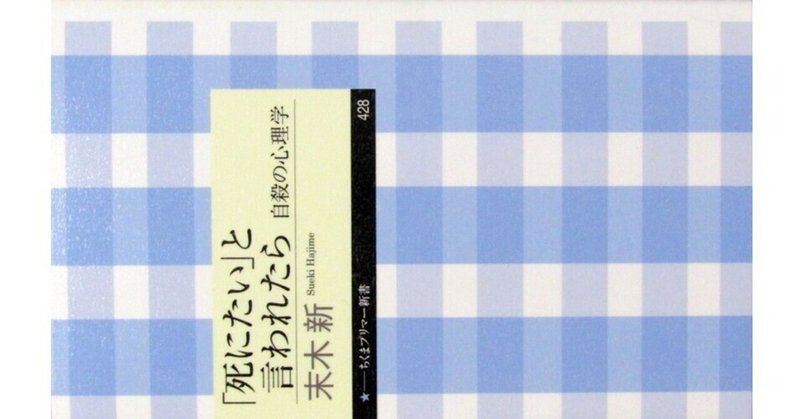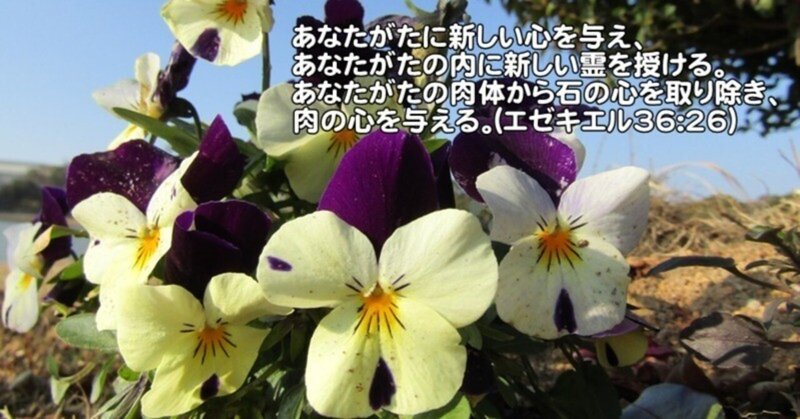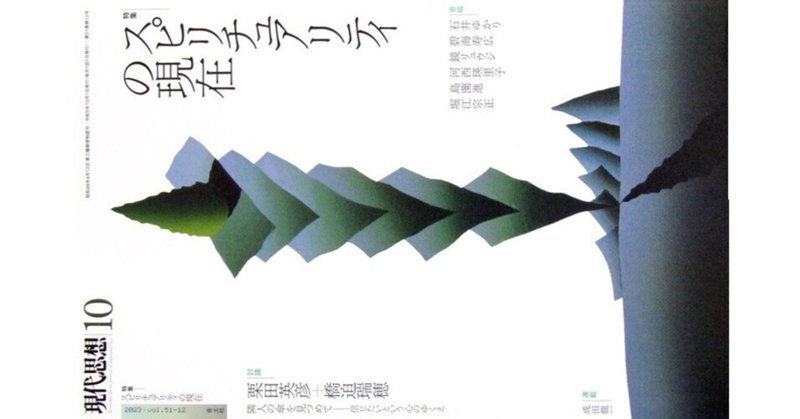ひとのこころ、見つめてみます。自分のこころから、誰かのこころへ。こころからこころへ伝わるものがあり、こころにあるものが、その人をつくり、世界をつくる。そんな素朴な思いに胸を躍らせ…
- 運営しているクリエイター
#読書
『現代思想 10 2023 vol.51-12 特集 スピリチュアリティの現在』(青土社)
時折購入する「現代思想」。多くの人が文章を連ねている。ずいぶんと思い切った論調も好きだ。なにより、世の中のメジャーな宣伝では運ばれてこない、だが非常に重要な視点を提供してくれるところが気に入っている。今回も、特集の「スピリチュアリティ」に惹かれて購入したが、執筆者の中には「占星術研究家」なる人もいて、しかもその文章が非常に面白かった。
オーソドックスに、スピリチュアリティについての背景や歴史を