
佐多稲子 『キャラメル工場から』 : 「獅子身中の虫」にも五分の魂
書評:佐久間文子編『佐多稲子傑作短編集 キャラメル工場から』(ちくま文庫)
佐多稲子は、1995年に1冊だけ読んだことがある。佐多の後期の代表作の一つである、野間文芸賞受賞長編『樹影』だ。

なぜ読んだのかと言えば、当時の私はすでに「古本屋めぐり」を趣味とする初版本コレクターであり、まだ30歳前後で元気だったから、大阪と神戸を中心に、とにかく古本屋を回りまくっていた。そんななかで、『樹影』を含む佐多の初版本を、まとめて入手したのがそもそものきっかけである。
一昨年退職するまで、私は大阪府警の交番勤務の警察官で、その勤務形態は三部制であった。
この「三部制」というのは、交番勤務をする「地域課」(旧称は、警ら課)には、1係、2係、3係と三つの係があって、この3つの係が、3日に一度の順繰りで、交番での当直勤務をする。だから、交番には、常時警察官が配置されているというかたちである。警察署(本署)が土日は休みでも、交番に「休み」が無いのは、そのためだ。
で、勤務する警察官の側から見ると、この「三部制」とは、次のような勤務形態ということになる。
「当直勤務日」は、朝から出勤して翌日の昼前まで交番で働く。その当直明けの日が「非番日」であり、そのさらに翌日が、朝から夕方までの勤務する「日勤勤務」か、または「週休日」だ。
で、この「非番日」の翌日が、ほぼ交互に「日勤日」と「週休日」になる。言うなれば、「当務・非番・日勤・当務・非番・週休」となって、それの繰り返しだと考えれば良い。つまり、6日に1日が「休み」になるわけで、普通の会社勤めや警察でも内勤勤務のような「週に1日」の休みよりは、休みが多いように見える。だが、これはは「半日勤務の土曜日」が無かったのと、「日勤」の日に「年休」を入れていくため、実質的に「6日に1日が休み」になったわけだ。当時は、当直勤務日には年休が取りにくかったのだ。
ここまで書いて、説明しなければならないと気づいたのは、私が若い頃は「週休二日制」ではなかったということ。土曜日は、お昼までの半日勤務が、会社でも学校でも当たり前だったのだ。
「当務・非番・日勤・当務・非番・週休」という実質「6日に1日の割合で休み」となると、普通の会社勤めよりも休みが多いという感じになるし、しかも、ポイントとなるのは、当直勤務を翌日のお昼前に終える非番日である。
元気な若者にとっては、この非番日は実質的に「休み」みたいなものだから、仕事を終えて真っ直ぐ帰宅することなく、私は夕方まで、神戸や地元地域以外の主に大阪市内の古本屋めぐりしたのだ。だから、若い頃の感覚としては「6日間に3日が休み」みたいなものだから、好きなだけ古本屋も回れれば、好きな読書もできる。そんなわけで、私は若い頃から「三部制はやめられない。趣味人の私にぴったりだ」とそう思い、生涯「交番勤務」で行こうと考えたのである。
言い換えれば、警察内で出世する(ための昇任試験の)ために、好きでもない法令の勉強をしたり、警察組織内ではそれが当たり前だと考えられている、内勤の専務員(刑事課員、交通課員、防犯課員、警備課員など)になることにも、私個人は何の魅力も感じなかった。昔から私は「みんながそうするから、私も」と考えるような人間ではなかった。流されるのは恥だ、という意識があったのだ。
で、若い趣味人だった私には、「6日間に3日が休み」みたいな「三部制」勤務は、好きなだけ古本屋めぐりができて本も読める、というだけではなく、「7日で1週」という世間のサイクルとはズレていることが魅力でもあった。
それは、世間並みに「土日・祭日が休み」ではない、ということであり、言い換えれば、平日の休みが方が多いということ(祭日の当直勤務日には、祭日手当がついた)。
だから、学生時代の友達とはなかなか休みが合わないが、もともと独りで趣味に没頭したいタイプだから、それで困ることなど滅多にない。また、警察官になってからも「仕事の時以外は、一般人」という主義とも信念ともつかない気持ちがあったので、非番や週休の日に一緒に遊ぶような警察官の友達には作らなかった。私が社会人になってから作った友達とは、基本的に「趣味の友達」であり要は「読書趣味」を有する友達で、そうした友人には、できるかぎり私の職業が警察官であることを伏せていた。なぜなら、「警察官」だという目で見られると、何かと面倒くさいからである。
ともあれ、「平日に休みが多い」ということは、人が多い「土日」に出歩かなくても済むという点にメリットがあった。非番日の会社帰りに、そのまま空いた電車で行きたいところへ行って古本屋めぐりをし、週休日にはいっさい出かけないで、家で本を読むことができたのだ。
さて、ここでやっと佐多稲子に話を戻すと、佐多の『樹影』を読もうと思ったのは、自転車で回れる地元の古本屋に、ある時、佐多稲子の初版本がたくさん出ており、しかも、その多くは「献呈本」だったため、これをまとめ買いしたことからだ。
それらの本の多くには、「謹呈」と印刷された付箋が挟み込まれているだけで、献呈を受けた人(本を処分した人)の名前はなかったはずだが、佐多のサインが入ったものはいくつかあったように思う。しかも、それらの本は、非常に安かったから、10冊近く買ったのではないかと思う。その頃はまだ、そうした「献呈本」というのを見たことがなかったから、それが値打ちものに思えたのだ。
いま思うと、値段(古書価)が安かったというのは、たぶん、左翼作家である佐多稲子の本は、一般にはそんなに人気がなく、右から左には売れなかったからだと思う。
また、私の地元の小さな古本屋では、そんな本に高い値をつけても売れないのは明らかだったから、安く出していたのであろう。当時は、ネット販売などなく、ごく一部の古本屋が「目録販売」もしている以外は、すべて店売り。来客の大半は、町中にポツンと建っている店まで足を運んでくれる近所のお客さんであり、東京の神保町などのように、地元以外からわざわざ足を運ぶような、コレクターを当てにしての商売など出来なかったのだ。
したがって、そんな町の小さな古本屋にとっては、左翼の純文学作家の初版本よりも、その頃売れていた流行作家のエンタメ小説本の方が、よほどありがたかったのである。
また、ではどうして、そんな「町の小さな古本屋」に、そんな本がまとめて出たのかといえば、それはたぶん、その古本屋の近所に、佐多稲子の友達だか共産党の同志だかが住んでいて、その人も高齢になったから本を処分したか、当人が亡くなったので家族がその蔵書を処分したかであろう。家族には、その本の価値などわからないから、適当に近所の古本屋に、二束三文で売ったのではないかと推察される。
ちなみに、私が、それらの本を買ったのは、『樹影』を読む少し前くらいだろうから、やはり1995年か、せいぜいその前年。一方、佐多稲子が94歳で他界するのが1998年だから、佐多が自著を献呈するような友人や同志もおよそ同世代だとすれば、その献呈本の元持ち主も同様に高齢であり、亡くなってもおかしくはない時期だったのである。
ともあれ、そんなわけで佐多稲子の初版本をまとめて買ったのは良いが、私はそれまで佐多を読んだことがなかった。だから、どれから読もうと思った時に、最初に『樹影』を手の取ったのは、この作品が野間文芸賞の受賞作だからで、代表作の一つだろうとそう考えたことと、当時の私は「長編小説主義」だったこと、それに『樹影』は「原爆」問題を扱っていたこともある。私は当時「原爆」問題に興味を持っていたのだ。
しかしながら、私が読んだ『樹影』は、古本屋で購入した初版本ではなく、講談社文芸文庫に入っていた、文庫本だった。その頃は勤め人だったので、単行本のハードカバーは、持ち歩きに不便だったのである。
その点、文庫本なら、通勤電車の車中は無論、仕事の休憩時間にも寸暇を惜しんで読める。文庫本なら、常時ポケットに忍ばせておけるからだ。
当時の私の制服上衣の内ポケットには、常に文庫本が入っていた。印象深かった少し前の「角川文庫のテレビCM」ではないが、刃物で胸を刺されても大丈夫、だったのだ。

角川文庫のテレビコマーシャルのひとつでは、黒人だったかが街角に潜んでいて、いきなり男性の胸にナイフを突き立てて逃げるが、男性は胸の内ポケットに角川文庫を入れていたから助かった、というシチュエーションのドラマ仕立てであった。上は、森村誠一原作の大ヒット映画『人間の証明』のポスター)
しかし、『樹影』のことが記憶に残っているのは、この作品の中味や面白さのせいではなく、読んだ場所や状況が特殊だったためである。
というのも、この本を読んだ1995年には、地元大阪では「APEC'95大阪会議」が開催されており、私はその警備にかり出されて、日頃の交番勤務ではなく、来日する外国要人の宿泊施設となるホテルの警備に、私服であたっていたからだ。
ちなみに「APEC」とは、次のようなものだ。
『英語表記「Asia Pacific Economic Cooperation」の略で「アジア太平洋経済協力会議」のこと。太平洋を囲む地域の経済協力を進める枠組みで、1989年に日本、米国、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポールなど12カ国で発足。91年から中国、香港、台湾が、98年にロシア、ベトナム、ペルーが加わるなどして現在の21カ国・地域となりました。設立条約はなく、法的な義務付けを伴わない自主的な取り組みとして域内協力を進める場となっています。電子機器の関税撤廃で世界貿易機関(WTO)の議論をリードするなど一定の成果を収めてきました。』
(「APEC」とは)
つまり、「APEC'95大阪会議」には、米国、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、中国、香港、台湾などの15ヵ国の政府首脳クラスの要人が集うので、大阪府警としては、前代未聞の警備体制を敷くことになったのだ。
で、私はというと、大阪の中心地にあるホテルの警備に当たった。各警察署から応援要員として派遣された者が、警察署単位で担当場所を指定されたはずだが、私が配置されたのは、たぶん天満橋の「帝国ホテル大阪」だったのではないかと思う。今では、もっと立派なホテルがたくさん立っているが、当時は「帝国ホテル」が最も格式ある「VIP御用達」だったのではないかと思うのだ。
まあ、今も昔も高級ホテルなどには縁もなければ興味もない私なので、記憶も曖昧なら、ホテル名も覚えていないのだが、ともあれ、そのホテルの最上階には「要人用のVIPルーム」があって、私はこの時の警備の下見で、初めて(1フロア1ルームの)「VIPルーム」なるものの中を覗けたので、「これは、部屋ではなくて、ホテルの中の家ではないか」と、そう感心した記憶だけは、ハッキリと残っている。

私は当時、西成警察署員だったはずだが、似たようなものをもらったかもしれない)
で、そんな警備についていた際の、私の背広の内ポケットに入っていたのが、佐多稲子の『樹影』であり、私は隙をみては『樹影』を読んでいたから、それが忘れられない記憶になったのだ。
で、『樹影』はどうだったのかというと、あまり面白くなかったという、漠たる印象しか残っていない。
無論、原爆問題を扱った純文学作品だから、エンタメ的な面白さを求めていたわけではなかったが、純文学作品としても「いまひとつパッとしない」という印象だけが残っており、話の中身などは完全に忘れてしまった。また、そんな具合だから、結局はそのために、佐多の別の本を読むこともないまま、今日に至ったのである。
○ ○ ○
さて、やっと当レビューの眼目である、佐多稲子の短編集『キャラメル工場から』だが、この短編集は、今年(2024年)に編まれたもので、戦前から佐多晩年までの、選りすぐりの短編が収録されている。だから、当然のごとく面白かった。
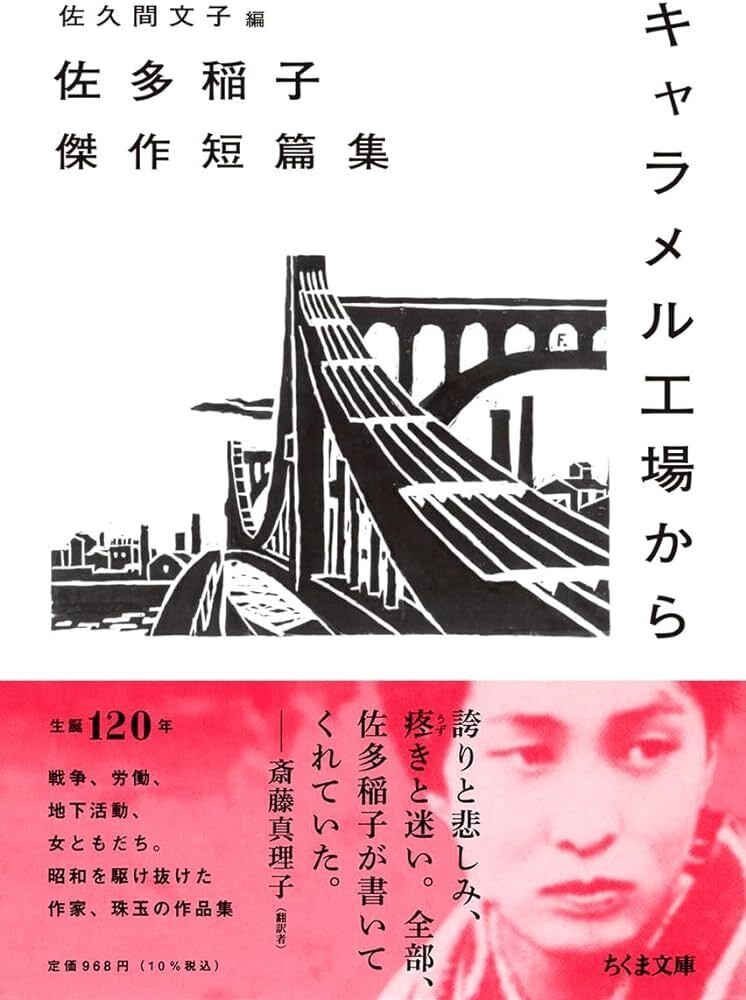
「編者解説」にも書かれているとおり、佐多自身も自分は「短編作家」だと言っていたようで、本書を読むと、たしかに佐多は短編向きの作家だと思う。
というのも、本書に収録されている短編はいずれも、人生のある場面を切り取ることで、人生というものを鋭く描いてみせるというタイプの小説だったからだ。
つまり、全部を描く、全部を説明する、といった長編向きな結構(構造)、あるいは、起承転結的な結構を備えた小説ではなく、言うなれば、スナップショット的な小説。だから、この人が、長編小説をむしろ「不得手」だと考えていただろうことは、本書からも容易に窺えたのである。
では、長編の『樹影』が、どうして「野間文芸賞」を受賞(1972年)し得たのかと言えば、それは、その頃にはすでに佐多稲子は「純文学文壇での大家」の一人だったからであろう。
「野間文芸賞」以前、すでに佐多は「女流文学賞」を受賞している(1962年)し、「野間文芸賞」の受賞後には、純文学短編を対象とした「川端康成文学賞」を受賞(1976年)し、それから1980年代には「毎日芸術賞」(1983年)と「読売文学賞」(1986年)受賞している。
あとの二つの賞は、作品に与えられるというよりも「作家の功労」に与えられる賞であり、要は「大家」だと公認され、その長年の功績を認められた、ということである。
言い換えれば、佐多はまず、力量と実績ある「女性作家」として認められて「女流文学賞」を受賞し、講談社が勧進元である「野間文芸賞」で、男女を問わない力量と実績のある純文学作家として認められ、その次に得意の短編を評価されて「川端賞」を受賞し、純文学文壇において確固たる地位を築いた後、しばらくして、大御所向け「功労賞」までもらう立場になった、という流れだ。
で、なんで佐多は、最初に短編集『女の宿』で「女流文学賞」を受賞して、女性作家としてその力量を認められた後に、長編の『樹影』で「野間文芸賞」を受賞したのかというと、それは、戦後も長らく、「文壇は男中心社会」であったためであろう。
女性作家は、文学賞レースにおいて、不利だった。当時は、「女性作家」ではなく「女流作家」、つまり「女の小説作家」という、言うなれば、ある種の「色もの扱い」だったのである。
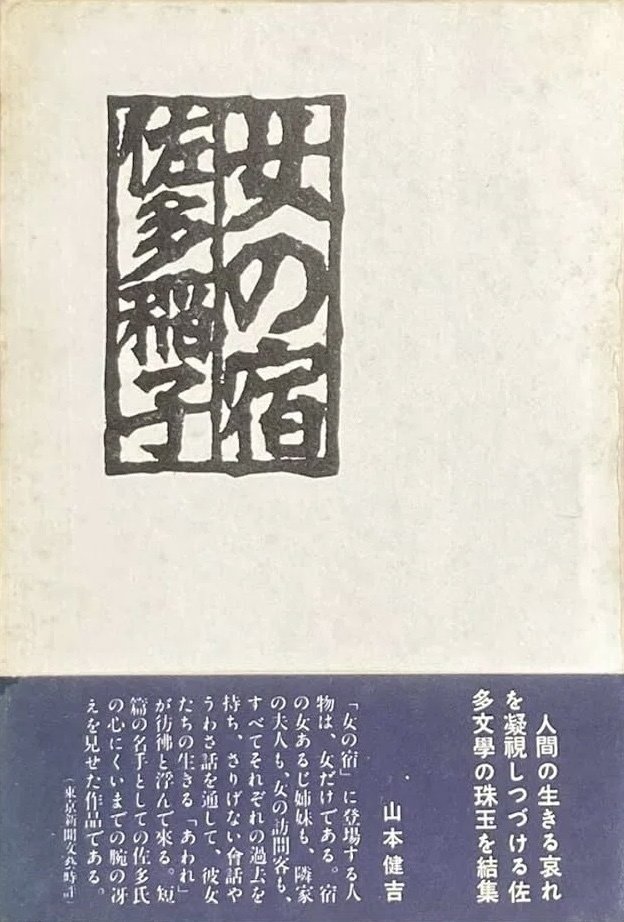
また、だからこそ「女性作家」の地位向上のために「女流文学賞」が創設されたのであり、それでもこの賞が「女性文学賞」という名称にならなかったのは、「男性文学」という言葉は「当たり前すぎて、存在しなかった」ために、それに対応する「女性文学」という言葉も存在しなかったし「思いもよらなかった」からだ。
で、佐多は「女性作家」の代表選手(先兵)の一人として選ばれ、そのあとにやっと、「長編重視の時代」を背景として長編の『樹影』で男女を問わない「野間文芸賞」を受賞し、さらにその後になって本領の短編があらためて評価され「川端文学賞」を受賞できた、というような流れなのである。
要は、「文学賞」の受賞にも、出版界内での歴史的な時代背景や政治的な背景が、今も昔もある、ということなのだ。
そんなわけで、佐多稲子の本領は「短編小説」にあった。
そして、そうした得意の短編の中でも、選りすぐりを集めたのが本書なのだから、これが面白くないわけがない。
これが面白くない読者とは、端的に言って、「純文学」の魅力がわからない文学オンチであり、要は「エンタメ」小説しか読んでいない、文学のど素人だということだ。
例えば、Amazonの本書の紹介ページに、カスタマーレビューを寄せているレビュアー「Amazon カスタマー」氏は、端的に言って「文学オンチ」である。
同氏の「小説の質としてどうなの?」と題するレビューは、懐古趣味だけの、ボケ老人さながらの小言にすぎない。
『 Amazon カスタマー 『小説の質としてどうなの?』(5つ星のうち1.0)
2024年6月27日
佐多稲子さんの名前は知っていたが読んだことは無かった。新聞の書評欄で「・・・昭和レトロ感もあり・・・」的な記載があったので、70歳の年寄りとしては、その感覚が味わいたくてこの短編集を購入した。しかし、私の個人的な感想としては、ストーリー展開上の説明不足も含めて色んな場面での説明不足が多々見受けられ、また、物語の終わり方も「そこで終るの?」的なこともあり、優れた小説とは思えなかった(もっと深く考えれば、理論的な否定ができるのだろうが、年をとると、そんなことを考えるのも面倒くさくなる)。で、全部読み終えることなく、ブックオフ行きにします。』
ご本人は『70歳の年寄り』だとおっしゃっているが、年寄りだから昔の小説がわかるというわけではないという、これはその良い見本であろう。私に言わせれば、同氏自身が「本読みの質としてどうなの?」ということにしかならない。
『物語の終わり方も「そこで終るの?」的なこともあり、優れた小説とは思えなかった』などと言うに至っては、お前は短編小説の筆法というものを知らないのかと、そう言わざるを得ない。
断言しても良いが、この人は70年間、ろくな小説を読んでこなかったし、そもそも頭が悪いから、自分の無能にも気づき得ず、身の程知らずにこんなレビューを「匿名」で書いたりするのである。要は、知ったかぶりで偉そうなことを言いたいだけの、臆病者の大馬鹿野郎だということだ。
そんなわけで、本書の収録の短編は、この「匿名ボケ老人」の評価とは真逆に、いずれも粒揃いで素晴らしい。
「貧しい庶民の生活の一コマ」を切り取った作品は、淡々としたなかにも、今でも胸に迫るものがあるし、戦争中、佐多本人としては「隠れ蓑」的に「従軍ペン部隊」に参加し、それを戦後に批判されたことに対する「やっぱり自分は、どこかで自分を誤魔化していたのではないか」と反省する自伝的短編にも、「等身大の人間」が見事に描かれている。
そこには、美男美女も登場しないし、ヒーローもヒロインも登場しない。劇的な大活躍も悲恋もない。わかりやすい痛快さもカタルシスも、泣かせの感動も無い。
つまり、私たちと同じような、普通の人間が、それでも「弱者の側に立とう」として足掻き続けた姿が、真摯に描き出されている。
戦前から「共産党員」として活動した佐多には、逮捕歴もあるし、そうした仲間の中にか警察に捕まって拷問死させられた者もいる。そうした過酷な状況下で、一人の女が、どのように闘い、時に敗れながらも生き抜いてきたのかが、すべての作品を通して浮かび上がってくる。

そして、そんな「共産党員」の作品を、戦後の「警察官」である私が読んだのであり、今回の短編集では、深く共感することもできたのだ。
なぜ、今も「共産党」と敵対している「警察」に属していた者が、それでも共感できるのかと言えば、それは佐多稲子が「人間」として、弱者に寄り添って書いていたからである。
警察官だって、全員が「共産党員」を敵視していたわけではないし、当然「権力の手先」としての「弱者の敵」だったわけではない。
「ペン部隊の作家」であった佐多と同様に、私もまた、幾ばくかの忸怩たる思いを抱えた、「獅子身中の虫」的な警察官であったのだ。


(2024年8月6日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
