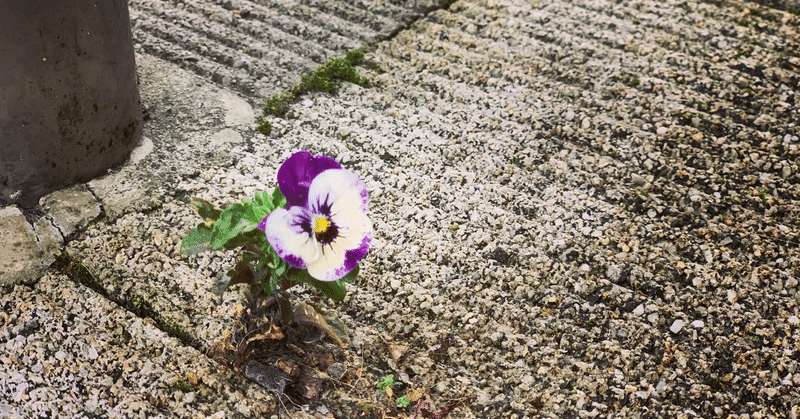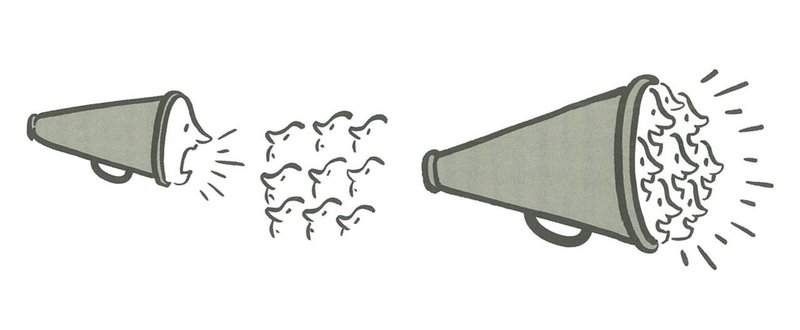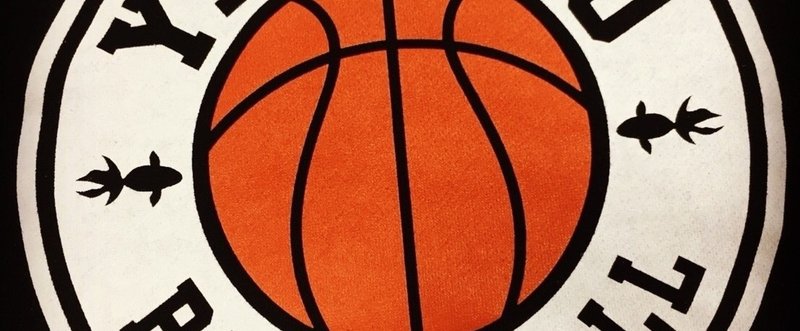マネジメント=管理とは「兵站(生産・物流・調達部門)を通じて限りある資源(ヒト・モノ・カネ・トキ)を把握・分配し、適時適切に適所で活かす」ことである。古来より兵站を軽んじ、人材や…
- 運営しているクリエイター
2018年4月の記事一覧
外国人を日本に招くことがサッカー界の発展に繋がらないと断言できる「8」の根拠【前編】
ハリル土壇場解任の中で、急遽言い訳として利用された「日本人監督でなければならない」という発言は論外として、「代表監督が日本人監督でなければならない理由」を正しく理解していない人が多いと感じます。その理由は決して単純なものではありません。私が数年間かけて思考した結果を書きたいと思います。内容の価値は保証します。
※この記事内における全ての発言に差別的意図は一切含まれておりません
根拠①:過去の事
ほとんどの人が勘違いしているグロースハックにおける最適なフレームワーク
グロースハックにおいて、最も有名なモデルはおそらく 「AARRR(アー)」モデルでしょう。
サービス全体をユーザーの行動に合わせた5段階のステージに分け、各段階の離脱率をファネル(ろうと)の形で整理したものです。
「AARRR」 は 、 ①ユーザーを獲得 (Acquisition、アクイジション)し、②そのユーザーにサービスの価値を感じさせ(Activation、アク
「正しい」けど「失礼」なひとを殺してはならない。
2週間ほど前のこちらの記事が話題になっていますね。
いくら正しくても、失礼だと敵視され、殺されてしまう。
Twitterでも好意的に拡散したこの記事ですが、私の感想は、「現実はおっしゃる通り」だけど、「こんな組織で働きたくないし、こんな空気をつくるべきでない」です。
本文から引用します。
残念ながら「正しいこと」をそのまま伝えると、「失礼」になることも多い。
・データがこう言っています
・