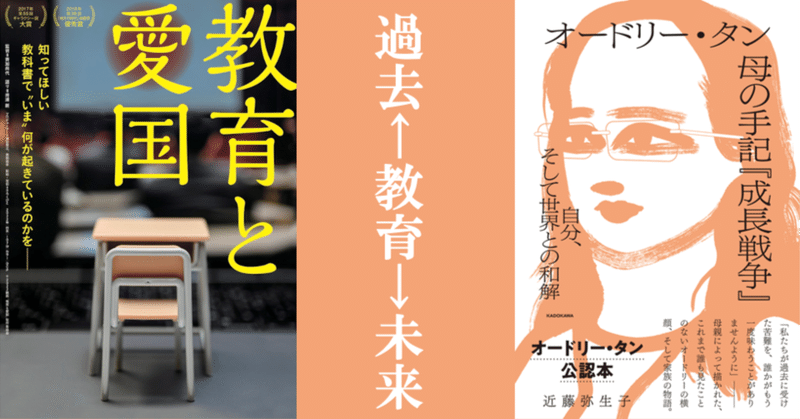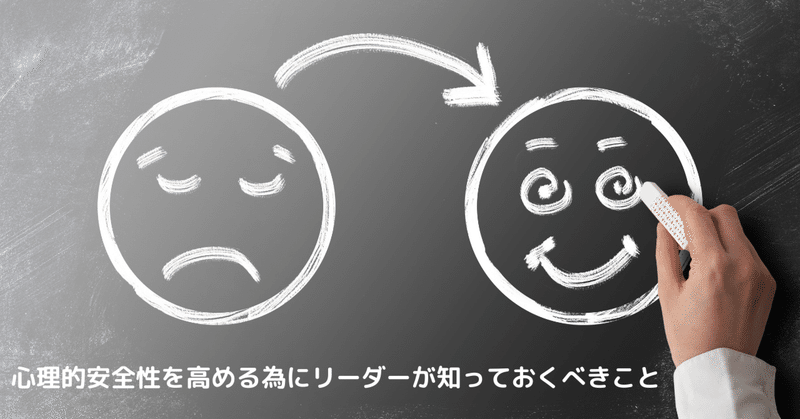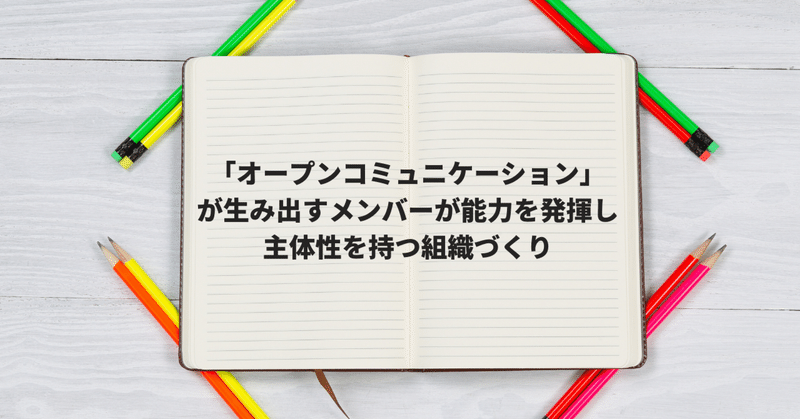- 運営しているクリエイター
#COMEMO
心理的安全性のために考えたい、たった1つのこと
今日は、「心理的安全性」について、考えていきたいと思います。
会社でも、組織でも、チームでも、コミュニティでも、親子関係でも、あらゆる場面で大切になってきていると感じるのが、「心理的安全性」。
心理的安全性は、何もアクションしなくても、高められるものではありません。意図的に高めていく必要のあるものと理解しています。
そして、立場や役割に関わらず、だれもが心理的安全性を高めることができると思っ
過去を向いた教育ではなく、未来の可能性のための教育にしていこう 〜『教育と愛国』と『成長戦争』の比較から
お疲れさまです。uni'que若宮です。
今日は久々に「教育」について書きたいと思います。
過去を向く『教育と愛国』の違和感先日、『教育と愛国』という映画を見てきました。
「愛国」という言葉があるように、政治的なテーマも半分入っていますが、日本の教育の問題について、改めて考える機会になりました。。。(教育に携わる方は是非みてほしいです。そして問題だと感じたらなにか変えるアクションをとっていき
新規事業開発の国際化にマネジメント能力がついていけるか?
海外で新規事業を創る
コロナ禍で一時的に停滞をみせていたビジネスのグローバル化が、昨年後期頃から徐々に盛り返しをみせている。例えば、インド市場に強いスズキは、インド北部ハリヤナ州に二輪車の新工場を建設することを発表した。近年、二輪や四輪車でよく見られるが、市場が急拡大し、大きなインドでの新工場設立とインドを主な市場とした新製品の投入が相次いでいる。ホンダのGB350やスズキのVストローム250S
心理的安全性を高める為にリーダーが知っておくべきこと
ここしばらくビジネスの世界においても「心理的安全性」という言葉を聞く機会は増えました。
漠然と「心理的安全性が高い組織は良さそうだ」と感じる人は多いと思いますが、なぜ組織づくりにおいて心理的安全性と向き合う必要があるのか、心理的安全性を高めるにリーダーはどう動くべきなのかなどについて、今回は考えていきたいと思います。
心理的安全性って何?そもそも心理的安全性って何なのでしょうか。
心理的安全
不確実性と対峙する時、心理的安全性が活動の基盤となる
戦後、何もかもが不足していた時代では、食べ物はあればあるだけ売れるし、洗濯機や冷蔵庫など、生活を楽にする製品は飛ぶように売れました。
長年の先達の努力により、企業の生産力は向上を続け、人々の基本的な生活の不足は解消されてきました。
それでも、企業はさらなる成長を求めています。
たとえ顕在的な需要が充足され、さらに人口が減少期に入った日本の環境においても、歩みを止めることはできません。
売上
「オープンコミュニケーション」が生み出すメンバーが能力を発揮し主体性を持つ組織づくり
リモートワークが中心の状況が2年以上続いている中、企業におけるチームのコミュニケーションも大きく変化しました。コミュニケーションの変化に伴い、チームビルディングの方法も変化が見られているのではないでしょうか。
今回は「テレワーク環境下でのチームビルディング」をテーマに書きたいと思います。
チームビルディングとは「チームビルディング」という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。基本的には組織
多様なメンバーをまとめるリーダーには「感情のファシリテーション」が必要だ
今日は、マネージャー(管理職)向けに「異なる部門の多様なメンバーを上手にまとめるには?」について書いてみたいと思います。
マネージャーの役割が大きく変わる新型コロナによる働き方の変化は、特にマネージャーの役割を変えると言われています。
これまでは、自らもプレイヤーとして稼ぐ「プレイングマネージャー」が多かったですが、これからは組織に変革をもたらす役割を期待されるのではないでしょうか。
例えば
「ギブファースト」の罠 〜ギブギブモンスターに気をつけろ!
お疲れさまです。uni'que若宮です。
コロナ禍が長期化の様相を呈し、経済的に個人にも企業にも大きな打撃となっています。その不安からちょっと世の中がピリピリしてきて、ストレス値が高まっています。そんな時だからこそ助け合いの気持ちが重要です。
「ギブファースト」という言葉をご存知でしょうか?
「ギブ&テイク」のうち「テイク」を考えずに、まず「ギブ」しようよ、ということなのですが、実はギブには