
映画 『百年と希望』 と 日本共産党 : 組織が先か、 個人が先か
映画評:西原孝至監督『百年と希望』
今年は「日本共産党」の創立百周年ということで、関連出版物がいくつも刊行されているが、このドキュメンタリー映画も、「日本共産党の、百年目の今を描く」いう趣旨で作られた映画である。
もっとも、この映画は、日本共産党の「公式」映画というわけではない。「公認」映画とでも呼ぶべき作品だ。
どう、違うのかといえば、まず本作は、現在の日本共産党指導部の基本方針にそって「現在の日本共産党の公式見解を紹介する」といったものではなく、共産党員ではないドキュメンタリー映画作家である西原孝至に、外部から見た「日本共産党」を撮ってもらうということで、内容には立ち入らない約束で、日本共産党側から制作を持ちかけた作品である。
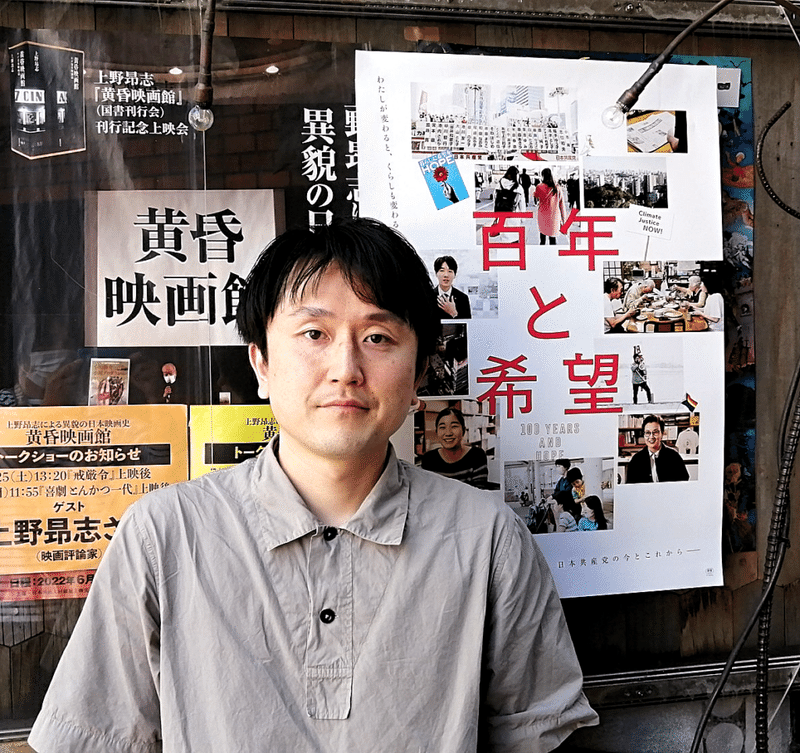
無論、監督の西原孝至が、『わたしの自由について ~SEALDs 2015~』(2016年)などの作品を撮っており、日本共産党にも一定の理解があるのを前提としての依頼であるから、決して批判的な内容になっているわけではない。だが、日本共産党「そのもの」を賛嘆する作品になっているわけでもない。

本作で描かれるのは、日本共産党の若手議員や選挙で敗れて下野中の元議員、『しんぶん赤旗』の編集局、党員歴60年のベテラン活動家、あるいは二十歳の若手活動家といった、「指導部」には属さない、いわば「現場」に近い人たちだと言えるだろう。
もちろん、『しんぶん赤旗』の編集局というのは、「現場」とは言いにくいのかもしれないが、そこで働いている編集局員たちの姿もまた、仕事に熱意を傾ける労働者のそれであって、「イデオロギーの人」というのとは違う。
この作品に登場する共産党員は、党の「基本方針」をそのまま体現する人たちではなく、それを基本としつつ、それぞれの持ち場で、自分なりのテーマを掲げ、その実現に向けて、実際に動き、語り、駆け回っている人たちだと言えるだろう。
したがって、議員たちを撮ってはいても、そこで語られるのは、主として、その議員がテーマとしている「ジェンダー問題」だとか「ブラック校則」問題といった、現場における個々具体的な問題であって、「天下国家」について大上段から語るようなものではない。
そうではなく、「生活に密着した問題」の向こう、「現場」で取り組む問題の向こうに、自ずと「天下国家」が存在するのだ、という立場だとでも言えるだろう。

そのため、この作品を観ても、「日本共産党の歴史」や「現在の基本的な考え方」といったことが、わかるわけではない。志位和夫委員長をはじめとした「党指導部」は、登場議員たちの街宣に応援で駆けつけたシーンくらいにしか登場しないのだ。この映画では、「指導部」は「雲の上の人」的にチョイ役でしかないのである。
だから、この映画が「今の日本共産党、全体の姿」を描いていないという点に、物足りなさを感じる人はいるだろう。
だが、それは監督自身、百も承知でやっていることであり、彼がこの映画でやっているのは、「外から見た、現場の日本共産党員」であって、「日本共産党の公式紹介」や「全体像」などではないからである。
では、この映画を、どのように考えるべきなのか?
日本共産党の「歴史的体質」といった「本質」問題が気になる人には、この映画に対し「所詮、枝葉末節でしかないのではないか。仮に、彼らは彼らなりに、現場で頑張っているというのが事実であったとしても、最終的には、共産党は共産党であって、今は、党としての力を弱いから、このように現場重視であらざるを得ないだけではないのか。イデオロギーを前面に出せないだけではないのか」といった疑問を、当然のごとく持つだろう。これは、もっともな話である。

しかしまた、そういう「大上段からの見方」しかしないからこそ、それが、ある種の「偏見」や「思い込み」や「色眼鏡」や「決めつけ」となって、「現に現場で動いている個人」や「現に現場で行われていること」が、適切に評価されていないという「現実」を、結果してもいるのではないだろうか。
言うまでもなく、どんな組織に所属する人たちであろうと、いろんなタイプの人、いろんな性格の人がいて、決して「一様」ではあり得ない。
組織の方針に素直にしたがって黙々と自分の仕事をこなす人もいれば、上の方針にいちいち逆らって文句を言わなければ気が済まない人、納得のいく説明がなされないかぎり動かないといった人もいるだろう。また、やる気があるのかないのかわからないけれども、やる時はやるし能力もあるといったタイプもいるだろう。気の強い人弱い人、弁の立つ人立たない人、みんなで賑やかにやりたがる人、一人で動きたがる人などなど。
いわゆる「活動家」と言われる人たちだとて、一様に「洗脳された、ロボット人間」だというわけでは決してないのである。
私は、こうしたことを、かつて所属した「創価学会」での経験においてよく知っているし、世間の「偏見」も知っている。創価学会員だからといって、世間の人が「イメージ」しているような「一様な存在」ではなかったし、今もきっとそうなのだ。
わかりやすい例で言うならば、「自衛官」や「警察官」といった人たちだって、同じである。
私たちは、「自衛官」や「警察官」というと、「お硬い」イメージを持ち、志操堅固な人たちだと思いがちだが、現実はそうではないはずだ。
事実として、彼らの中にも「でもしか自衛官」や「でもしか警察官」もいるだろう。本当は、別の職業に就きたかったのだが、そうはいかなかったので、やむなく「自衛官」や「警察官」になったという人も、公言はしないだろうが、絶対に少なからずいるはずだし、彼らの中にも「いい加減なやつ」とか「ずるい奴」とか「やる気のないやつ」などというのも絶対にいるはずで、みんながみんな、真面目でやる気があり信念を持っている、などということはあり得ない。
しかし、では、彼らが「自衛官」や「警察官」ではないのかと言えば、決してそんなことはないだろう。災害や事故や事件が発生すれば、仕事として現場に駆けつけるとしても、現に目の前に、苦しんでいる人や悲しんでいる人がいれば、彼らはその使命感に燃えて、損得抜きで、そうした人たちのために働くだろう。自分たちに与えられた「力」を使って、その「使命」を果たそうとするだろう。一一そうした「ギャップ」を含み持つものこそが、現実の「組織」であり「集団」なのである。
そして、これは「宗教団体」や「政治集団」とて、同じことなのだ。
大筋では、方向性を同じくしているからこそ、その「組織・集団」に属しているのであろうが、しかし、そこに存在するのは、結局のところ、「トップ」も「末端」も、ただの「人間」だ。能力や意志の強さに差があるとしても、それでもやはり、多様な個性を持つ人間でしかない。
だから、「組織・集団」というものを見る場合、たしかに、その「組織・集団」の「思想や綱領や使命」といった「基本情報」を参照する必要はあるけれども、そうした「観念」が、個々の人を動かしているわけではない、ということだけは、心しておくべきだろう。
もちろん「イデオロギーに取り憑かれたような人」がいるというのも事実である。しかしそれは、その人の「選択的意志の強度」の問題であって、決して「イデオロギー」が、「妖怪」のごとく積極的に、人間に取り憑いていく、というわけではない。
ある「イデオロギー」に対して、「命を捨ててでも、それを実現してみせる」というような人もいれば、「理想として素晴らしいと思うが、そのまま現実化するのは困難だから、是々非々で理想に向かうしかない」というような人もいるだろうし、「まあ、理想は理想で、個人的には信じていないけれども、ひとまずここが私の居場所だし」といった人もいるだろう。
そうした「組織・集団」の「リアル」は、日本共産党においても、創価学会においても、自衛隊や警察においても、基本的には何も変わらないはずなのだ。
つまり、その「組織・集団」の「思想や綱領や使命」を見ることは必要だけれども、それが自走しているわけではなく、結局は、それを選んだ「人々」が、その「組織・集団」を作っているのであり、「個々人」無くして「組織・集団」は無い、ということなのである。
だからこそ、「現場の人」「末端の人」もまた、「現実」なのだ。
それが、そのまま「中央」や「上層部」の姿ではないとしても、それでもそれは、間違いなく、ひとつの「現実の姿(側面)」なのである。


私たちは、ある「信念」を持った人を見ると、「あの人はイデオロギーに取り憑かれた人だ」というふうに見がちである。
しかし、そういう「物の見方」こそが、ある種の「イデオロギー的な偏見」なのではないだろうか。
人間だれしも、いろんな考え方を持っており、その考え方に従って、他の考え方を、否定し排除している。その場合「私の考え方は中立客観的であり、イデオロギーではないが、相手のそれは偏頗な信念としてのイデオロギーである」などと断じることは、果たして「中立客観的」な態度だと言えるだろうか?
もしも「私の立場もまた、私の美意識に従って選ばれた、一つの立場であり、一つの信念である」から、他人から見れば、一種の「イデオロギー」なのかもしれないと、そう考えられるほどに、自己に対して「客観的」であるのなら、もはや、その「所属組織や集団」の性質で、その構成員個々を「一様な存在」だと見たり、その「組織・集団」が、そのイデオロギーによって存在するものであるかのような、単純化された見方はできないのではないだろうか。
つまり、私が言いたいのは「組織・集団」というものは、本当は「人が作る」ものである、ということだ。
そして、「人が変われば、組織も変わる」ということなのだ。
だから、「組織の基本性格」だけに注目して、構成員「個人」を見なければ、それは、その「組織・集団」を、正しく見ていることにならないのではないか、ということである。

たまたま、嫌なやつと出会ったから「やっぱり共産党は」とか「やっぱり維新は」というのは、やはり「偏見」であろう。また、その逆も「真」であろう(つまり、たまたま良い人と出会ったことだけをして、その組織を判断するのも「偏見」だが、これも得てしてあることだ)。
そうした個々の情報が「雰囲気を掴む、一つの材料」にはなるとしても、所詮それは「象の尻尾でしかなく」、それですべてを裁断しようとする態度は、根本的に間違っているし、横着怠惰に過ぎよう。
だから私たちは、機会が与えられるならば、「個人」をもちゃんと見て、ちゃんと評価すべきなのだ。
その上で、その個人の深いところまで踏み込んでいき、「実際、どうなんですか?」と切り込むことをしなければならない。
どんな「組織・集団」にも、良い人もいれば、嫌な奴もいる。決して、個々は一様ではないという現実がありながら、しかし、それが「組織・集団」を現に構成しているという重い現実に対し、私たち、もっと真摯に、犀利に、切り込んでいくべきなのである。
(2022年7月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
