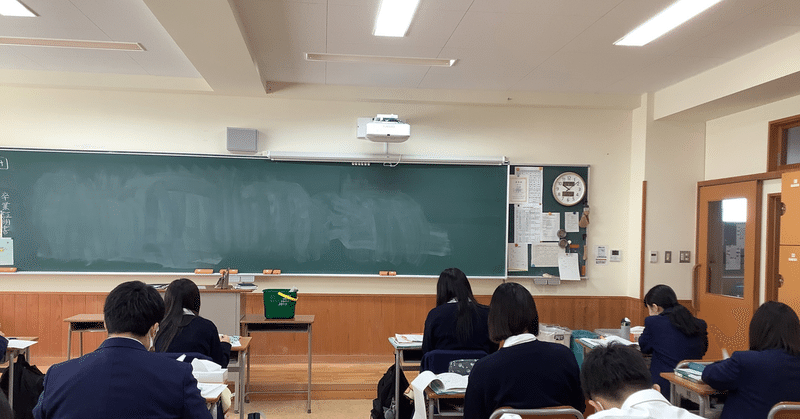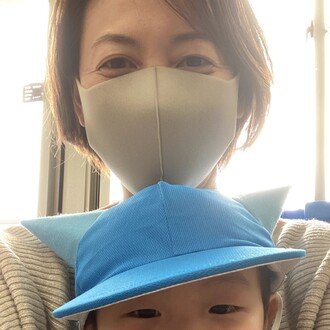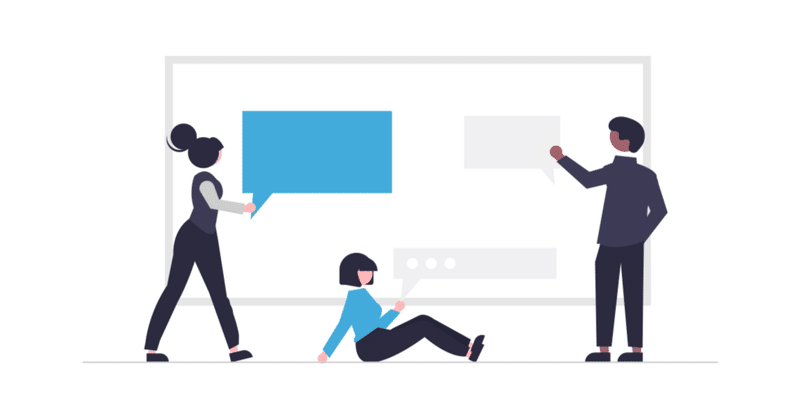#学校
「学校が変わる!解決志向で取り組む学校教育相談実践講座」
福島県教育センター教育相談チームに所属しています。
今年度最後の当チーム担当の専門研修「学校が変わる!解決志向で取り組む学校教育相談実践講座」が終わりました。
この講座では
「生徒指導提要や解決志向アプローチを学ぶことで生徒指導観を見直すきっかけを作る」
「一人でも多く幸せな子供が増えるよう、ケース会議を効率的に行う具体的な手法を体験的に学んで持ち帰ってもらう」
ことをミッションとして行いました。
ママ教員、保護者の立場からリフレクションしたデジタル・シティズンシップ教育
多くの人にデジタル・シティズンシップ教育を知ってほしい一心で、イベントを企画・開催しました。
こちらが開催企画に関する記事⬇︎
こちらが当日のレポートです。⬇️⬇️
私は主催者として、教員として、そして保護者としての立場からも、楽しみながら学ばせていただきました。
ちなみに私はiPad User's Salon東北支部アドバイザーというものを仰せつかっているのですが、
「保護者視点からの意見も
高校教員初任研一次研修で「生徒理解と生徒指導」を担当しました
先日の基本研修に続き、一次研修として40名の初任者対象に3日間の研修が行われました。基本研修での担当講座についてはこちら。
今回の研修は残念ながら対面がかなわず、オンラインでの研修に変更されてしまいました。前提として、受講者は1画面であること(サブモニターなし)を考慮しなければなりませんでした。
今回のミッション私が担当した講義・演習「生徒理解と生徒指導」でのミッションは、
①生徒理解の上で
新しい時代の子どもたち、そして大人ができること
新しい時代新しい時代、創造社会、Society5.0などと言われ久しいです。
学校にスマホやタブレットなどの持ち込みがOKという動き、
昔の鍵っ子はスマホっ子と呼び方が変わり、
ゲーム依存は病気に認定されたので保険適用となり、、、。
本当にここ数年の変容は目まぐるしいですよね。
出世する人の要素も変わったそうです。
あるIT企業幹部によると、次の5項目で昭和と令和の違いが明らかのようで