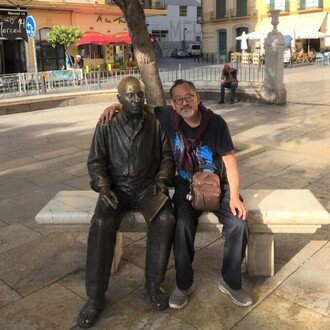- 運営しているクリエイター
2023年12月の記事一覧
<ラグビー>2023~24年シーズン(12月第五週)
(どうでもよい「話の枕」です。関心ない方は飛ばしてお読みください。)
私の棲んでいる場所にある都営住宅が、次々と取り壊されて更地になっていく。一部は新たな高層の都営住宅に建て替えられているが、十年ほど前は古い都営住宅が立ち並ぶ一種壮観な風景の地域だった。そのうち、倉庫だったところにマンションが次々と建てられ、街並みは一新していった。今や、マンションに住む若い家族とインド人や中国人、都営住宅に
<書評>『言語と自然』
『言語と自然』 モーリス・メルロポンティ著(1952-60年の講義録) 滝浦静雄・木田元訳 みすず書房 1979年(原書は1968年)
哲学書の翻訳者として著名な木田元によれば、ドイツの哲学者エルネスト・カッシーラーが『シンボル形式の哲学』で結論に至らなかった後を継いで、結論を出すべく試行錯誤をしたのが、フランスの哲学者モーリス・メルロポンティであり、その記録が本書にあるという。先日苦労の末
<閑話休題・芸術一般>写真のような絵と写真
写真のような絵と写真とは、いったいどこがどう違うのだろうか?
普通に考えれば、同じようにしか「見えない」。そして、昔よく聞いた言葉として、「写真がすでにあるのだから、絵の役割は写真になることではない。むしろ、写真とは違うものを表現すべきだ」ということがあった。そのため、マティスやピカソのような、あるいは印象派のような、対象そのものではなく、対象から受けた「印象」や自分の中に沸き起こった感情を
<ラグビー>2023~24年シーズン(12月第四週)
(どうでもよい「話の枕」です。関心ない方は飛ばしてお読みください。)
〇 クリスマスにフライドチキンを食べるというのは、日本だけの習慣だろう。ちなみに、アメリカのサンクスギビング(感謝祭、収穫祭)では、ターキー(七面鳥)を食べるが、代わりにチキンを食べる場合がある。一般的にチキンはどの国でも安価だから、季節行事とは関係なく扱いやすい食材だ。もっとも、日本のクリスマスは単なる金儲けの行事またはお
<閑話休題>結局、言っていることは同じだと思う。
定年後自分の時間がたっぷりとできたので、古今東西の宗教関係の本を少しずつ読んでいるが、毎回思うのは「言っていることは、結局同じなんだよな」ということだった。まあ、こんな言い方でこんなことを書くと、「何も知らない奴が、いい加減なことを書いている、たいした自己中心的で自信過剰な奴だな」と揶揄されるだけかも知れないが、そうした「自己中心的かつ自信過剰な読み方」の(悪しき事例)と思って、寛容の心で接して
もっとみる<書評>『神智学 超感覚的世界の認識と人間の本質への導き』
『神智学 超感覚的世界の認識と人間の本質への導き』 ルドルフ・シュタイナー著 高橋巌訳 イザラ書房 1977年
神智(人智)学で著名なシュタイナーが、神智学を紹介するために最初に出した本。この内容をより詳細に述べたものとして、『神秘学』を後に出版している。巻末にある本人の自歴と解説を読むと、シュタイナーは、19世紀末オーストリアという、当時の知的世界の最先端の地域で、カントからヘーゲル、そして
<閑話休題>大悟または私とは何か
大学を卒業するとき、就職指導の一環として、「大学で何をしてきたか」というものを自己アピールの準備として書かせられた。普通、こういう場合は「友人を沢山作った」、「部活動を一所懸命やった」、「経済活動の仕組みを勉強した」、「一般教養を深められた」、「いろいろなところへ旅行した」、「アルバイトで社会経験を積んだ」等々を書くのだと思う。
ところが、かなりの変わり者であった私は、そこに「私とは何か、な