
映画『窓ぎわのトットちゃん』 : 「人間を描く」正統派の傑作
映画評:八鍬新之介監督『窓ぎわのトットちゃん』(2023年)
今年のアニメーション映画の最高作だと断じたい。
私は、今年の早い時期に、今年のアニメ映画の傑作として、渡邉こと乃監督の『金の国 水の国』を挙げておいたが、本作はそれを軽く超えていく傑作だと言ったら、渡邉こと乃監督とその作品を出汁にしたようで本当に申し訳ないのだけれど、本作を観れば、たぶん渡邉監督も納得してくれることと思う。
そのほかに、今年どんなアニメ映画が公開されたのか、もうほとんど忘れてしまっているが、それほど本作は、ずば抜けて素晴らしかったのだ。
本作の原作である、タレントの黒柳徹子の自伝『窓ぎわのトットちゃん』は、1981年に刊行されて大ベストセラーになり、海外でも高く評価され、今も読み継がれている「名作」である。一一だが、私はこの原作を読んでいない。

黒柳徹子その人には、前々から好感を持っていた。私の場合も、黒柳を知ったのはテレビのトーク番組『徹子の部屋』だったのだが、それをたまに視ているだけでも、彼女の、ある意味「空気を読まない天真爛漫さ」に好感が持てたのだ。「この人は、本当に思ったことを喋っているんだな」と感じさせるものが、そこにはたしかにあった。
そして、もうひとつ好感要因は、黒柳が「ユニセフ親善大使」として活動しているというのを知ったことだ。
黒柳の「Wikipedia」には、次のようにある。
『芸能活動以外にも、国際連合傘下のUNICEF(ユニセフ、国際連合児童基金)親善大使としての活動が特に知られる。親善大使には1984年アジアの人物として初めて就任し、その後最古参のメンバーになった。当時のユニセフ事務局長ジェームス・グラントは、任命理由として黒柳の子どもへの愛と、障害を持つ人々や環境への黒柳の広範囲な活動と実績を挙げている。以後、アフリカ、アジアなどの途上国を毎年欠かさず訪問し、現在までの訪問国数は30ヶ国に上る。親善大使としての活動に対して、ユニセフからは、1985年に「第1回ユニセフこども生存賞」、2000年に「第1回ユニセフ子どものためのリーダシップ賞」を受賞。また日本政府からは、2003年に勲三等瑞宝章(現:瑞宝中綬章)を授与された。
黒柳がユニセフ親善大使に就任することになったきっかけは、当時ユニセフ事務局長だったジェームス・グラントが『窓ぎわのトットちゃん』を緒方貞子の紹介により読んだことである。』
いくら有名人で、お金にも困っていないとは言え、これだけのことはダテや酔狂でできるものではないし、今回、本作『窓ぎわのトットちゃん』を観て、黒柳のこうした活動が、彼女の原点から真っ直ぐに出てきたものだというのが、とてもよくわかった。
ちなみに、私は、上で言及されている「緒方貞子」に対しても、かねてより畏敬の念を持っていた。黒柳にしろ緒方にしろ「本物の女性」は、男なんかよりずっと強いなと、そう思い知らされる感じを持っていたのだ。

しかし、そんな私が、どうして黒柳の自伝『窓ぎわのトットちゃん』を読まなかったのかといえば、その「あらすじ」として「通常の学校に馴染めなかったトットちゃんが、フリースクールに通い、いきいきと成長していく姿を描いた」ものであり、そこに「戦争の影が差す」といった、いかにも「リベラル」流に「優等生的な物語」を予感される部分に警戒したからだ。
トットちゃんは「優等生」ではないようだが、物語の方は「優等生的」なのではないか。悪い意味で「リベラル・イデオロギー」的な作品なのではないか。「そっちの人たちが、無闇に絶賛する」態の作品なのではないかと、そう警戒したのである。
また、どうして、このように強く警戒したのかというと、私は同系統の作品として、これも大ベストセラーになった、グラフィックデザイナー・妹尾河童の自伝的小説『少年H』(1997年)を読んで、あまり感心しなかったからである。
この自伝小説が原作の同名劇映画を観て「悪くない」と思い、読もうかどうしようかと迷っていた上下2巻本の原作を読んだのだが、期待したほどではなかった。
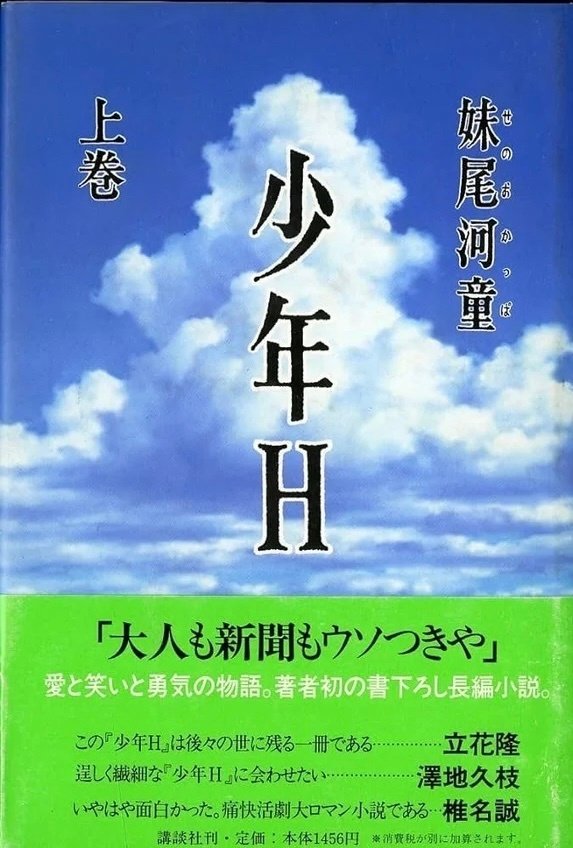
たしかに、悪い作品ではないという意味においては「良い作品」であり「良心的な作品」であるとは思う。しかし、それ以上の「小説としての力」を感じなかった。あくまでも「その善意における優等生的な内容において、評価できる作品」に止まっているという印象が強かったのだ。
だから、それ以前から、気にはなっていたが読むにまでは至らなかった『窓ぎわのトットちゃん』も、「同系統」の作品として、すっかり読む気が失せてしまったのである。
○ ○ ○
そんなわけで、今回の「アニメ映画版」も、当初は観る気などぜんぜん無かった。アニメ映画化と聞いても「今頃? ああ、原作の続編が刊行されたから、このタイミングなんだな」という程度にしか思わなかった。続編の刊行はテレビニュースか何かで視て、知っていたのだが、当然、まったく興味はなかった。
ただ、他の映画を観に行った際にたまたま見た「予告編」が、かなり好印象だったので「もしかすると、ちょっと面白いかもしれない」とは思ってはいたのだ。だが、それもそれだけで終わって、実際には観なかった公算の方が高かった。
ところが、先日、どうしても大阪梅田まで出かけなければならない用事があった。しかし、その用事のためだけに、出かけるというのはいかにも気が重かった。
一昨年の退職以来、私は本当に、好きに生きているから、気の向かないことは、ほとんどしなかった。昨年、やむを得ずにやった初めての確定申告の、なんと面倒であったことか。今年は、無収入だったので、確定申告をしなくて済むとわかって、なんと嬉しかったことか。もちろん、贅沢きわまりない話だというのは重々承知している。だが、本当のことだから仕方がない。
ともあれ私は、家にいて、本を読み、映画のDVDを観、こうしてレビューを書くこと以外は、食って寝ることしかしない生活を、すでに1年半ほどやっているが、それにまったく飽きていないというのは、レビューの更新頻度を見ていただければわかるだろう。これは純粋に、楽しいからやっているのであり、だから、お代もいただかないのだ(笑)。
そんなわけで、私は、できるかぎり家から出たくはなかった。それで寂しいなどということは、まったくない。だから、家から出るのは、食料を買い出しのためにバイクで出かける際の30分間程を別にすれば、映画を観に出かける時に限られていると言って良い。
映画は、大阪梅田(各駅停車で三駅隣り)まで出かけるか、十三(一駅隣り)に観にいくしかないので、不承不承、出かけるのだが、今回の場合は、やむをえない「雑用」のために出かけるため「せめて映画を観て帰ろう」と、そう思ったのだ。
しかしまた、すでに観たい映画は観てしまっていたから、何を観ようかと上映中の作品をチェックしてみたところ、最初に決めたのが『窓ぎわのトットちゃん』であり、もう一本は「右肩上がりの大ヒット中」と評判になっているらしい、こちらのアニメ映画の『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』であった。当然のことながら、昭和37年(1962年)生まれの私は、原作漫画の方は齧った程度だが、テレビアニメの『ゲゲゲの鬼太郎』は、子供の頃に何度も繰り返して視ている。今で言うところの「第1期」と「第2期」であった。
○ ○ ○
さて、肝心の本作アニメ映画版『窓ぎわのトットちゃん』だが、これは「自伝」をもとにした作品だけに、あらすじらしいあらすじはないのだが、いちおう「あらすじ」的なものを紹介しておこう。本作は、戦前から太平洋戦争(第二次世界大戦)にかけての東京郊外を舞台にした作品である。
『好奇心旺盛でお話好きな小学1年生のトットちゃんは、落ち着きがないことを理由に学校を退学させられてしまう。東京・自由が丘にあるトモエ学園に通うことになったトットちゃんは、恩師となる小林校長先生と出会い、子どもの自主性を大切にする自由でユニークな校風のもとでのびのびと成長していく。』
(「映画.com」の「解説」より)

つまり本作は、「戦前から戦争へ」という時代を背景にして、トットちゃんの『のびのびと成長していく』姿を描いていく作品であり、決してトットちゃんが「大冒険」するようなお話ではない。そんな時代を生きた、実在した少女の姿を描いた成長譚なのである。
だが、筋らしい筋がない作品というのは、分析的な批評が書きにくい作品だということでもある。
大変に「完成度の高い、作り込まれた傑作」なのだけれど、「完成度が高い」「作り込まれている」「人間が描けている」「傑作だ」といくら連呼したところで、この作品固有の「美質」を語ることにはならないのだ。
参考にしようと、ざっと目を通した「映画.com」のカスタマーレビューは、どれもおおむね共感・同意できるものだった。曰く、
(1)「トットちゃんがいきいきと描けている」
(2)「尊敬する恩師・小林宗作氏への、リスペクトを込めた描写が素晴らしい」
(3)「戦争の影を、子供の目を通して、見事に描いている」
(4)「オルタナティブスクールの必要性が叫ばれている、今の時代にぴったりな作品」
(5)「作画が素晴らしい」
(6)「胸を締めつけられるような感動に泣いた」


どれも当たっていると思う。
しかし、こうしたことを語るだけでは、「批評」にはならないという感じがあり、それは私がこの作品に感じたものを、うまく言語化できていないということでもあった。
しかし、これもいつものことだが、何を書くかの構想が固まってから書くのではなく、とにかく書き出してみようと思い、参考になるものはないかと、いつものように「Wikipedia」や「映画.com」のカスタマーレビューなどをざっと眺めていたところ、これだというのが、ついに見つかった。
「映画.com」のカスタマーレビュアー「たけ(c)」氏のレビュー「教え」の中の、次の言葉である。
そうだ、そのとおり。本作の素晴らしさは「高畑勲演出のような静かな巧みさ」にあったのだ。しかも、高畑作品の中でも、その狙いが成功した良作の部類に入る作品に近い、「生活と人間」をきちんと描いた「傑作」だったのである。
例えば、私がこの作品に惹かれた最初の理由は、「予告編」ですでに感じられた、主人公トットちゃんの「いきいきした描写」である。
この印象は、映画本編を観ることで裏づけられた。主人公のトットちゃんは、とにかくよく喋り、よく動き回る「エネルギーに満ちあふれた、子供らしい子供」であった。
だからこそ、画一的で集団主義の公立学校教育では「はみ出し者」になってしまったのであり、学校の先生からすれば、トットちゃんが「面倒な子」だというのもわからない話ではない。だが、トットちゃんその人に注目すれば、こんなに魅力あふれた子供もなかなかいないというのは明らかだ。子供が本来持っている「生きる力」に、人並み以上にあふれ、それをふりまいていないわけにはいかない、トットちゃんの人間的魅力は、誰にも否定できないものなのではないだろうか。
一一だが、このような「説明」では、本作の魅力が語れたようには思えなかった。
しかしそれが、「たけ(c)」氏の『高畑勲演出のような静かな巧みさ』に触発されて、語るべき言葉が出てきたのだ。「これは書ける」という手応えが生まれたのである。
トットちゃんの魅力とは、かの「ハイジ」と同質のものだったのである。「あの名作アニメ」の序盤で描かれる、「あの、下着一枚で、アルプスの野山を笑いながら駆けまわっていた、まるで屈託というものを知らない、あのハイジ」である。一一こう言えば、「なるほど」と膝を打ってくれる人も、少なくないはずだ。

つまり、(1)の「トットちゃんがいきいきと描けている」というのは、具体的に言えば、あの「ハイジ」を思い出してくれれば、それでわかってもらえるはずだ。
しかも、トットちゃんは、実在の人物を元にしているだけあって、ハイジに勝るとも劣らない存在感があるのだ。これでは、トットちゃんに魅せられないはずがないではないか。
だが、本作での「演出の妙」は、そうした「わかりやすい」部分だけにあるのではない。その典型が、トットちゃんが転校したフルースクール「トモエ学園」の園長だった「小林先生」の描き方である。
「予告編」などでは、小林先生がトットちゃんと初めて会った時に言った『君は、ほんとうは、いい子なんだよ。』という、いかにも「子供に理解のある、理想の教育者」的な言葉が前面に出て、へそ曲がりな私などは、かえって鼻白んだのだけれど、本作で感心したのは、この園長である小林先生が、ひとクラスだけの「トモエ学園」の、たったひとりの担任教師である、まだ若い女性教師の大石先生を、子供たちの目のないところで、厳しく叱責しているシーンだった。トットちゃんが、たまたまその部屋(園長室?)の外を通りがかり、いつもとは違う小林先生の厳しい声にびっくりする、というシーンである。

大石先生がなぜ叱責されたのかというと、授業中に大石先生がふと口にした「冗談」について、それを後で知った小林先生が、決して「冗談では済まされない」と判断したからである。
その冗談とは、大石先生が子供たちに「進化論」の話をしていて、猿から進化した動物だからこそ、人間には「尾骶骨」というものがあるのだと、黒板に図示して説明した後、ちょっとした「冗談」として、ある男子生徒に向かって「○○くんのお尻には、まだ尻尾があるんじゃないのかな?」みたいなことを言って、子供たちの笑いを取った、というものであった。
はっきり言って、普通ならこれは「冗談」で済まされてしまうことだろう。大石先生に悪気がなかったのは明らかだし、その冗談を向けられた少年も「そんなことないですよお」と、それが冗談だとわかっているから、半照れ笑いで受け流していただけだった。一一だが、小林先生は、この時の少年の気持ちを洞察していたのである。
園長室で、小林先生は大石先生に対して、はっきりと怒りを滲ませた厳しい口調で「あなたには、ああ言われた彼の気持ちが分からなかったのですか」と叱責した。その少年が、半笑いで受け流したとしても、やはり自分が特に名指されて、尊敬する先生に「猿に近い人間」認定されたと感じて「傷ついたであろう」ことを見逃さなかったのであり、要は「傷ついて当然の言葉」だと、そう考えたのである。
大石先生は、その指摘を受けて、泣きながら「私が間違っていました、浅はかでした」と、心ならずも子供の心を傷つけてしまった自分の鈍感さに、心からの悔いの言葉を漏らしたのである。
で、今どきなら、この小林先生の叱責が「厳しすぎるのではないか」というような意見も出てくるだろう。「怒るのではなく、叱る」「叱るのではなく、優しく指導する」べきだといったような、当節流の考え方である。
たしかにそれにも一理はある。しかし、少なくともこの描写は「あんなに優しい、物分かりの良さそうな小林先生」の、芯のある「教育への情熱」をひしひしと感じさせるものであった。
「これは絶対に、許してはいけないこと。改めてもらわなければいけないことだ」と思って発せられた「真剣」な言葉だというのが、よく伝わってきたし、それは、たまたま盗み聞きをしてしまったトットちゃんにも伝わったからこそ、トットちゃんは生涯、小林先生への尊敬の念を失わなかったのではないだろうか。ただ「優しい」だけではなく、「激しいまでの情熱をうちに秘めていた人」としての小林先生を。

もう一点、「感心した演出」について紹介しておくと、(3)の「戦争の影を、子供の目を通して、見事に描いている」という部分である。
こうした作品で「戦争批判」をやると、特に、子供を出汁に使ってそれをやると、いかにも「リベラル・イデオロギー」的な「説教」臭がして、かえってウンザリさせられることがある。私が、『少年H』を評価できなかったのも、まさにそうした部分であったのだ。
だが、本作は、そうではなかった。それを強く感じさせたのは、本当にさりげなく、かつ観客にも深い印象を残す、その演出だったのだ。
トットちゃんが、トモエ学園に転校になった際、最寄駅「自由が丘」駅の「切符切りの駅員さん」に、トットちゃんが、回収した切符をもらえないかと話しかけたことから始まる「ささやかな交流」が描かれるのだが、物語の後半で日本が戦争に突入した後、ある日突然、その駅の切符切りが、女性に替わっていたのである。
トットちゃんは「あれっ、いつもの駅員さんじゃないな?」という様子で、小首を傾げて改札を通り過ぎるだけなのだが、このシーンが示しているのは、その温厚な駅員のおじさんが、兵隊にとられて出征した、ということなのである。
つまり、トットちゃん自身は気づかないところで「戦争の影」が、天真爛漫な彼女の周囲にまでしのび寄ってきていたという、これは「見事な演出」だと、私は思わず唸らされたのだ。
前述の「小林先生の大石先生への叱責」と同様、このエピソードも、もしかすると「原作」にそのままあるものなのかもしれない。だとすれば、その成果の半分は原作にあるとも言えるのだが、しかし、こうした「地味なエピソード」を落とすことなく、きっちりと拾い、きちんと描いて見せたところにこそ、本作の「傑出性」がある。
同じ原作をアニメ化したり劇映画化したりしても、同じような傑作にならないのは、こういうところに「大きな差」があるからなのだ。これこそが「演出家の目」であり、その力量の示しどころなのである。
本作は、こうした「緻密かつ丁寧な」演出と、その意を受けて「丁寧に描かれた、登場人物たちの所作(作画)」において、『アルプスの少女ハイジ』や『母をたずねて三千里』『赤毛のアン』といった作品を彷彿とさせる「傑作」であったと、私はそのように評価したい。
残りの次の3点も、本作が、そのような「正攻法」によって生み出された作品だったからこそ、「どこそこが良かった」ではなく「いい作品だった」と言わしめる作品、「これ見よがしなアピール」でも「これ見よがしな作画」でもないところで観客を魅了する、傑出した作品となっていたのである。
(4)「オルタナティブスクールの必要性が叫ばれている、今の時代にぴったりな作品」
(5)「作画が素晴らしい」
(6)「胸をしてつけられるような感動に泣いた」
○ ○ ○
一回観れば二度とは観る気にもなれなければ、その必要もないような作品や、それとはまた逆に、一部の「作画」や一部の「泣かせシーン」だけを観るために、ことさらに何度も観ては、その「鑑賞回数を誇るための作品」などとは違い、本作は、人が、人間というものへの希望を見失ったときにこそ、また観てみたいと思わせるような作品となっている。トットちゃんのように前を向こうと、そう励ましてくれる作品なのだ。

戦況の悪化によって「トモエ学園」が閉園せざるを得なくなり、閉園式が行われたあと、トットちゃんは小林先生に「私が大人になったら、トモエ学園の先生になってあげる」と言って、小林先生を喜ばせる。
しかし、その「トモエ学園」も、のちの空襲の際に焼夷弾の直撃を受けて灰燼に帰して、結局は(歴史的には)再開できなかった。
そんな、いままさに燃え上がり、焼け崩れる「トモエ学園」の前に立って、小林先生は落胆するのではなく、「さあ、今度はどんな学校を作ろうか」と、不屈の闘志をみなぎらせた言葉をもらす、そんなシーンがある。
私はこのシーンを、ほぼ間違いなく、本作におけるオリジナルの描写であり、実在の小林先生こと小林宗作へのオマージュを込めた、「イメージシーン」であろうと考えた。
だが、「Wikipedia」をみるかぎり、これも、「逸話」として残っているものであり、事実かどうかは確認できないまでも、本作での創作ではなかった。
いずれにしろ、「Wikipedia」に載っていないような、その後の小林の詳しい軌跡を、私は知らない。だが、歴史的事実がどうあれ、黒柳徹子がその後に「ユニセフ親善大使」となって、世界の子供たちのために尽力したのは、小林先生の志を継いだからに他ならず、それは、先生との約束どおりに「トモエ学園の先生」になった、ということなのではないだろうか。
夢や希望は、必ずしもそのままのかたちで実を結ぶとは限らないとしても、それでも希望を捨てずに、それを願い続けるならば、それはどこかで、少し違ったかたちではあれ、何らかのかたちで実現されるものなのではないだろうか。
本作は、今のような時代にあっても、「前向きな希望」を観る者に与えてくれる、小さくとも明々と点る灯りのような、そんな「傑作」である。

○
(2023年12月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
