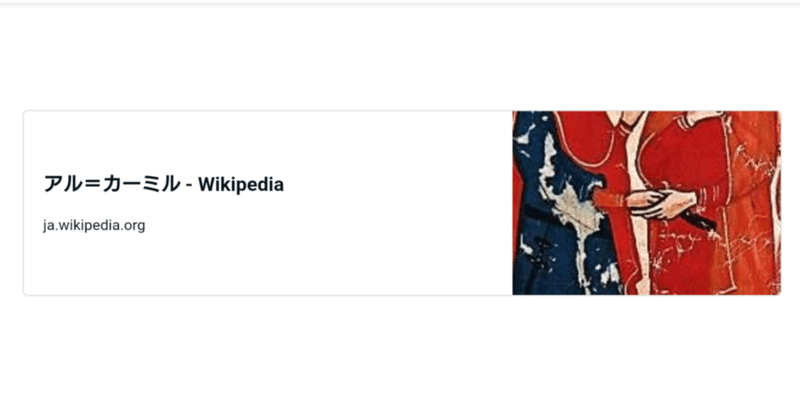
パクス・ヒュマーナ 〜平和という“奇跡”〜 その4.4 平和は相互努力 協定後のリアルな定着作業 平和裏にエルサレムを統治できた背景 当たり前過ぎて意識しなくなっていること
ネタバレですがフリードリッヒ2世に平和裏にエルサレム統治を快諾したエジプトのスルタン、アル·カーミルもまた評価されるべきかと思います。
NHKさんの作品を取り上げ、平和への1つの切り口、史実を元にした深堀りをするという話です。
(特に駐在したイスラエル、飽きるほどデレゲーションのアテンドデレゲーション行ったエルサレムと私の人生に大きく影響を与えた稀有な経験に直結しています。ですから食い散らかした現役時代を卒業したこともあり、コンテンツとして残す事に意義ありという認識です。立ち止まって丁寧に考察して行きます。)
今回は、平和裏にエルサレムを統治できたヤッファ協定後のリアルな定着作業を考察したいと思います。
そもそも両者間の膠着を美しく収めたアル·カーミルは相互の面子が立つという趣旨で
大きな戦火をを避けるための協定締結
を提案したのでした。
合意した協定は、詳細まで可能な限り丁寧に煮詰めたと言っても、それは当然大筋で平和的という話でした…
協定の詳細に拘(こだわ)るのは、サラリーマンなら、その実効性定着まで拘るのもサラリーマン。
(笑)。以下に定着、ソフトランディングするまでの丁寧な作業を考察してみました。
フリードリッヒ2世とアル·カーミルで決めた協定ですから、エルサレムに接するダマスカスを統治していたやんちゃな弟が亡くなったとはいえ、その継承者たる若き新スルタン、アル·ナーシルは自分の頭越しに決められた協定には反対でした。必然の反応として父の兄たるアル·カーミルに対して反旗を翻しました。具体的な戦術としては、上述の協定で土地を没収されたイスラム教徒、不利益を被った民衆を扇動するというものでした。詰まり若干間接的。
しかも、極めて激しい性格の父に比べれば対応は甘く、想定の範囲内に収まり、アル·ナーシルと不利益を被った民衆を一纏めにして効率的に鎮圧することができたのでした。
一方、キリスト教陣営も手放しでは喜べない状況でした。というのもフリードリッヒ2世が破門されていた状態のままであったからでした。破門されていた皇帝の快挙という何とも教皇側からするという跛行的な状況。詰まりキリスト教陣営もまた一枚岩ではありませんでした。
こちらもそもそもエルサレムを担当していた現地側の総大司教もざわつくのです。手こずっていた難題を、破門状態にある皇帝が遠征で…詰まり外から来て、有り得ない、“交渉での解決”を、しかも見た目には極短期間で成功させたという話ですから、面白くないのは当たり前でした。総大司教もまた扇動という戦術を選択しました。“協定は欺瞞(ぎまん)”というロジックでの糾弾でした。まぁ、苦し紛れ感が否めないロジックに見えます。それも有ってか、糾弾止まり。想定内ってところです。
お次は、テンプル騎士団や
ヨハネ騎士団。
彼らは、ソロモンの神殿跡地がイスラム教徒の統治のまま残っている協定は許されないという抗議をしました。詰まりアル·カーミルは相互の面子を保つ目的で、フリードリッヒ2世が例外として譲歩した…
アル·アクサ寺院
岩のドーム
のある神殿の丘
そして、エルサレム周辺の村は現実的な対応としてイスラム側の統治のまま、但し巡礼は許可するというのは、不十分という主張でした。しかしこれも大事にはならず抗議の範疇を超えませんでしたので想定内で収まりました。
この様に糾弾や抗議が拡大することなく限定的。多数派にはなりませんでした。
と言うことで、キリスト教徒側はフリードリッヒ2世の人徳と実績で収めるという落とし所で収めたのでした。これもまた教皇からすると面白くない話でした。しかも武器を使わずに交渉で聖地を奪還したのは、当時の人々の理解を遥かに超越して居ました。
ですから専門家曰く、それは今日でもフリードリッヒ2世の評価が、特に欧州では相対的に低評価側にバイアスが掛かっているという形で残っているということだそうです。
キリスト教にとって教皇が行う破門という扱いがそれ程重いというのも…。イスラエルに駐在し、ユダヤ教徒のイエス・キリストからのキリスト教を肌で感じる立場に有った私としては、甚だ違和感が有ります。イエス・キリスト、and/or彼等の神は、一体如何に思っているのでしょうね…
何れにせよ、スルタンたるアル·カーミル、皇帝たるフリードリッヒ2世の相互の現実的な協定の仕上がりは、想定内での定着作業の甲斐有ってソフトランディングという形で想定通り10年間有効に定着したのでした。
サラリーマン的には“出来すぎ”感が否めません。でも史実という扱いなので脚色は無い。
こんなお2人の仕事だからこそこうやってNHKにも取り上げられてるんですよね。
つづく
…………………………………………………………………………………………[経緯]
その1では、神聖ローマ皇帝のフリードリッヒ2世がその理性的な能力を発揮し十字軍として交戦すること無く、交渉でエルサレムの統治権を得たという史実の話でした。
その2.1。その偉業を成し遂げたフリードリッヒ2世が3歳で父を亡くし、4歳の時に母方の持つシチリアの王となりました。そしてその理性的な能力の根源を、同年母が他界する4歳までに得たという話でした。そして… (格別の知識·能力を持って)4歳で孤児になったのでした。
その2.2。その後の児童期の話。
母からの幼児期のエリート教育、教皇からの児童期前半のエリート教育、そして多民族の思惑の中で揉まれた経験がファンダメンタルズ形成の礎となったようです。
その2.3。少年期父親の元部下のドイツ人による教育と地中海交易盛んな市中を徘徊し得た経験、そして歴代王の残した蔵書の乱読という話でした。
その2.4はフリードリッヒ(フェデリコ)2世が平和裏にエルサレムを統治できた背景、特に教育という切り口での詳細な考察のまとめでした。
その3は、フリードリッヒ2世に最大の成果に関する関する専門家のコメントを紹介。彼の翻訳活動がルネサンスに及ぼした多大な影響を考察しました。
その日4.1。平和裏にエルサレムを統治できた元はフリードリッヒ2世の異文化交流力。学問の分野で親交の厚かった交渉相手のエジプトのスルタン、アル·カーミルは気心が知れ、戦いを望まないフリードリッヒ2世との関係を上手く利用しエルサレムをキリスト教徒に統治させることで弟の領地との緩衝地帯を設け、兄弟間の無用な争いを回避することを狙ったのでした。
その4.2。アル·カーミルの弟の死が状況を一変。そもそもの交渉の前提が消えた為に形勢逆転。膠着するも、アル·カーミルが、フリードリッヒ2世と親しいファーラッディーンを交渉役に就け膠着を崩しました。そのゲームチェンジャー崇高な理由でエルサレムの平和を実現したのでした。
その4.3。エルサレムの平和を実現した条約(協定)の詳細を考察しました。崇高な目的達成実現の為、現実的な落とし所を探った素敵な契約の細部でした。
……………………………………………………………………………………………
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

