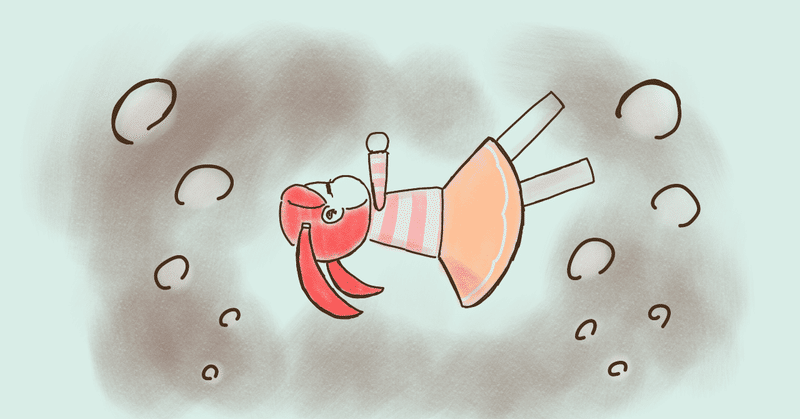
『無職沼』
『無職沼』
夏の盛りをすぎたある日のことだった。
そのとき、私は無職十一ヶ月目だった。
毎日、ハローワークへ通うこと以外にすることが何もなかった。お金もないし、恋人もいない。友人たちはふつうに仕事をしていて忙しく、なかには結婚している人もいるので、彼らとは容易に会うことができなかった。自然とひとりの時間が多くなる。
ある朝、目を覚ますと、体が気怠く、上唇の右端が痙攣しており、頭の中で、ごうおーんごうおーん、という梵鐘が鳴る音がある一定のリズムで響いていた。のみならず、顔がメリケン粉をまぶしたように白く、眉毛は薄く、一重まぶたの目が死んでいた。
私の目の前には巨大な闇が立ち塞がっている。
右も左も上も下も全部、闇だらけの底なし沼だ。
なんてひどいザマなんだ。こりゃあ、近々、死ぬな。少しずつ、闇が私の体を蝕んでいく……
そう思った私は柄にもなく、山を登ることにした。
市内郊外にある自然観察森林公園がある山である。
そこは約十キロの散策路、広場や東屋などがあり、気軽に散策や山登りができるところらしい。
なんとなくの思いつきだった。思い立ったが吉日というヤツである。気分転換にもなると思った。
私は納豆ご飯を食べて、正午すぎに自宅を出た。
自転車を立ち漕ぎでかっ飛ばし、あっという間に駅前につくと、そこから市営バスに乗った。そして、三十分ほどバスに揺られた。バスの中は年寄りしかいなかった。私は窓の外をぼんやりと眺めていた。
飛行機が北から南へ青空を二つに切り裂いていた。
山の散策路は空を遮るような高い樹木に囲まれており、枝葉の隙間からは午後の明るい光線がさしてくる。また、道中は植物や昆虫の観察ができ、野鳥の啼き声なども耳に入った。その中を歩いていると、心地よい静けさで心がおだやかになり、平生、感じることのできない癒しを私は総身に感じた。
私は大学を卒業してから、まともな仕事に就けなかった。県内外にある百八十くらいの様々な会社を受けたのだが、全て不採用になった。だから、仕方なく、アルバイトなども受けてみたが、そのほとんどがなぜだか不採用になる。しかも、受けた求人の八割は面接まで行けず、最初の書類選考で落とされるのだ。私は不採用通知が自宅のポストに届くたびに死にたくなるような絶望と焦燥と虚無に襲われた。
運もなければ、努力はほとんど報われない。私はそう思っている。ただし、ある意味では報われないことは必ずしも不幸なことでもないとも思っている。
なぜなら、報われない人は苦しんだ分だけ、凡人には絶対に会得できない強靭な独自のエネルギーを腹の中に隠しているからだ。これが一番恐ろしい。
森の奥は黒々と葉が茂る杉や檜の雑木林が日の光を遮っていて薄暗いが、ひとりで歩いていても不安や孤独を感じなかった。なぜなら、道中、たまに人とすれ違うからである。それは年寄り夫婦やランニングする女子学生であり、すれ違うときに向こうから、「こんにちはー」「がんばりましょう!」などと笑顔で挨拶された。近頃、人と接する機会が減っていた私は、その些細な人とのコミュニケーションが心地よく感じられ、私の心を快活にさせた。
散策路はただの一本道ではない。山の中を毛細血管のように道が方々に枝分かれしている。私は好奇心から、故意に山の奥へと続いている道ばかりを選んで、東屋などで休み休み、悠然と歩いていった。
先月、ある会社の採用面接のとき、俺は世の中のすべてを熟知しているみたいな顔をした中年男から、
「キミは趣味とかあるのかね?」
「あ、はい。映画鑑賞です」
「映画?最近はどんなの観たんだ?」
「ブラウンバニーです。ヴィンセント・ギャロの」
「全く知らないな。キューティーハニーならどこかで聞いたことがあるような気がするがね…」
「へえ。割とマイナーな映画ですから…」
「私は映画を観ないんだ。あれは時間のムダだ。たとえば、二時間の映画を観るなら、私はその二時間を仕事に使う。その方が有意義だと思わないか?」
などと言う社畜のハゲオヤジの頭を馬の蹄か何かで思いきり殴打してやりたかった。馬の蹄は魔除けになるらしいからちょうどいい。ぶっ殺してやる。
その後、ハゲオヤジは正露丸を噛み砕いたみたいなにがにがしい顔をして、私の履歴書を無言で眺めていた。無論、その会社は不採用になった。
沢沿いの道を歩いていた。浅くはない沢の水は底が見えるほど清澄透明であり、水の流れはゆるやかだった。川面を眺めながら歩いていると、どこか遠くでチリンチリンという熊鈴が鳴っていた。
沢沿いの道の終わりには急勾配の山の斜面が待っていた。斜面にむかって朽ちた丸太の階段が右へ左へと延々と続いているように並んでいる。
斜面を登りきると山の尾根に出た。私の全身は汗まみれだった。体が芯から熱く、燃えるようだった。心が躍動しており、心地よい疲労を感じていた。
視界が拓けた展望の中に出ると、遠く正面にある大小の山々の稜線が脳波のようにうねっていた。その山々の前景には、櫛比している人家の屋根が橙色の夕日を受けて、魚の鱗のようにキラキラと美しく輝いている。私は絵がヘタだから描けないが、油絵にしたいような風景だった。私の頭上では、澄んだ声で、ヒッヒッと啼いている野鳥の声がしていた。
先日、ある会社の採用面接のとき、猫じゃらしのような眉毛をした田舎の元百姓みたいな中年男から、
「うちの会社に入りたいのならば、まず、オレを口説いてみろ。さあ、どうだ。やってみろッ!」
と開口一番に言われた。私は腹が立った。
やかましいわ、ボケ。その前に、お前、タバコを吸いながらの面接ってどういう神経してんの?小太い足も組んじゃってるし。面接官失格だからね。こんな会社、こっちから願い下げだよ、さようなら。
腹の中でそう思った私は、愛想笑いを浮かべて、一応、志望動機と自己PRなどを真面目に披露したが、終始、男は渋面で反応が冷淡であり、タバコの煙を吐き出しながら、「で、最後に何か質問はある?」と言った。無論、その会社も不採用である。
山の尾根を吹く風は荒々しかった。風が私の髪の毛を頓着なく掻き乱していく。また、尾根筋は硬い地質のためか、木の根が地中に入れずに地表を這うように複雑に絡み合っていた。だから、歩きづらい。
下りの山道は急勾配の岩だらけのでこぼこした険しい道だった。山道の右手は切り立った断崖になっていて、崖下には群青色の大きな沼があった。
私はふと、「生きていてもつらいだけだし、あそこに飛び込もうかな」と考えたが、思いとどまった。
夕闇がそこまで迫っていた。山全体が冷え冷えとしてきて、空気の肌触りがあきらかに変わった。
はあっと息を吐くと白かった。私は完全に日が落ちる前に山を出なければならないと焦った。
急ぎ足で下山した。山道はだんだんと道幅が狭くなる。両側を熊笹が覆い、先の尖った葉が顔や手に触れるとチクチクして痛かった。山全体が不気味なほど静かである。鳥の声も風の音も何も聞こえない。
空は墨色になり、濃い煙のような雲がせわしなく流れていた。星や月はどこにも見当たらなかった。
すると、眼下の展望を遮る樹木の枝葉の隙間から、市街地の灯りが見えた。その小さな街の明かりを見ていると、なぜだか懐かしさを感じて安堵した。
あの明かりの中のどこかに私の自宅があり、友人の家もあり、私が次に働く職場もあるのだろう。
また、もしかすると、今後出会うかもしれない好きになる人の家なんかもあるのかな、などというバカみたいなことを考えていると感傷的になり、しんみりすると同時に早く街に帰りたいと思った。
山道の出口付近には木でできたお地蔵様があった。
元々、ここに生えていた木から掘り出したような感じであり、顔の造りが些かいびつである。
お地蔵様はおだやかな顔をしており、足元には小石がいっぱい積んであった。私はその辺にある小石を拾い、お地蔵様にお供えをすると、「よい仕事が見つかりますように…」と言って、手を合わせた。
〜了〜
愚かな駄文を最後まで読んでいただき、
ありがとうございます。
大変感謝申し上げます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
