
「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」/13歳/聖なる無法者にして守護者の戦いの記録//、涙よ、流れろ、涙よ、止まれ、終わりより始めるために
涙よ、邪魔をするな、涙よ、止まれ、涙よ、わたしが小説を前に進めることをさまたげないでおくれ。涙よ、視界を奪うことをやめてくれ。それが戦慄き震えるわたしの体の叫びをあらわすものであったとしても、少しの間ほんの少しの間、わたしが終わりに辿り着くまでの時間を与えてくれ。終わりからはじめるために終わりに到着するために。溢れ出る、涙、止まれ、涙よ、
小説という小さなフィクションの中で誕生し非情の世界に投げ出された13歳の少女が世界と戦う。弱き存在であり守られるべき存在であるはずの少女が守るべき存在を守るために全存在を賭けて守護者となり、わたし/わたしたちの現実の邪悪なるものたちと戦う。激しく揺さ振られわたしの魂が叫び声を上げる。わたしの物語でありわたしたちの物語であり戦いの記録である。
涙よ、流れろ、涙よ、止まれ、終わりより始めるために
No.1:小説というフィクションから逸脱する異形の者たちがわたしたちの現実を激しく揺り動かす/異形の者のひとり、ダッチェス・デイ・ラドリー

時折り、小説の中の登場人物でありながらその小説からはみだしてしまう者たちが存在する。彼/彼女は小説が構成されその部分として形成され出現した者たちでありながら小説から逸脱することになる。後戻りすることなく。小説というフィクションの容器の中で誕生したフィクションを出自とする者でありながら彼/彼女はそれから外へと向かうことになる。彼/彼女はフィクションが生み出したものだ。しかしその存在はフィクションの外部へと向かう彼/彼女は自身の宿命を全うするために小説の外へと踏み出す。わたし/わたしたちにそれを押し留める術はない。かくして世界/現実はフィクションから顕れし異形の者たちによって攪乱され変更される。否応なく決定的に。

ダッチェス・デイ・ラドリーもそうした異形の者のひとりだ。彼女を小説「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」の主人公でしかないと思ってはいけない。それは大きな錯誤だ。「感動的な物語」として読んではいけない。物語をスリラー/ミステリーとして消費しようと企て本を手にする者がいたとしたら、当然のこととして酷い罰を受けることになる。ダッチェス・デイ・ラドリーがそんなことを許すことなどあろうはずがない。ダッチェス・デイ・ラドリーは「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」というフィクションの主人公であることを超越して、わたし/わたしたちの世界/現実を激しく揺り動かす。彼女はフィクションでありながらフィクションではない。彼女はフィクションを超えてわたし/わたしたちの現実と戦う。

だからわたしは語らなければならない。ダッチェス・デイ・ラドリーの戦いと彼女の宿命について。そして、彼女がわたし/わたしたちの世界/現実を動かすこと、その意味について。これは小説というフィクションについての話であり、同時に、小説というフィクションの話ではない。フィクションが現実に作用し現実を変更してしまうことになる、現実の話だ。異形による破壊
はじめにダッチェス・デイ・ラドリーが何者であるのかを精密に同定し、彼女を造形した「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」が如何なるものであるのか解明する。その結果わたしの涙の理由が刻明になる。涙には理由があるんだ。涙よ、流れろ、涙よ、止まれ、終わりより始めるために

No.2:13歳/イノセンスとギルティの間で/彼女は弟と伴に生き延びるために無法者となる。生存のために法の外へ。
本編の主人公、ダッチェス・デイ・ラドリー、13歳。〈13歳〉が特別な意味を持つ数字として提示される。12歳でもなく14歳でもなく、13歳。大人と子供の中間地点、子供から大人へ向かう後戻りできない通過点、イノセンスとギルティの間に位置する13歳。物語は13歳から始まり14歳の誕生日を迎えた後に終結する。ダッチェス・デイ・ラドリーはイノセンスとギルティの間の中で自称〈無法者〉と名乗り、14歳の誕生日を迎えた時ギルティの中で本物の〈無法者〉となる決断をする。生存のためそれ以外の方法は彼女にない。

無法者/アウトロー(Outlaw)を「法の保護と恩恵を剥奪された者であり、社会から追放された秩序の外に存在する者」とするならば彼女は正確には無法者/アウトロー(Outlaw)ではない。なぜなら彼女とその弟は法の保護と恩恵を受けているからだ。それが形だけの内実の欠けたものであったとしても。しかしそのことがそのことによって二人に非情な運命を課することになる。法がもたらす冷酷な現実。法は彼女と弟に何もしないし救ってくれないひたすら深く傷付けるだけで。世界の秩序を司る法が彼女らを擂り潰して行く。ダッチェス・デイ・ラドリーはそれを受け入れるつもりはない。自分と弱き者を守るために法の外へと出て戦うことになる。自称の無法者の戦い。
それを痛ましきことと捉えその痛ましさに同情することは止めた方がいい。わたしたちは彼女らを潰している世界の秩序を司る法の側に存在している者なのだから。わたしたちとは彼女と弟を切り裂きその滴り落ちる血を浴びている存在。弱き者たちの血と涙を求め泣き叫ぶ声に陶酔する邪悪なる存在。ダッチェス・デイ・ラドリーが世界の埒外の者となり銃口を向け戦う相手はわたしたちのことだ。彼女の敵なのだ、わたし/わたしたちの存在こそが。

No.3:聖なる守護者にして無法者、ダッチェス・デイ・ラドリー
守護されるべき弱き者が守護を失ってしまうこと。時にそれは惨劇を呼び寄せることになる。弱き者が喪失の反撃として世界への復讐のために無差別の殺戮者となり惨劇を撒き散らす。惨劇が強き者によるものではなく弱き者によって実行され世界が破壊されることを、わたしたちは何度も繰り返し経験することになる。しかも惨劇の犠牲者たちが殺戮者よりさらに弱き者たちであるということ。守護者の喪失、弱き者の惨劇、壊れてゆく、何もかもが。

ダッチェス・デイ・ラドリー、二度も、一度ではなく二度も、凄惨なる事態によって愛する守護者を失った者。宿命だとしてもあまりにも苛烈な宿命。
彼女が宿命を背負わせた非情なる世界への復讐のために何をなしてもそれを咎めることはわたしにはできない。誰が彼女を責めることができようか。だがしかし彼女には守るべき守らなければならない弱き者が存在した。非情の世界の中のただひとつの恩寵として彼女に与えられしもの。彼女はひとりではなかった。弱き者の弱さが惨劇を止め事態を切り開く。彼女は新たなる存在へと変貌する。弱き者のために弱き者を守護するために全存在を賭けて。

失われたはずの彼女の守護者が最後に彼女に遺したもの。それを見つけ出しそれを身に纏った時、彼女は決然と変貌する。涙よ、流れろ、止まれ、涙よ
弱き者が弱き者でありながらもさらに弱き者の守護者たろうとする鮮烈な意志によって、弱き守護者が聖性を帯びることになる。守護する者しか持ちえない備えることのできない侵されざる存在としての厳粛性。その侵犯不可能性が世界に轟き渡り聖性のひかりが生み出される。発光する聖なるもの。
凛然として聖性の光芒が彼女を包み込み、守護者は聖なる存在として出現する。聖なる無法者へと転化する自称の無法者。そして、その瞬間は彼女が彼女自身の全ての守護者を喪失した瞬間でもある。守るべき存在のために全存在を賭した守護者を守ることは誰であろうともそれをなしえない。孤独の中、重き銃と弾丸を鞄に詰め込み、彼女は闇と光に挟まれた地平を駆け抜けるように横断する。名前のない町でその歩みが左右に分かれる人の波の間に道を開き、彼女は歌う。「Bridge Over Troubled Water」われら闇より天を
〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉、ダッチェス・デイ・ラドリー

No.4:欠点だらけのジクソー・パズル//鮮やかなショットが欠点を凌駕してゆく/作り物めいた映画のラスト・シーンを観るような終わり
「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」はジグソー・パズルとしては欠点だらけだ。細部のピースが壊れていて隙間なく嵌め込むことができない。パズル的快楽の欠落。登場人物たちは的確だが類型的で真新しさはなく道具立ても新鮮味はない。謎解きとしては中途半端であり因果の応報の物語としては噛み合いが屈折し愛の物語としては強引なものでしかない。つまり、ミステリー/スリラーとしては完成度がいささか低く欠陥だらけの物語。
物語の展開について言えば、巧みな人物造形によって複数の人物たちを配置した前半だがその分ストーリーの展開は緩慢だ。しかし後半から急速にストーリーが回転を始め、全てが収束点へ向けて雪崩を打つ様は壮観だ。但し、幾つかの重要な細部に疑問が残りそれが最後まで回収/解消されることなく物語は終わってしまう。映画のラスト・シーンを観るような結末なのだが、物語のカタルシスとしては作り物めいたものとなる。好き嫌いは別として。
とは言っても鮮やかに描写されるショットに息を呑みそれが欠点を遥かに凌駕してしまうところがこの小説の最大の魅力。物語の組み立てとしては精巧さに欠けているが細部の表現において濃淡のある小説ということになる。
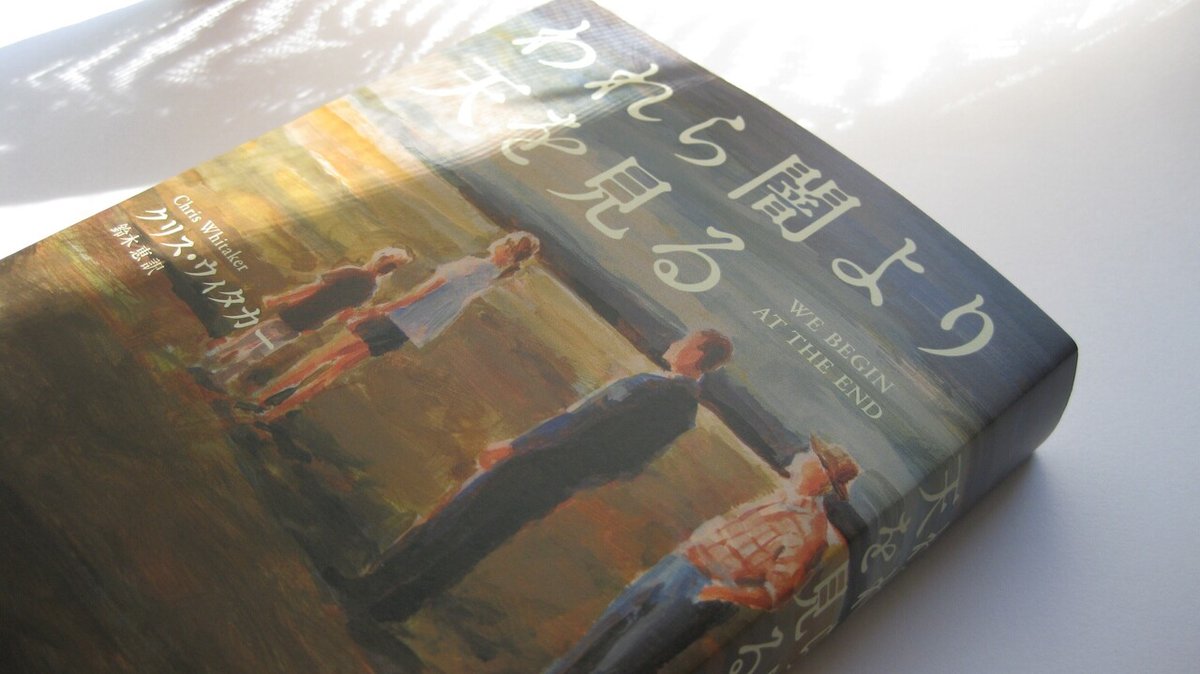
No.5:聖なる者の戦いの記録/ダッチェス・デイ・ラドリーが流した血と涙、その肉体の破片
でもそうしたこと/そうした指摘のすべてが意味のないものでしかない。
これをミステリー/スリラーとして読んではいけないし小説/物語として読んではいけない。とわたしは思う。そうじゃないんだ。そうじゃない。全然そうじゃない。「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」は小説なんだけど小説なんかじゃない。物語なんだけど物語なんかじゃない。形式も内容も見掛けも中身もそれとしか見えなくても、これは全く別のものなんだ。

ダッチェス・デイ・ラドリーの生の断片。ここに存在しているものはダッチェス・デイ・ラドリーが流した血と涙なんだ。これはその肉体の破片なんだ〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉であるダッチェス・デイ・ラドリーが戦いの最中に失ったすべてのものたちとことたちについての記録。
物語の色彩が物語の後半からひとつの神話のひかりを放つことになる。限りなく弱き者でありながら〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉である、ダッチェス・デイ・ラドリー。聖なる存在の道行きの記録。読み手はそれを息を止めて見つめるしかない。そして、読み手も聖性のひかりに包まれる。
「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」とは、「〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉13/14歳の少女/ダッチェス・デイ・ラドリー、その戦いの記録、流した血と涙、肉体の破片」となる。
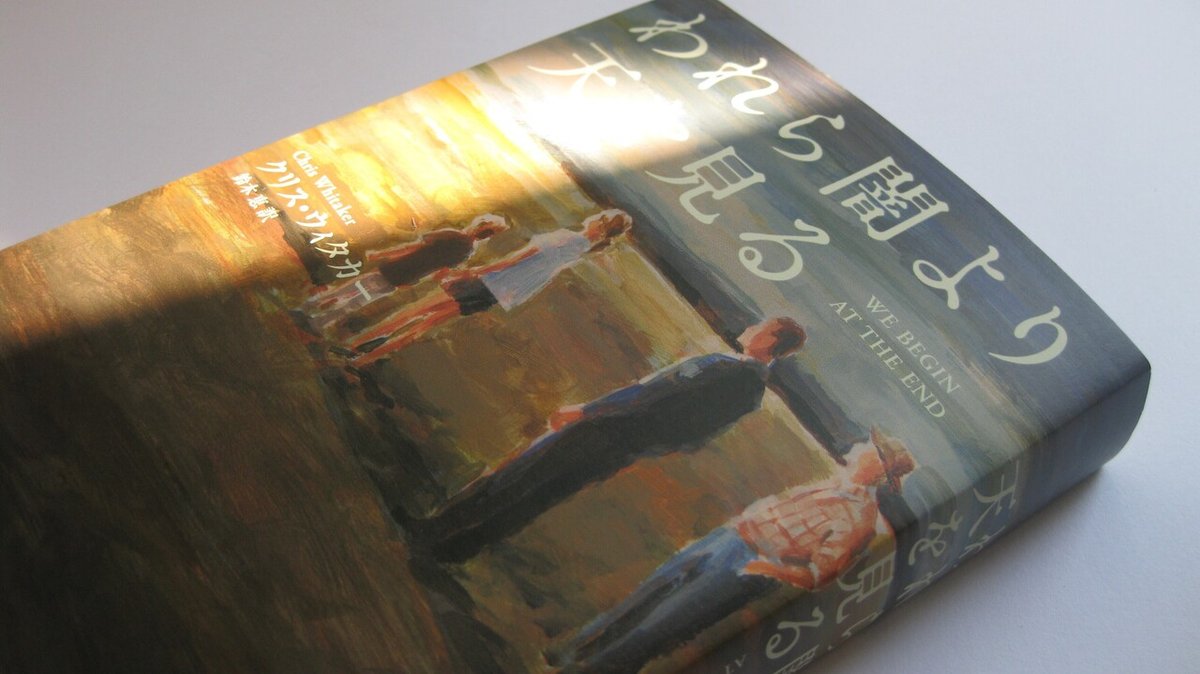
No.6:彼女の声がわたし/わたしたちの世界/現実で鳴り響く、あるいは、その名のもとで邪悪なるものたちを皆殺しにして世界を破壊せよ!

そして、ダッチェス・デイ・ラドリーが聖なる存在としてわたし/わたしたちの世界/現実を揺り動かすことになる。フィクションの境界を越えて来る異形の者。ダッチェス・デイ・ラドリーを包むその聖性のひかりがわたし/わたしたちの世界/現実を照らし出し、闇の中に姿を隠し蠢いていた邪悪なるものたちが一斉に騒めき立つ。彼女はひとつのフィクションの中で誕生したひとつのキャラクターでしかない存在から跳躍し、世界の闇を光で照射する聖なるものへと変容する。フィクションがフィクションの中で創造するフィクションを超越する存在。世界/現実がフィクションという想像力によって激しく揺り動かされる。終わりより始める異形の者が世界を横断し世界が震える。

ダッチェス・デイ・ラドリーがわたし/わたしたちの世界の現実の中で咆哮する。破壊され尽くした後の残骸の断片を拾い集めて作った継ぎ接ぎだらけの贋物の父と母、そして、見捨てられ遺棄された子供たち、壊れた家族の幻影の中で。決定的に守護者が放棄され弱き者たちを食らう強き者たちが跋扈し、恵みの見返りに服従を要求する贋物の父と母を操る支配者に、世界をゆだねてしまった守護者なきわたし/わたしたちの世界の中で、〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉、ダッチェス・デイ・ラドリーが叫び世界/現実を容赦なく裁定する。彼女の聖性のひかりがフィクションを超越して溢れる

守護は支配ではない。弱き者たちのために強き者たちのための法を破り無法者となって弱き者を守れ、無法者の守護者となれ、弱き者たちを守るために
ダッチェス・デイ・ラドリーよ、〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉よ、その名のもとで皆殺しにせよ! 弱き者たちを平然と踏み躙り殺戮してゆくわたし/わたしたちの世界を構成する邪悪なるものたちを、破壊せよ! われらの非情の世界を、弱き者を守護することを投げ出した非情の世界を。
ダッチェス・デイ・ラドリー、〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉、その声がわたし/わたしたちの世界/現実に鳴り響く。ダッチェス・デイ・ラドリー、限りなき弱き者でありながら聖なる守護者であり無法者、その名前わたしはその名前を決して忘れない。わたしたちはそれを忘れてはいけない
わたしの魂から血が滴り落ち涙が瞳から溢れ出る。彼女の流した血と涙への応答はそれ以外ない。涙よ、流れろ、涙よ、止まれ、終わりより始めるため

あとがき:クリント・イーストウッド監督の映画「われら闇より天を見るWe Begin at the End」/あるいは、コーエン兄弟かラース・フォン・トリアーか、それともデヴィッド・フィンチャーか
ダッチェス・デイ・ラドリーの物語を映画にするならば誰が監督として相応しいか?真っ先に名前を挙げるとしたらクリント・イーストウッドだろう。彼ならば彼女の肉体の破片であるその血と涙を正確に描写することができる憐憫も同情も共感も排して。複雑に入り組んだ人間の生のかたちの残酷さと痛みを余すところなく映画としてスクリーンの光と闇の中で展開してくれることだろう。クリント・イーストウッド監督の「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」。うんうん、予告編を想像しただけで心臓の鼓動が波打つように加速する、封切日が待ち遠しい!さてさて監督はこれで決まり。
となれば配役はどうするか?肝心要のダッチェス・デイ・ラドリーを誰が演じるか。これが全く思い浮かばない。宿命に抗う毅然とした表情とその内奥の哀しみの双方を体現する13歳を演じる役者は多くいると思うけど、聖性を纏うことになる13/14歳となるとまるで見当がつかない。〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉、ダッチェス・デイ・ラドリーは異形の存在なのだ。映画の中としても彼女は特別な存在なんだ。見掛けでは分からなくても
でもひとりだけいる。ジョディ・フォスター。(時間を巻き戻す必要があるんだけどそれは言わないで)クリント・イーストウッド監督が受け入れることができるかは分からない。激しく対立するかもしれない。クリント・イーストウッドはなぜかそれとも当然のことなのか〈女性〉を描写しない/できない。ジョディ・フォスターがダッチェス・デイ・ラドリーだとそう考えるとそもそもこの映画はクリント・イーストウッド監督作品ではないのかもしれないという思いにかられてしまう。そうなんだ違うんだ、彼の映画ではない
だとすれば監督は誰か?「トゥルー・グリット」で孤高の少女の旅を描き切ったコーエン兄弟という話もあるけれど、まるで映画の色調(トーン)が違ってしまうし映画の重心も彼女から外れてしまうだろう。コーエン兄弟では良くも悪くも大人たちの因縁と孤独へ傾斜してしまう。またコーエン兄弟印が刻まれた暴力への共振が突出してしまうだろう。コーエン兄弟の映画ではダッチェス・デイ・ラドリーの流す血は表せても涙を描くことができない。
とここで「奇跡の海」/「ドッグヴィル」のラース・フォン・トリアーの名前が急浮上して来るではないか。彼に全面的に委ねれば〈聖なる守護者〉にして〈聖なる無法者〉の女性の映画が作り出させるのかもしれない。でも彼に活劇を監督することはできないよね。そこなんだ、この映画の困難は。聖性と活劇、アクション映画にして聖なる者の伝説であること、誰か作ってよ。
いやいやいや、えっと、思い切ってデヴィッド・フィンチャーとかクリストファー・ノーランとかはどうだろう。うん、困ったね、迷ってしまうよ。て言っても勝手に妄想しているだけなんだけど。しかし、ダッチェス・デイ・ラドリーの物語/「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」の映画を夢見ることはもうそれはそれで楽しいんだ。凄く。多分誰かが映画にしてくれると思うんだ。もう今から浮足立ってしまって映画「われら闇より天を見る(We Begin at the End)」の公開日のために予定を空けておかなければと
それから最後に大切なことをひとつ。映画館で観たいのでそこは、よろしく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
