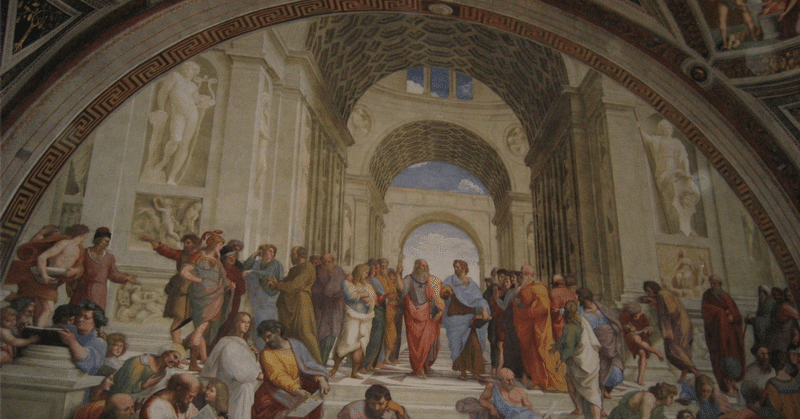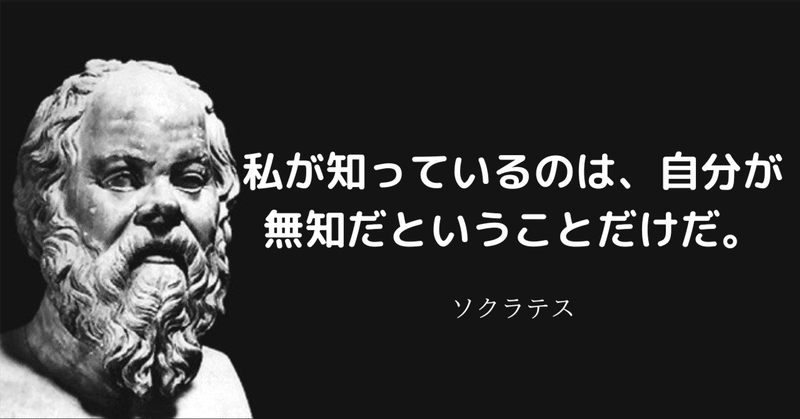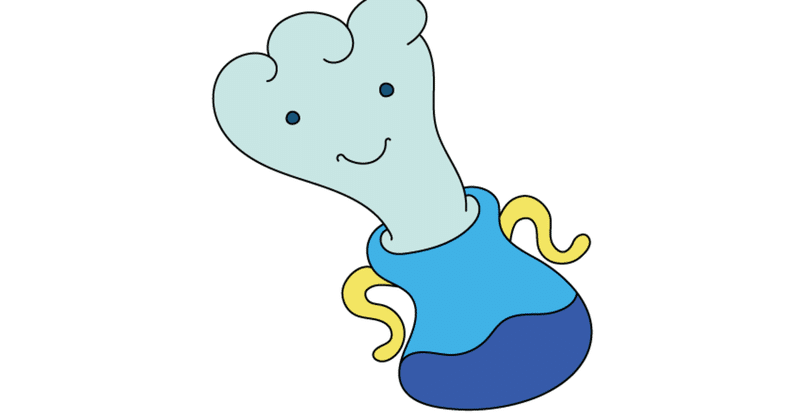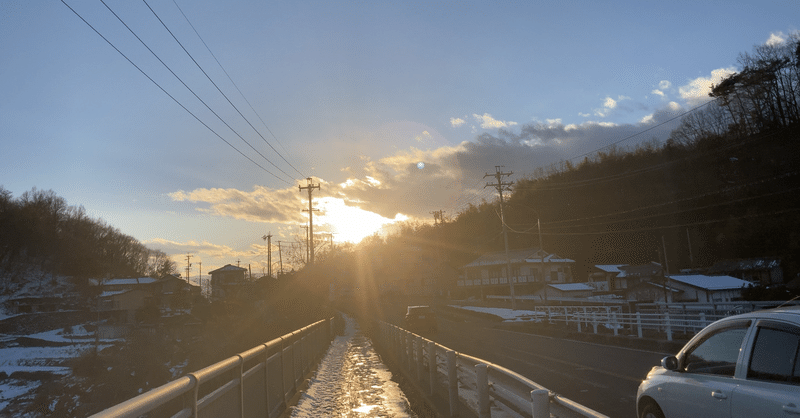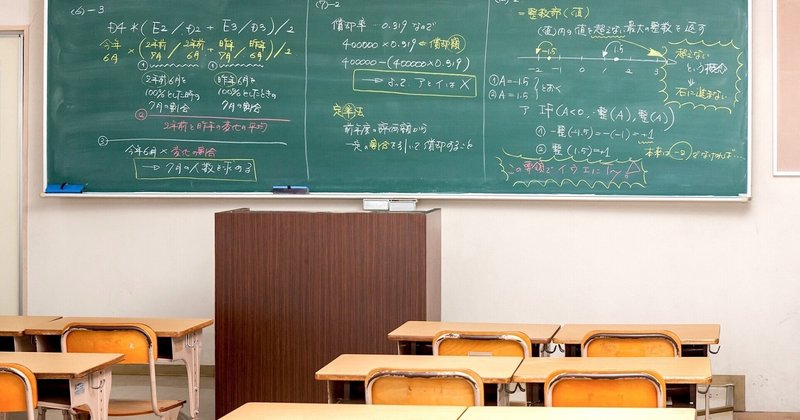#哲学
『禅とオートバイ修理技術』 要約と解説
はじめに
『禅とオートバイ修理技術』は、1974年に出版されました。著者パーシグが息子クリス、そしてサザーランド夫妻の3人と共に17日間の旅をした自伝的な内容です。
かつて大学教師だったパーシグは、思索にふけるあまり狂人であると見なされ、(当時は合法だった)電気ショック療法を受けました。彼は記憶の大部分を失いながらも、教師時代に残したメモを再び読みながら、『クオリティとは何か?』という問いに
古典哲学:ソクラテスと「無知の知」
あなたは、10年後の1月1日にどこで何をしていますか?それは本当ですか?絶対にそうしていると言い切れますか?
今こんなことを質問されて、答えられるでしょうか。
誰にもわからないことについて、真剣にわかろうとした人たちがいました。ソクラテスもそのうちの一人です。彼は『無知の知』を発見した偉大な人物です。
紀元前400年頃、ギリシャのアテナイという町に生まれたソクラテスは、後の哲学者に多くの