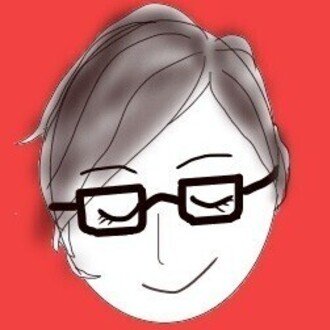2021年11月の記事一覧
信長の琵琶湖大作戦~天下取るには資金稼ぎから
尾張(愛知県西部)という小さな小さな田舎の国の、守護代の織田家の中でも一番の格下である弾正忠家に生まれた織田信長が、天下人になるために最初に目を付けた最優先のものとは?
ズバリ資金です。
まだこの時代は、武将というものは自分の生まれた生国にこだわって、生涯その土地を守り、そこを中心に領土を増やすというのが王道でした
しかし、彼はこの田舎の小さな国から、4度も国替えして「応仁の乱」以後、室町幕
比叡山と高野山の違いは何だろう? 秀才エリートVS天才カリスマ
過去に、比叡山も高野山も紀行した時、どちらも日本仏教にける聖地ではあるのですが、それぞれ感じた印象はまったく違うと思いました。
単純な発想として、比叡山を開いた最澄と高野山の空海の仲が悪かったから?
開山した二人の性格の違いがそうさせたのか?
全く違う雰囲気を持っています。
一言でいうと、比叡山はレストランもなければコンビニもない「近寄りがたいほどの霊山」だし、
高野山はコンビニや飲食店も土
奈良・京都だけじゃない! 古代大阪にあった難波京をご存じですか? #大阪歴史博物館コラボ企画
あの大化の改新で遷都した! 大阪市街地の地下に眠る、古代大阪で繁栄した「難波宮・難波京」について大阪歴史博物館の情報とともにご紹介します。
「何と(710)見事な平城京」「泣くよ(794)うぐいす平安京」……嗚呼、懐かしい、遠い学生時代の覚えた年号語呂合わせ。みなさまこんにちは、ミュージアム部のmitu.です。古代の「京」と聞いて思いつくのは、奈良の平城京・京都の平安京ではないでしょうか?