
「文は人なり」の本義 : 仲正昌樹をめぐって
(※ 再録時註:本稿の冒頭近くで、仲正昌樹の二著に触れているが、本稿は書評ではない。本稿で語りたかったのは「人となりの出ていないような文章はつまらない」ということである。なお、私は本稿において、仲正にかなり辛く当たっているが、その後も彼の「現代思想入門」系の著作は読んでおり、それなりに重宝していて、肯定的な評価も与えている。私が、本稿で指摘しているような、仲正の「クセの強さ」は、特に初期の著作に多いように思う。未読だが、仲正は2009年に『Nの肖像 統一教会で過ごした日々の記』(2020年に新版『統一教会と私』)という自伝的な著作を刊行しており、彼の屈折には、こういう経歴から来る部分もあったのではないかと、私は今にして思っている)
最近読んだ、金沢大学法学部教授・仲正昌樹の著作2冊、『なぜ話が通じないのか コミュニケーション不自由論』(晶文社)と『日本とドイツ 二つの戦後思想』(光文社新書)に関連して、「文は人なり」ということについて書いてみたい。
それまでまったく知らなかった仲正昌樹という著述家の本を手に取ったのは、その本のタイトルと帯文に強くひきつけられたからである。『なぜ話が通じないのか コミュニケーション不自由論』の帯文は、次のようなものである。
『 人の話を聴きなさい!
「歴史の終焉」のなせるわざ?「大きな物語」が終焉したから?
知識人から2ちゃんねらーまで、日本社会に蔓延する
「話が通じない病」を撃つ、哲学・思想エッセイ! 』

先日、ホランドくんが、滝本竜彦のひきこもり小説『NHKにようこそ!』を論じて言及していたように、昨今の日本におけるコミュニケーションは、「ひきこもり」の傾向を強めており、一方でそれを補うように、携帯(メール)やブログ(ネット)などの間接的コミュニケーションツールが、爆発的な広まりを見せている。
無論、これは矛盾した現象ではなく、日本人、特に若者の「コミュニケーション」が、大きなメリットとリスク(デメリット)をともなう「直接的コミュニケーション」から、相対的にリスクの少ない「間接的コミュニケーション」(間接度の高いコミュニケーション)に移ってきているということなのであろうし、人が人間関係において過剰に傷つきやすく脆弱になった(「他者忌避的脆弱さ」を強めた)反面、それでも他者とのコミュニケーション無しには生きていけないという「他者依存的脆弱さ」をも強めているという、「悲劇的な二律背反」の強まりを示すものなのではないだろうか。
このような現状認識から、私は前記の『なぜ話が通じないのか コミュニケーション不自由論』に興味をもったのだが、内容的には、期待したほどのものではなかった。
「日本とドイツの、戦後責任の取り方の違い」という問題を考える上で参考にしようとして読んだ『日本とドイツ 二つの戦後思想』にも言えることだが、著者・仲正昌樹の主張は、ごく大雑把に言えば(帯文にもあるとおり)、「左右を問わず、日本人は、虚心に他人の話を聴こうとはせず、自分の言いたいことを言うだけだから、まともなコミュニケーションが成立しないのだ」ということだと、まとめられよう。この意見自体は、至極ごもっともな「正論」であり、誰もが少なからず感じていることでもあろう。
だが問題は、人が「日本人は、虚心に他人の話を聴こうとはせず、自分の言いたいことを言うだけ」だと言う場合、たいがいは、この「日本人」に「自分(自身)」は含めておらず、そこに指示されている「日本人」とは「自分以外の、多くの日本人」でしかない、という事実である。
実際、私も、自分では「他人の話をよく聴いている」つもりだが、私が他人の話に耳を傾けない人間だと評価している人は少なくないようだし、本書『なぜ話が通じないのか コミュニケーション不自由論』の著者である、仲正昌樹の自己認識もまた、同様のようなのだ。

『 自分でもこういうまとめ方が良かったのか、と疑問が残っているところがあるが、それらのポイントには読者の〝具体的で建設的な批判〟を待ちたい 一一 一冊の本にまとめて書く時には単純化や細部の切り捨て、ある程度強引な再構成が必要であるということを基本的に理解しないまま、「話が雑でいい加減だ」とだだっ子のような〝批判〟をするのが、日本のドイツ思想史研究家もどきには多いが、ああいうのは要らない。』
(『日本とドイツ 二つの戦後思想』、「おわりに」の末尾部分)
一般向けの教養書だとは言え、ドイツの思想史を勉強してきたという専門家の大学教授による専門的な書物の「あとがき」に、こうした過剰とも思える言葉が書きつけられているのを「異様」だと感じる読者は、決して少なくないはずだ。
ネットに数多存在する「アマチュア評論家による書評」を瞥見すれば、基本的事実について無知なまま、「思いつき」だけでご託宣を垂れたようなものや、評価の根拠を論理的に説明する能力のない者による無責任な放言も決して少なくない。
「一億総評論家」とは、もうずいぶん昔に言われた言葉だが、その当時、この言葉が「評論家」と名指す者の多くは「口答による(文筆によらない)評論家」であった。
しかし、ネットの発達以降、「一億総評論家」の「評論家」も、プロの評論家と同様の「文筆による評論家」という形式を備えるにいたっている。
だから、仲正昌樹が、そうした「評論家」に嫌な思いをさせられてきたというのは、容易に想像できるだけではなく、事実として『なぜ話が通じないのか コミュニケーション不自由論』の方で、その実例が示されてもおり、仲正は、そういう「人種」は相手にしないというのを大前提とした上で、さらに同じ「研究者」の批判であっても、仲正の考える「常識」に反するようなものには「耳を傾けるつもりはない」と、そう言っているのだ。
まあ、こう言いたくなる気持ちもわからないではない。しかし、そういう目に遭っているのは、なにも仲正ひとりではない、というのも明らかな事実で、多くの人は、そういう理不尽と思える現状に、不満や怒りを感じながらも、自ら、コミュニケーションの回路を断つような言動は、自制しているのではないだろうか。
その意味では、上に引用した文章に感じられるのは、やはり仲正昌樹特有の「自制心の無さ」と「自己中心的心性」だと言えるのではないだろうか。
じっさい、仲正がここで言っているのは、
「私が自分でおかしいと気づき得るところ以外については、批判するな。感想もいらない。また、私が自分でおかしいと気づき得る部分について論評する場合でも、それは必ず、私が『具体的で建設的な批判』だと評価しうるような形でなされなければならず、私の意に沿わない形式での批判は許可しない(つまり、実質的に、批判は許さない。そんなものは要らない)」
ということであり、端的に言えば、これは「他者の意見は要らない」ということ、言い換えれば「自分の意見だけで良い(自分の意見を追認する意見しか、聞く耳を持たない)」ということである。
一一つまり、こういう「聞く耳を持たない」人物が「左右を問わず、日本人は、虚心に他人の話を聴こうとはせず、自分の言いたいことを言うだけだから、まともなコミュニケーションが成立しないのだ」という趣旨の「批判」を、他人に向けて発しているのだから、これが「自己矛盾」だというのは、至極わかりやすいところだろう。
したがって、仲正昌樹の著作を読んで「興味深い」のは、著者「仲正昌樹の意見」そのものではなく、それが「仲正昌樹というコミュニケーション不全者の症例報告」という意味合いにおいてなのである。
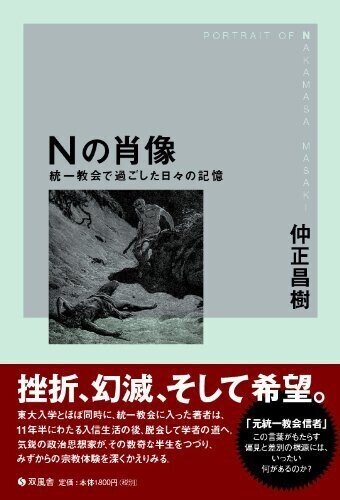

もちろん、仲正昌樹は、頭も良いし勉強家でもある。また、ある面では稀有なまでに正直(これまでの四十数年の人生で、性交も自慰もしたことがない、等と表明)な人物だから、どちらの著作も、「一般論」としては(つまり、仲正に、そのように言う権利があるのか否かは別にすれば)傾聴に値する意見は多々ある。
しかし、面白いのは、それだけ「頭が良く」て「よく勉強している」人であったとしても、「自分のことは、なかなかわからない」し、そのために安易な「自己正当化」に傾きがち、だというのも事実。さらに、それが正直に「文章に表れてしまう」という事実なのだ。
例えば、私の文章には「理屈っぽい」「狷介」「熱い(情が濃い)」「過激」「攻撃的」「反骨(反・権威)」といった特徴がはっきりと刻まれているだろうし、それは善かれ悪しかれ、私という人間の特性を正直に反映したものだと言えよう。また、そういう「内容」面だけではなく、「文章」面(文面)の問題として、「くどい」「流暢さに欠ける」「ぎこちない」「悪文」といった特徴も、私の「欠点」でもあれば、「長所」と裏腹に存在する「特異な個性」の反映であろう。
「文は人なり」と言っても、もちろん「文章を装う」のは、ある程度は可能だし、事実、多くの人は自覚的にか無自覚的にかに関わりなく、文章を装っている。
では、「文は人なり」と言えるような文章は、どのような局面で出てくるのかと言えば、それは人が「真実を語ろう」とした場合なのではないだろうか。
もちろん、これは「自分の真実を語ろうとした場合」だけを指すのではなく、一般的な、いろんな「真実」個々について、それを語ろうとした場合に、それに附随するかたちで「自分の真実」が語られてしまう、という意味である。
例えば、本格ミステリマニアが「本格とは何か」について熱く語れば、その文章には、その人の「人となり」が正直に表れるだろうし、家族を戦争で失った人が「戦争とは何か」を語れば、それが思想的に右寄りであろうと左寄りであろうと、いずれにしろ、その人の「人となり」が比較的正直に反映されたものになるだろう。
つまり、「自分の真実」を偽ろうとして、なかば意識的に「文飾」し「きれいごと」を語ろうとしないかぎり、文章には、その人の「人となり」は反映されてしまう。
本気で何か「意味のあることを書こう」とすれば、その人の「人となり」や、「思考形式」や「思考能力」が、問わず語りに語られしまう(反映表明されてしまう)ということだ。
だから、逆に言えば、アマチュアの「上手な文章」ほど、「中身が無い」という意味で「つまらない」ものはない。(無難に)何も語っていないからこそ、言葉だけが「流暢」に流れる文章となっているのである。
もちろん、文章というのは「読みやすい」に越してことはない。その意味で「うまい文章」「流暢な文章」であるに越したことはないのだが、しかしそれは、その前提として「読むに値する中身」があっての話であり、「中身」が無いのであれば、うまかろうが流暢であろうが「そのそも読む価値が無い」のだ。
じっさい、「わが心の師」である大西巨人の文章を例示するまでもなく、自身の思考をふかく探り、それを正確に文字に移そうとする思索的文章家の文章は、しばしば「個性的」であり、その意味で「読みにくい文章(悪文)」であることが少なくない。「意味が取りにくい」とか「難解である」と評価されることも決して珍しくはないのだ。
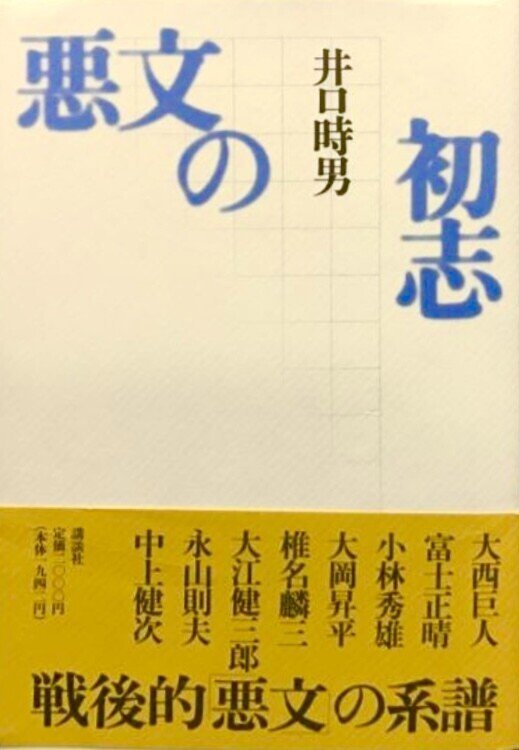
それに対し、教育委員会が主催する「作文コンテスト」で優勝するような子供の文章は、「流暢」で「文意明快」で、おおむね「感動的」なものばかりである(つまり、紋切り型)。
したがって、私が「文は人なり」という言葉で語りたいのは、「流暢な文章」を書く「うまい文章家」というのは、人間的にも洗練されており優れている、ということを意味しはしない。
「文は人なり」という言葉は、まず人が、何らかの「真実」を語ろうとして、自身のもてる力をふりしぼるという「努力」が大前提であり、それ無くしては成り立たないものなのだ。
つまり、私がここで言いたいのは、人は「何であろうと、自分の真実を語るために、文章を書くべきである」ということであり、その上で、そこに表れた「自分の人となり」に注意深くあるべきだ、ということだ。
表面的に「うまいだけ」の文章なら、「作文コンテスト」の常連たちに任せておけばいい。
私たちは、そうした「浅瀬を渡る」ようなことで満足すべきではない、と言いたいのである。
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
