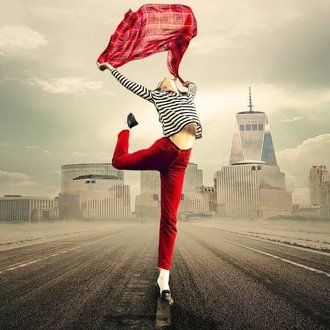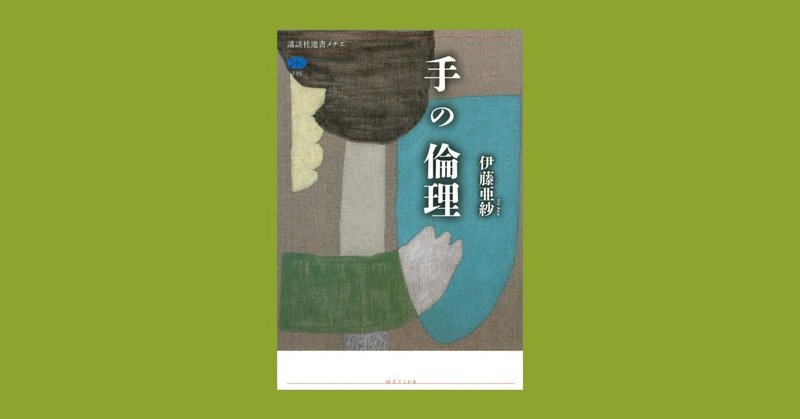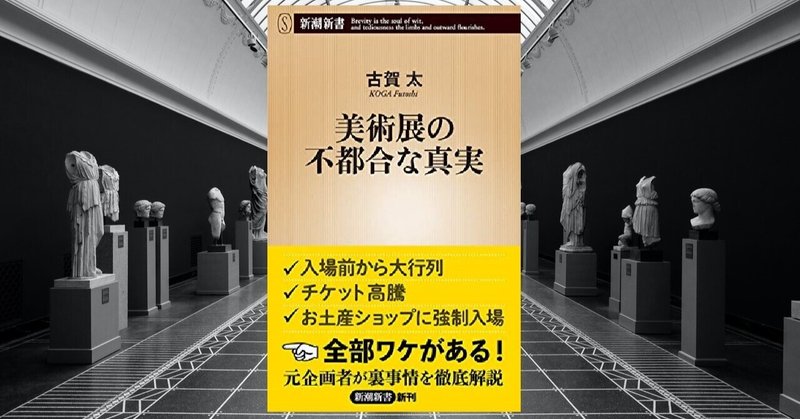#本
『闘う舞踊団』金森穣著:Noism(ノイズム)の新潟での奮闘を記録した本
海外で活躍後に日本に戻り、海外(ヨーロッパ)と日本の芸術文化の土壌や質の違いを強く意識しながら、それでも日本での意識や現状を変えたいと組織を立ち上げて困難の中でも活動を続けている人といえば、バレエではKバレエカンパニーの熊川哲也さん、そしてコンテンポラリーダンスではNoism Company Niigata(ノイズム)の金森穣さんが思い浮かぶ。
Noismは、りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館を
『手の倫理』伊藤亜紗著:介助やスポーツから「触覚」を考察する本
「触覚」について美学者が考察した本。研究者も一般の人も読めるように書かれている。
キーワードは、「ふれる」と「さわる」、「道徳」と「倫理」、介助・介護、スポーツ、コミュニケーション・伝達、信頼、共鳴、不埒など。
体育の授業が目指すのは、他人の体に失礼ではない仕方でふれる技術を身に付けること、と聞いて、著者の伊藤は感銘を受けたという(p. 24)。私は、そのように考える体育科教育学の研究者がいる
『美術展の不都合な真実』古賀太著:安易で企画意図がない企画展が増えた理由
現在は日本大学 芸術学部 映画学科 教授で、かつては国際交流基金で日本美術の海外への紹介、朝日新聞社で展覧会企画を手掛けた著者が、日本の美術展の世界でも特異な実態を解説する本(2020年発行)。
「混みそうな美術展」は展示概要を見ればすぐわかる本書の内容はわりと周知の事実だと思っていたことが多かったが、一般にはあまり知られていなかったのだろうか?著者はあとがき(「おわりに」)で「一般にはほとんど
マンガとダンスの身体:夏目房之介教授最終講義「マンガ研究はなぜ面白いのか」
漫画と舞踊を身体という共通性で捉える漫画研究の夏目房之介氏が若いころ漫画を描いていたということで、テレビ番組「浦沢直樹の漫勉」に言及し、また趣味で中国武術をしていて、漫画を描くこととの関係性を指摘し、漫画の身体性を語っていた。
最近、久しぶりに絵や文字を手で描・書いて、体を動かすことで紙に線が生み出されていく、あの独特な感覚が自分には必要なのではないかと考えているところだったので、上記の話に興奮