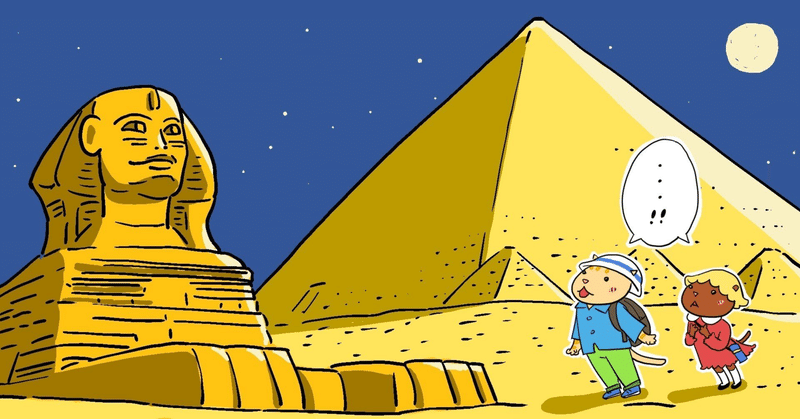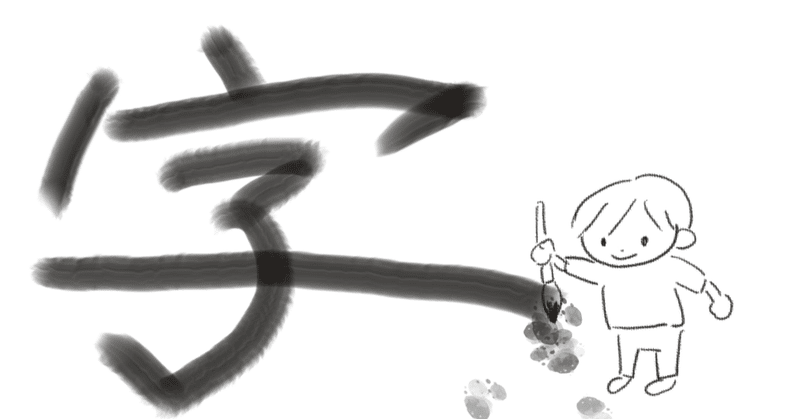- 運営しているクリエイター
#子育て
二男、今日は学校お休みDAY。色々なことが日々あり、その対応に追われていますが、その為に自分が「親」として存在しているのだ再認識中。今シーズンのゲーム数も少なくなってきたけれど、昨日はBリーグのバスケ観戦に行き、元気をもらいました!ありがとうレバンガ北海道!!バスケ最高~!!!

学校に行かないという選択。「二男、学校に行くってよ。①」
始業式の一昨日。二男が小学校に初登校した。
前日の夜に持ち物を準備し、鞄にしまう。「明日から学校か〜」と言いつつ、嫌な雰囲気ではない。始業式の朝も早起きして、身支度を整えていた。緊張して早く目覚めたのかもしれない。
玄関や下駄箱、教室の様子なども、何もかも初めて。二男に事前に説明はしたけれど、「朝、玄関とか教室とかまで一緒に行った方がよければ行くよ?どうしたい?」と尋ねると、「どっちでもいいよ
学校に行かないという選択。「自発的な学びとはどこから始まるのか。」
2月の終わりに長男の中学の定例面談があった。
学校に通わない選択をしている長男もこの春には中学3年生となる。所謂、不登校の子どもたちが進級するにあたり、もし望むのであれば、再度同じ学年で学ぶという選択もあるのだそうだ。私が中学生の頃には、そのような制度というか選択肢はなかったので、なるほど、そんなものがあるのか、本人さえ望むのであれば、そういった時間を過ごすものアリなのかもしれないな、と思う。
漫画みたいな毎日。「探しに行くよ、内なる花を。1」
毎年、何故だか9月、10月は駆け足で過ぎていく。
夫や末娘の誕生日があったり、幼稚園の誕生会にお祭り、そして、家族が私の誕生日を張り切ってお祝いしてくれるムードが高まるからだろうか。
北海道では、夏が終わると途端に、「雪が降るまえに」という空気が漂う気がする。
雪が降るまえに、庭を整え、畑を片付け、家の補修をし、衣替えをし、寒くなる前に、あれもこれもやっておこう。
そんな気持ちになる。
漫画みたいな毎日。「探しに行くよ、内なる花を。3」
旅の記録1・2はこちら。
高校のオープンスクールに向かう途中で10キロの渋滞にはまった私たち。
明らかに開始時間には間に合わない。
夫の「学校に電話してもらえる?」という一言で、今やれることをやらなくてはと、モードを切り替え、高校に電話を入れる。
渋滞にはまってしまい遅れてしまうことを伝えると、学校の方は「わかりました!くれぐれも気をつけていらしてくださいね!」と言ってくださった。
渋滞を抜
漫画みたいな毎日。「探しに行くよ、内なる花を。2」
旅の記録1はこちら。
今回の旅の一番の目的は、長男が興味を持った高校のオープンスクールに参加すること。
本来は中学3年生が参加対象だが、遠方に住む我が家の状況を考慮していだたき、参加を快諾していただいた。その対応も柔軟な印象を受け、どんな学校環境なのだろう?と益々興味を持った。
神奈川に住んでいる姉の家に宿泊させてもらい、そこから長男のオープンスクールに参加することになった。しかし、神奈川か
学校に行かない選択。「不安や焦りはどこから来るの?」
昨日のつぶやきにも書かせていただいたが、先日、二男の個人面談があった。
いつだって個人面談だよね?うちのバアイ・・・と夫と笑って面談の予定を確認する。本来であれば、個人面談は、保護者と担任の先生との面談であるが、我が家は月に1回程度、先生とお会いしているので、毎月が個人面談である。
しかし、その時間をとっていただくのも、あたりまえではないよなぁ、と毎回感じている。子どもが学校に行っていれば、先
どのくらい?を知りたがる大人たち。
相手の事を知りたいと思った時、あなたなら、どんな質問をしますか。
あるいは、しませんか。
子どもたちに大人が聞く。
「どのくらい好きなの?」
「どのくらいの時間、勉強してるの?」
「どのくらい知ってるの?」
どのくらい??????
こどもたちのこたえはだいだいこんな感じだ。
「ん~、わかんない。」
友人のお子さんがラジオに出演することになり、先日、収録があったそうだ。そのお子さん
「世界でいちばん、面倒だ。」と思うこと。
ある日、夕飯の支度をしていると、長男(11歳・小5)がやってきた。
「お母さん、お母さんにとって世界で一番面倒臭いことってなに?」
い、いきなり、深い質問ですね。料理をしながら、頭の中でアレか?コレか?と考える。一番って言われると、わからないものだ。だって、いろいろあるよな~タイミングや事柄によっても面倒と思ったり、思わなかったりするし。そんな時は、そのままの質問を本人に返してみる。
「あな
海老で鯛、ではなく海老で蟹を釣る?
夫不在・3日目。
車で一時間ちょっとの水族館に行きたいと子どもたち。雪が降ると運転するのが怖いので、冬には訪れたことがなかった。
子どもたちの目的は、水族館の外側にある。
水族館は海に隣接しているので、岩場にいろいろな生き物がいる。すぐに見つかるのが「カニ」だ。夏場は、バケツと糸と餌のスルメイカをもって、水族館内を一回りした後、閉園まで延々とカニ釣りをするのだ。
↓こんな感じ。
この日は
なんにもないところほど、よくあそぶ。
夫不在・2日目。
子どもたちと近隣の自然教育園へ。
昆虫好きの長男が小さい時から時々訪ねている場所だ。春~秋の間は、小学校の農業体験などもやっていて、田植えやじゃがいも栽培などもしているそうだ。敷地内にはマルメロやナツグミの大きな木があり、小さな池にはルリボシヤンマやアマガエルがいる。
施設の館内にはナナフシが飼育され、玄関の脇のスペースに餌のハイビスカスと共に育てられている。飼育ケースも仕切
野生のカバだったり、山猿だったり。
一昨日、子どもたちと近所の山に登って雪山を一気に滑り降りる「尻滑り」をする。ふかふかの雪を蹴散らしながら斜面を滑り降りるのは、豪快&爽快。
しかし、向かった山は直角に近い傾斜だった・・・。子どもたちは、そんなことを気にも止めず、山に登り始める。最初の登り始めこそ、ふかふかの雪が積もっていて足場を見つけられず手間取っていたが、あっという間登っていく。3歳の娘もだ。
山を見上げても、子どもたちの姿
どんなにちいさなことがらも、〈させること〉は、できない。
新学期早々にコロナウイルスの影響で学校が休校になったときのこと。長男の担任は転勤してきた方で、あまり顔をあわせることもないまま、休校となっていた。
毎週、木曜・金曜に長男、二男それぞれに担任から電話がかかってくる。健康面・生活状況の確認のためだ。先生方は休校中でも、様々な業務に追われているであろうに、ひとりひとりに電話をするというのは、大変なことだと思う。
その金曜日、長男の担任から電話があり
和を以て貴しと為す。せめてこどもたち3人の話くらいは聞き分ける能力がほしい。
聖徳太子といえば、一万円札の肖像。なんだか好きだったな。10人の話しを聞き分ける。うらやましい。
そして、「和を以て貴しと為す」ではじまる十七条の憲法。
夫は常々、こう言っている。
「『聖徳太子以来”和を以て貴しと為す”という考え方を元に、他者を攻撃したり自分ばかり突出したりしないように振る舞う全体主義的な文化が、良くも悪くも日本には根付いている』といった話をよく耳にするけど、『和を以て貴し